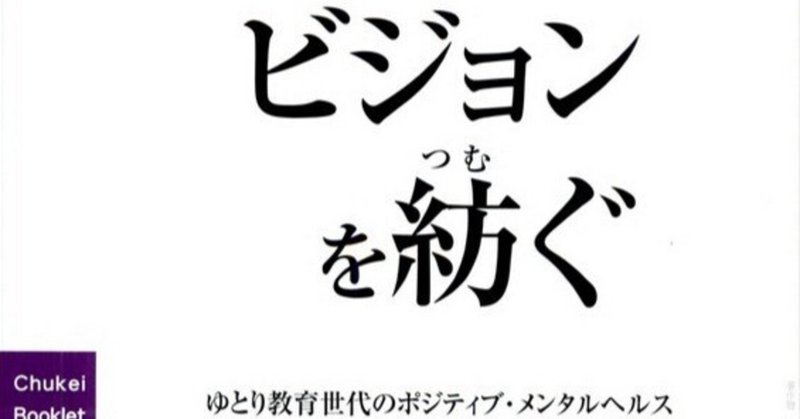
所長コラム⑩「ビジョン・クラフティング研究所」のビジョン
社内外から「ビジョン・クラフティング研究所って何?」と質問を受けることがあります。「ジョブ・クラフティングの仲間なの?」と言われることもあります。この場を借りて、当研究所の命名のルーツや目指すビジョンをお伝えできたらと思います。
ビジョン・クラフティングのルーツは、2008年頃に社内で頻繁に行われていたディスカッションにあります。当時、将来の若年層の適応障害の増加を予測して、VISIONプログラムの開発を行いました。
その頃の状況や問題意識は、2009年から中部経済新聞社にて連載された「次世代型メンタルヘルス対策」に記してあるのですが、適応支援にはストレス反応の早期発見・早期対応ではなく、変化が発生した社員と1on1で話して、その変化を語れるよう支援するアプローチが重要だと指摘しました。
日々、多くの相談を受けているジャパンEAPシステムズならではの観点だったと思います。この連載は、以下の書籍「ビジョンを紡ぐ」に取り纏められ、広く販売されましたが、残念ながら今は絶版となっています。
VISIONは「Vision is shaped in our Narrative」の略語で、ナラティブ・アプローチを活用したプログラムです。変化を語れるようになる支援を通して適応促進を目指すのですが、個人向けと集団向けに分けて、「ビジョン・ナレーティング」「グループ・ナレーティング」と名付けて実践しています。尚、ビジョン・ナレーティングは、このnoteでも紹介しています。
グループ・ナレーティングの取り組みも、多くの企業や自治体で実施してきており、その成果は事例として論文に取り纏めて投稿し、査読を経て学会誌にも掲載されています。また、以下の書籍にも、グループ・ナレーティングの取り組みの詳細が示されています。
松本桂樹(2012)ハイリスク期に焦点を置いたメンタルヘルス対策における1次予防の取り組み, 人材育成研究(7), p99-105
冒頭の通り、よく「ジョブ・クラフティング」と間違われるのですが、ジョブ・クラフティングが日本で認知されるようになったのは2016年頃と言われます。「ビジョンを紡ぐ」の書籍は2010年出版であり、ビジョン・クラフティングは、この「ビジョンを紡ぐ」を英語にしたものなのです。
ビジョンは、最近だと「パーパス」と表現される概念とも近いといえます。人的資本経営、パーパス経営の重要性が叫ばれる現在、経営者や管理職は自らのビジョンやパーパスを語れるようになることの重要性が高まっています。自律的キャリア形成を考えても、社員は自らが「大切」と考えることを認識し、かつ周囲に伝えていけることが重要となります。
私自身が抱いているビジョンは、「ひとりひとりが、より良い未来を描くビジョンを語れるようになること」です。ひとりひとりが大切に思うことを大切にできる社会にしたい。そのためには、心理的安全性が確保された場において、安心して自らが大切だと思う「人」「もの」「価値観」を振り返り、幾度か語りの試行錯誤を繰り返すなかで、自らが納得でき、かつ他者にも伝わるビジョンが一緒に紡げたらいいなと願っています。
■所長プロフィール
松本 桂樹(まつもと けいき)
株式会社ジャパンEAPシステムズ 取締役
神奈川大学人間科学部 特任教授

精神科クリニックにて心理職として勤務後、日本初の外部EAP専門機関であるジャパンEAPシステムズの立ち上げを担う。 現在もEAPコンサルタントとして、勤労者の相談を多く受けている。
臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、キャリアコンサルタント、1級キャリアコンサルティング技能士、日本キャリア・カウンセリング学会認定スーパーバイザーなどの資格を保有。
