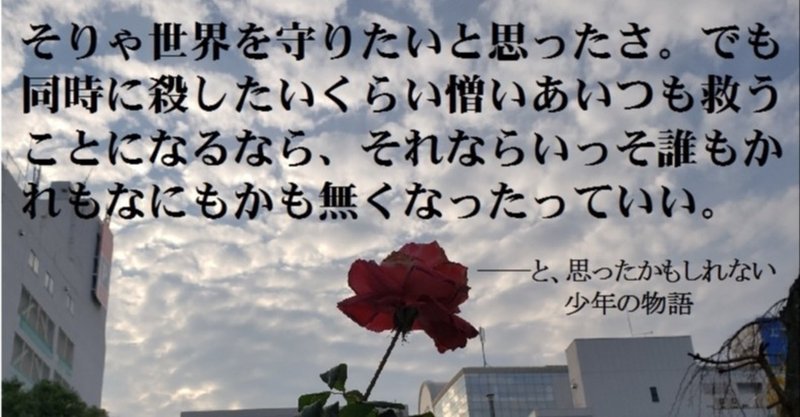
「四度目の夏」16
おじいちゃんの笑顔と怒鳴り声
「ところで、一年ぶりに会う友達、マサキ君との時間はどうだった?」
隣に座る益司さんが食卓で訊いた。
佳奈江さんがじいちゃんの首にスタイを付けた。マジックテープ式で、片手でつける素早さに手慣れたものを感じる。
「彼は陽に当たらないから肌が抜けるように白くて、暗い部屋だからよけいに白さが浮出ってた。痩せてるし…ちゃんと食べてるのか気になったけど、ブレンダが毎日の食事を作ってるみたいだし」
世界を賑わせたホクトマサキが彼だってことは、益司さんにも内緒にすることにした。
「あの辺りはアーリーリタイヤした夫婦なんかが多い住宅地だからね、よく無人バイクが食料を運んでいるのを見るよ。ふもとにできた大型ショップモールから運ばれてるんだ。きっとそのマサキくんのところにもそうやって食料が運ばれてるんだろう。もっともマシンがスーパーに買い出しに行っているのかもしれないけど」
「ブレンダってやつがスーパーに買い物? ないわー。もしそうなんなら、学校で超話題になっとるとって。けどそんな話きいたことないで」
よっくんが割って入った。
今日は昆布だしの筑前煮と金目鯛の煮付け、小松菜と油揚げのおひたしだ。
「あとでスイカをいただきゃんしょんね」
おばあちゃんがキッチンから声を出した。それから「佳奈江、おじいさんの筑前煮をジューサーにかけて」と言った。しばらくするとフードプロセッサーのけたたましい音が鳴り響く。おじいちゃんにはレンコンは固くて噛み砕くことができない。というか、歯そのものがほとんどなくなっている。
おじいちゃんは口の中に食事を運んでもらうと重そうに顎を上げるけれど、口に食事が入るとカクンと顎を落としてモシャモシャと口を動かす。
でもほとんど歯がないから噛みしめる動きをすると顎がなくなったかと思うくらい顔が縮む。スプーンで口に入れてもらうときには口を開けて再び顔が大きくなる。それを繰り返した。ときどき唇の端から食べ物が漏れる。それを佳奈江さんやおばあちゃんが布巾で拭く。昨日には短かった白い髭がもう伸びて、形を失くした筑前煮が白い髭にとろっとついてしまう。それを佳奈江さんとばあちゃんが拭う。
口元を拭ってもらったおじいちゃんはお礼を言うように顎をカクンと勢いよく落とした。そしてムフっと息を吸い、口を膨らませた(息を口の中にため込むことで首を支えているように見えた)。それから頬に力を入れて笑顔を見せた。この三年間毎年白雲岳に来たけれど、初めて見るおじいちゃんの笑顔だった。
「おじいちゃんが笑ってる!」
ぼくは心でつぶやいたつもりが、びっくりしすぎて声に出してしまった。
「じいちゃんな、認知症がすすめばすすむほど、ええ笑顔するようになったんよ。今日はまたゴキゲンじゃ」
よっくんが嬉しそうに言う。
おじいちゃんを見ると、にんまりとまだ笑っている。笑い声を響かせるわけじゃない。本能で笑っているような、ただただ笑う——なんていうか、純度の高い笑顔だ。まるで赤ちゃんみたいな――こんなにしわしわなのに、赤ちゃんみたいな。
「筑前煮がおいしかったんしょね。おじいさんの好物だのん。よかったわねぇ、おじいさん」
おばあちゃんがおじいちゃんの髭を拭く。おじいちゃんは感無量といった笑顔で頷いた。それからまたカクンと俯いた。
笑顔。
菩薩の顔を模したアナスタシアの笑顔とも違う――ぼくはふとブレンダを思い出した。
「今日、マサキの家でアナスタシアが紅茶を淹れてくれたんだ。バニラの香りがするフレーバーティだったんだよ。ぼくは夏でもあったかい飲み物が好きなんだけど、それがあったかい紅茶でさ」
「あら素敵。ビッグデータには人の好みまで学習されて記録されてるのかしら」
「それはあるみたい。この年齢、この顔立ち、この喋り方で、およその好みを割り出すんだ。あ、でも」
ぼくは言葉に詰まった。ブレンダはオフラインだ。ビッグデータにつながってないはずだ。てことは、最初からそういったデータはあらかじめ初期設定されてるってことなのかな。
「そういえばおととしの夏にお義姉さんここでわたしたちにチョコチップスコーンを焼いてくれて、そのときに言ってたわねぇ。小さいころにあなたは癇癪持ちで、わけもなくよく泣いていて、そんなときはミルクチョコレートをからませてスコーンを焼くと、その匂いで泣き止んで、食べると笑顔になった、って。甘い香りはもともと好きなのよね」
佳奈恵さんが笑いながら言った。
「そうかも……あれ、なんか恥ずかしいな」
ぼくは味噌汁をすすった。甘い香りがすきなのは認める。けど、なんでブレンダがそれを知っているのかな。
確かにぼくは視力がすこし弱いぶんだけ、匂いには敏感だった――それってすごく個人的なデータだけど。突然、雷のような怒鳴り声が飛んだ。
「箸を加えるな! 行儀の悪い! 蔵に閉じ込めるぞ!」
ビクッと震えて、口のなかにあった箸をとっさに引き抜いた。叫び声の主はおじいちゃんだった。
「ちょっと、おじいさん! この子はわたしらの息子じゃありゃせんよ。あんたの孫だがね」
おばあちゃんがたしなめるように言った。
おじいちゃんは目をこれ以上ないくらい見開いて、白く濁った瞳でぼくを穴が開きそうなくらい凝視して、またカクンとうなだれた。
おじいちゃんの隣の椅子で、その様子をみっちゃんが呆然と見ていた。みっちゃんが小さなスプーンを口にくわえたままだ。
「ぼく、もしかして父さんに顔が似てるのかな」
ぼくはおばあちゃんに訊いた。おばあちゃんも、それからほかのだれも、それには答えなかった。ただなんとなく、おばあちゃんの顔が申し訳ないような、それとも違う、さびしいような、そんな表情になった。
ぼくの言葉は宙に浮いたまま、着地する場所を持たなかった。しかたなくぼくはご飯をほおばった。そして箸が口の中に残ったままにならないよう注意した。
今年の夏、父さんがここにまた戻ってくることを、おばあちゃんは待ってた。きっと待ち望んでいた。この夏、夏まであと少し、おばあちゃんが父さんに会える日を、じっと変わらない毎日、変わらない白雲岳で、待っていた。
朝と夜の鐘の音を聴いて、季節の移り変わりが一巡りして、ようやく会えると思っていたら、ぼくだけがやってきた。ぼくしかここに来なかった。
おばあちゃんはさぞがっかりしたにちがいない。
三年前にひょっこり妻と子供を連れて戻ってきた一人息子は、たわむれに三回やってきて、そしてまた来なくなった。
ぼくは急に居心地が悪くなって、食事がのどを通らなくなった。
この家の日常を、ぼく一人が来たことで、おもしろくない形に歪ませているような気がした。
おばあちゃんや佳奈恵さんやほかのみんなにますます気をつかわせてしまう。だけどぼくはとてもこれ以上ご飯を食べられなかった。
「ぼくは君と出会えてうれしいよ。こんな甥っ子がいるなんて知りもしなかったから。なにせここではお義兄さんのことはタブー……コホンコホン」
とつぜん明るい声で言ったかと思うとせき込む益司さん。そこに叩みかけるように「タブーってなに?」とよっくんが訊いた。「たぶーたっぶー」とみっちゃんが歌うように真似た。
「でも今は違うよ。君は賢くて頼もしい僕たちの家族だ。歓迎しているよ」
「なぁタブーってどういう意味なんな?」
よっくんが佳奈恵さんい訊いた。佳奈恵さんは困った顔して益司さんに目をやった。
「それは、父さんがお坊さんになることを拒んだから? おじいちゃんは父さんが嫌なの?」
益司さんも佳奈恵さんもおばあちゃんもぼくを見た。でもおじいちゃんだけはうなだれたままだった。つんのめるようなすごい角度で。まるで首の骨がなくなったみたいに。
「お義父さんが、つまり君のおじいさんが、君のお父さんがこの家を、白雲岳を出て行ってしまったことを、息子に対してたいそう厳しくしてしまっていたと、それは後悔していたんだ。白雲岳の百日修行を子供の時分から課していたし、読経を誤れば蔵に閉じ込めもした。精神が研ぎ澄まされるようにと食事も最低限だったと聞いている。それでいて10歳年の離れた妹が生まれれば女の子は猫可愛がりした、少年時代のお義兄さんが寺を出ていきたがるのも当然だったかもしれない」
ぼくはおじいちゃんを見た。ちょうどそのタイミングで口からよだれが出て一筋垂れた。
「その若いころの禁欲のせいで、父さんは今若い女に入れ込んでるんだね」
ぼくはわざと大げさに肩を上げて言ってみた。
ちょっとは場が和むかと思って言った言葉だけど、おばあちゃんと佳奈恵さんの目は冷めていて、これぽっちも笑わなかった。ぼくの言葉も視線も持って行き場をなくして、ぼくはいよいよ泣きそうになった。
発端のおじいちゃんといえば、ぼくの声なんてまるで届いていないように見える。おじいちゃんの耳はわざわざ塞がなくても聞こえないようにできてるんだろうか。
隣に座っている益司さんがふっと肩を揺らして笑い声をあげた。それから益司さんは笑ってしまったことをごまかすように握った手を口に当てている。
「えー、あのさ、禁欲のせいかどうかは別として」
益司さんが言葉を続ける。
「君のお母さんがお父さんを愛していたことは、おととしとその前の夏の二度の訪問で伝わっていたよ。それから、君のお父さんにとっても、君のお母さんは唯一無二の存在だったと思うんだ。妻としても、仕事のパートナーとしても」
「母さんが危篤ってときに、そのときもあの女と旅行に行ってて、その死に目にもあわなかったのに? それに仕事のパートナーだったのは、母さんが父さんの会社にいたころのことで、その時母さんが開発したセキュリティソフトがバカ売れしたからで、父さんは母さんの利用価値を見出して妻にしたってのが、ほんとうのとこだと思うんだけど!」
ぼくは叫んだ。
そしてまたやるせなくなる。ここにいる善良なひとたち、平和な家族をいやな気持にさせてしまう。こんなに穏やかな食卓なのに。
わかっていてもぼくは自分を止めることができなかった。
最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。
