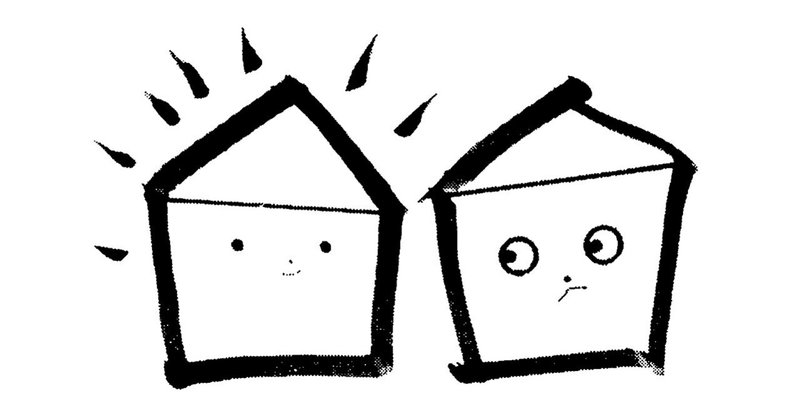
遊んで欲しい童具に子どもが関心を示さないときには、親がまず遊んでみせる
童具を子どもに買い与えても、押しつけて「遊びなさい」と無理強いすれば反発を買うだけでかえって逆効果です。たとえ直接、口に出して強制しないとしても、顔色や態度に表れます。子どもがそれを察知すればやはり拒否反応を起こして童具で遊ばないこともあります。
そこで、ふたつの解決策を紹介しましょう。
第一の方法は買ったおもちゃを、親からではなく、親戚とか近所の人に手渡してもらうことによって、子どもが喜々としてその童具で遊び始めたという例があります。
こうした子どもの心理を把握して、たまには親から子へという与え方の図式を転換させてみるのもいいでしょう。もちろんこれは心理的働きかけにおいての転換です。つまり、今まで親から与えられっぱなしだったものへの興味を、別の角度からの与え方で積極的な興味にしむけるようにしたのです。
次には「となりの芝生はよく見える」の諺もあるように、他人が持っているものは欲しいし、他人のやっていることは自分もやってみたくなるのが人情です。これは大人も幼い子どもも同じことのようです。
とくに子どもにとって、その“他人”がもっとも信頼している母親の場合なら、いっそう欲望は強くなります。そういう心理をうまく逆手にとり、母親がいかにも楽しそうに黙って遊んでいる姿を子どもに見せると、子どもは「なんだろう?」と近づいてくるはずです。子どもが近づいてきても、すぐに童具を与えず、なおも親が遊んでいるようにすれば、子どもは自分もやってみたい強い衝動や欲求を感じ、しばらくすると親の手からおもちゃを奪って遊び始めるでしょう。これが第二の方法です。
しかし、こうした心理作戦がいつもうまく成功するとは限りませんし、何度もくり返し行っていれば、子どもの心に“免疫”ができて母親の行為を演技として無視する恐れもあります。大切なのは、子どもの言葉や態度、また感情の動きを見つめるだけの余裕を持ち、適切なチャンスをつかまえて子どもの自発的な意志を尊重することです。
そして、なお理想的を云えば、大人が童具で遊ぶことに積極的な興味を持つということでしょう。そうすれば、演技をする必要などはなくなります。童具には大人にも興味を抱かせる秘密がいろいろ隠されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
