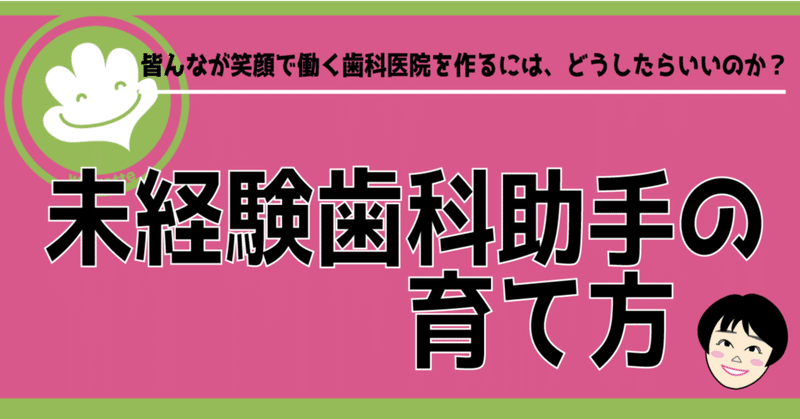
未経験歯科助手を採用したら・・・。
昔々昭和の時代の歯科医院では、未経験の歯科助手を採用して、歯科医院の院長先生仕様に育てたものです。
ところが、最近の歯科医院は経験のある歯科助手を好む傾向があるように感じます。
これは、育てることの難しさからくるのかもしれません。
新人教育は難しい。
私も、年齢と共に新人教育を任されるようになりました。
歯科衛生士の新人もいれば、未経験で歯科助手を始める人もいます。
それぞれに、接し方を変えます。
新卒歯科衛生士の場合には、3年間の歯科衛生士学校での教育を経て、就職したのですから、ある程度のことは理解できていると、思っています。
だからこそ、プライドを傷つけるようなことは言えません。
どこまで理解できているのかがわからないので、こんなこと注意して大丈夫だろうかと、非常に気を使います。
それに比べて、未経験の歯科助手は、患者さんくらいの知識しかありません。
しかも、歯科の治療を受けたことのない人は、歯科医院にさえ行ったことがありません。
そんな人に1から教えるのですから、人手不足で採用したのに大丈夫?と、他のスタッフからは不評です。
聞こえるように、
「だから、経験者を採用して!って先生に言ったのに、なんで未経験とるかなぁ」
と、言われた人もいます。
「まぁ、そう言いますけど、あなただって最初は未経験歯科助手ですよね!」
と、言い返したいところです。
だから、最近の未経験歯科助手は、メンタルもタフでないと、やっていかれません。本当に大変です。
未経験歯科助手を育てる!
『未経験歯科助手は覚悟がないとなれない・・・。』というそうですが、
私は短大生の頃、普通にアルバイトとして歯科医院で働き始めたいわゆる歯科助手を舐めてるタイプでした。
だからこそ、未経験歯科助手の気持ちがわかるんですよね。
もっと、暖かく見守りましょうよ。
先生も含めて、同じ事を何回も質問できる雰囲気を作りましょうよ。
と、思っています。
ほら、ブラッシング指導だって、最後に患者さんに、
「わからなくなったら、何回でも質問に来て下さいね。
覚えてない!なんて怒りませんからね。」
と声をかけますよね。
未経験歯科助手教育も同じです。
よほどの天才でない限り、1回で覚えるなんてできません。
いいんですよ!何回も何回も同じことを教えているうちに、
いつか覚えます。
とは言っても、人材不足で採用したのですから、1日も早く一人前になってほしいですよね。
そのためには、教える順番とメリハリが大切です。
1〜3日間に覚える事。
4〜10日間に覚える事。
〜1ヶ月に覚える事。
1ヶ月〜3ヶ月に覚える事。
と、分けて教える事です。
最初はほとんど患者さんですから、専門用語禁止で、
歯科の知識がなくても出来ることから教えていきます。
特に初日は、緊張していますから、歯科の知識満載の仕事を教えても、
自信をなくすだけです。
それよりも、新人でも頑張ればできる事を1つ完璧に覚えるよう指導します。
例えば、これだけは今日中に完璧に暗記して下さいと話し、
覚える時間を与えます。
まず最初に完璧に覚えて欲しいのは、朝のルーティーンです。
なぜかと言うと、
歯科の知識がなくても、できることと、
この朝の仕事さえ完璧にできるようになれば、
たとえ、他のスタッフが遅刻や急に欠勤したとしても、
とりあえずは、患者さんを迎えることができるからです。
こんな簡単な仕事、時間を与えてまで覚えなくてもできるようになると、
思っていらっしゃる先生は多いと、思いますが、
他にもスタッフがいたりすると、何ヶ月も全くやらずに過ぎてしまう事は
よくある事なんですね。
急に、いつもやってくれているスタッフがお休みで、
バタバタする事ありませんか?
これは、最初にきちんと覚えなかった事が原因です。
たとえ、やらずに過ぎたとしても、
正確なメモをとっていたら、そのメモを見て、確認しながら動くことができます。
それから、時間を与えて覚えてもらうことで、
この仕事は、間違えないよう覚えなくちゃいけない仕事と、
認識してもらうこともできます。
時々、覚えているかどうか、テストするのもいいと思います。
間違ったからと、叱るのではなく、確認のためのテストですから、
正しいことを、再度覚えればいいんです。
笑顔で、テストするのが、コツです。
指導する順番
すぐにできる仕事から教える。
指導する順番ですが、なんの脈絡もなく、次々に説明する人がいます。
中には、「歯科は同じことの繰り返しだから、早く覚えて!」と、
あれもこれも説明する先生もいます。
言いたいことは、わかりますが、
同じことの繰り返しと言われても、未経験歯科助手には、
なんのことだかわかりません。
そうではなく、せっかく採用したのですから、
初日でもできる仕事から、指導します。
だから、朝のルーティーンと加えて、帰りのルーティーンです。
1日の最初と最後の仕事は、掃除をしたり、洗濯したりと、
歯科の知識がなくてもできる仕事満載です。
きっと、自信を持って働けると思います。
そして、仕事が終わったら、
「やっぱり、1人増えると助かるね〜、ありがとう!」
と、声をかけてあげて欲しいです。
この1言で、新人さんはホッとするはずですし、
よし!明日からも頑張って働こう!と、
やる気になります。
「仕事なんだから当たり前じゃん!」と、
知らん顔する人が、います。・・・結構います。
これでは、新人さんは、
もしかしたら、できない自分が足手纏いなんじゃ・・・と、
落ち込んで帰ることになります。
最悪・・・「辞めます。」
なんて連絡が入ることにもなりかねません。
診療時間内の最初に覚える仕事は、患者さんの誘導と片付けです。
どちらも簡単そうですが、できない人もいます。
難しいのは、患者さんへの言葉がけです。
ある程度社会経験のある人なら、すんなりとできるようになりますが、
新卒となると、言葉遣いを教えるところから指導します。
例えば、患者さんが来院したことを先生に伝える場面で、
「患者さんが来ました。」
では、NGですよね。そこはやはり、
「患者さんがお見えになりました。」とか、
「患者さんがいらっしゃいました。」と、言って欲しいです。
若者にとっては、普段使っている言葉ではないので、
切り替えが難しいですが、根気よく指導していくしかありません。
言えてないなぁと、感じたら、何度も一緒に口に出して
体で覚えるのがいいようです。
もう一つの片付けは、少しだけ知識が必要になりますが、
最初に絶対にやってはいけない事を伝えます。
例えば、ハンドピースを水につけないようにするとか、
バーを水に流さないよう注意するとかです。
そのためには、下げたバット類の中から
最初に水につけてはいけない物をどかすことを伝えます。
この片付けの作業工程を、何度か一緒に行います。
「バットを下げたら・・・」
「ハンドピースとバーをどかす!」と、
声に出して言いながら一緒に行動します。
ここで、リズミカルに言いながら動くと、
体に染み込みます。
さぁ、ここでも
「〇〇さんが片付けてくれるから、楽〜ありがとうね。」
と、お礼を言いましょう。
言われて嫌な気分になる人はいません。
治療の準備ができるようになるには・・・
次にできるようになって欲しいのは、治療の準備ですよね。
治療の準備とは言っても、
治療の内容を理解し、準備できるようになるのは、まだ先です。
なにしろ、4日目ですから。
まずは、理屈抜きで、器具の形と名前を覚えます。
とは言っても、いきなり次々に教えてもいけません。
例えば、最初は歯を削る器械に絞って教えます。
コントラやタービンなどは、頻繁に登場するので、
覚えやすい器具です。
物と名前が一致するように教えます。
加えて、バーとポイントを教えます。
いよいよ治療の準備です。
虫歯の小さい順に教えます。
1日目は、CR充填の器具器材の物と名前を覚えます。
全てを並べて、まずは、幾つ使うのかを教えます。
治療の順番に沿って、番号を振り、
物の名前を覚えるよう指導します。
すると、CR充填には幾つの器具を準備するかがわかれば、
帰路でも、復習できます。
この際にも、これがCR充填の準備で、これがインレーの印象・・・と、
次々に教えるのではなく、1日1種類に止めましょう。
1つ1つ丁寧に覚える方が、実は確実で速かったりします。
もちろん、優秀で次々に覚えられる人もいるかもしれませんが、
早く覚えることにばかり神経を使っていると、
丁寧さや正確さが、いい加減になる傾向にあります。
歯科は、医療ですから、丁寧さや正確さはとても大切です。
先生方の中には、早く出来ることに対する評価が高いこともありますが、
仕事は早いけれど、適当な仕事をする人を大勢見てきました。
どちらがいいのか、ぜひ考えてみて頂きたいです。
出来るようになるための練習をする
10日を過ぎた頃から、1ヶ月間で、
セメントの練り方や印象材、石膏の練り方などの練習を始めます。
これは、最初の数日はただ練れるようになるだけの練習で、
しっかりと練ることができるようになったら、
トレーに盛る練習。
トレーに盛るのが上手になったら、
寒天との連合印象の際のタイミングを覚えます。
リズミカルに、先生とのコミュニケーションの取り方
声がけの仕方なども教えます。
ここまでを、リズミカルにできるようになったら、
いよいよ石膏に注ぐ練習です。
石膏の練り方のコツや、
全額トレーの場合には、必ず一方向から注ぐなどの
コツを教えます。
最初は、やって見せて、
次に何度も練習します。
バキュームの仕方も指導を始めます。
これまでの10日間は、先輩がどんな風にバキュームを入れているのかを、
観察するよう話をしますが、
多分、何をどう見たらいいのかが、わからないのが現実です。
そこで、バキュームの目的を頭に入れてもらいます。
ただ、口腔内の水を吸えばいいのではないことを、伝えます。
加えて、先生によって、こんな時はこうして欲しいという希望がある場合には、
伝えることが大切です。
レントゲンの準備や、タブレットの使い方なども必要に応じて、指導します。
これらの指導は、時間のある時に、行なって欲しいと思っています。
患者さんのレントゲンを撮りながら、
「ちょっと来て。教えるから・・・。」
というのは、辞めて頂きたいです。
なぜなら、患者さんの撮影準備中となれば、
どう考えても、質問することは憚られますよね。
聞きたいことがあっても、聞き返すことのできない状況の中での指導は、
覚えられない・・・と、思った方がいいと思います。
よくある光景で、
「わかった?」
「はい・・・。」
と、終わりますが、理解できていないことは多いからです。
私は、質問したい性格なのですが、
「はい」と、返事をするしかなかった記憶があります。
今だったら、図々しく
「すみません、1度で覚えられそうもないので、あとで質問させて下さい。」
と、言っていると思います。
実は、この質問できる雰囲気を作ることが、
未経験歯科助手を育てる上で、重要と考えます。
もし、そのような雰囲気のない歯科医院であるならば、
先生が率先して、他のスタッフに声をかけて欲しいと思います。
ただ、こんな話をしても、そっぽを剥かれることもある事を
覚悟して話して下さい。
素直に協力してくれた時には、
「うちのスタッフが、素直な人ばかりで良かった!ありがとう!」と、
伝えて下さい。
ここ大事ですよ!
繰り返しで、能力アップする
3ヶ月までは、とにかく基礎的なことを繰り返して、
スピードアップする時期です。
スピードアップといっても、先ほども言いましたが、
丁寧さと正確さは、譲れません。
毎日毎日働くうちに、歯科の仕事は同じことの繰り返しの意味が
わかってくる時期でもあります。
わかってきたからこそ、
なんでだろうと疑問を持つ時期でもあります。
ですから、先生から時々、
「わからないことはある?」
と、声をかけてあげて欲しいと思います。
たとえ、その質問がものすごく基本的な事で、
こんなことも分かってないのか!と思ったとしても、
思ったことは心の中に置いておいて、
説明をして欲しいと思います。
忘れてはいけないことは、
数ヶ月前は、素人だったという事です。
2年も3年も学校で学んだわけではないので、
ぜひ、広い心で、接して欲しいと思います。
そろそろ、歯科治療についての知識を覚える時期です。
今までは、理屈抜きで器具の名前などを覚えましたが、
歯科の治療の知識を覚えることで、
なぜこの器具が必要なのかが、理解できるようになります。
歯科の知識については、
予防から、
虫歯の進行に合わせて順番に話を進めると、わかりやすいと思います。
これも、患者さんに虫歯の治療を説明するのと同じです。
専門用語は使わずに、説明してあげて欲しいと思います。
3ヶ月6ヶ月と過ぎ、1年経つと
様々な器械のメンテナンスなども、覚えるようになります。
それらも、忘れないようメモするよう伝えましょう。
まとめ
未経験歯科助手を雇うと、育てるのに時間がかかり、
できるようになったら、辞めていく・・・と、
こぼす先生は大勢いらっしゃいます。
辞めないよう、
笑顔でいっぱいの歯科医院を、作って頂きたいと思います。
さて、そうは言っても、
「暇じゃないから、質問されても困るんだよね。」
という声が聞こえてきそうです。
そこで、未経験歯科助手のためのカンニングメモとも言うべきmemoを
現在制作中です。
未経験あるいは、ブランクのある新人歯科助手の採用が決まったら、
お使い頂きたいと思っています。
今回ここで話した内容に沿ったmemoです。
文房具屋さんでノートを購入するのなら、
ぜひこのmemoを使って欲しいと思います。
と言うわけで、現在制作中です。
第1弾を、次回お届けできるよう準備中ですので、
乞うご期待!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
