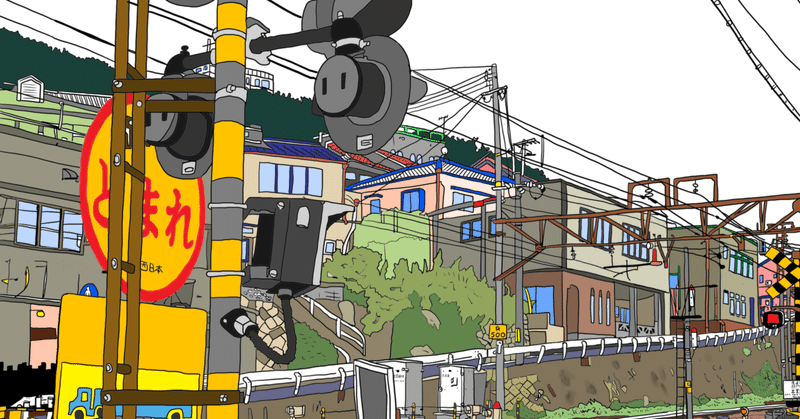
ミニコミ(今で言うジン)への参加
大学時代、と言うか、正確に言えば、大学を出て就職もせずにフラフラして土気色の顔面で街を徘徊していた頃、私にお声掛けしてくれたのが、表題にありますような、当時はミニコミ誌と呼ばれていた、小冊子の編集長でした。
編集長との出会いは古く、大学の書籍部という小さな書店の中での事でした。当時のそこには「ガロ」をはじめ、青林堂の書籍がふんだんに陳列されていて、文化的渇望を孤独に感じていた私には、心のオアシスとなっていました。
そこのコピー機に、だいじなレポートの原稿を忘れてきてしまったので、問い合わせに行ったら、まだ編集長ではないその書店のお姉さんは慌てて、だいぶ慌てて私の資料を一緒に探してくれました(しかし見つからなかった)。
時が下って(遡る事はない)、どういうキッカケでそのお姉さんと再会したかは、あんまりここには書けないような、チョットした、いや、大きな交流があったからなのですが、SNSもない時代に、よくぞまあ交流していたな、顔も知らずに、と言った感じなので察して下さい。運命的な、奇跡が持続していたと言っても過言ではないです。
それである日、いよいよ会いますか、という約束をしたので、当時住んでいた都内某所の営巣地から、中野の書店街に出かけました。
ところがなかなか会えない。大体、顔や服装とかよく分からないまま、よくも約束なんかしたものだな、認めたくないものだな、と思うのですが、基本的に私の方がウロウロしまくって、ようやく一時間後位に、そのお姉さんを発見しました。何か、本を立ち読みしていて、その横顔が、見覚えのある、大学書籍部のお姉さんだったので、若干ビビりました。
その編集長のお誘いにより、中野の、木造の喫茶店に入りました。木造だけあって、コーヒーを運んでくる店員さんの足音でさえもギシギシ軋むような感じの店で、一般的なおしゃれさんは敬遠するような一種陰惨な感じさえ漂う、薄い色の木目は、もしかしたら紙か段ボールで出来ているようにも思われる頼りなさがありました。
そこでコーヒーを飲みながら、ミニコミ誌の事など、話しました。何を具体的に話したかはよく覚えませんが、店内にかかったクラシックの曲に、私が「パヴァーヌ」と反応して言ったら、編集長が何も答えなくて、その曲を聴いていたのが、強く印象に残っています。
編集長は慌てん坊でしたが、どう考えても頭のキレが違いました。あと、お姉さんだと思っていたら、実は一つ年下でした。そういう、私とは全く別世界の文化を背景に持っておきながら、何でかどしてか、共通する、目には見えないものがあり、かつ、それらは会話によって、簡単に共有できるものでした。不可思議な記憶なのですが、まあ、不可思議なものはいつまで経っても不可思議の範囲からは外に出ません。
その内、ミニコミ誌のタイトルが決まり、編集長が集めた人達の紙原稿も集まったので、私と印刷・製本の作業をしました。大学の同窓会的な機関の建物内にある、古くさ〜いコピー機にてそれを刷りました。当然ですが対価を払ってです。対価の割には何回も印刷機の中で紙詰まりが起こるというスグレモノでした。製本は、文化系サークル会館という建物内で実施。この辺、私が既に経験していた、漫画研究会での製本の知識が役立ちました。編集長は編集長で、その事をよく知っているようでした。
100部程、完成させたミニコミ誌は、今となってはどこへ無料配布したのか、全く記憶に無いです。おそらく、編集長が、色々な所、主に都内の各種お店に、頭を下げて回ってくれたのだと思います。肝心の私が何を載せたかというと、たった4頁の漫画でした。これ、戦力になるのかな?と思ってましたが、他の人が文章ばかりだったので、それなりに存在感を示せたのではないかと振り返ります。
その後、細々、出版を重ねたそのミニコミ誌は、第9号までは確実に出したのを覚えていて、何回かは、私が表紙も担当しました。白黒のザラ紙のA5版のソイツが、どれだけの文化的威力を発揮したかは定かではありません。私の手元にも、本当はもっとあるはずなのに、今すぐに手元に出せるのは、第9号の1部だけになってしまいました。それほどまでに、強い時代の波がうねって砕け、強い夏の日光や冬の降霜などによってミニコミ誌は傷み、すさんで、滅んでいったのでしょう。それは、朽ちたという事でもあるのでしょう。中野のあの喫茶店は朽ちずにまだあるだろうか、ある訳ないな。と、思うと、葬送曲のメロディが、またやたらとしっくりきて、何か泣きそうにまでなってきました。
編集長とは、受験の合格発表の番号が羅列された立て看板のある、東京大学の構内で会ったのが最後になりました。文化の薫り高く、彼女からは萩尾望都を学び、私からは白土三平を紹介したりして、これといった盛り上がりは特に感じられない、とある女子と男子との交流でした。ワタクシ的には、編集長にはよく叱られましたが、実際には存在しない妹のように思っていた節があり、そのせいで、かえって彼女からの薄い恋心に気付く事はついぞなかったのです。最終的に、上野駅のペデストリアンデッキの上で、何かもう別れがたいような感じがする、ほの暖かい春の夜風が吹く中、私は、編集長の今夜の宿の事に一言も言及せずに「あっ終電が来た!」と言って、地下鉄銀座線に飛び乗って帰ってしまいました。ここに至って「あれ?」と、違和感を覚え、何も始まっていない事にケリをつけてしまったと言うか、何か正体の分からない不安に駆られながら、腕組みをした自分の姿を、地下鉄の窓に見ていました。
東京ともミニコミ誌とも文化とも、一旦お別れをした私は、その後、尾道に帰郷し、段々と腐っていきます。腐敗臭を撒き散らしながら、泣いたり喚いたりする日を迎える事になります。そんな時の事は具合がどうかするのでここには記しませんが、何か、振り返ってみるに、ミニコミ誌よりも、だいじなものを、置いてきたような気がしてならないです。そしてそれはもう二度と来ない季節の事で、もしかすると、東日本大震災の巨大な津波にのまれているかも知れないのです。それは想像の域を出ないですが、お前、この記事でもっとミニコミ誌の事を紹介せえよ。とは、最後に思いました。
ご拝読ありがとうございました。何だか今回長くなり失礼しました。また書きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
