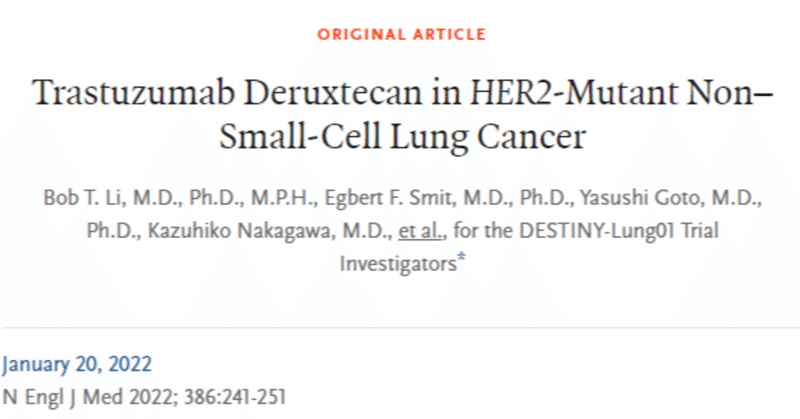
HER2 mutant 非小細胞肺がんに対するTrastuzumab-Deruxtecan (DESTINY-Lung 01試験)
N Engl J Med 2022 ; 386: 241-251
HER2変異NSCLCは全体の3%ほどを占め、女性、やや若年患者、never smorkerなどと関連があり、他の遺伝子変異NSCLCより脳転移の割合が高く予後不良である。HER2変異NSCLCに対するICIの奏効割合は7-27%と比較的不良。肺がんのHER2-targeted therapyのcriteriaは設定が難しく、乳がんなどと比較して頻度も稀である。これまで行われてきた抗HER2療法の効果は一定しないが、T-DM1は44%の奏効割合と報告あり。
Trastuzumab deruxtecan (T-DXd)はHER2変異NSCLCに対するP1試験でORR 72.7%であり、かつHER2蛋白の発現に関わらずHER2受容体-抗体薬をinternalizeしやすいことが確認された。
DESTINY-Lung 01試験はHER2過剰発現およびHER2変異NSCLCに対するT-DXdのP2試験。HER2変異, copy数はOncomine Dxで検索し、ほとんどはexon 20のinsertion (86%)。その他はキナーゼドメインであるexon 19, 20のSNV、あるいは細胞外ドメインであるexon 8のSNV。copy数増加は95%CIの下限値が4以上と定義。HER2蛋白の発現はIHCで1+~3+と判定。抗HER2療法の治療歴のある患者は除外されたが、afatinib, poziotinib, pyrotinib等のHER2 TKIは登録可。非感染性ILDの既往および画像でILD疑いの患者は除外。T-DXdは3週毎に6.4mg/kgで投与。
primary endpointはORR。SecondaryはDuration of response (DOR), DCR, PFS, OS。探索的評価項目としてTime to response (TTR)と奏効のpotential biomarker。
91例の患者が登録。内訳は34%がアジア人, 44%が白人。PS 0が25%, PS 1が75%, HER2のキナーゼドメインの変異が93%, 7%は細胞外ドメインの変異。治療ライン中央値 2。66%にICI既往あり。36%にCNS転移あり。Never smoker 57%, 肺切除既往 22%であった。
結果
55%の患者が奏効。1例がCR、残りはPRであった。DCR 92%。治療歴やCNS転移の有無によらず奏効は認められた。脳転移例の8/14例 (RT歴あり), 10/19例 (RT歴無し)に各々PRを認めた。median DOR 9.3ヵ月。median PFS 8.2ヵ月。median OS 17.8ヵ月。CNS転移のあった患者のPFSは7.1ヵ月, OSは13.8ヵ月であった。
AE≧G3は69.2% (内、薬剤関連46.2%)で好中球数減少、貧血、悪心、疲労等が中心。ILDは26%(24例)に認められ、G1 3例, G2 15例, G3 4例, G5 2例であった。ILD発現までの中央値は141日 (範囲 14-462日), 持続期間は43日だった。転機として13例が改善、1例が後遺症あり、2例が未回復、6例が治療中、2例死亡。肺切除の既往のある患者の内では、8/20例がILDを発症した。

治療効果とbiomarkerの関係は上図の通り。HER2 IHC過剰発現や増幅に関係なくどのmutationに対しても効果があった。
HER2過剰発現ではなく、HER2遺伝子変異に対する結果というところが興味深い。T-DXdはHER2蛋白をターゲットとして、DXdを放出し抗腫瘍効果を示すという薬なのに、何故HER2 IHCの発現が効果予測マーカーになっていないのかが謎ではある。何故T-DXdがHER2変異NSCLCに対し抗腫瘍効果を示すかについては、discussionでも「今後の研究が必要」とまとめられている。
HER2変異はHER2受容体のinternalizationとT-DXdのuptakeも促進することが治療効果につながる可能性は示唆されているが、HER2発現が無ければそもそもuptakeも出来ないのでは……。今一つ納得がいかない説明である。
Mypathway試験でTmab+PERがORR 21%, T-DM1の試験では44%であったことから、純粋にHER2経路を抑えることが必ずしも治療効果に繋がっていないことが分かるので、プラスαの何かしらの機序が働いている可能性。ADCC活性など免疫学的作用がその一つになるのだろうか?
AEについてはILDが26%の患者に発現しており、臨床医として何とも恐ろしい薬剤であることは確かである。第一三共HPの適正使用ガイドでは
・ 年齢 <65歳 (HR 1.56)
・ 日本人 (HR 2.08)
・ 肺合併症 (喘息, COPD, ILD, 肺線維症, RT肺臓炎等の既往) (HR 1.75)
・ 腎機能低値 (HR 2.73)
・ 診断からの期間>4年 (HR 1.82)
・ 初回投与量 > 6.4mg/kg (HR 2.92) (6.4mg/kgジャストは1.30)
・ baseline SpO2 <95% (HR 2.14)
が統合解析によって導かれたrisk factorと記載されている。それ以外にも非特異的なILDのrisk factorとして、
・ 肺手術後
・ 呼吸機能低下
・ 酸素投与
・ 肺へのRT既往
・ 多剤併用化学療法
などが挙げられている。どうも肺に慢性炎症の存在があると良くない印象。
良い薬なのは確かなのだがこれだけriskが高いと何とも考えてしまうなあ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
