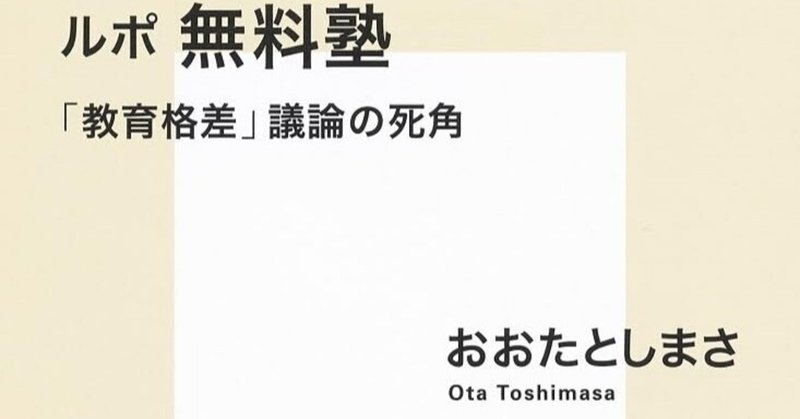
【書評】『ルポ無料塾 「教育格差」議論の死角』(おおたとしまさ・集英社新書)
「教える技術はさしたる問題ではない。子どもの「わからない」に寄り添う気持ちが重要」(P42)
この言葉が、無料塾の本質を端的に表していると感じた。
無料塾に通う子どもたちに必要なのは、勉強で得られる知識そのものではなく、「この世の中にはまだ善意が残っているという手触り」(P72)である。その手触りこそが、子どもたちに対する最大の励ましになる、というわけだ。
私が関わっている風俗や売春の世界でも、善意ある大人との出会いがないまま、子ども時代を過ごした女性が少なくない。彼女たちに声をかけてくるのは、見返りを求める大人、自分の都合の良いように利用したがる大人だけだった。
一切の見返りを求めず、純粋に善意だけで自分のことを心配して、手助けをしてくれる大人がいる、親以外の大人から愛されている実感を得られる、という事実に触れた経験は、その後の人生を生きていく上で、どんな知識や情報よりも役に立つ「他者を信頼する/信頼される力」を育むベースになる。
善意の手触りを得られない場合、人は「なんで自分だけ?」と傷つき、「どうせ、自分なんて」と自らを卑下し、最終的に「どうせ、お前らは!」という不信と攻撃のループに陥っていく。
教育格差を放置する、ということは、この他者への不信と攻撃のループの連鎖、それによって個人や社会が傷つき続けることを放置する、ということに等しい。
「能力」を競い合って他者を蹴落とすのではなく、それぞれの得意技=「機能」を持ち寄ってチームや組織で活躍することが称揚される社会になれば、「格差」は「分岐」に変わる。
違いを無理に消したり、標準化しようとするのではなく、それぞれの持っているトンガリやデコボコをうまく組み合わせて、チームとしての力を最大化する社会=「差があっても、誰も嫌な思いをしない社会」を目指すべき、という著者に主張には、大いに共感できた。
読者は、知られざる無料塾の現場の事例を通して、自らの教育観や能力観の問い直しを迫られるだろう。
本書を通して、「大変だけれども、かわいそうではない」子どもたち、それを支える熱量の高い大人たちの「手触り」を、ぜひ感じて頂きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
