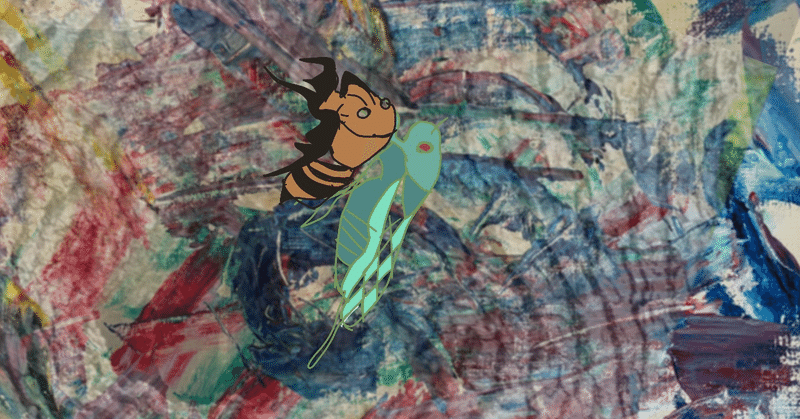
蝉の断章の記憶 第7話
全集を読み終えると季節は夏だった。強い陽射しが朝の窓から入り込む。蝉の合唱が始まって蒸し暑くなった。あれから自分の作品のことはすっかり忘れて、読者として人生を満喫した。
しかし、ただ漫然と日々を過ごしていたのではなかった。読んだ本には文字の形をした原石が埋もれていた。それを採集し、記憶の標本箱に陳列し、時々、出しては眺めた。飽きると、公園のベンチで太陽の光を浴び、好奇心で近づいてくる小鳥に微笑んだ。
わたしにはセンスがある。これは事実だ。そしてそれは運命を待っていた。だとしたら準備しておく必要がある。季節は巡り、再び羽化の時が来る。もう一度、いや、何度でも謳うことになる。創作用のメモが毎日、貯まっていくのは楽しかった。今度は、第一作のようにいきなり情景が浮かぶことはなかった。でも構わない、もうわたしは以前のわたしではない。根拠のない自信がわたしを支配していた。
そろそろ時期が来ていた。背中がむずむずするから? 部屋を暗くして自分の作品の書かれた本を机の上に置く。すると待っていたようにそれは輝いた。読み始める。初めてこの本を手に取るつもりで。新鮮な感覚。読み終えた時、わたしは震えていた。瑞々しい感性が散りばめられていて、文字にそれが宿っていた。羽化の準備が整ったとわたしは直感した。
ただ、何か引っかかる部分がある。最初から読み直そう。驚いた。
『蝉の断章の記憶』
と、冒頭のページの真ん中に記されていた。わたしは、元々タイトルは滲んで読めなかったのを思い出した。だが、今は、はっきり読めた。それはわたしが書いたものではなかった。だが、書いている間、あるいは書き終えてから今までの間に試行錯誤し、最後に決めた処女作のタイトルそのものだった。まるで、誰かが側で盗み見して横取りして勝手に書いたみたいだった。
わたしは文字を指でなぞった。作品のタイトルは物語の全体を示す看板のようなものだ。いや、それだけでなく今後のすべての作品の——わたしという作家(もうわたしは自分を作家と信じていた)の——DNAとなる重要なものだ。わたしの筆跡でないこのタイトルを、いったい誰が書いたのだ? それが自分のものでないとしたら、わたしの作品とは言えないじゃないか。誰かが、「あれは俺が考えたものだ、オリジナルじゃない」と言うかも知れない。場合によっては著作権の侵害だと。わたしは何とかタイトルの文字をインク消しで消して、書き直した。しかし翌日見ると、再び元の誰かの文字に戻っていた。
不安になったわたしは立ち上がり、部屋を歩き回った。少し開いた窓の隙間から風が流れ込んで頬に触れた。ヒヤリとした感触。そのせいで、わたしは冷静さを取り戻した。
待て、待て。最初見た時、確かにタイトルは読めなかった。それは、わたしが考えたものではない。そして今、判読できるように変形したのは、何か化学変化と偶然が重なってそうなっただけの話だ。繰り返すが、わたしは執筆を始めてからタイトルについて想いを巡らしていた。そして得た結論が、書かれたタイトルとたまたま一致した。
あくまでも、この物語を始めたのはわたしなのだ。逆に言えばわたしが抵抗して始めないこともできた。始めなければ終わらなかったし、この作品は生まれて来なかった。結局イニシアティブはわたしが握っていた。それに、同名のタイトルで、違う内容の作品なんて、音楽の世界にはよくあることだし、同姓同名の人間だって沢山とは言わないまでも実際、いるじゃないか。商売の世界なら、商標でもめるケースは多々有る。でもこれは一品製作の、芸術の世界の話なのだ。たまたま別の人間が同じ命名をしたとしても、要は、中身の勝負なのだ。
タイトルを変更しようか? ちらっと考えた。でも、わたしにとって、このタイトルは魅惑的だった。誰かの落書きのようなこんな文字なんて、どうせ誰も知らないだろう。書いた人間だって多分覚えていないだろう。将来問題になることもないだろうと腹を括った。
さてと——。わたしは次作のメモを整理し始めた。最初にタイトルが浮かんだ。
『○○の冒険』
今度はしっかりと自筆で書き込もう。何かが生まれる前の鼓動の高まりを感じつつ万年筆を手に取った時、玄関のチャイムが鳴った。インターホンに映った姿に見覚えがあった。フェスティバルで全集を買った男だった。彼は挨拶の後、手に持っているものを見せた。最近のカメラは性能が良い。豪華な本だった。掘り出し物? わたしは自分の推測の答えが知りたくてドアを開けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

