
昭和40年生まれ世代にとっての 「赤塚不二夫」とは。
2008年8月。赤塚不二夫が他界した。もう10年前になるのか。。。
昭和40年男の自分がコドモだった頃の何気ない日常生活の中で、気が付けばすぐそばにいつもいるような感じ。
ギャグとしては当たり前のように影響を受けていて、そして学校の教科書とは別の教科書とも言える著作の数々。
あまりにも自分の記憶の中の大きなシェアを占めている氏について、大人になった今、あらたまって“赤塚先生”なんて書くのが照れくさいくらい身近な存在だった気がする。
タリラリラーン ほえほえ~
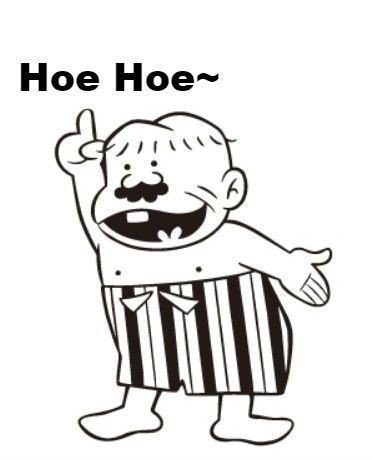
小学2年生くらいの頃に、小学館から出ていた入門シリーズの「マンガ入門」を手に入れたこともよく憶えている。たしか監修は赤塚不二夫だった。いや、挿絵を担当していただけだったのかもしれないが、当時、読んでいると赤塚不二夫にアドバイスされていた気分になっていた記憶は、かすかだがしっかりと残っている。
ちなみにこの入門シリーズは、「野球入門」やら「将棋入門」まで、いろんなの持っていた。特に巳年世代・昭和40年男・女の方々。友達の家に行ってもこのシリーズが何冊か机に並んでいたりしたものだ。表紙・背表紙の装丁、とても印象に残っている。そうそう、甲子園のマウンドに立ったことが自慢の親戚の叔父さんが、「野球入門」ぢゃなく「スケート入門」をくれたことも印象深い出来事として深く脳裏に刻まれている。
それにしても、最近のコドモたちに比べてワシら巳年世代は、何気にいろんな趣味にすぐ首を突っ込んでいた気がする。当時の小学生、好奇心旺盛過ぎ。野球から釣り、ラジオ作り、漫画描いたり、鉄道だったり、切手だったり…ふれ幅も広い!
でも、そんな時代、いつも赤塚ギャグが傍にあった。共通言語だったのか、仲間意識を高めるためのある種のツールだったのか? なんて言えばいいのかわからないけど、赤塚ギャグで同世代が繋がっていたのだ。今風に言うと「共有感」ってやつかもしれない。
それは、他校の連中と一緒になるような地元の水泳教室や、ボーイスカウト的なアウトドアイベント、少年野球、その他もろもろの習い事などの場で顕著に感じられたものだった。
まったく別のエリアの小学生同士が最初はけん制しあいながらも、赤塚ギャグでお互いの心が繋がっていくのである。
赤塚不二夫が病床に臥すようになる少し前の頃だろうか、当時の仕事仲間が、モノクロページの企画で赤塚不二夫を訪ねてインタビューした。
お酒は完全に止められる程身体の具合もよろしくなく、普段から杖をついて歩く状態だったというが、マネージャーだか娘さんだか(前妻だか本妻?)が部屋から出ていって、取材チームと赤塚不二夫だけになったとたん、その杖の持ち手の部分をひねって、そこからウイスキーの小瓶を出したという。
「お前も呑まないとインタビューは始まらん」とかなんとか言われたそうだ。
杖にカラクリの仕掛けがあって、そこに酒が隠してあったのだ。
取材から帰ってきてその同僚から聞いた話は、その後原稿になった部分とはまた違った面白さに溢れていた。(というより、とても原稿にして公けにはできない話だ、下品過ぎて!)
ただ、そんな馬鹿話からは、元気そうではあるけど実はそうでもなさそうな深刻さもちょっと伝わってきたことも憶えている。
08年8月2日に亡くなり、7日の葬儀でのタモリさんの弔辞には心を打たれた。
あなたの考えは、すべての出来事、存在をあるがままに、前向きに肯定し、受け入れることです。
それによって人間は重苦しい“意味の世界”から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を断ち放たれて、その時その場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち『これでいいのだ』と。(タモリさんの弔辞より)
当時ほとんどの新聞社・放送局がこのタモリさんの言葉の中の“意味の世界”というところを
“陰(イン)の世界から解放され~”と書いていたことが気になってしょうがない。(タモさんの発音的にはそう聞こえなくもないのだが。。。)
“赤塚不二夫”的なものを身近に感じて育ったワシら昭和40年世代の人ならば見当が付くように、ここは
“意味(イミ)の世界から解放され~”とするのが正しいと思う。
つまりあの時代を牽引したナンセンスギャグのことだろう。赤塚不二夫といえば“意味”から解放された例のナンセンスギャグ(=意味のわからないギャグ)だった。
赤塚不二夫をセンセーと呼ぶのなら、あえてセートと言えそうな世代の一人としては、そう思わずにはいられない。テレビのテロップで「陰の世界~」と出てからは、週刊誌、Webを含むほとんどのメディアが「陰の世界」としていたけど、多数が正解とは限らないと思うんだよなァ。。。

それにしても、タモさんの言った
「私もあなたの数多くの作品の1つです」。
という言葉もとても印象的だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
