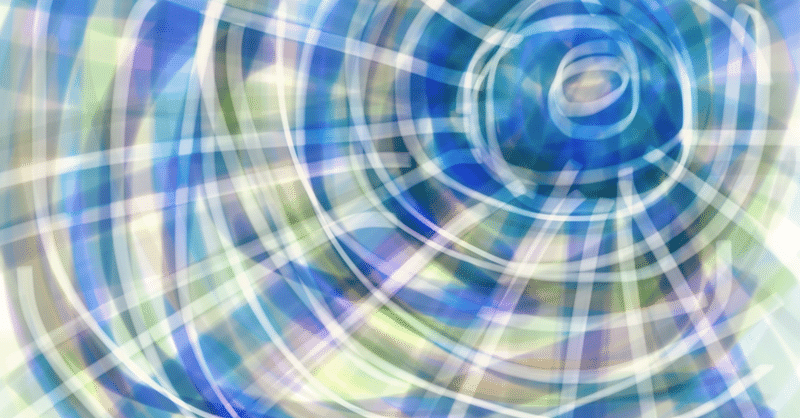
耳底の川
穏やかな風が前髪をめくった時、眺めの良い場所から街を見下ろした時、すれ違った子供が笑っていた時、好きな人と目が合った時。
あ、そうだ、川、と思い出す。
川。
毛先。後ろ姿。
また、彼女に会うことはあるのだろうか。
随分と久しぶりになってしまった。
前に故郷へ帰ってきたのは、3年くらい前か。毎日を消費していると、季節が変わっていることにも気付けずに、年月だけが経ってしまう。あっという間だ。
飛行機に乗り、電車に乗り、駅のホームを踏んだ。風が吹き抜ける。目をグッと瞑り、パッと開けると、匂いがした。この町の匂い。いつも私のそばにあったものだ。長く離れていたのだと実感する。改札を出ると、雲が多いのに外は明るく、少し離れた空には青空が見えている。光が射して空気が煌めく。美しいと思う感情にくっついて、脳裏に出てくるあの場所。
大きな川。
水面と合わさる髪の毛の端っこを思い出す。
あの光景は、美しいこと・楽しいことと紐でくくられていて、一緒に引っ張り出される。
それは重りとなり、私が私自身を手放してしまいそうになった時に、引き留めてくれる。
彼女と2人でよく遊びに行った、あの川。私達はセーラー服を着ていて、まだ17歳だった。同じクラスで隣の席。最初に話しかける理由なんて、そんなものだ。
彼女は優しくて穏やかで、誰かが傷をつけるのなんて簡単なのではないかと心配になるくらい、澄みきっていた。
教室にいる時間だけでは足りなかった。町は田舎で、ファミレスもファーストフード店もない。行くところがないので、人気のない河原で、座って話をした。テレビ番組の話。担任の先生の話。隣のクラスの男子の話。向かい合ったり並んだりしながら、何時間でも話していられた。笑い続けた。邪魔をするものは何もない。水が流れる音が寄り添うだけだ。
彼女と似ていて、優しく穏やかな川だった。この町には海もある。川の先は海に繋がっているので、「同じじゃん」と言われてしまうかもしれないが、海はだだっ広くて怖い。川は岸があって、終わりが見えるから安心する。そんな話を彼女にうっかりしてしまったら、「いい場所、知ってるよ」と、連れてきてくれた。人が全然来ないところや、すぐそばに木がたくさん生えているところが気に入った。川の空気に触れていると、彼女がより一層、清く輝いて見えた。どこへでも行けるし、何にでもなれる私達の若さを、透明な水面が吸い込み弾いて、揺れていた。
私達以外の人が来ることは滅多になかったが、あの日は違った。
放課後、いつも通り、小石が敷き詰められている河原に座り込み、向かい合って話をしていた。彼女と私の声だけがあったはずの空間に、急に、男の野太い声が落ちてきた。叫んでいる。自分の親より上の年齢に見える男が、怒鳴ってきた。手をぶんぶん振り回してきて、「どけ」と言っているようだった。聞き取れないその怒鳴り声を受け取らないようにして、彼女と私は走って逃げ出した。後ろを振り返らず、ただ走った。彼女は私の少し前を駆けていた。艶々で透明感がある髪の毛の先っぽが、光って揺れる。水面に似ている。川から少しだけ、連れてきたのかな。
どこまでも走れると思ったけれど、限界はきた。川から遠く離れた道で、私が立ち止まった。彼女はまだ走れそうだったけれど、足音が1つ消えたことに気付いて、こちらへ歩いて近づいてくる。息が上がる。男の人の怒鳴り声は、怖い。足がすくんで、走るどころか立っていることも、ままならなくなった。道端に座り込む。
彼女は小さい両手で、私の耳を包むように塞いだ。私の耳は幼く汚れていなかったけど、大人達の言葉をきちんと拾えた。彼女の手も幼く柔らかかったけど、私を救い上げるには充分だった。
怒鳴り声は鈍く、耳の中をぐるぐる回る。
私の両耳を包んだまま、彼女は口角だけをクッと上げる。笑顔を作ったはずなのに、泣きそうに見えた。あどけない瞳に見つめられる。まるで、この世界に2人きりみたいだ。声を出さずに、唇だけ動かして言ってくれた。「だいじょうぶ」
川の音は届かないはずなのに、遠くで薄っすら水が流れているのが分かる気がする。2人きりみたい。水の中。怒鳴り声の、薄いところと濃いところがぶつかり合って混ざる。
手の温度が耳に移り、じんわりと温まってくると、嫌なものが自然と消えていく。
呼吸が整い、足が動くようになった。
帰り道、私は恥ずかしかった。ダメなところを見られた。弱っちいところ。ダサいと思われていたら、どうしよう。背筋を伸ばして歩いている彼女に何か言われる前に、喋って埋めないといけないと焦り、急いで言葉を出す。
「やばかったね、あれ、ほんと気持ち悪い」
彼女はクスクス笑って言った。
「ああいうこと、生きていればあるよね」
あるのか。珍しいことではないのか。「よくある」と言うように、私の顔を見て、頷く。
そうなんだ。また生きていれば、あるのかもしれないのか。それをもう、知っているなんて。急に自分より大人に見えて、置いてきぼりにされた気分になる。
「そんなの、うんざりだな」
不貞腐れたように、つい言ってしまった。声を出さずに、また彼女が笑う。
笑うと、普段は大きくて零れそうな目が、三日月型にぴったり閉じる。
いっぱい笑ってほしいと思った。
丁字路に辿り着く。2人の家の方向は、反対だ。
「じゃあ、また明日」と手を振り、分かれ道を進む。私は足を止め、しゃんとした後ろ姿が小さくなっていくのを、こっそり見る。夕陽が彼女の歩く先を照らしていた。
あの日と同じように、駅の前の道路に陽が当たっている。
学校を卒業して、私は遠く離れた街に、彼女はこの町の近くの、同じような町に移り住んだ。日常の中で彼女を想う時間が段々と無くなり、連絡はとらなくなった。今はもう、連絡先も分からない。最後に交わした言葉がどれだったかも、見当がつかない。
私は年を重ね、大人になった。彼女も同じく、そうだろう。
去年思い出せていたものが、今年は忘れている気がする。そうやって、少しずつ、輪郭が削れていく。面積が少なくなって、声が遠くなっていく。私達は確かにそこにいたはずなのに、本当のことだったのか、疑う時もある。見失いそうになってしまった時は、耳の底から必死にかき出して集める。内緒話、笑った顔。透明な水。
あの時間が、彼女がいたという事実が、それだけが私を支える。音や光が、記憶の隙間を流れる。今思い浮かべているものを、明日になっても変わらず描けるだろうか。
私の耳はもう幼くない。人並みに起こる、幾つかの出来事が溜まって垢となり、色が変わって別物のようになった。当時の私の耳が、少しは残ってるはずだと信じてすがりつく。
流れていかないで。
離れて日々を過ごし続けるとしても、忘れてしまわないで。
あの子の顔、そして名前。
駅から、次の電車が到着するアナウンスが漏れて聴こえてくる。
辺りを見回すと、自分と変わらないくらいの年齢の女の人が子供と並んで歩いている。キャッキャと話す声が、私の近くまで散らばる。美しい。繋がって、蘇る。
水の音。
透き通りそうな毛先。
三日月みたいな目。
だいじょうぶ。
水の音。
水の音。
あれ、名前は何だっけ。顔はちゃんと覚えている。
いや、顔もぼんやりとしてきた。
水が、通り、過ぎていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
