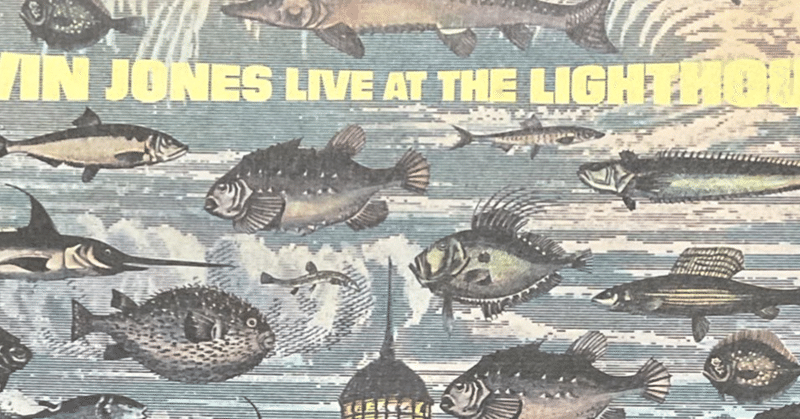
Steve Grossman研究-70-80年代のスタイル変遷を検証する― おまけ:1987年のライブ映像ご紹介(と奏法解説)
私の知る限り、グロスマンは1975年、1986-88年、2014年に来日して日本各地で演奏しているのだが、ハイブリッドテナーの本領を最も発揮したのは1987年だったと思われる。っていうか、ある意味グロスマンの生涯のピーク時期だったかも。今回はその映像の話。
(注:映像紹介するだけのつもりだったのだが、書いているうちに盛り上がってグロスマン奏法解説みたいになってしまった。文章長くてすみません)
映像発掘:1987年のグロスマン
もしかするとこの年、地方ツアーは無くて新大久保Somedayで一週間ぐらい連続して演奏しただけかもしれない。Somedayでの演奏は、基本的に日本のプロミュージシャンが毎日日替わりのピアノトリオでサポートしていた。
私も3日くらい観に行ったかな。当然ウォークマン隠し録り音源もいくらか持っているのだが、グロスマンの死の直後、なんと隠し「撮り」映像が流出!(って実はこの映像の存在は前から知ってたけどw)
下のリンクがプレイリストです。全部で11曲!!ってことは二日分なんだろうな。同じTシャツだけどw グロスマンのソロだけ切り取ってるのも実に良いw
いや、今改めて観て聴いてますが、ほんとこれ世界文化遺産登録したい異常な記録ですよ。そもそも、グロスマンは適切なパッケージングを第一の目的とするスタジオ録音であまり真価を発揮できないタイプで(Love is the Thingみたいな例外もありますが)、ライブ盤でもそれはそれなりに制約がある場合が多いので、アルバム中心で聴いているリスナーの皆様には凄さが伝わらない。
というわけで、ジャズテナーサックスプレイヤー業界では世界中で尊敬されているはずなのだが、メジャーなフェスティバルでの演奏はほとんどなく、クラブギグばかりなので、当然、映像も限られる。なので、2000年代に入ってからはともかく、1980年代の映像はほぼ無かったと思う。
1987年といえば、当然スマホなどというものはなく、ついでに言えばメモリービデオカムもなく、恐らくは嵩張る8mmビデオをカバンに忍ばせて、という文字通り隠し撮りの世界だったと思うんですが本当によく残してもらいました。ありがとうTさん!!!
映像からみるグロスマン奏法の注目ポイント
というわけで、すべてのジャズテナー吹きが憧れるグロスマンのキャリアのピークを余すことなく捉えたと言っても良い、滅茶苦茶貴重な映像なわけで、テナー吹きは全員正座して観ましょう。お経だと思って毎日一回観ても良いくらいだ。途中で吐きそうだけどw
とはいえ、グロスマンビギナーの方は何に注目するとよいか分からないかもしれないので、信者歴40年の私が、信者として真似したいポイントを中心に解説してみます。
演奏の姿が格好悪いけど演奏は恰好良いw
まだ当時30代半ばだったと思うのだが、髪型、格好、服装が実にダサいw 髪の毛ボサボサだし、なんかすごく不健康な太り方してるし。どうでもいいTシャツとジーパンだし。と思ってよく見るとTシャツの日とほぼ同じ色のトレーナーの日がww まあ気にしない人なんだろう。
演奏上の特徴としては、殆ど正面を向かないww ずっと横向いてて、なんとなれば客席にケツ向けて吹き続けたりしてるw まあグロスマンあるあるですね。 おかげで隠し撮りがバレないというメリットもありそうww 横向き奏法は私もセッション等の時、結構な割合でコピーしてますw しかし、ケツ向けて吹いてても印象が全く変わらない轟音ってどういうことかと思いますな。
さて、横を向いてる映像で注目したいのは顔とマウスピースの角度ですね。この人、盛り上がるとマイク無視してサックスを上げたり下げたりするわけですが、マウスピースが口に入るところの角度はほとんど変わらない、要は頭(首)とサックスを合わせて動かしているのがよくわかります。バラードの時(特にテーマ)はちょっと変えているかもしれないけど、まあ、殆ど誤差ですな。プロも含めて、サックス動かすと角度まで変わっちゃう人がいるけど、あれは如何かなあとよく思います。
上下に動かすとは言うものの、基本的に、サックスはちょっと身体から離して正面に構えています。この身体とサックスの距離も真似したいものです。このぐらいのガタイが無いと難しいけど。
あと、指が実にいい感じですね。全体的に柔らかく丸めて優しく抑えている感じで、目いっぱいブロウしている場面でも力が入ってない。左手の人差し指以外は殆どキーから離れないのも含め、サックス吹きとしては真似するとよいポイントなのかと思います。
あと、珍しく正面から撮れているMr. Sandmanを観るとよくわかりますが、この人、演奏中は基本的目を開けています。なにか観てるのかなとも思うのですが、視線は天井、っていうか、要は「白目を剥いている」状態に近いw これもグロスマンフリークとしてはコピーすべき要素でしょう(私もよく真似してるw)。
音がヤバすぎる
この時期のライブを生で観た人は全員同意するかと思いますが、とにかく音が凄まじい。特にアドリブが盛り上がってくると力いっぱい吹きこんで、まさに「轟音」。でも決して変に割れたり(意識的に割ってるところはあるけど)不安定になったりしないのが凄いです。でかいリアルトーンだけじゃなくて、音量小さめのサブトーンも密度が濃い。そして、フラジオのソ、ラ、シあたりの物凄さと言ったら!(フラジオを通常域と同じ様に吹いてしまう最近のプレイヤーと違って、これらの音はそれぞれ性質や使いどころが違っているのがまた良い)。
さて、注目すべきは、音量、というか改めて音の密度が、ロングトーンでも、八分音符でも、下手すると16分音符でもほとんど変わらないところでしょうか。私は最近「ロングトーンからの羊羹タンギング」練習というのを提唱しているのですが、まさにそれのお手本というか目指すべき姿ですね。
あと、この映像の歴史的価値を高めているのは、New Moonのソプラノでしょうか。私の知る限りグロスマンがソプラノ吹いてる映像はほとんどないわけで、それだけでも貴重ですが、この映像で聴けるソプラノの音の凄さと言ったらもう座りなんとかですよw。私も生で聴いて、以前「怪鳥の鳴き声」という表現を使いましたが、異常な倍音の入った高音域だけでなく、音の密度が凄い中音域も素晴らしいです。まさに、コルトレーンはきっとこんな音だったんでしょう。映像ということで、楽器の持ち方(基本的にはずっと持ち上げて吹いてる)や、顔と楽器の角度も学ぶべきポイントかと思います。
ちなみに、この時使用している楽器ですが。テナーは多分自分の楽器でアメセルのF#無しMark VIとオットーリンク(7番とか8番とか普通のやつ)。ソプラノもMark VIとセルマーのメタル(これは借り物だったという情報もある)。ちょっと以外なのは、リードがべろべろだった(柔らかかった)という証言があること。私、それも含めてすっかりコピーしておりますw
異常にドライブする八分音符
もう全曲凄いです。タイムの化け物。分かりやすいのはOleoですかね。BPM330とかでの、このドライブ感。このテンポで八分音符の裏から始まるフレーズの異常なフィット感。途中でリズムセクションがバラバラになりかけたとき、四分音符吹いて、合わせに掛かったりしてますね。グロスマン優しい。
当然ファーストテンポだけではなくミディアムやスローも完ぺきなわけですが、今回観て、改めて凄いと思ったのが、八分音符のフレーズと16分音符のフレーズが交互に出てきた時の違和感のなさ。私などは調子に乗って16分音符のフレーズ始めちゃうと、八分音符に戻れない時があるのだが、タイムとドライブ感が全く同じなので行き来が自由自在。
ミディアム、スローといえば、この頃のグロスマン、バッパー化に伴い、その前はあまり吹かなかった、跳ねる八分音符を吹き始めてますね。Whims of Chambersとかね。音符としては三連に近いかもしれないけど、タイムが良くて、表も裏も音の密度が変わらないので、全く阿波踊り的に聴こえない。タンギング、アーティキュレーションも含めて、これもよく分析すべきポイントかと思います。
ハイブリッド感あふれつつ、男らしいフレーズの連発
グロスマン、この頃はすっかりバッパーになっているので、すべての曲で美味しいロリンズ系バップフレーズを連発してます。まさに、「思わずコピーしたくなるバップフレーズ」オンパレード。
一方で、盛り上がってくると数種類のグロスマンフレーズを惜しげもなく繰り出してきます。基本的には跳躍系、またはクロマチック系の、要はコルトレーンっぽいフレーズなので、ロリンズとコルトレーンの上質なハイブリッドが出来上がり。まあ、私は聴き過ぎているからかもしれないが、その行き来が自由自在で何の違和感もないというのがまた素晴らしい。いわゆるインとアウトの行き来ですね。
いわゆるグロスマンフレーズなんですが、同じフレーズを同じ曲で何回も使ってます。実に男らしい。一体、一晩で何回同じフレーズ吹いているのであろうかw いや、ソロが長いからしょうがないのだ。と思って改めて映像の長さを観てみると、すべてが5分越え。この映像、グロスマンのソロだけで他の奏者の演奏はすべてカットされてますのでwやっぱり大抵一人で5分以上はソロやってるんだな。でも、どういうわけか全然飽きません。信者だからか。
長いと言えば、フレーズ始めてから終わるまでの長さも特徴でしょうね、誰かがグロスマンの八分フレーズは「吐きそうに長い」と評していたが、まさにその表現がピッタリです。フレーズが長くてどこで止まるか分からないから、聴いている方もブレスが出来なくなるのだな。息の長さだけではなく、アイディアの豊富さ、タイムの安定性が相まって成り立つ特徴と言えましょう。
ついでに、アドリブの途中、フレーズの合間で「あっ」とか「うっ」とか思わず声が出るのも美味しいですね。私もよく真似させていただいておりますw
選曲が素晴らしい
当時のグロスマンスタンダードてんこ盛りの選曲です。とはいえ、Eronel とか、Like someone in Loveとか美味しいコード進行のスタンダードあり、New Moonや415 Central Parkとかの若干モード系グロスマンオリジナルあり、Mr. SandmanやAnother Youなどの始まると止まらない系の曲あり、超高速Oleoあり、そして、最後は珠玉のEasy Livingで締めるという。ああ、書いてるだけで涙出るw 信者の皆様は、無心で楽しみましょう。
おまけ:同時期の隠し録り音源
上記は、映像の話でしたが、当時、音だけ隠し「録り」していた人はたくさんいるはずで、あちこちに音源が残っていると思われます。そのうちのいくつかを下記ご紹介。基本的には映像と同じ時期なので、凄さも同様です。たまに日本人のサックスプレイヤーが乱入したりしますが、なんちゅうか、グロスマンの凄さが際立つというか。これ以上は止めておこうw。合わせてお楽しみください。
これは1986年だから上に採り上げた映像の一年前ですかね。
一晩分の音源がまとまってます。
ここからは1987年の音源を一曲ずつ。
チュニジア、冒頭に出て来るブレークからのピックアップはフレーズ、八分音符のドライブとまさに理想的です。イェイ!
ソプラノもう一曲。怪鳥。
止められない止まらないグロスマンのMr. Sandman。テーマからソロになってドラムとデュオになってまたベースピアノ入っても止められない。10分経ってようやく止めたと思ったら、ピアノソロの後にまたドラムと4小節交換。絶対なんかやってるだろ。最後ルバートしたのち「B!」とエンディングのコードをリズム隊に大声で指示して終わるのも実に粋ですな。
他にも私の手元にいくらか音源があるので、興味のある方はごにょごにょ。。
当初の目論見に反して妙に長くなりましたが、以上でございます。あー疲れた。特に映像方面は皆様心して、できれば大音量でご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
