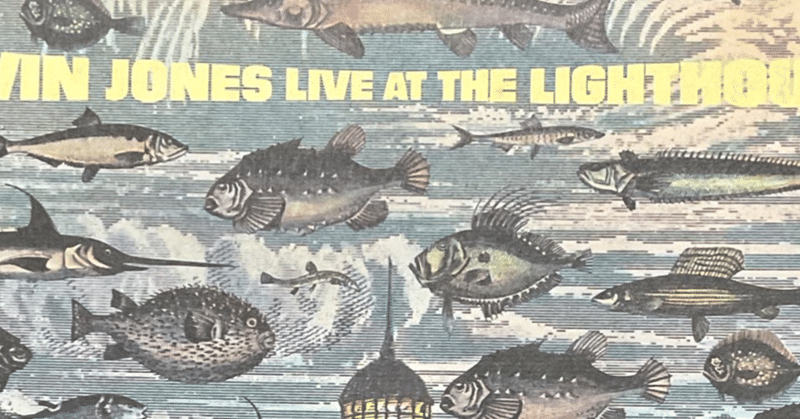
Steve Grossman研究-70-80年代のスタイル変遷を検証するーその4 電化サウンドへの傾斜と裏側でのアコースティック回帰 ‘76-‘78年
本論全体を通じて言いたかったこと、すなわちグロスマンのハイブリッド性(とその凄さ)については前回書いてしまったので、これ以降は蛇足気味ではあるのだが、まあ、そういわずに70年代後半を検証してみたい。
70年代の音楽シーンとグロスマン
おそらく、70年代にあっても、NYでのローカルなセッションにおいては、日本で残された記録の様な極めて伝統的なジャズのスタイルでの演奏を繰り広げていたであろうグロスマンであるが、レコードを通じて表に出てきた音楽はちょっと違っていて、当時のジャズシーンの影響を色濃く受けたものだったと いえる。要は「電化」「ロック」「クロスオーバー」さらには「フュージョン」といったキーワードで語られる環境である。
1976年当時といえば、電化ジャズのパイオニアであるマイルスが自爆→活動休止するのと入れ替わるように、ヘッドハンターズ、ウェザーリ ポート、リターントゥフォーエバー、マハビシュヌなど、いわゆるマイルススクール出身者の電化サウンドが一世を風靡していたのは言うまでもない。ジョージ ベンソンが「ブリージン」を出したのもこの時期だし、もう少しするとリーリトナーや、ラリーカールトンが出現する。まあ基本的にピアノはキラキラエレピ、 ポリシンセ積極導入、ギターはオレンジスクイーザー、色づけに民族音楽チックなパーカッションでもいれようか、っていうのがジャズ業界のトレンドだった。
一方、そうはいってもNew Yorkあたりにはロフトムーブメントなるトレンドもあって、暑苦しい連中が、どちらかというと精神性と体力に重きを置いた暑苦 しいジャズをやっていたりした。逆にいえば、この時期にわざわざGiant Stepsとか、Recorda meとかGroovin’ Highなんぞという過去の偉人の作品をご機嫌に、などという奇特な人は極めて少なかったということだ。
というわけで、もともとマイルスバンドや自らのリーダー作で電化されたジャズをやっていたグロスマンとしても、基本的にはそのムーブメントに乗っていたともいえる。当人が希望していたかは定かではないが。
この時期の重要音源:メジャーな活動から
では、この時期のレコーディングを並べてみる。活動の中心は、Stone Allianceというバンドである。
Stone Alliance/Stone Alliance 1975/6 1976/6録音
Steve Grossman/Terra Firma 1976/4録音
菊地雅章 東風/Wishes 1976/8 録音
Stone Alliance/Con Amigos 1977/4 録音@ブエノスアイレス
Terra FirmaはStone Allianceにヤンハマーが加わっているだけで、要は初リーダーと同じメンツだ。
さらに、Stone Allianceは、最近になってブレーメン、アムステルダム、ブエノスアイレスでの各ライブがCD化されている。一応全部持っているので録音日付を チェックしようと思ったのだが、どこにも何も書いていない(笑)。そもそもこのCD群いい加減なんだよなあ。ライブインブエノスアイレスと、ライブインア ムステルダムのジャケットにおそらく同じ日のステージの写真使ってたりして(服装および楽器のセッティングが同じ-面白いので写真アップします)。
しかし、ビニール盤で持っているCon Amigosの日本語解説には「76年にトリオでデビュー作を吹きこんだ彼らは、同年10月から77年4月にかけて、チリ、ウルグアイ、ブラジル、アルゼ ンチン、パラグアイという中南米5カ国を歴訪するツアーしており、その最後の訪問地で録音されたのが本作である。また77年秋には欧州各国をツアーしてい る」なる文章があった。7カ月かけて5カ国のツアーってなんだよってツッコミはともかくとして、これらのライブアルバムは1977年の春および秋にレコーディングされたものと思われる。
当時の活動の中心であったStone Allianceであるが、改めて書いてみると、グロスマンとジーンパーラ(eb)、ドンアライアンス(ds/perc)のトリオ編成が基本である。当時はウェザーリポートの対抗馬、みたいな騒がれ方もしたらしいが、今冷静に聴いてみるとそんなタマではない(笑)。そもそもキーボードとギターのいない クロスオーバーのバンドなんてのは形容矛盾みたいなもので、なにか特徴があるとすれば、たまにアルゼンチンタンゴ関係者が入るとかそんなもんである。
曲は、バリエーションに富んでいるように見えて、毎度似たような曲をやっている。当時のグロスマンフリークにはおなじみのお経ジャズ、”King Tut”とか!Zuru Stomp”とか。さらにライブだけだが、1980年代以降にもやってる”Taurus People”とか”New York Bossa”などのグロスマンスタンダードも。演奏のテイストも、楽器編成からくる単調さは免れないし、音楽的なコラボレーションやハプニングの要素も実は希薄だ。その意味でもウェザーあたりの計算された(かつ、自然発生的でもある)サウンドとはえらい違いだ。
しかし、当時のグロスマンのブチ切れプレイがコード楽器レスのトリオ編成で思う存分楽しめるという意味での価値は高い(特にライブ盤)。特に ”Taurus People”や”New York Bossa”は結構難しい(とはいえII-V進行が基本の)コード進行の4ビートチューンであり、ある程度「ハイブリッド感」を楽しめると思う。 ”Arfunk”なんて曲も一発でのブチ切れソロが強力。ちなみに、3枚のライブ盤のうち、ブエノスアイレスだけは商用化されるのに適切とは思えない音質の悪さなのではないのでお薦めしません。
この時期の重要音源:マイナーな活動から
さて、上記はホームグラウンドである米国におけるメイジャーシーンを狙った活動であるといえるが、実は同時期に欧州でその後の活動を示唆するような重要なリーダー作を二枚録音している。上記Stone Allianceの活動と合わせて考えてみると、これらの録音は彼らのツアーの最中に、グロスマン単独で地元ミュージシャンと制作したと思われる。
Born at the Same Time/ 1977/11/25録音@パリ
一枚目はフランスジャズ界の重鎮ダニエルユメール(ds)を含んだピアノトリオにグロスマンが加わった作品。フリークの間では有名ですな。いわゆ る当時のグロスマンスタンダードであるお経系の曲ばかりであるが、基本的にはアコースティックなジャズ。特記すべきはやはり”B面一曲目”の”A Chamada” であろう。いわゆる一発もので、凶悪に煽りまくるバックの上で気が狂ったように吹きまくる。この曲でやられてしまったという初期グロスマ ンのファンも少なくないであろう。いわゆる「ブチ切れ」という言葉はこのテイクから生まれたといっても過言ではあるまい。グロスマンフリークになりたければ避けては通れない名演(迷演?)ですな。下のYou Tube
19'40"くらいからです。
New Moon/ 1978/1/14-16録音@パリ
さて、問題(そして、本日のポイント)は二枚目である。これは一転してJean Francois Jenny Clarkという長い名前のアコースティックベーシストとの地味なDuoアルバムで、グロスマンは自らのサックスのほかにピアノを多重録音している。基本的には、お経のような単調で暗いグロスマンオリジナルが続くのだが、最後に突然”Out of Nowhere”と”Body and Soul”というバップ&スタンダードチューンが出てくる。両曲とも余計なピアノが入らない完全デュオなのだが、特に”Out of Nowhere”はテーマの吹き方からアドリブから、まさに50年代ロリンズを彷彿とさせる完璧なバップスタイル演奏されており、正に現在のスタイルの原点ともいえるテイクになっている。”Body and Soul”の方は、イントロからそのままアドリブに突入して1コーラスで終わる。これも若干コルトレーンあたりのエッセンスを感じさせつつ、アドリブはモロバップである。You Tubeの29:20くらいから聴いてみてください。
私がこの二曲を初めて聞いたのは、グロスマンといってもライトハウスと菊地雅章ぐらいしか聴いた事の無かった時期であり、とても同じ人の演奏とは 信じられなかった。同じ人だとしても、きっと冗談だかパロディだかやってるんだろうなあと思ったりしたものだが、今から考えてみると、テナー吹きとしての この人の本質であり、「実はもともとやりたかったこと」を素直にやっちゃった、ってなところなんだろう。やっぱりグロスマンって音楽家というよりは、テ ナーサックスのジャズが大好きな職人気質的「テナー吹き」なんだろうなあ。と改めて思う今日この頃です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
