
初めての床貼りに挑戦!
DIY初心者のいっぷくですが、2021年ゴールデンウィークを使って、初めての床貼りにチャレンジしました!
今回は、うまやんと2人で挑戦した床貼りの模様を紹介します。

・畳の四畳半
ヤイラジハウスには、土間から離れに上がる畳の四畳半がありました。
サイズも中途半端で、日当たりもあまり良くない…ということで古民家購入当初から床に張り替えて図書室として使うことに決定!
いよいよ、自分たちで畳を床に変えることにしました。
床貼りまでの簡単な手順です。
①畳をはがし、荒板だけにする
②床下のチェック、大引や根太の確認
③荒板の上に根太を貼る
④スタイロホームを入れる
⑤合板を貼る
今回は畳の厚さ5.5cm分を根太と合板で埋めなくてはいけません。最終的に畳があった高さで面を合わせれば、段差のない床に変わるはずです!
・床下のチェック
まずは不要な畳をはがし、荒板だけの状態にします。さらに荒板もはがし、床下の大引や根太を確認しました。

おおむね、大引も根太も状態は悪くありません。束石があり、その上に柱。横に大きく太い大引があり、柱に支えられています。その上に根太が貼られている、基本的な床の構造でした。
ただし、一部の大引は少し木が弱くなっているようにみえたので、元の大引の横に、新たに大引きの役割を果たしてくれる太い木材を入れました。このように大引きの隣に新しい大引きを入れる方法は、わが軍師、良き相談相手の専務からのアドバイス。
固定する方法はいろいろあるようで、鋼製束を入れたり、束石を入れて柱を立てたりすることもできますが、私たちはコンクリートブロックで手軽に支えています。もし弱った大引きに何かあっても、新しい大引きが支えてくれるはず。

ついでに一部の根太も交換します。これで床下の作業は完成!
・新しい根太を貼る
床下のチェックや補修が終われば、いよいよ新しい根太を張る作業です。畳下になっていた荒板の上に、格子状に根太を貼ります。根太同士の間隔は「ピッチ」というようです。かっこいい!
採用した基本の根太のピッチは303mm。ただし、本棚を置くことになる部分は少しピッチを狭く取ります。使った根太はコメリの赤松角材です。6本入りで約1000円と、お買い得!お世話になりました。
根太を貼るときは、適当な木材で303mmピッチが作れる定規を作りました。根太と根太の間にこの木材を挟めば簡単に間隔が作れるので、いちいち定規ではかる必要がありません。
根太を仮置きしたらインパクトドライバーで穴をあけ、ビスで固定します。うまやんが穴をあけ、私がビスを差し込み順番に固定していく作業。言葉がなくても、ビスやビットを手渡しできるようになり、私も呼吸がつかめてきたみたい。
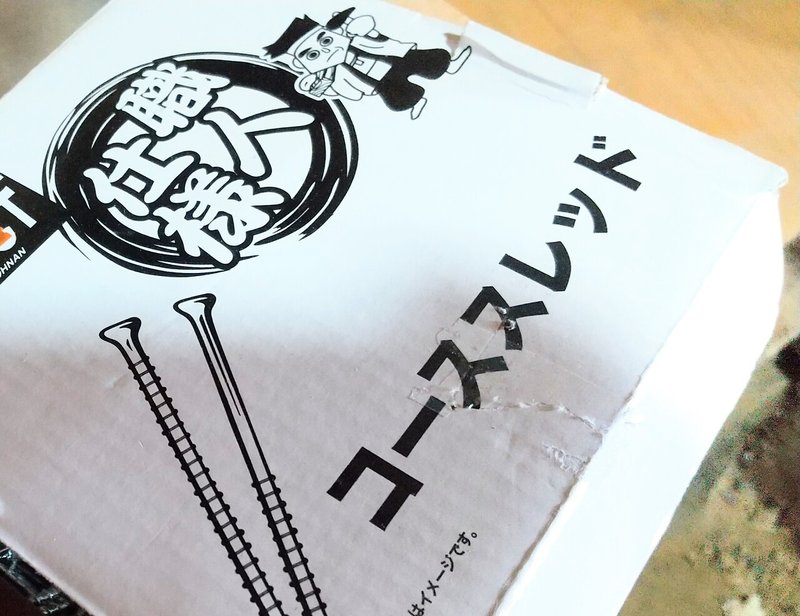
いっぷくもインパクトドライバーに挑戦!

ここまで床貼り作業の前半部分を紹介してきましたが、次の記事ではいよいよ床になる合板を貼る作業に入ります!
床を張るぞ、床を張るぞ、床を張るぞ〜
— うまやん@ヤイヤイラジオ (@umayan2020) May 2, 2021
はじめての床張り中(和室→洋室)なので今週のヤイラジはお休みさせていただきますm(_ _)m#ヤイラジ#古民家DIY pic.twitter.com/a5CDhfSrwn
ヤイヤイラジオの配信もお休みしての大仕事!笑いどころなしの真剣勝負の作業ですが、無事に床が貼れるのか、ぜひ続けてお読みください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
