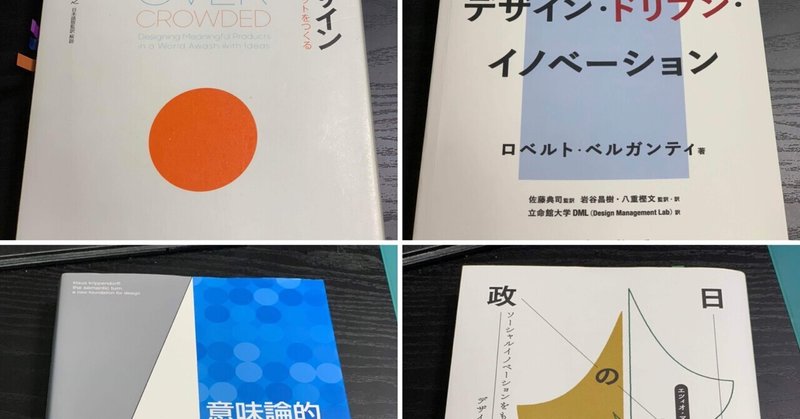
意味のイノベーションにおけるディスコースの重要性。思索途中の垂れ流しメモ。
安西さん、連日のオンライン読書会でしたが、やはり実りは多いですね。ほんとに定期的に考える時間があるのは嬉しいです。
で、今日(文化の読書会)でちょっと議論になっていたことを、忘れないうちに、雑駁ですが、書きとめておこうと思います。ただ、勢いで書いていますので、かなり粗いです。そのあたりは、また練っていきたいと思います。ご容赦ください。
以下は、安西さんに向けての文章というのではなく、意味のイノベーションに関心を持っておられる方々に向けて、というのを念頭に置いています。
********
まず最初に。私自身は、意味のイノベーションの提唱者であるベルガンティの議論を、すごく積極的に捉えています。そのうえで、ちょっと備忘録的にメモします。あくまでも、思索の途中経過の垂れ流しです。
意味のイノベーションという概念は、『突破するデザイン』が翻訳されて以降、日本でもそれなりに(かなり?)普及したのではないかと思います。論文などのレベルでは、まだそれほど多く出ているわけではないようですが。とはいえ、デザイン×経営の文脈では、かなり見かけるようにはなりました。そのこと自体は、喜ばしいことだと思っています。
その一方で、すごく違和感を覚えることも少なくありません。この言葉を使ってらっしゃる方々のお考えもまた、それぞれに異なるでしょうから、十把一絡げに言うのも大いなる誤りです。ただ、ときどき、何らかの提案を創出する側が意味を創出し、それを享受する側に「与える」かのようなニュアンスを感じさせられる言説にも出会います。
たしかに、『突破するデザイン』でインサイドアウトという考え方が採りあげられています。創出する側に湧き起こる衝動、これはまことに大事です。私もそこには賛同します。
しかし、ベルガンティの議論において解釈学が顔を出すように、享受する側がその提案をどう解釈するか、ここに意味が生まれるという点が、ややもすると忘れ去られているのではないかと危惧させられることがあるのです。
こう書くと、じゃあアウトサイドインではないかという指摘があるかもしれません。しかし、それはきつい言い方で恐縮ですが、根本的に間違ってます。根本的に、間違っています。2回言いました。
提案ないし作品を創出する側は、その人に映る環世界(Umwelt)への認識や、そこから生まれる感覚や感情、感性、そしてそこから湧き出てくる衝動などに立脚しています。一方、享受する側もまた、独自の文脈をすでに有しています。享受する側は自らの文脈に即して、その提案ないし作品を解釈し、摂り込んでいくわけです。その解釈する際のものさし、そしてその解釈から評価が生まれるわけですが、その評価のものさしこそが意味です。
したがって、ものさしとしての意味は、享受者によって「それは、自分にとってのものさしだ」と認識され、受け容れられなければ、いかに提案者が提示しようと、意味として成立しません。
そうなると、提案者と享受者のディスコースがめちゃくちゃ重要になるわけです。
これは、別に面と向かってお話しするというようなことを言っているのではありません。もちろん、対面でのディスコースもありますが。むしろ、提案ないし作品を介して、提案者と享受者がそれぞれ自律的な存在である状態で、それを自らにとっての意味として落とし込んでいく、さらには新たに解釈していく、そういうプロセスをさします。
このディスコースを考えるとき、本来の意味での〈批評〉ということの重要性も浮かび上がってきます。批評というと、他人事的に良し悪しをあげつらうというような理解が多いですが、違います。むしろ、一人の享受者として、その提案ないし作品をどういう意味において受けとめたのか、それを考え、言語化する営みが〈批評〉だと思うのです。その点で、真正面から向き合っている〈批評〉は、提案ないし作品を磨き上げることにもつながるわけです。
そこには、意味のずれも存在します。それって、当然のはずなんですよね。人って、それぞれ別々の文脈で生きているわけですから。そのずれを知り、受け容れつつ、近づいてみたり、離れてみたりする。それがディスコースではないかと思ったりもするのです。仮にずれていたとしても、そのずれがうまくリズムとして合っていれば、その出会いは幸せであることもあり得ます。むしろ、ずれているのにそれを直視せず、無理やりに合わせようとするときにこそ、不幸な状態が生まれるのではないでしょうか。
だからこそ、自分自身の関心の赴くままに突き詰めていくということもまた、すごく大事になると思うわけです。
このプロセスとしてのディスコースに着目すること、こここそが意味のイノベーションを捉えるうえでのcriticalなポイントの一つではないかと、私は考えています。
********
尻切れトンボではありますが、勢いがあるうちに言語化しておこうと思って書きました。またこのあたり、ディスコースさせてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
