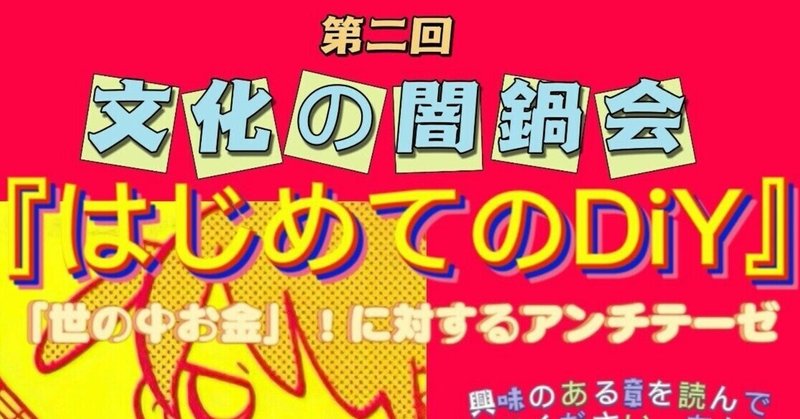
【第2回】文化の闇鍋会レポート 『はじめてのDiY:何でもお金で買えると思うなよ!』
皆さんこんにちは!
立教大学大学院社会学研究科、小泉ゼミに所属している修士2年松本です。
秋晴れの気持ちがいい天気だった2022年9月28日、ついに第2回『文化の闇鍋会』が開催されました!
(本当は7月に行うはずだったのですが、なんやかんやあり2ヶ月延期しました…)
今回の企画運営担当は、小泉ゼミ所属修士1年のオウさん。
毛利嘉孝著『はじめてのDiY:何でもお金で買えると思うなよ!』を読み、議論しました。
小泉ゼミではお馴染みの社会学者・毛利嘉孝先生、そして、ゼミ生にとって聖書的な存在の本書。私も卒論執筆の際、どれだけお世話になったことか…。
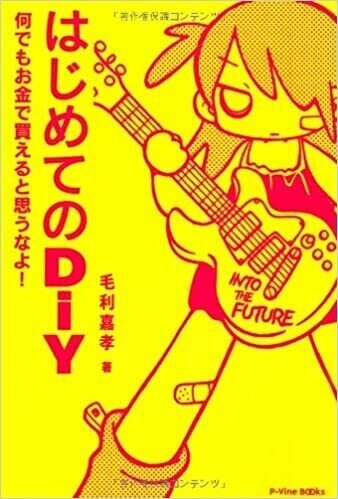
タイトルに「DiY」と入っていますが、こちらは一般的に言われる、日曜大工的なDIYとは少し異なり、「まずは、自分でやってみよう!(Do it your self)」という思想そのものを指します。(日曜大工的なDIYと区別するため、意図的にIが小文字の「i」になっています)
皆さんは「すべてが資本主義に支配されている」(p21)なんて思ったことはありませんか?お金を払えば、欲しいものはなんでも手に入れられる社会の中で、「今目の前にある商品以外に、自分が本当に欲しいものがあるんじゃないのかな?もしいま目の前にないなら、じぶんでその欲しいものが作れないかな?」(p21-p22)と考えることが、DiYの思想の最初の一歩だと述べられています。
この本は、もともとフジテレビのウェブマガジン『少年タケシ』で連載されていたコラムを書籍にまとめたものということもあり、非常に読みやすく、イラストや写真が豊富に使われているため、「学術書はとっつきにくいな…」という方々も、気軽に読み進められます。内容も、思想の説明はもちろん、社会背景を織り交ぜながら、多くの実践事例が紹介されているためとにかく楽しい!(この読みやすさ・面白さから、ゼミ生にとって聖書的存在なんだと思っています)
読み進めていくうちに、自分も何かやってみたい!という気持ちになります。
今回「闇鍋会」では、本書のテーマに合わせて、オウさんが、中国のDiY的実践についての論文を紹介してくれました。中国は、政府の権力が大きく、「文化」という面で弾圧されてしまっている状況だと思っていたため、中国でもDiY的実践が(細々とではあるけれども)行われているということは、とても興味深かったです。
他にも、課題図書での事例はある種の「閉じたコミュニティ」のなかで行われているのではないか?という私の指摘に対しての議論だったり(これに関しては、外部から見ると「閉じている」と感じられるけれどもそうではない。外部が勝手に「閉じている」というイメージを作ってるだけ。という結論に達しました。なるほど・確かに…&自分の視点の狭さに反省…)、オウさんが関心を持っている中国の「寝そべり族」についての議論をしました。
DiY的な思想・実践について、改めて多くを考えさせられる時間だったと共に、自分には何ができるかな?とワクワクする時間でした。
さて、次回の『文化の闇鍋会』は、修士1年の齋藤さんが担当します。
10月26日(水)の18時から開催予定です。
次回の課題図書は、『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践』(フィルムアート社)。会場は未定であるため、追ってお知らせします。
『文化の闇鍋会』は、文化や芸術、ライフスタイル等々、さまざまな角度から現代社会を見つめる研究会です。
興味・関心のある方は、どなたでもご参加ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
