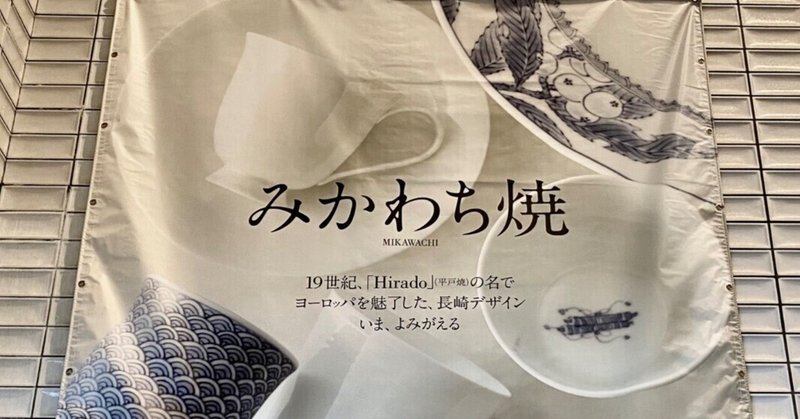
みかわち焼を学び感じる旅
三河内駅を降り、三川内のやきものの里を巡ってきた。
平戸窯悦山を後にし、北へと向かう。通り沿いにある
建物は佐世保市うつわ歴史館と三川内焼美術館。本当
は先にこちらを訪れてから、作品にふれて興味のある
窯元へ訪れるのがよさそうだが、まずはやきものの里
へ向かった旅。さて、あらためてみかわち焼を学ぼう。



























少しずつ盛り上げては削る緻密な作業だ







平戸松山窯のYouTubeチャンネルで美術館の紹介も。
作陶されている方の視点での解説も興味深い。
初めて訪れた三川内焼のやきもの里。九州はうつわの
産地であふれている。博多から日帰りで訪れることの
できるうつわの風景にひかれている。そして、まずは
行って感じてみる。うつわを学び感じる旅を続けよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
