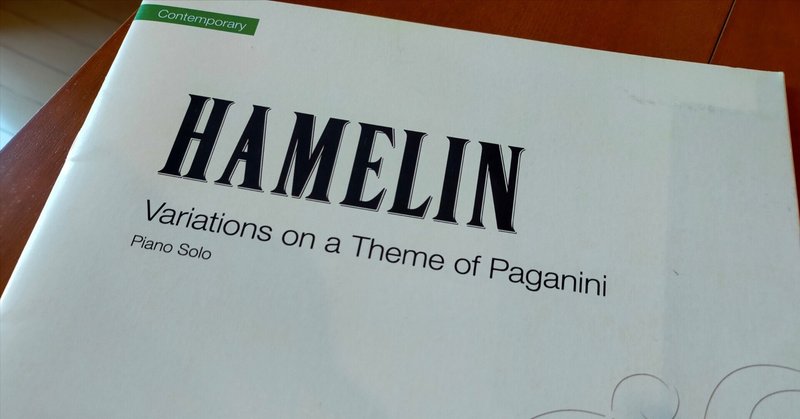
楽譜のお勉強【97】マルカンドレ・アムラン『パガニーニの主題による変奏曲』
2024年も「楽譜のお勉強」を続けていきます。今年最初の「楽譜のお勉強」はピアニスト・コンポーザーによるピアノ独奏曲から始めてみます。マルカンドレ・アムラン(マルク=アンドレ・アムランとも、Marc-André Hamelin, b.1961)はカナダのピアニスト、作曲家です。技術自慢の演奏家で、演奏が難しいことで知られるピアニスト・コンポーザーのゴドフスキーやアルカンらの作品を広く世に紹介してきた功績は大きいです。作品はやはりピアノ独奏曲が中心で、華やかなピアノの演奏技巧を凝らしたロマン派的音楽性と程よく刺激的な近代和声の響きが人気です。2009年に完成した『短調による12の練習曲集』(«12 Études in all the minor keys» for piano)は難解な現代音楽調でなく、モダンな響きで高度の技術を習得できるエチュードとして、しばしばピアノ学習に用いられます。本日は『パガニーニの主題による変奏曲』(«Variations on a Theme of Paganini» for piano solo, 2011)というピアノ独奏曲を読んでみたいと思います。

初期ロマン派のヴァイオリニスト・作曲家のニコロ・パガニーニ(Niccolò Paganini, 1782-1840)はヴァイオリン独奏のための『24のカプリス 作品1』(«24 Caprices» for violin solo, op.1, 1817)で一世を風靡します。特にその第24番イ短調の主題は、多くの作曲家に愛され、変奏曲の主題として用いられてきました。現代でも増え続けるパガニーニ・ヴァリエーションの数を数えることは難しいのですが、有名な作曲家の手によるものだけでも、ブラームス、リスト、ラフマニノフ、ブラッハー、ルトスワフスキ、リーバーマン、一柳慧、ロイド=ウェッバー、イザイ、ロックバーグ、サイ、ローゼンブラットなど、枚挙に遑がありません。特に有名なブラームスとラフマニノフの曲は、どちらもピアノ曲であり「パガニーニの主題による…」というピアノ曲のジャンルとして定着した感あります。原曲のヴァイオリンを用いた変奏曲は意外と少ないのも特徴です(上記作曲家の中では、イザイとロックバーグの曲だけです)。
ここまで時代や地域を越えて作曲家たちが一つの主題に固執するというのも珍しいです。しかしそのため、私個人としてはこの主題による新しい曲のレパートリーを知ることにやや食傷気味です。特に変奏曲の形式を踏襲している場合は、主題が最初に来ることがほとんどで、即座に「またか」という思いになります。この「またか」を押し除ける新しいインスピレーションを持った楽曲が生まれないとも限らないので、一応気にして聞くようにするのですが。
アムランの『パガニーニの主題による変奏曲』は、主題と14の変奏から成る10分ほどの楽曲です。主題の提示はオクターブ奏によって素直にパガニーニの主題が演奏されます。和声付けに主題の5度上の音と増4度上の音を重ねて、短2度を頻繁に用いることによって、モダンなスパイスが効いてはいます。しかし、よく知られた主題を、主題と理解できる形で工夫も乏しく提示していることは変わらないので、タイトルとも相まってこの後の聴取ではずっとこの主題の影を探すことになります。おそらく「あの変奏曲のあそこら辺の変奏に似ているな」とか思ったりすることでしょう。有名な主題はキャッチーで聴衆の心を捕えますが、なんだか呪縛のようにも感じます。こういう主題と向き合っていこうという作曲家の動機はどんなものなのか気になっています。
第1変奏は主題の和声構造を踏襲、主題のピッチを強調しながら重音奏で駆け上がったり、下行したりします。フレーズの節目に現れる不協和音は手の構造を活かしたものが多く、弾きやすさと和声構造からの開離の両方をうまくこなしています。
第2変奏は両手がそれぞれ16分音符で疾走するトッカータです。中間部で高音域の半音階的和声進行が生まれ、主題から進行を少し大きく離すことで曲を推し進めています。第2変奏を聴いてこの後の展開に少し期待が高まりました。
第3変奏は分厚い和音の跳躍を軸にした技巧的な変奏です。華麗なピアニズムを楽しむには良いですが、第2変奏でもたらされた和声的な拡がりは収束し、主題への回帰志向が強い点が気になりました。
続く第4変奏は、バス・ラインに半音階的進行が顕著で、和声の進行に伴って右手のメロディーも半音による倚音を多く経過するので、やや予想しづらい線が現れてくるのが魅力的です。後半ではアーティキュレーションをがらりと変えて繊細なレガート奏で大きなフレーズを作り出しているのも良いコントラストになっています。
第5変奏には「舟歌風に」という演奏指示が書かれています。複合拍子になるので、雰囲気が変わり、コラール調の美しい音楽になります。変奏の最後にはショパンの有名な『舟歌』のパスティーシュのようなフレーズが出てきてピアノ音楽ファンに対するサービス精神を感じます。
第6変奏は少し変わった5連符の連続による音楽です。右手と左手は交互に演奏し、響きの雰囲気もなんだかメンデルスゾーンの『厳格な変奏曲』を思い出しました。手を交互に演奏してコラール風の音楽を奏でる箇所が結構あるからでしょうか。
第7変奏は『パガニーニ変奏曲』というジャンルにおいてもかなり定番の変奏曲です。和声を右手の上行形による分散和音と左手の下行形による伴奏音型に分けて弾くものです。途中で手の役割が交替したりもしますが、改めて現代の作曲家が書いているのが不思議なくらい古典的で、頻繁に聞いてきたものです。
私が個人的に一番興味を惹かれたのは、第8変奏です。旋律線がしばしば短7度の重音で奏され、和声感が良い具合にぼやけて、半音階進行も相まってなかなかエッジの効いた響きです。音を選び取るセンスを感じました。
第9変奏は広範囲の音域をカヴァーするアルペジオの連続です。主題は和声的要素のみに収斂されているので、響きとピアニズムのみを味わう感じです。しかし、ピアノ技巧としてはとても常套的なものなので、目新しい様子はありませんでした。
変わって第10変奏はなかなか個性的です。全休止の小節がいくつか挟まり、有音部と無音部のコントラストが激しく、抽象的な陰影があります。このような変奏を思いつくのならば、私も有名な主題による「変奏曲」を考えても良いかもとも思いました。「変奏曲」の作曲は、まるで作曲家の音楽的ボキャブラリーと発想の豊かさを試されているような気になります。
さらに第11変奏も個性的です。ヘミオラのポリリズムで抽象化された主題がゆったりと弾かれるのですが、ところどころ唐突に別の音楽ジャンルとして解釈された変奏の断片が挿入されます。ゆったり揺蕩うように流れる音楽の中に突然、チャールストン、サルサ、フリスカ(チャルダシュの部分)などが聞かれるのです。楽しい驚きがあります。
第12変奏は楽曲の終わりに向かって散らかった音楽を収めているようなニュアンスがあります。9/8拍子で、ゆったりと弱奏で持続する音階とアルペジオの中間のような音型が行き来します。大きな山を作るわけでもなく、間奏曲的な役割を感じます。
第13変奏はカンタービレの抒情的な楽章です。最終変奏の前に歌心ある音楽を置くことはとてもよくあることで、効果は高いです。感情豊かな歌ですが、転調は非常に頻繁で、実際に小節の途中でどんどん調号が変わります。14小節しかないのに、イ長調→変ニ長調→ロ短調→ト短調→ホ長調→ハ短調→ロ短調→変ロ短調→ニ短調→嬰ハ短調→ト長調→嬰ト短調→ハ長調→変ニ長調→イ短調と、15回も調号を変更しながら転調します。もちろん確定的に調性を聞くことができる箇所は極めて限定的です。
最後の第14変奏は、変奏曲の常套的な終曲である、長めのコーダを伴う技巧的な速い音楽です。変奏としては主題を聞き取りやすい素直なものですが、中間部でパガニーニの別の主題を用い、24番のカプリースの主題と二重奏にしている点が耳を引きます。用いられる主題はパガニーニの『ヴァイオリン協奏曲 第2番』の第3楽章の主題です。「ラ・カンパネラ」と呼ばれるこのロンドは、リストが主題を用いて有名なピアノ曲を書いたことでとても有名です。パガニーニの最も有名な二つの主題で二重奏を作るというのは、なんだか小賢しい感じもしますが、有名なメロディーを聴きたいと思っているピアノ・ファンには嬉しいサービスのようにも思います。最後は華麗に技巧を示してこれみよがしなピアノ・ソロ音楽が締め括られます。
華やかな演奏効果を持ち、分かりやすい主題を新しい響きで楽しく聞く音楽は、強い求心力を持っていると思います。ただ、これは相当演奏家がお客様に喜んでもらおうという視点かなと感じました。私も、自分の音楽をお客様に聞いていただき、喜んでいただきたいのは一緒ですが、私自身が演奏家でないため、「私の技巧を通して」という視点はありません。隅々まで凝らされた作曲技法、演奏技法の数々に対し、音楽に驚かされ、気付かされたことの少なさは気になります。しかし、いくつかの変奏曲では、ハッとする瞬間があったのも事実です。自分が「変奏曲」というジャンルに、あるいは「パガニーニ変奏曲」という牙城に今取り組むとしたら、何ができるのか、あるいは何かできることがあるのか、逡巡した時間でした。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
