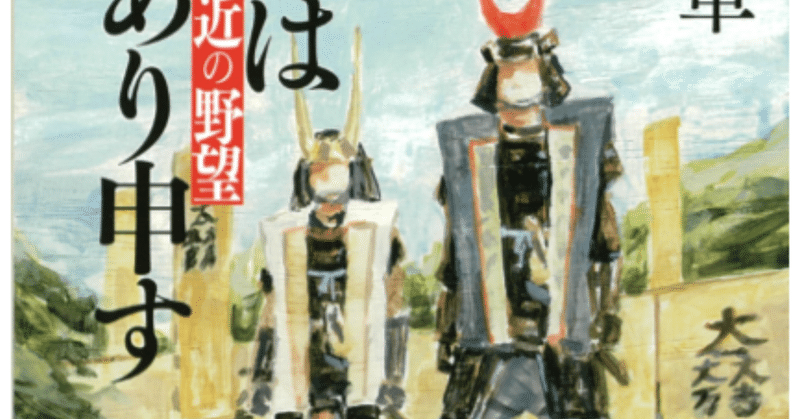
文芸の浪花節が好きです
【PR】
清々しいまでにオフ終了のお知らせです。
ありがたいことにゲラやら手直しやらのお話が入ってきたので、粛々とこなしていこうと思いますよー。やっぱりあれですね、慣れない休みなんて取るもんじゃありませんね。
さて、現在シャバでは出版に関するあれやこれやで大騒ぎになっております。わたしとしては特に述べることはないのですが、皆さんのご意見を眺めているうちに、我々作家と世間の皆様の認識の間にちょっとしたずれがあることに気づきました。業界の慣習みたいなものって案外その外の人にはご理解いただけない概念ですもんねえ。
いえね、わたしたち業界の人間は「信義」とか「人情」とか「矜持」という言葉を当たり前のことのように用いますが、業界の外の人たちは奇異に感じるみたいです。TLを眺めていると、わたしたちの業界のこうした言葉に対して、何甘いこと言ってんねん、的な反発を抱いておられる向きもかなりあるようなのです。
実はこれ、文芸業界の事情に関わっているんですよねー。
出版社は本を作り、取次さんや書店さんを通じて本を販売する機能を有しています。けれど、普通のメーカーと違うのは、その商品の核を外部委託する場合がかなりあるということ。個人事業主(場合によっては企業ですけど)である作家やライターと組んで本を作るのです。
けれど、わたしたち作家は下請けというわけではありません。建前上、出版社に「出版権」という著作権上の権利の一部を出版社に貸与して、その権利料をいただいているという形なので、出版社と作家はイーブンの関係です。
けれど、これは「建前上」であることに注意してください。言い換えるなら、法の上のことと言ってもいいでしょう。実際には、出版社の方が作家より力が強い場合が多いことは言うまでもありません。
とまあ、こんな建前があるおかげか、我々の業界では出版契約書は本が刷り上がってから、それどころか本が売り出されてから締結なんてことも結構あります。
裏を返すと小説の依頼から着手、作成、完成に至るまで、一切何の保証も契約もないということです。
するとどうなるか。
結局、我々作家も出版社側も契約ではない何かで細い糸を結び直そうとするわけです。
「あの人なら信用なる」
「あの人に頭を下げられたら、俺も頑張るっきゃない」
「あの人が俺のことを認めてくれている」
こうした人と人とのつながりが一般社会でいう契約に等しいものとして機能するのです。
わたしたちの業界の浪花節は、こうした機序で生まれたのではないかというのがわたしの考えです。
もちろん、こうした契約ではない結びつきは、いつかこの業界からも排除されてしまうかもしれません。外国での出版のように事前に契約を組み、その上で作業をする、そんな時代が来るかも。
でも実は、わたしはこんな浪花節な文芸業界が嫌いではありません。
とはいえ、この業界の輪がどんどん小さくなっているのが昨今の悩みの種で、ある程度の合理化を図り、三方良しで収益を挙げなくてはならない時代です。
何を残し、何を変えるのか。
煎じ詰めると、そうした話なのかもしれませんねえ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
