
絶神のエデュシエーター 絶対なる風 2
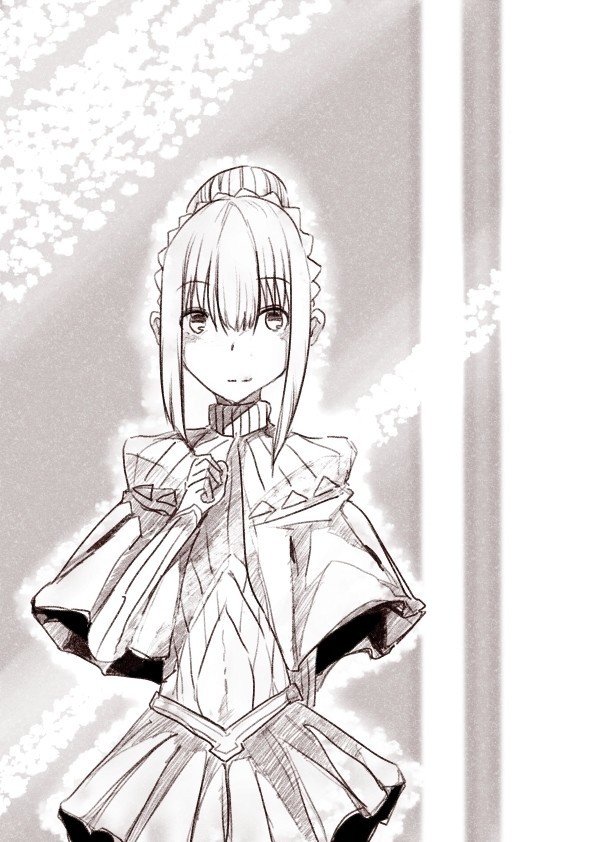
フラヌ街。
大迷宮プルートより北方。
迷宮開放による町おこしを生業とする街の一店にて。
「だっひゃっひゃっひゃっひゃっひゃっひゃっひゃ!!」
その大きな笑い声は響いた。
「だから、本当だってば!」
「いや、本当だとしても笑い話だろ!あひゃひゃひゃひゃひゃ!」
ゲイルはとある女性と会話していた。
『おめかし屋』ブリオーン。
その店主である女傑アギルタ。
右目の眼帯に、豊満な胸が特徴的な装飾好き。
彼女は今にも杯を煽りそうなほどのテンションで大笑いを上げていた。
「どこらへんが笑い話なんだよ!」
「全部だよ全部!ユーグの爺さんの知り合いじゃなきゃ他のやつぜってー信じねぇから!」
ユーグとは、大賢者ユグドルの外での仮名である。
世間一般では永く隠遁していると信じられている賢者は、案外世俗的だ。
時折ゲイルと一緒に街の一つにでも顔を出し、好々爺として情報や物品を仕入れていく。
本人曰くこれを繰り返すことが「長年生きるコツ」なのだそうだが。
「あの爺さんなら言い出しかねねぇけどお前も愚直だな!身よりも振る舞いの心得もない小娘ちゃんを名前つけて拉致ってくるたぁ見上げた馬鹿さだわ!」
「うるさい!いつも騒ぎにしようとしないでよ!」
…爺ちゃんの関わる相手はこういうタイプしかいねぇ。
人の話題を肴に酒を嗜み、飲んだくれては次の日も飲みふける畜生共。
のんべぇの集いの一角には、間違いなくこのアギルタが入ると思われた。
閑話休憩。
さて、『おめかし屋』というのは、服装や化粧、文字通りおめかしを生業とした店である。
迷宮踏破者が大半モグリである、ということはよく知られた話だが、それでも迷宮は多くの金銀財宝、様々な秘奥を抱え込んだ冒険者にとってのターニングポイントだ。
モグリであろうが稼ぎには利用できる機構であるということであり、浅層を用いてのトライアンドエラーを繰り返し、日々を生きている冒険者も少なくはなかった。
だが、やはり迷宮踏破者というのは悪いイメージがつきまとう。
名に相応の実力を持つものは少なく、大抵は詐称じみた低級の実力者の集いである。
浅層で生きるものは町おこしを行う運営者の掌の上であり、実際にその迷宮の構造をよく知るものは、冒険者ではないということなのだ。
これでは払拭できるものも払拭できぬ。
差別に追われ、少しでも身なりを整えんと必死に奔走する冒険者をターゲットとした職業。
それが『おめかし屋』である。
…最も、本当に腕のいい冒険者は詩人によって功績と名誉が保証される。
元来貴族のたしなみと言われたこのおめかしを生業とした店舗を、上の者が使用しないという世の流れは、世間への痛烈な皮肉ではあるのだが。
「で、だい。つまり目当てはそこの小娘ちゃんの服かい?」
「うん、お願い。とりあえずかわいいやつで」
「お前そいつに気が有るだろ?スケベニンゲン」
「身もふたもないことを…」
「??」
ゲイルは動揺を隠しながらも、アギルタの挑発をなんとかスルーした。
ユグドルの頼りにする人物の一人であるアギルタの腕は良い。
単なるおめかしに留まらずに、服の着付けや装備の新調、整備まで行える人間だ。
流石に鍛冶は他の店員に任せているようだが、詩人などからの情報提供にも聡く、世間に流れている様々な情報を見聞する判断力も持ち合わせている。
やはり単なるおめかし屋とは言いづらい人物であった。
「ま、そういうことならとびきりかわいく仕上げてやるから待ってな、高く取るけどな。来な小娘ちゃん」
「そーいうことらしいよ。いってくるね」
「うん、行ってきて行ってきて」
アギルタの下衆な言葉に思わず真顔になりかけるゲイルだったが、幸いルナには丁寧に接することが出来た。
そう、あの時から油断は欠かしていないのだ。
家に帰るまでが迷宮探索ともよく言われているのである。
アギルタは頬を釣り上げ、片手で小銭のジェスチャーを揺らしながら、着付室へと入っていくのだった。
「はぁ…疲れるなぁ」
こういった人物とは、ちょっと話すだけでくたくただ。
ゲイルが浮き世離れした人物であることも一つ有るが、アギルタは元から世渡り上手の遣手である。
いわば大人と子供の差、人生経験の違い。
戦いの腕は鍛錬でどうにか出来る。
だがこういった人生の厚みは、生きた年月で大きな差が出ることは明白であった。
そうして待つこと数十分。
服のとサイズの選定を終えたアギルタが、着替えたルナを伴ってゲイルの前に姿を表した。
「てなわけで、人形みたいだったから、手折れば折れそうな」
「冗談でも言わなんでよ」
「やっぱ気があるんじゃねお前?」
「うるさい!」
「??」
純真だ。
明鏡止水。
決してやましい独占欲や気など有りはしない。
出会って数日の少女に対し、相応の真摯に扱うべきだろうと意識を改め、ゲイルは尋ねた。
「で、どういう服だって?」
「貴族の令嬢さんっぽく。ゲイル、お前さんも見てくれは悪くないし、服の傷の付け方も一流だ。だから相応のグレードの娘さんがいれば…うーん、グッド」
「いちいち発言がひどい!」
「事実を言ったまでさ。来な、小娘ちゃん」
「うん」
そうして、ルナが顔を出した。
服全体を髪と同じ白を基調とした色合い。
妖精のように軽やかな肌着とローブ、ミニスカート。
白のストッキングに包まれた両足は蠱惑的で、今にも誰かをさらいそうな妖艶さがあった。
総じて、月の妖精と言ったところだろう。
ゲイルが脳内でそう結論づけたところで——
「わたし、きれい?」
「待って」
私、綺麗?はやめて。
一昔前に伝聞で流行った口裂け女の怪談の決め台詞だよねそれ。
質問に答えたが最後、地の果てまで追っては、竜さえ屠り殺す。
半ば真実や実在性が疑われる話だ。
一瞬呆けて、哀れな少年はやっと我を取り戻す。
「ゲイルー?」
「綺麗、すっごく綺麗だけど…アギルタさぁん!」
「ははははははははは!いい顔してたねぇ!」
「やっぱりか!」
「?さっきからなんのはなしー?」
ともかく、ルナは非常に綺麗だった。
本来ならば語彙力を失うほど魅力的な美しさが有ると言って過言ではない。
我を取り戻したその後に、なおもそのようなことを考えていると——
「ほら、なに突っ立ってんだい。これ服の替えに、それから」
「それから?」
「髪は三つ編みのシニヨンで結ってある。これからあんたが結ってくんだから、今日覚えな」
「えぇーっ!?」
「何がえぇ、だ!それでも男かお前?」
そう言われると、アギルタは店の端に置いてあるかつらを取り付けた女性の石膏人形の元へとゲイルを連れ去り、ねちねちと髪結いの方法を教えるのだった。
悪辣な面が目立つが、こういったところを目の当たりにすると、アギルタが女傑とされる所以を垣間見ることが出来た。
「……」
一人取り残されたルナは暇だったので、ふわりとその場を舞っては店内の品物を眺め続けた。
◆
「お前ら、ここんところの『闘神(エデュシエーター)』については知ってるかい?」
「えりゅしえーたー?」
会計をしようとしたタイミングで、アギルタが尋ねた。
「闘神ってのは、えらく強くて、百年に一度現れる『神の戦士』のことさ。」
「かみのせんし?」
「そこらへんも知らないんだな。まぁいい、説明してやるよ」
顔に疑問符を浮かべるルナに親身に接するアギルタ。
尚、しきりにゲイルを見つめては、どうしたどうしたと下衆た笑みを浮かべてくる。
何が目的だろうかと気になったが、まぁ大したことではないのだろう。
それはそれとしてむかつく、とは思ったが。
「むかしむかし、この世界を作った神様がいたらしい。名前を『アークレア』」
創造神アークレア。
全知全能の存在。
はるか昔に海を浮かべ、陸を作り、星々を浮かべたというという原初の神。
太陽や月が回るのも、今も世界が続いているのもこの神様の力であり、我々生命はその恩恵を受けて生きている…そう言い伝えられている。
アークレア信仰ともされる、世界中の人々が信じる絶大な教えだ。
「で、このアークレアが遣わせて、神の力を持たせた戦士が『闘神』という」
「闘神は様々な恩恵をもたらし、文明を賑やかにさせ続けた、だっけ?」
「そうそう。アークレア信仰も、この闘神崇拝に地続きとなっている文化だ」
ゲイルの合いの手に、宗教的分枝の存在を答えるアギルタ。
闘神崇拝とは、神々の遣いとして現れた闘神を、救世主や盛栄の神として祭り上げる文化のことである。
闘神は神の血を持っているとも言われ、その血が交わった子孫が、今の時代に生きる生命であるとも言われている。
人族——ヒューマン。
獣人族——ビスティロープ。
竜神族——ドラゴニュート。
森人族——エルフ。
土人族——ドワーフ。
精霊族——エレメント。
巨人族——トロール。
機人——ノイディアス。
亜人——フェアリー。
ここに時折人を襲いに現れる魔物を織り交ぜて、数え切れないほどの命があり、それらは世に残った闘神の恩恵から生まれたと言い伝えられている。
恩恵とは先も述べた血に、神術の源となる十二の性質——属性など。
これらは闘神の数だけ存在し、種族ごとに持ちうるものが比較的異なっていた。
「んで、今年はその闘神様が遣わされる年だって話だぜ」
「そーなの?」
「ああ。この街もお祭り騒ぎで大賑わいさ。色々なとこに寄っていくと良い」
無論、フラヌ街もこの闘神を崇拝する街の一つである。
救世祭、あるいは闘神祭とも呼ばれる、各地で百年に一度行われる祝い事。
後者は闘技大会など、冒険者や戦士の祭りごととしてそう称されることが多く、この街で言うならば、前者の救世祭が正しい、ということになる。
「ただ、この闘神様ってのは、何も良いことばかりじゃない」
「なんで?」
「大きすぎる力を持っていると言われてるからだ。災いを呼ぶ、という側面もある」
「ちからがおおきいとどうしてそうなるの?」
「争うからさ。闘神は他の闘神と引き合い、争うと言われているんだ。その理由はわからない。だけど、その争いは確実に世界を巻き込み、言葉に出来ないほど大きな爪痕も残す——ともね」
あくまで言われておる、という話だ。
闘神の戦いを目の当たりにしたものは居ない。
少なくとも、長寿族ではない人族の中に居ないことだけは確かと言えた。
だが、その危惧はゲイルにも理解できた。
「ここも、何か被害にあうかもってことだよね?」
「かもしれないねぇ。詩人はこれ幸いと便乗して英雄譚を広める気満々だそうだけど、私にゃあそこまでのバイタリティは無いよ。精々逃げる準備だけはしてあるけどね」
「たいへんなんだね」
「そうさ、大変な年なんだ」
アギルタはそう言い切ると、飾ってある花壇の木の枝葉を剪定して、小洒落たものを口に咥えた。
本来であれば彼女は葉巻を嗜むそうだが、仕事場では匂いを移すことも出来ず、もうかれこれ何年も吸っていないのだそうだ。
そういったところばかりはなんとも律儀だと、ゲイルは思っている。
「んじゃあ、銀貨10枚で」
「たっけぇ…」
「こればっかりはうちも譲れないからねぇ、腕でやってんだ。いい服めかしといて文句はなしだよ」
「まぁ稼ぎはあるけど、8枚!8枚で!」
「9な」
「ちぇー」
一般に宿に一泊するのに必要な一人分の代金が銀貨2枚程度だと考えると、やたら高い。
ただ、ルナに用意した服に替えまで考えると、これは妥当なものであると言える。
素材自体は非常に良質で、破れにくく洗いやすいとのこと。
それに、なにより可愛すぎる。
月の妖精を目の当たりにできた以上、ぼったくられているという感情は捨てるべきだ。
「へい、毎度あり!」
「くっ…!」
そういった納得を作り出す能力は、アギルタの最も得意とする商売道具であった。
ゲイルは今日もまた、女傑の罠に敗北したのであった。
「あのひと、いいひとだったね」
「うん、そうだね…うん」
なんとも言えない感情を抱えたまま、ゲイル達はブリオーンを出た。
とりあえず宿を探そう、と思いたち、目的地まで歩く。
その中で——
「あいや、君たち!テウアーズ印、飴雲売ってるよー!」
「!」
ルナが反応した。
屋台商人。
行商街に欠かせない屋台での売り物を提供する商人。
その商人が、不思議な綿のお菓子を持っていた。
「何ですか、それ?」
「機神テウアーの技術で作り上げた、口の中で解ける雲の飴さ!食べてみるかい?」
「たべれるの?」
「おうよ、綺麗な嬢ちゃん!家での土産話にもなるぞぉ!」
「ゲイル、たのんでいい?」
テウアーの技術、等と称されているが、要は機械仕掛けだ。
神術の一つ、機術によって構築された機構を用いて菓子を作り上げているのだろう。
興味津々な瞳で、ルナがこれを見つめていた。
その双眸は純真などきどきに包まれており、これを裏切ることはゲイルには出来なかった。
「すみません、二人分で」
「あいや!銅貨16枚頂くよ!」
ゲイルは転術を使わず、常日頃持っている貨幣袋から銅貨を指定数取り出す。
亜空にも貨幣は忍ばせてあるが、あくまで予備用だ。
擦られても良いように、普段は無いものとして扱っているのだ。
「ほら、ルナの分」
「うん!」
飴雲がまとわりついた棒を渡され、ルナはこれをのんびりと見つめた。
やがて「どうやって食べるの?」と聞いてきたので、少しずつかじるか、舐めればいいと伝えた。
「……おいしい!」
すぐに飴雲を平らげたルナは、再びこれをおかわりするのだった。
お金があると明日を生きる力になり、執筆の力に変わります。 応援されたぶんは、続きを出すことで感謝の気持ちに替えられればなと思っています。 自分は不器用なやつですが、その分余裕の有る方は助けてくだされば幸いです。
