
【カール・マルクスの生存戦略2パス目】「永久革命論」スキームからの脱出
まずは前回投稿で語られた知見について「準安定状態の発足・持続・終焉を観察する」進化論的アプローチの観点からまとめてみましょう。
ドイツにはまず「恣意的に既存の伝統的価値観を揺るがすと判断した発言を様々な形の取り締まりや自粛の強要によって阻止する」権威主義体制が実存し、カント(Immanuel Kant,1724年~1804年)やヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年~1831年)のディスクールの難渋さ、(数学界に物議を醸す研究の発表を見送った)数聖ガウス(Carolus Fridericus Gauss, 1777年~1855年)の沈黙などはこれに由来する。その一方で、そうした「公表される文献の難解さ」や「重要知識の秘匿」はパトロンや弟子を集める為の宣伝手段=生存戦略として機能していた。
「こんな中世同然の知的環境ではイギリスやフランスに敵わない」と考える若者達がヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)を結成したが、それが「今まで情報化されてこなかった領域の情報化=それまで2種類の出目しか観測されてこなかったコインの「3以上」、それまで6種類の出目しか観測されてこなかったサイコロの「7以上」を探す冒険の旅」になると予見出来たのはせいぜいカール・マルクス(Karl Marx,1818年~1883年)くらいで、残りは「歴史の掃き溜め送り=いかなる観測主体からも参照されない既存情報の事実上の外測化」を余儀なくされてしまった。
ただし、この観点はあくまで「ヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)の発足・持続・終焉」を観察する準安定状態の単位として設定した場合の観測結果に過ぎず、ここではむしろ文学者として不朽の名声を獲得したハインリヒ・ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797年~1856年)、当時は神秘的天才と誉めそやされたが後に「ただの時々頭がおかしくなるおじさんに過ぎない」と看過され「フランスのおでん屋にツケで飲むのを断られ、店の前で首を吊って死んだ哀れな末路」が語り継がれる事でかろうじて「歴史の掃き溜め送り」を免れたジェラール・ド・ネルヴァル(Gérard de Nerval, 1808年~1855年)の様な生き様は完全視野外に置いている。人類の知識がその様な多様体構造になっているからこそ、観測対象ごとに「(最外縁の補集合を空集合φ=0と置く)閉世界仮説」を採用して「(観測結果を個別感流する為に)隔壁を落とす」必要が生じるともいえる。
この様な状況を「準安定状態の発足・持続・終焉を観察する」進化論的アプローチは「適者生存というが、有効な生存戦略があらかじめ最初から定まっている訳ではなく、条件や定義によってもその内容は変わってくる=それ自体は多様体理論に従って(名義尺度でしか測れない)単極球状体(Monopolar Sphere)表面上の任意の点の間の関係として観測されるに過ぎない」と要約する。
ネルヴァルの例が暗喩するのは「時代精神(Zeitgeist)=歴史の任意の時点でのルベール測度において観測主体の間で共有される系統に残れる事を目指す」生存戦略もあり得るという事。例えば「東アジア文明圏の人間は漢文から、英国人やフランス人がラテン語文献から、ドイツ人はギリシャ古典からの引用を好む」といった人類の知的条件を珊瑚礁に例えれば、個々の観察主体の振る舞いがそれを形成する珊瑚虫のそれに重なってくるという事である。かかる状況を珊瑚礁=遺伝子側から眺めた景色は「ドーキンスの利己的遺伝子論」より、最先端の「中立進化説」に近い様に思える。そもそも個々の観察対象が共有情報に名を残す道を生存戦略をして選ぶ事と、珊瑚礁の全体像を超越的に決定する単一の意図が存在しない事は矛盾しないといえる。
もしかして、この話が以下の内容に関係してくる?
1844年8月から9月にかけての10日間エンゲルスがマルクス宅に滞在し、2人で最初の共著「聖家族」執筆を約束。これ以降2人は親しい関係となった。
この著作はバウアー派を批判したもので、「完全なる非人間のプロレタリアートにこそ人間解放という世界史的使命が与えられている」「しかしバウアー派はプロレタリアートを侮蔑して自分たちの哲学的批判だけが進歩の道だと思っている。まことにおめでたい聖家族どもである」「ヘーゲルの弁証法は素晴らしいが、一切の本質を人間ではなく精神に持ってきたのは誤りである。神と人間が逆さまになっていたように精神と人間が逆さまになっている。だからこれをひっくり返した新しい弁証法を確立せねばならない」と訴えた。
それではこの観察結果を魚類の進化の歴史と重ねてみましょう。
カンブリア大爆発から8000万年後の4億6000年頃の海の覇者は10~20年を掛けて体長5mを越す大きさに育つ(イカやタコの先祖)オウムガイ(鸚鵡螺、Nautilus)であったので、当時の古代魚は硬い外郭を身にまとい海底にへばりついて暮らしていた為に泳ぎはあまり得意ではなかった。
そうした古代魚のうち一部が(陸と海の挟間などで塩分濃度が安定してない)汽水域へと逃れ「既存生物の82%が死亡した」といわれるデボン期(4億800万年前~3億6000万年前)後期の大量絶滅を生き延びた。彼らのうち一部は海棲甲殻生物の覇権が終わった海に戻り、また別の一部はさらに陸の奥へと進んで両生類に進化した。
当時の「陸に上がった」古代魚の生存戦略について思いを馳せてみよう。①定期的に大量絶滅が起こる海はまだまだ怖い。②汽水域では既に「魚類の百獣の王」鮫の先祖が発生しており、彼らも一緒に海に戻るのだから生存環境の改善には自ずと限界がある。③その点当時の陸地にはまだ植物と昆虫しか存在しておらず、天敵に食われる心配をしなくて良い。
「革命の世紀の活動家の世界」への転身を決意した若きマルクスの場合はどうだったのでしょうか。もちろんその世界には既に数多くの古株活動家が闊歩していて「まだ植物と昆虫しか存在していない新天地」などではあり得なかったのです。
歴史の掃き溜め送りにされた「革命の世紀の活動家達の生き様/死に様」
とはいえここで天がマルクスに味方します。アーノルド・ルーゲ(Arnold Ruge,1802年~1880年)やオーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui, 1805年~1881年)を筆頭に、当時の古株活動家の多くは中世以来の伝統を誇る秘密結社的思考に拘束されており、新しい血を切実に欲していたのでした。
その一方で1848年以降、欧州全域に広がった産業革命の波がたちまち「国王と教会の権威主義への永久抵抗者達」を時代遅れの産物にしてしまい、彼らの存在そのものが「対消滅=歴史の掃き溜め送り=いかなる観測主体からも参照されない既存情報の事実上の外測化」を余儀なくされる展開を迎えてしまったという訳です。
経済人類学者カール・ポランニー曰く「保守派の思想的足跡の支離滅裂さを笑うな。彼らにとっては生き延びる為の現状への最適化こそが最優先課題。だからどんな無茶苦茶な方向転換だって恐れず遂行する。翻って我々革新派は理論的一貫性に拘泥し過ぎる。それで時代の遺物になりやすい…」。そしてまさにこうして「国家の集団脱皮」が加速した1848年改革以降の欧州では「国王と教会の権威主義に宣戦布告した」旧世代の既存活動家達の多くが脱皮の必要性を思い付く事すらなくただただ死に絶えていったのです。
それでは個別例の観測に移りましょう。
フェルディナント・フライリヒラート(Ferdinand Freiligrath,1810年~1876年)
ヴェストファーレン出身の詩人・翻訳家
1843年初めの『ライン新聞』の禁止や『ドイツ年報誌』への弾圧は、フライリヒラートにドイツの自由が失われつつあると気づかせ、政治に傾斜した詩を書き始める。
1844年8月、新しい詩集『信念の告白 Glaubenbekenntnis』が出版され、その詩集が表明している民主主義思想への弾圧を予期し、妻を連れてベルギーへ脱出する。ブラッセルでやはり亡命していたカール・マルクスと出会い、交友のきっかけをつくる。
1845年にスイスのマイエンブルクへ移り、自作の詩(O lieb,solang du liebenkannst)に曲をつけてくれたフランツ・リストの訪問を受けている。アメリカ詩人のバイヤード・テーラーがやってきたのもこの頃である。その年の秋にホッティンゲンへ居を移り、ゴットフリート・ケラーを知る。ユーゴーやフェリシア・ヒーマンズ、テニソン、ロバート・サウジーの詩を翻訳したのもこのスイス時代である。
1846年夏、ロンドンへ渡るが貧困に苦しみアメリカ移住を考える。
1848年2月からフランス・ドイツで革命が起こるとフライリヒラートはその進展を熱心に見守り、5月にはライン州デュッセルドルフへ行き、共和制とドイツ統一のアジテーターとして活動する。パンフレットに印刷され配布された彼の詩が、8月には革命煽動罪として司法当局によって告発され、10月の陪審裁判で無罪釈放となり、彼はライン地方で政治詩人・民主主義者として名が知れわたる。その月の下旬に『新ライン新聞』が創刊され、マルクスやエンゲルスとともに編集責任者の一人となり、詩を寄稿している。しかし翌年の5月17日には新聞はプロイセン政府の弾圧のもと廃刊を余儀なくされ、1851年5月にふたたびロンドンに亡命する。イギリスでは詩の編集や翻訳、ドイツ語新聞への寄稿、輸入商の事務員などで生計を立て、政治活動からは離れていく。
1855年頃にアメリカのウォルト・ホイットマンに注目し、紹介に努めるとともに独訳も進めている。
1861年にプロイセン国王による大赦令が出て1868年に帰国しシュトゥットガルトに住む。詩作とロバート・バーンズなどの独訳に専念し、ネッカー河畔のカンシュタットに没する。66歳没。
カール・シャッパー(Karl Schapper,1812年~1870年)
ヴァインバッハ出身のドイツ人革命家。秘密結社「正義者同盟」(別訳語:「義人同盟」)の創設者で、同同盟を「共産主義者同盟」へと移行させることを推進した人物。カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルスらを取り込み、対立するヴィルヘルム・ヴァイトリング派に抵抗した中心的存在である。また第一インターナショナルの総評議会委員もつとめた。
1831年、ギーセン大学の農林学科で学ぶ。この頃、学生組合に入り、1833年にはフランクフルト蜂起に参加。スイスに移ってジュゼッペ・マッツィーニのイタリア・サヴォア州遠征において亡命ポーランド人部隊とともに行動をしている。ドイツ人手工業者たちとも関係を結び、手工業職人協会創設に尽力した。その後、1834年創設の秘密結社「追放者同盟」の一部を吸収して新たな秘密結社である正義者同盟(義人同盟)を設立。
1839年、ロンドンに移ると、1840年2月に「ドイツ人労働者教育協会」を設立。この組織が各国の亡命活動家たちやチャーティスト運動の事実上の結集軸として機能することになる。以降は左翼活動家の国際的連帯を目指して運動を展開してい木、その過程で従来のルイ・オーギュスト・ブランキおよびヴァイトリングたちの考える直接蜂起行動の見直しを行い、独自の段階革命論の構想を持つに至る。ヴァイトリング派との対立を深める中で孤立していたマルクスとエンゲルスとの連携を決断。
1847年6月に共産主義者同盟第1回大会を行う。この際の綱領草案『共産主義の信条』はシャッパーのイニシアティヴにより書かれたものである。11月に第2回大会が行われ、この中で綱領の執筆をマルクスに委任することが決議される。こうしてシャッパーの校閲を経て1848年2月に出版された文書が『共産党宣言』(共産主義者宣言)である。
1848年革命挫折後は、革命の今後のあり方を巡り「ヴィリヒ=シャッパー派」としてマルクス派と対立。後に和解。1870年死去。
「マルクスの孤立」は、組織運営者としてはあんまりアレ過ぎたから。
1846年2月、ブリュッセルにロンドンのドイツ人共産主義者の秘密結社「正義者同盟」との連絡組織「共産主義通信委員会」が創設されるがマルクスの組織運営は独裁的と批判される。創設してすぐにヴァイトリングとクリーゲを批判して除名。そのあとすぐモーゼス・ヘスが除名される前に辞任し瞬く間に「民主的な独裁者」の悪名をとるようになる。
同時期マルクスはフランスのプルードンに参加を要請したが、「運動の最前線にいるからといって、新たな不寛容の指導者になるのはやめましょう」と断られ「可愛さ余って憎さ百倍」の精神で数カ月後プルードン批判する『哲学の貧困(1847年)』を発表。プルードンの著作『貧困の哲学(仏:Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère)』を階級闘争の革命を目指さず、漸進主義ですませようとしている物として批判した内容で、この中でマルクスは「プルードンは労働者の賃金とその賃金による労働で生産された生産物の価値が同じだと思っているようだが、実際には賃金の方が価値が低い。低いから労働者は生産物と同じ価値の物を手に入れられない。したがって労働者は働いて賃金を得れば得るほど貧乏になっていく。つまり賃金こそが労働者を奴隷にしている」と主張し、剰余価値理論を萌芽させた。また「生産力が増大すると人間の生産様式は変わる。生産様式が変わると社会生活の様式も変わる。思想や社会関係もそれに合わせて変化していく。古い経済学はブルジョワ市民社会のために生まれた思想だった。そして今、共産主義が労働者階級の思想となり、市民社会を打ち倒すことになる」と唯物史観を展開して階級闘争の必然性を力説する。そして「プルードンは、古い経済学と共産主義を両方批判し、貧困な弁証法哲学で統合しようとする小ブルジョアに過ぎない」と結論している。
新たな参加者が現れず、停滞気味の中の1847年1月、ロンドン正義者同盟のマクシミリアン・ヨーゼフ・モルがマルクスのもとを訪れ、マルクスの定めた綱領の下で両組織を合同させることを提案。マルクスはこれを許可し、6月のロンドンでの大会で共産主義通信委員会は正義者同盟と合同し、国際秘密結社「共産主義者同盟 (1847年)」を結成することを正式に決議した。またマルクスの希望でプルードン、ヴァイトリング、クリーゲの三名を「共産主義の敵」とする決議も出された。
「迂闊に近づきたくない爆弾」という印象ですね。正直、ヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)から脱して実際に1848年革命を経験して「迂闊な放棄は組織壊滅を招くだけ」と学ぶまでの間のマルクスには「永久革命論を否定する相手は(理論吸収はしても)最終的に相手を全面否定する」狂犬のイメージがつきまといます。それは彼なりの「革命の世紀の活動家」に混じって生き延びる為の生存戦略だった訳ですが、もしそれだけに終わっていたら彼ら同様の歴史的寿命を迎え、その後歴史に名前を残す事もなかった事でしょう。
ヴィルヘルム・ヴァイトリング(Wilhelm Weitling, 1808年~1871年)
手工業職人出身のドイツ人革命家
当時ドイツの手工業職人は、昔からの修業上の慣わしとして、またよりよい労働条件を求めてヨーロッパ諸都市を渡り歩いた。ヴァイトリングも1826年~1827年頃、腕一本で飯を食う遍歴職人となって故郷をあとにした。1830年代初にはライプツィヒの仕立作業場で働き、その後ウィーンへ、さらに1835年にはパリへと渡り歩く。
もともと革命騒ぎの多い都市パリで、亡命ドイツ人の共和主義的な秘密結社・追放者同盟に加入。その後1836年4月一度ウィーンへ行き、1837年9月ふたたびパリへ戻って、今度はドイツ手工業職人中心の新結社・正義者同盟に加入。指導部のカール・シャッパー派としばしば対立した。
既に18世紀フランス啓蒙思想や19世紀フランス社会主義思想を独学で習得していたヴァイトリングが処女作『人類、そのあるがままの姿とあるべき姿』(Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte, Paris、1837年)を発表。この著作中では機械化の促進による労働の軽減および時短による自由時間の創出を要求し、農民や職人が同時に芸術家や思索家である共同社会「財産共同体(Guetergemeinschaft)」の思想が打ち出されている。
1839年5月パリでブランキら四季協会(季節協会)が暴動事件を画策。この暴動と正義者同盟のとの関係は不透明だが、この夜にシャッパーが逮捕され、ロンドンに追放される。これに伴い、同盟内部は組織的に打撃を被り、混乱状態に陥る。ヴァイトリングはこの時点でパリを離れていたため逮捕を免れた。その後正義者同盟の再建を企図しスイスのジュネーヴへ移り、雑誌『ドイツ青年の救いを叫ぶ声』を創刊。主著『調和と自由の保証』を刊行する。バクーニンはこの頃、スイスにおり、共産主義者時代の彼の「見えざる独裁」理論にヴァイトリングの三月革命前の独裁理論は大きな影響を及ぼした。また、若きマルクスに対しても共産主義思想形成上で影響を与えたことが推測される。
1843年『貧しき罪人の福音』を完成させるが、その中ではトーマス・ミュンツァー的な千年王国論・メシア共産主義を説き、実践面では社会的匪族(Sozialbandit)による徹底的な所有権攻撃を提起した。この著作の為にチューリヒ州警察に逮捕される。同年秋にはスイスからプロイセンへ護送され、翌1844年プロイセンからも追放され、同年8月ロンドンへ着く。
ヴァイトリング派は正義者同盟ロンドン本部のシャッパーと「革命か啓蒙か」の路線をめぐり討論を闘わせ、しばしば対立した。また1846年3月にロンドンからブリュッセルへ渡り、マルクス派とも連携を試みるが、マルクスとも革命論をめぐって対立する。いずれの論争も決裂に終わり、1846年末、大西洋を渡ってニューヨークに上陸。解放同盟(Befreiungsbund)を設立。
1848年革命勃発に際して一度ドイツへ戻るが、1850年にはニューヨークで移住ドイツ人労働者に向けて宣伝機関誌『労働者共和国(Republik der Arbeiter)』を発行し、1851年アイオワ州クレイトンで共産主義的なコロニー「コムニア」(1847年設立)の運営に参加、さらには1852年労働者同盟(Arbeiterbund)を結成。こうしてアメリカでも精力的に社会改革・労働運動を継続していったが、ニューヨークに来てからのヴァイトリングの思想と行動には、フランスの社会主義者・アナキストのピエール・ジョゼフ・プルードンの影響が俄然強烈に印象づけられる。それは、交換銀行と協同企業、一言で表現すれば労働者アソシアシオンの標榜である。労働者協同企業と交換銀行の連携によるアメリカ大陸横断鉄道の建設はそのハイライトである。しかし、アメリカ社会の激しい資本主義的転変の渦中で、労働者協同社会を展望するというヴァイトリングの構想は行き詰まり、1860年代には政治的・社会的活動から引退。
1854年に同じドイツ系移民だったカロリーネ・トッドと結婚し、6児をもうけた。1871年1月インターナショナル・ニューヨーク支部の親睦会に出席した直後に死去。
欧州における活動に限界を感じてアメリカに新天地を求めたヴァイトリングでしたが、そもそも「国王と教会の権威主義体制に手工業者の秘密結社で対抗する」土壌が存在しない土地柄だった上に、対立図式が工場主と工場労働者の利害調整に推移していく重厚主義的発展を目の当たりにして容赦無く「歴史の掃き溜め送り」を余儀なくされてしまった訳です。
ゲオルク・ヘルヴェーク(Georg Herwegh, 1817年~1875年)
シュトゥットガルト出身のドイツ人政治詩人
法定期限の軍務に服している時に上官と2回もトラブルを起こし、1839年に国境を越えてスイスに逃亡。1841年に政治詩集である『生けるものの詩』(Gedichte eines Lebendigen) を発刊、1万5千部を売り上げ、一躍人気作家の仲間入りを果たした。
以降、ドイツ民主主義の偶像となり、1842年に帰国しプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルムに謁見を許され、王をして「あっぱれな敵手に敬意を表する」とまで言わしめたが、その後すぐにプロイセン警察から国外へ追放され、プロイセン宮廷の御用商人の娘エンマを連れ1843年にスイスのバーデンで結婚した。イタリアをへてパリに到着し、ダグー伯爵夫人の寵愛を受けイワン・トゥルゲーネフやパーヴェル・アンネンコフ、ニコライ・オガリョーフやミハイル・バクーニン、アレクサンドル・ゲルツェンと交際するようになった。
1848年にパリで2月革命が起こり、3月にはパリ在住のドイツ民主主義者が委員会をつくり、フランス民主主義への祝辞を贈ることとドイツの革命運動を援助することを決定。ヘルヴェークが委員長に選出された。妻のエンマが主導者として600の義勇兵を組織し、シュトラスブルクを出発しバーデンに向かう。4月27日にスイスの正規軍と国境付近のドッセンバッハで遭遇、50人の犠牲者を出して義勇軍は壊滅しフランスへ逃げ帰る。
政治的にも経済的にも窮迫し、1849年にかけて友人となったゲルツェンの家庭を訪問するようになったが、その年の夏からゲルツェンの妻ナターリヤと不倫関係に陥った。この関係は1851年まで続き、ヘルヴェークはゲルツェンから絶交を申し渡され、一家でジェノヴァに退去した。
その後は諷刺雑誌への投稿、ドイツ総合労働者協会 (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) に参加するなどしたが、かつての評判は取り戻すべくもなかった。その後はバーデン=バーデンに定住し、同地で没した。
こうして全体像を俯瞰すると、1848年革命勃発によって、皮肉にもそれまで欧州中に潜伏していた革命家ネットワークがまとめて一気にその準安定状態を失い「武力には武力で対抗するしかない」現実が急速に浮上してきたとも見て取れます。
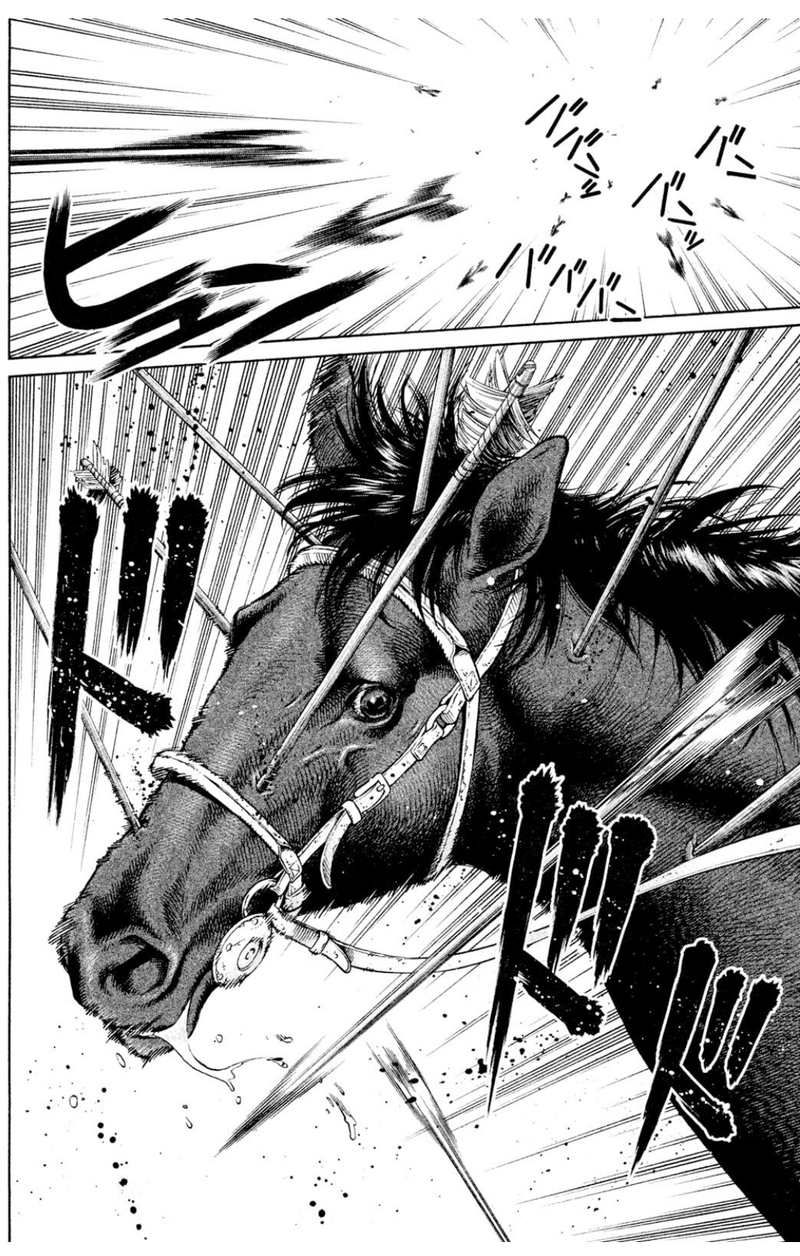
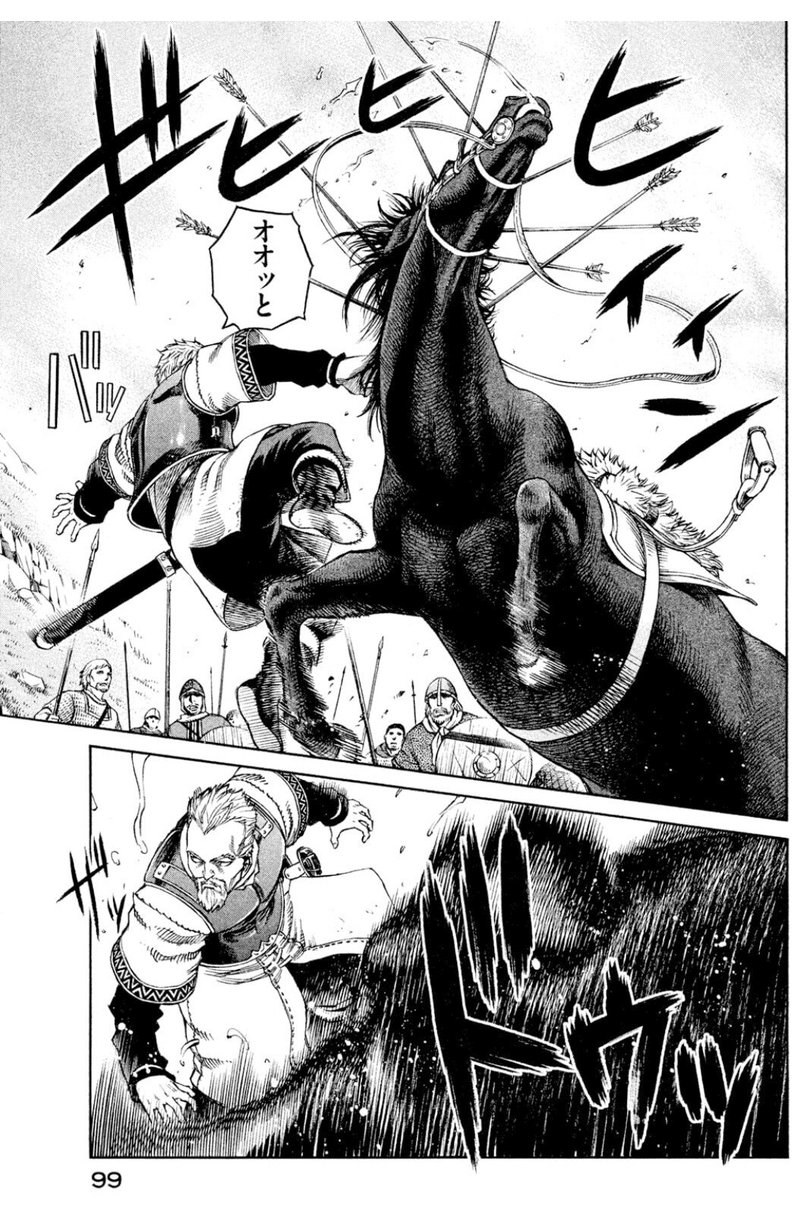
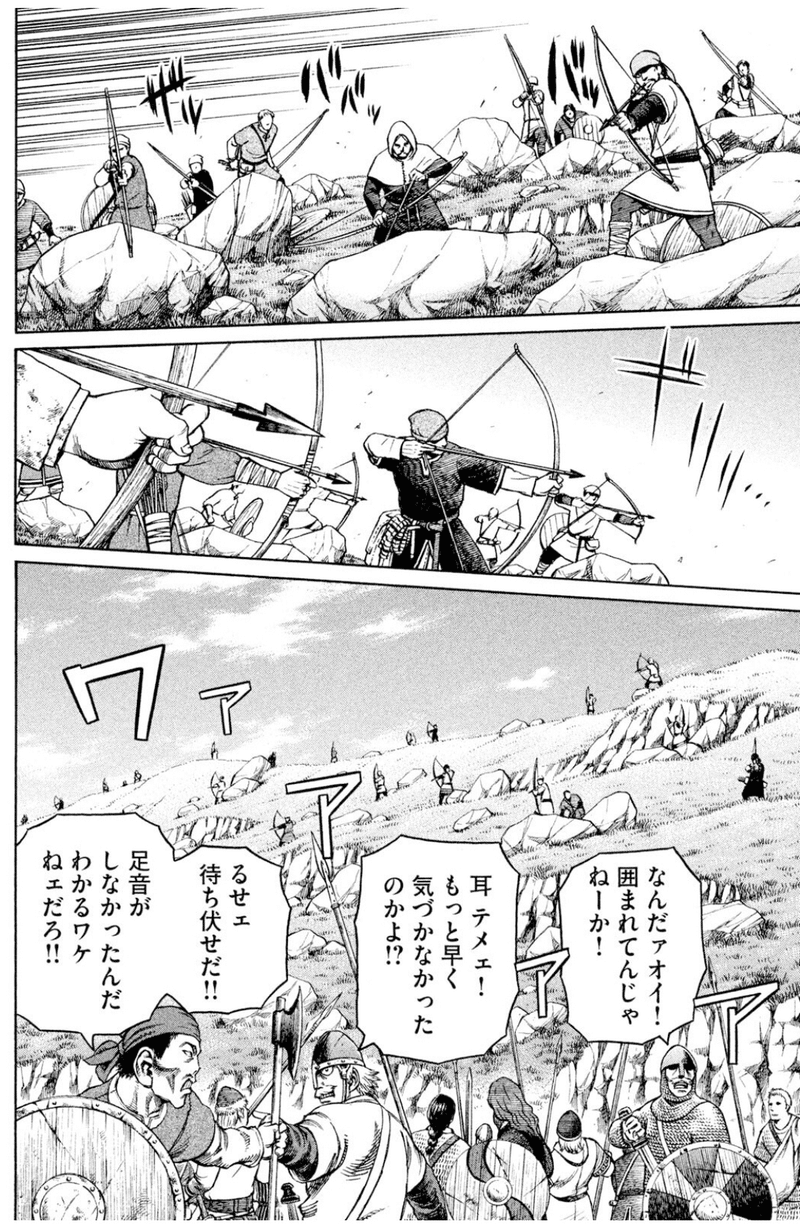
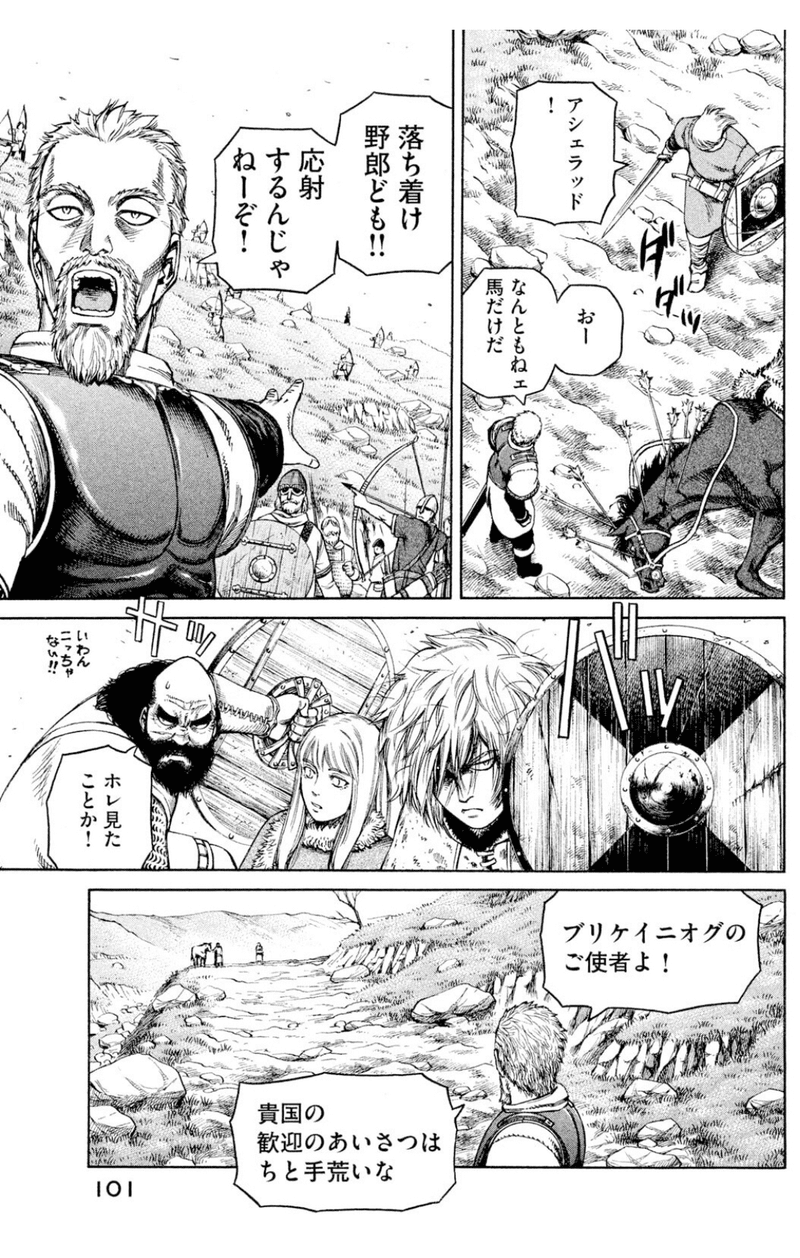
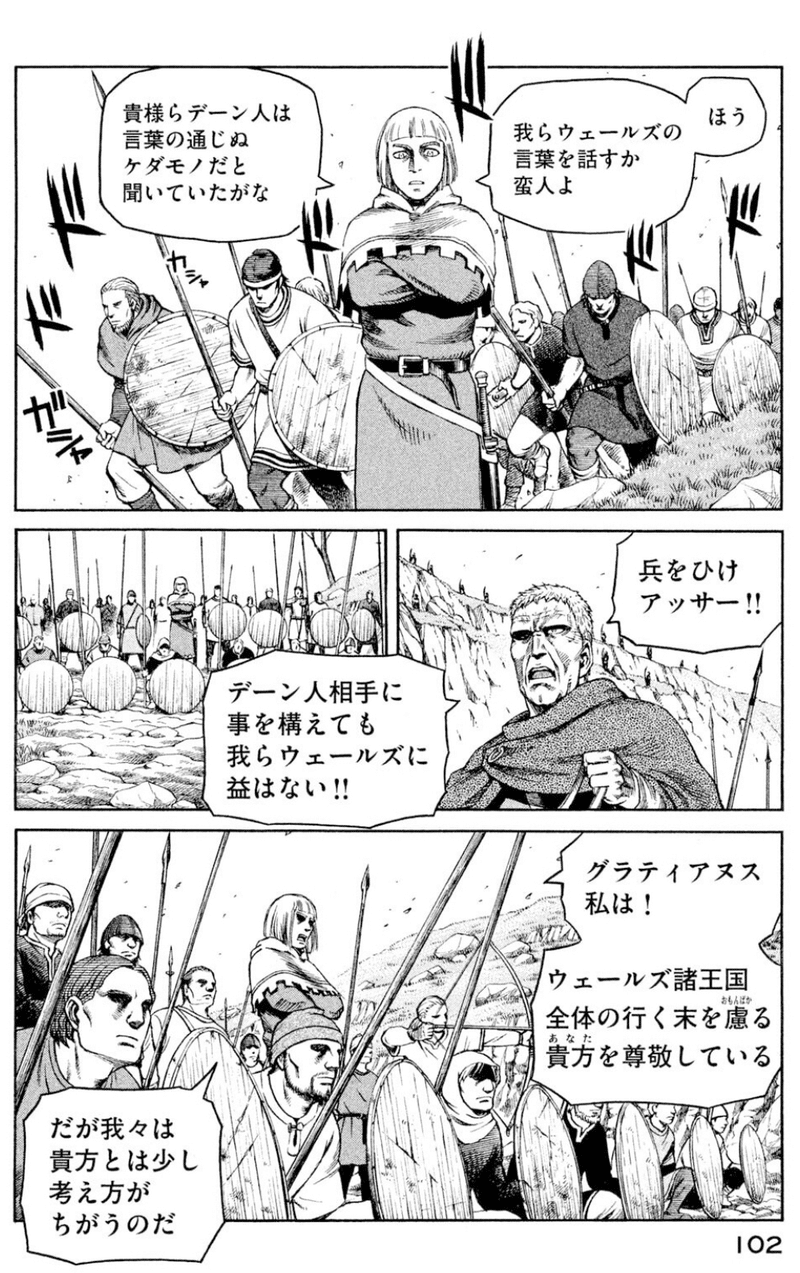
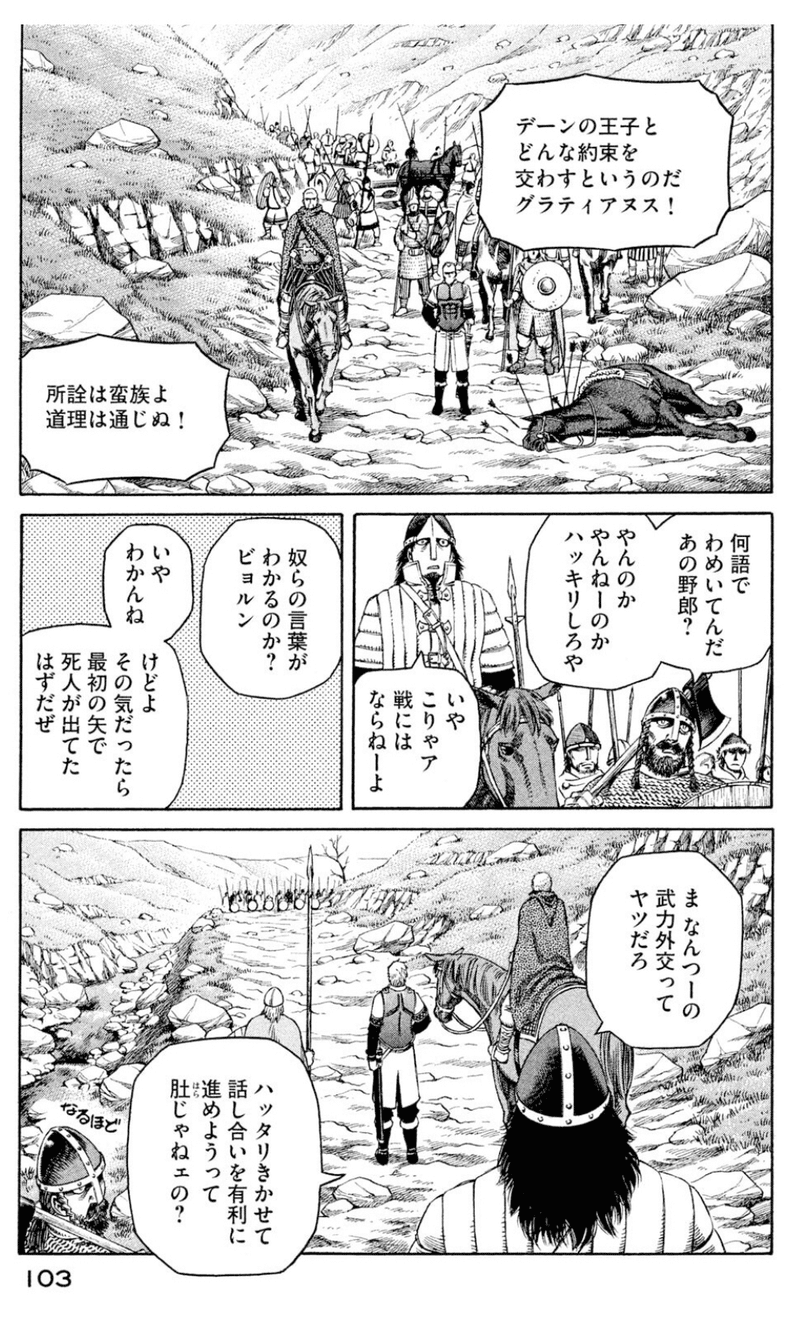
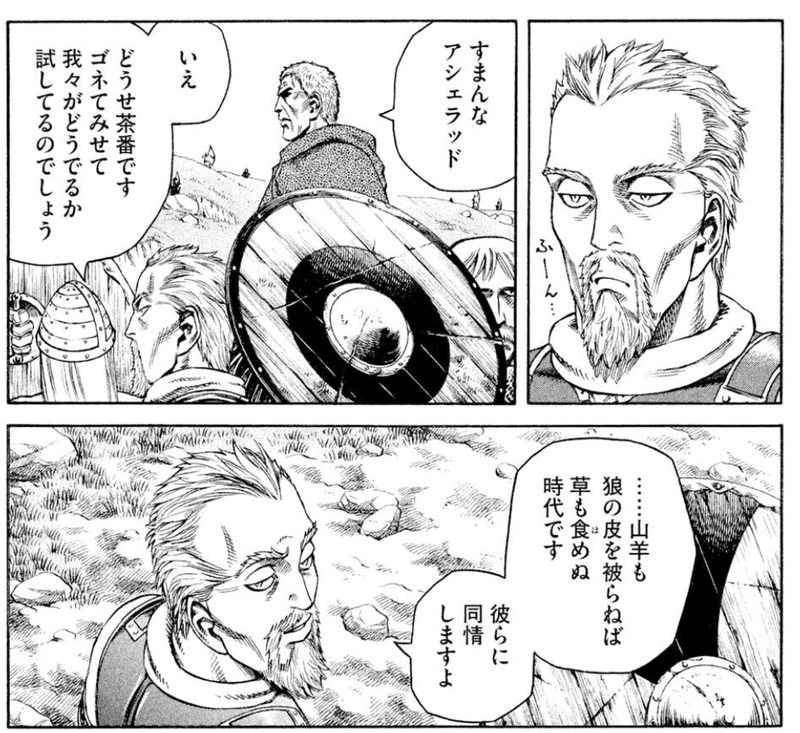
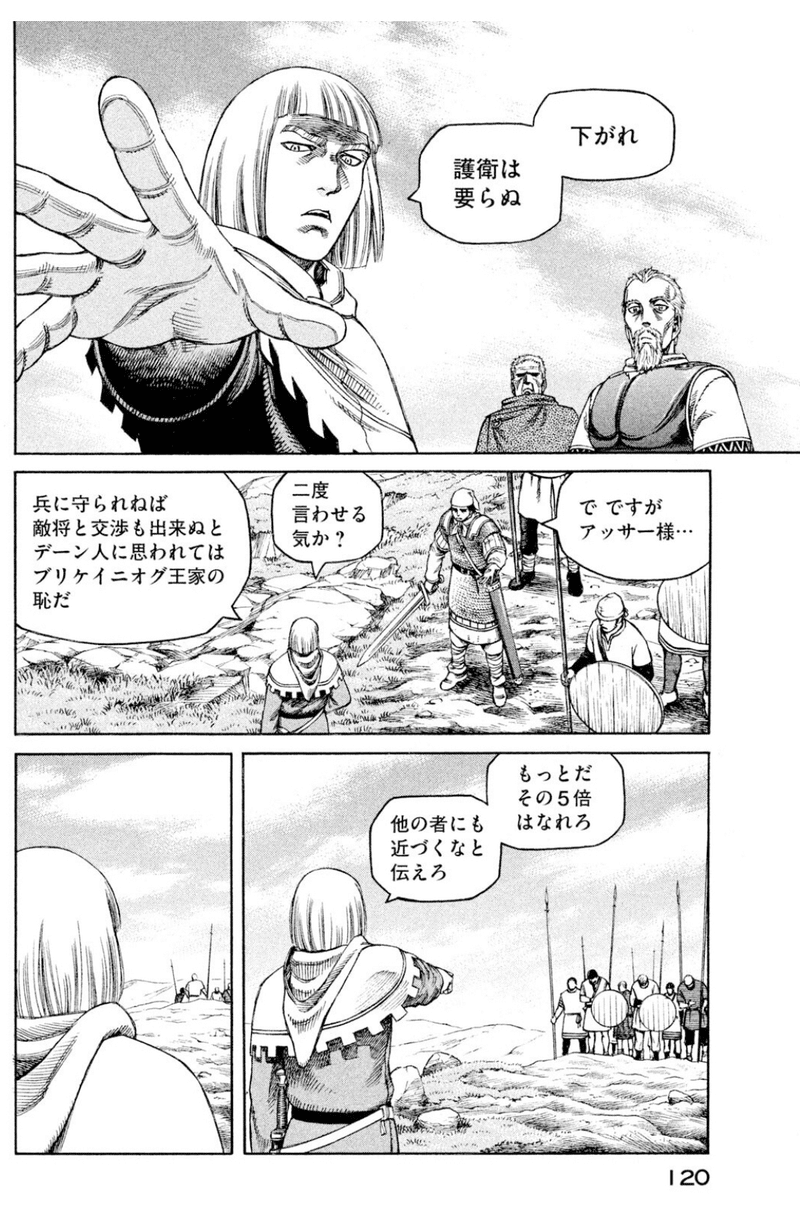
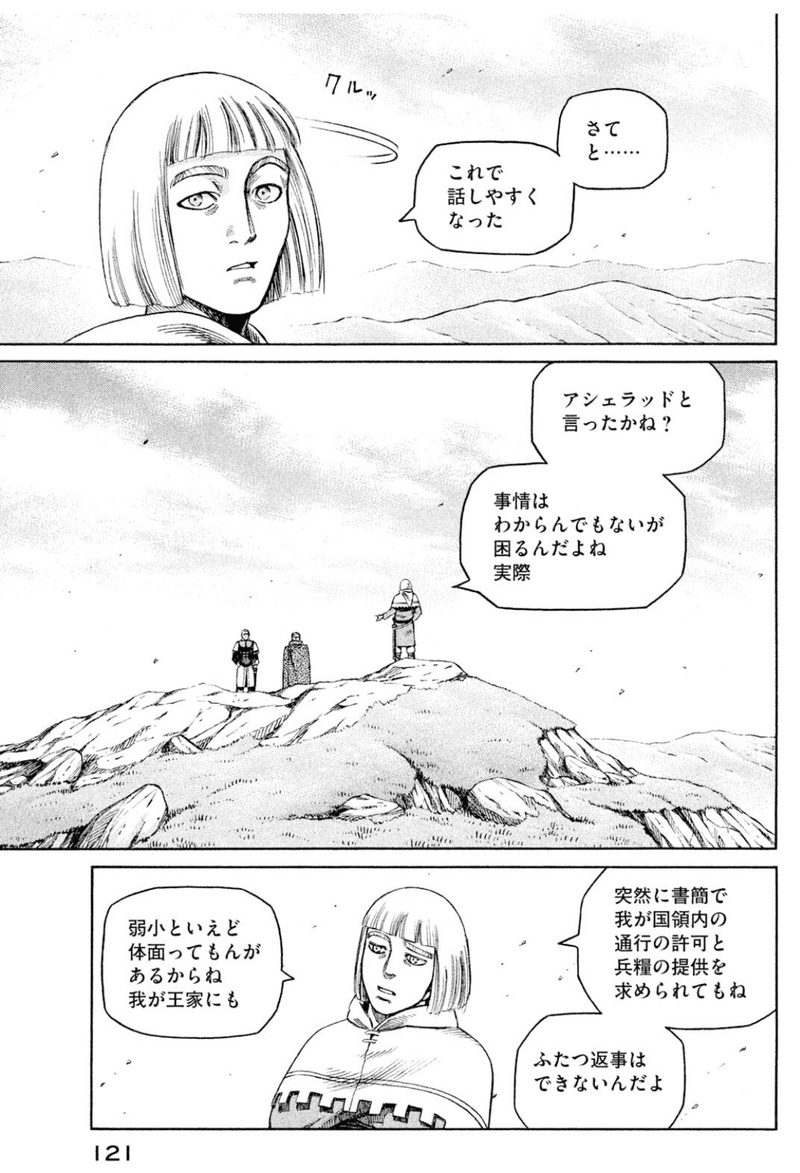
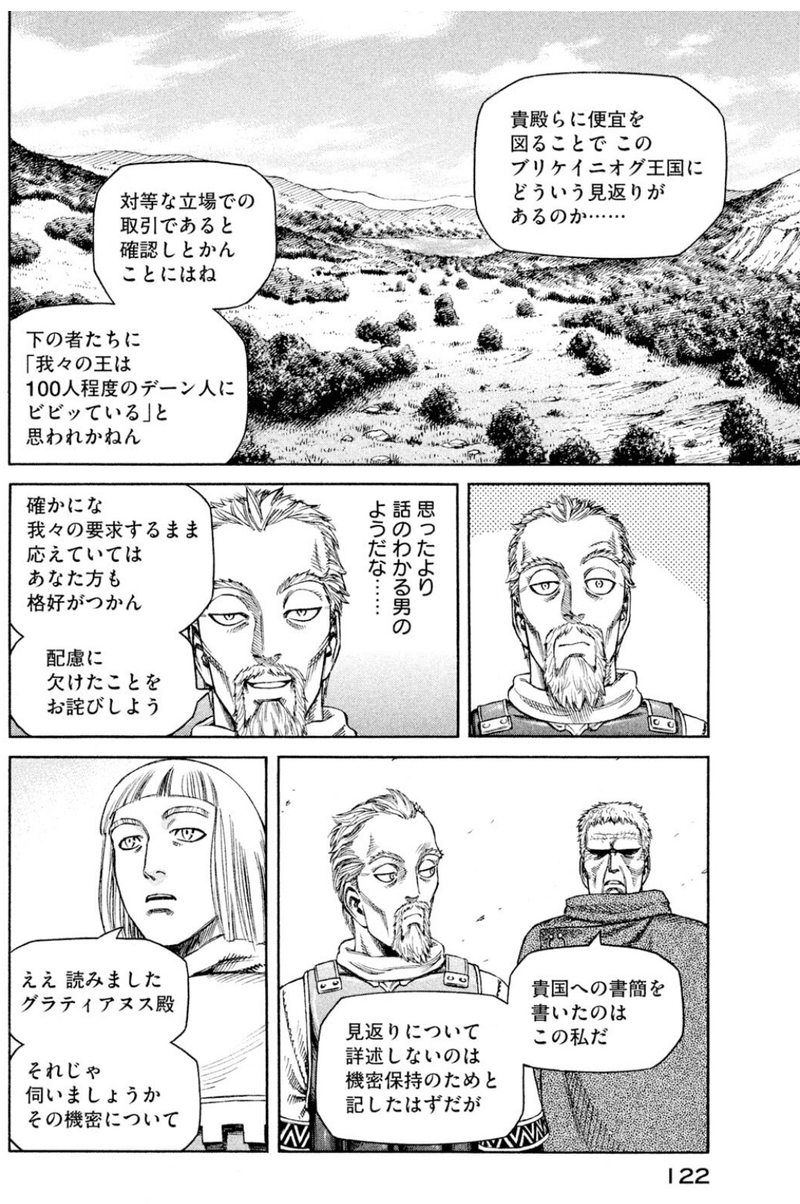
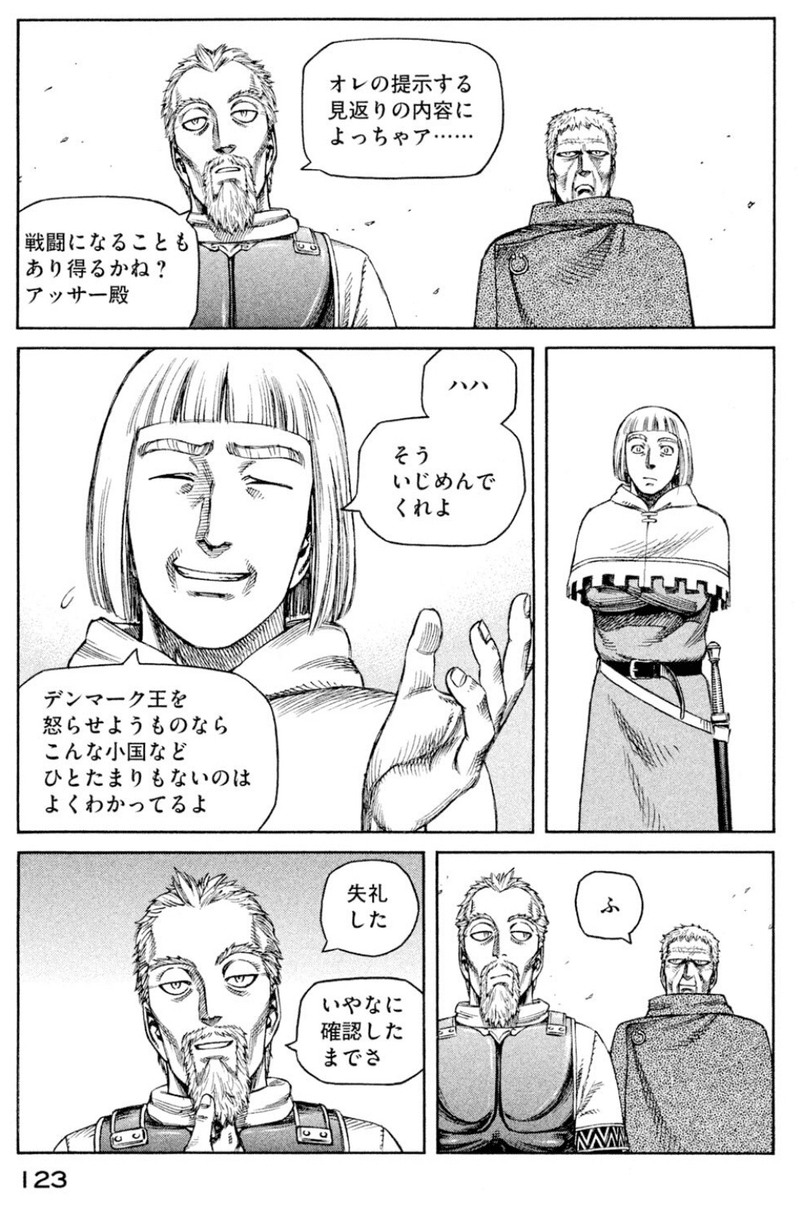
プロイセン国民議会が停会する直前に納税拒否を決議したので、マルクスはこの納税拒否の決議をあくまで推進しようと11月18日「民主主義派ライン委員会」の決議として「強制的徴税はいかなる手段を用いてでも阻止せねばならず(徴税に来る)敵を撃退するために武装組織を編成せよ」と宣言。フェルディナント・ラッサールがデュッセルドルフでこれに呼応するも11月22日に反逆容疑で逮捕されてしまう。マルクスも反逆を煽動した容疑で起訴され、1849年2月8日に陪審制の裁判にかけられたが陪審員に反政府派が多かった為無罪判決を勝ち取る。おかげで『新ライン新聞』はその後もしばらく活動できたが、軍からの警戒は強まり3月2日には軍人がマルクスの事務所にやってきてサーベルを抜いて脅迫したが、マルクスは拳銃を見せて追い払った。エンゲルスは後年に「8000人のプロイセン軍が駐屯するケルンで『新ライン新聞』を発行できたことをよく驚かれたものだが、これは『新ライン新聞』の事務所に8丁の銃剣と250発の弾丸、ジャコバン派の赤い帽子があったためだ。強襲するのが困難な要塞と思われていたのだ」と語っている。
19世紀後半に入ると欧州における革命運動の主戦場は産業革命導入の為に「後進国」ハプスブルグ君主国から脱しようとするサルディーニャ王国王統サヴォイア家によるリゾルメント(Risorgimento=イタリア統一運動,1815年~1871年)と、プロイセン王国王統ホーエンツォレルン家がオルミュッツ協定(1850年)の雪辱を果たしたドイツ帝国(1871年~1918年)建国過程へと推移した訳ですが(かつてイングランドのノルマン朝(1066年~1154年)やプランタジネット朝(1154年~1399年)が単なるフランス・カペー朝(987年~1328年)の臣下でなく独自に王の称号を有していた事がイングランド独立の鍵となった様に、この時代にはサヴォイア家やホーエンツォレルン家の王の称号がハプスブルグ君主国からの分離独立運動の鍵となった)、かかる新たな準安定状態の到来に「ヘーゲル左派からの転戦組」たる「狂犬」マルクスは既にある程度まで前適応を終えており、現実の1848年革命の洗礼を受ける事ではっきりとした自覚に至った側面がある様に思えます。
とはいえ「革命の世紀の活動家の一員」として彼ら同様かかる新状況への適応までは出来ず、「経済学批判(Zur Kritik der Politischen Ökonomie, 1859年)」出版時のパトロンにして「社会民主主義の父」ラッサール(Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle, 1825年~1864年)と決別。現場活動家としての経歴はそこで終焉してしまったという訳です。
「恐慌原因説」からの脱却
当時の欧州革命家達の視線には「1848年革命は1847年恐慌を原因に起こった」なる観点が存在した様です。
田中克尚「1847年恐慌とJ.ウイルソンの見解 : 不均衡理論の一典型」
それで彼らは次の恐慌到来を待望する様に…おや?何か聞こえてきたぞ?
宋人有耕田者,田中有株,兔走,觸株折頸而死,因釋其耒而守株,冀復得兔,兔不可復得,而身為宋國笑。今欲以先王之政,治當世之民,皆守株之類也。
宋(殷の後裔が封ぜられた国)の人が田を耕していた。田の中に切り株がある。そこへ走って来た兎が、切り株にぶつかり、頸を折って死んだ。その人はそこで鍬を捨てて、じっと切り株の番をして、また兎がぶつかるのを待っていた。しかし兎はもう手に入らず、その人は国じゅうの笑いものになった。今、先王の政を以て、当世の民を治めようとするのは、すべて切り株の番をする類いである。
再び訪れた準安定状態存続の危機…そさいてここで再びマルクスの「今まで情報化されてこなかった領域の情報化=それまで2種類の出目しか観測されてこなかったコインの「3以上」、それまで6種類の出目しか観測されてこなかったサイコロの「7以上」を探す冒険心」が炸裂した訳ですが、流石にすぐではなかった模様…
淡路憲治「パリ・コミューンとマルクス(1)」
マルクスとエンゲルスは,次の恐慌の時期を52年と予測した。しかし,52年恐慌の予測ははずれた。すると彼らは52年から56年の時期にかけて,次々と来る年も来る年も恐慌の予測をしたが,そのいずれもがはずれた。しかし,1857年には,資本主義史上,最初の世界恐慌ともいうべき本格的恐慌がやってきた。彼与は,この57年恐慌にひきつづきやって来るだろう革命にすべてを賭けた。しかし,結局,この57年恐慌の時期もまた彼らの革命への期待ははずれた。こうした推移に関連して,後年のエンゲルスは,『階級闘争』への1895年の例の「序文」で次のように回顧ししている。
まずエンゲルスは,例の50年秋の新見解の提出について,「われわれは少くとも革命の第一局面は終ったこと、そして新しい世界経済恐慌が勃発するまでは,なにごとも期待できないことを,すでに50年秋に声明した」と述べ,それは従来の見解の「一つの本質的訂正であった」と自己批判している。
ところが1857年恐慌の時期においてもまた,彼らが期待したような革命がお
こらなかった。その点に関連して,彼は次のように述べる。 「しかし,歴史
は,われわれの考えをもまた誤りとし,当時のわれわれの見解が一つの幻想
であったことを暴露した。歴史はそれ以上のことをした。」「歴史は,大陸における経済発展の水準が,当時まだとうてい資本主義的生産を廃止しうるほどに成熟していなかったことを明白にした。歴史は,これを1848年いらい全大陸をまきこんだ経済革命によって証明した。」
ここでは,50年秋以前の見地の「本質的訂正」として打出された, 「恐慌→革命」説もまた,1857年恐慌の体験をとおしてみるときは,「一つの幻想」にすぎなかったことが語られている。
(中略)
こうして,1850年秋における,革命の早期再燃の予測とブランキ主義的見地の否定にひきつづいて1857年恐慌を体験した後において,永続革命論がマルクス,エンゲルス において決定的に影をひそめることになったと考えられる。
こうして話は、私の提唱する「1859年認識革命」説へと繋がっていく次第。
こうして話が一巡した辺りで以下続報…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
