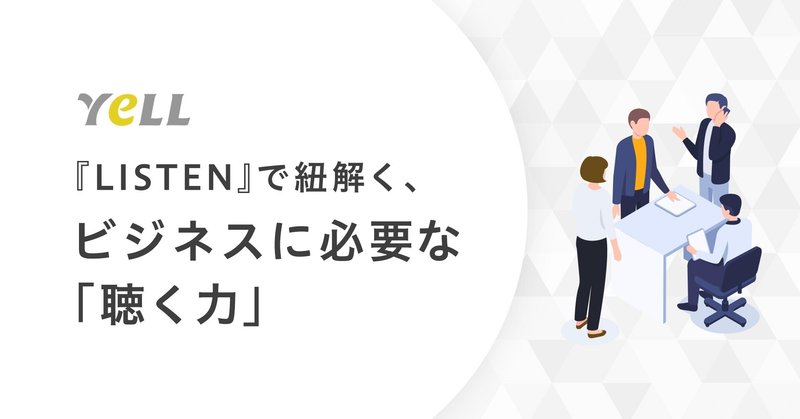
『LISTEN』で紐解く、ビジネスに必要な「聴く力」|聴き合う組織をつくる『YeLL』のnote
聴き合う組織をつくるべく、ビジネスの現場に「聴くことの大切さ」を広めていこうとしているエール。
このたび、新たに1on1力向上 オンライン研修プログラム「YeLL|聴くトレ」を開発し、1人ひとりの聴く力を向上させていく体験型学習サービスを提供することになりました。年間8,000回以上の社外人材による1on1セッションを提供しているノウハウを活かし、良質な聴かれる体験と言語化する体験を味わっていただける内容となっています。
先日発売された『LISTEN―知性豊かで創造力がある人になれる』(日経BP)でも、「聞くことはビジネスの原点である」という話が、多く紹介されていました。中でも印象的だったのが、2012年にグーグルで調査・分析されたプロジェクト・アリストテレスに関する記述です。
グーグルではほとんどのプロジェクトをチームで取り組んでいます。メンバーが仲よくなって業務をどんどん片づけるチームもあれば、敵意やつまらない不満をつのらせ、それが内輪もめや陰口、無視やサボタージュなど組織の機能不全につながるチームもあり、なぜ違いがあるのかを知りたいと考えたからです。(『LISTEN』P230より引用)
そこで明らかになった、人が一緒に効率よく働くために必要な性格、プロセス、エチケットとは何だったのでしょうか?
「素晴らしいチーム」の誕生には、何が必要なのか———『LISTEN』を中身を紐解きながら、エールが新たに開発した1on1力向上オンライン研修プログラムについてご紹介します。【編集部 林】
もっとも生産性の高いチームにあったもの
プロジェクト・アリストテレスには、統計学者、組織心理学者、社会学者、エンジニアなど多様なメンバーが集結。グーグル内にある180チームを分析し、素晴らしいチームが生まれる理由を細かく調べ、共通するパターンを探りました。人柄、バックグラウンド、趣味、生活習慣、チーム構成、進捗管理・・・あらゆる側面から3年間、データ収集を続けて、ようやく結論を導き出します。
それが、「もっとも生産性のあるチームはメンバーの発言量が大体同じくらい」「社会的感受性の平均値が高い」という事実でした。
つまり、声のトーンや顔の表情など非言語的な手がかりをもとに、お互いの感情を直感的に読み取る能力に長けていたのです。
言い換えると、グーグルの調査で明らかになったのは、成功するチームではメンバーの話をお互いに「聴き合って」いたと言うことです。
メンバーは交代で発言し、お互いの話を最後まで聞き、言葉にされていない考えや感情を理解するために、非言語の手がかりに注意を払っていました。
そのため、チームの人たちは思いやりがあり、その状況に合った反応をするようになりました。さらに「心理的安全性」と呼ばれる、言葉を遮られたり意見を一蹴されたりする心配をせずに、情報やアイデアを交換しやすい雰囲気をつくっていたのです。(『LISTEN』P231より引用)
仕事に感情を持ち込むことに、抵抗を感じる方は少なくないでしょう。「個人的な好き嫌いや、その日の気分次第で、仕事のパフォーマンスが左右されるなんてあり得ない」と思ってしまうのも、当然です。ところが、感情を持ち込む方がお互いを理解し合えるようになり、発言しやすい状況が自然とつくられ、結果として生産性が上がっていたのです。
1950年代から言われていた「聞くこと」の大切さ
実はこの発見は、すでに傾聴研究の父であるラルフ・ニコルスが1950年代に主張していたものと重なっています。当時は「聞けるようになれば仕事がよりよくできるようになるだろう」と論じられていたそうです。
1980年以降に雇用が拡大した職業はほぼすべて、高いレベルで人間関係づくりが求められるものです。
一方で、主に分析的思考や数学的思考(そこからアルゴリズムがつくれるもの)が必要となる仕事は、なくなりつつあります。(『LISTEN』P231より引用)
現代ではなおさら、人間関係にまつわる悩みはつきません。エールにも日々、さまざまな企業からお悩みが寄せられています。
<実際にいただいたお客様の声>
●リモートワークでメンバーの様子がわかりづらい、コミュニケーションに課題を感じる
●管理職と現場リーダー・メンバーの意識に温度差を感じる
●対策として1on1を行うが、具体的な進め方は自己流で、効果が出ているかわからない
●部下のモチベーションや気持ちを引き出す話の聴き方がわからない
まずは、自分の感情に耳を澄ます
「聴くことは大切なんだ」と意識できたとしても、すぐに全社員が聴けるようになり、最強のチームが誕生するわけではありません。具体的に、何をどうすれば良いのでしょうか。
その答えが、「感受性」という言葉に隠されています。
会話の感受性が高い人は、話された言葉に注意を払うだけでなく、そこに隠された意味に気づいたり、声のトーンの微妙な変化を察知したりするのに長けています。(中略)また、会話の感受性は共感の前段階で発揮されるものと考えられています。共感を抱くには、自分がこれまで経験した関わりの中で抱いたり学んだりした感情を呼び起こし、それを発生した状況に適用する必要があるためです。(『LISTEN』P256より引用)
さらに会話の感受性が高ければ、不安を感じることなく人の話を聞き、あらゆる意見に耳を傾ける「認知的複雑性」も高まるそうです。
多くの人の話を聞いた経験がないと、会話に出てくる微細なシグナルにうまく気づくことはできません。
直感や第六感と呼ばれるものは、実は気づく力でしかない、と言われます。
多くの人の話を聞けば聴くほど、人間が持つ多様な側面に気づくようになり、直感も冴えるようになります。(『LISTEN』P257より引用)
つまり、話を聴いて自分が何を感じているのか———自分自身の感受性に気がつくところから、始める必要があるのです。自分の内側に湧き上がった感情を相手に伝えていくことは、チームの生産性向上へと少しずつ繋がっていきます。
「聴く力」は、ビジネススキル
もちろん、一朝一夕に実現できるものではないでしょう。チームのメンバー全員がお互いを「聴き合える」ようになるまでには、それ相応の時間もかかります。さらにコロナ禍における社会情勢の変化から、「もう少しスピーディに、事業変革に取り組みたい」とのニーズも増えてきています。もはや「聴く力」は、ビジネスを円滑に進めていく上で欠かせない、必須スキルであると言えるでしょう。
次回のnoteでは、実際に1on1力向上 オンライン研修プログラム「YeLL|聴くトレ」の開発に携わったエール開発責任者の声をご紹介します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
