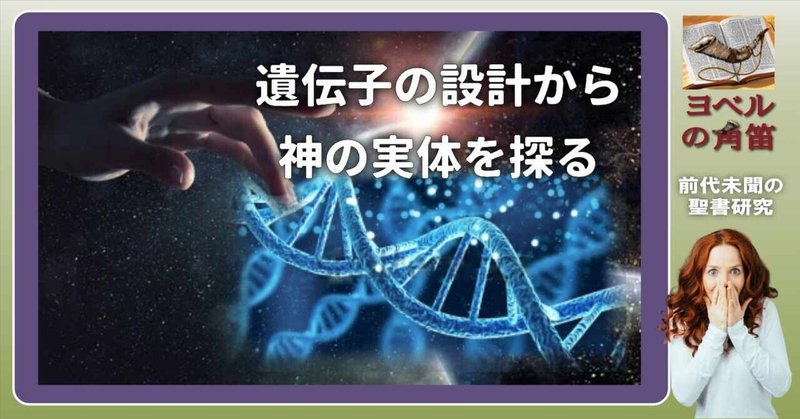
遺伝子の設計から神の実体を探る 第四章
■第四章 子なる神と人との関係
聖書中の様々な箇所で言及されていることから明らかなように、キリストとして住まれた元の存在、つまり「独り子、言葉、ロゴス」は私たち人間の創造に与ったのですから「神」と呼ばれる正当な方であることは明白です。
これまでに、神とみ子との関係、そして両者と人問男女の関係について考えてきました。
最終章として、み子と人間との関係についてさらに考察を深めたいと思います。
ここで、これまでの四つの記事の中で述べてきた要素がすべて合体することになります。
ここでは「家族」というキーワードに沿って、み父、み子、男、女の関係について論じてみたいと思います。
家族の創始者は神です。子孫繁栄のための生殖の機能を人に付与され、結婚という取り決めを定められたのも神です。
そこから、夫婦、父、母、子などの概念が生まれ、そうした人間にとって理解しやすいように、霊的な存在に関しても、み父、独り子、神の子たち(天使)などの表現によって聖書が記されていることが分かります。
神は物質の存在ではないので、たとえば神の手、足、目という表現などは確かに比喩の類かも知れませんが、しかし、そもそも人が「神の像(image)」に造られているということを考えますと、神がご自身を人間の姿にたとえた比喩というより、むしろ逆で神の顔、手、足、目の玉などの霊的な特質(属性)が具現化されたものが、文字通りの人間の顔や手や足として形になっているのではないかと思います。
以前にも書いたことですが、「人格神」という表現がありますが、辞書にはこのように記されています。
【人格神 じんかくしん personalgods:とは
宗教学の用語。固有の知性と意志をそなえ,独立した個体的存在として考えられた神または神聖なるものをいう。キリスト教の神ヤハウェやイスラム教における神アッラーが典型。】一 ブリタニカ国際百科事典より
人が神に造られたわけですから、神に人格があるというより、人に神格があるという方が事実に即していると思います。ですからわたしはよく、神が人格神なのではなく、人が神格人などだと言ってきました。
《神について知りうる事柄は、彼ら(不信心と不義なもの)にも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が造られときから、目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。従って、彼らには弁解の余地がありません。》(ローマ1:19、20)
被造物を通して神を知ることができる、いやむしろ、そのように神ご自身が意図されているということですから、なおのこと「人間」の人格特性を通して神の「神格、神性」すなわち、より神らしいところを知ることができるようになっていると断言できるでしょう。
罪が入ったとはいえ、人間も神の子であり(ともかく本来の造りとしては)神のかたちなわけですから、よく似ているはずです。
もし一人の神のうちに三つの位格(ペルソナ)が存在し、目的や状況にとよってその現れ方が異なる、というような神学/教理が真実であるなら、当然、人間にも三つの人格が備わっていて、状況によって、的確な人格が表に出てくるはずです。そうではありませんか。
もしそうでないなら、人は神に似てもおらず、神のかたちにはなっていないということになります。
「ペルソナ」はもともとラテン語で「仮面」を意味する語です。
もっとも、かつてはそうした「多重人格」と呼ばれていたものは、最近では「解離性同一性障害」と呼ばれますが、一人の人間にある複数のペルソナ(パーソナリティ)のうちのひとつが、状況によって外に現れるという病理があります。しかしそれは決して本来の人のあるべき姿ではないでしょう。
ともかく、家族的な、人との関わりやその形態も、やはり「神のかたち」のうちに含まれるでしょうから、人間の間に見られる夫婦や親子といった感覚やシステムは、神に由来するものです。
もちろん聖書の中には「家族」という概念からの比喩的表現もあります。
たとえば、神はご自分を「夫」に、そしてイスラエルを「妻」に準えられています。
あるいはキリストはご自分を花婚に、そして会衆を花嫁に例えられました。
しかし、別の場所では、キリストは必ずしも男性としてだけでなく、エルサレム対してご自分を「めん鳥」になぞらえて、そこでは父性というより母性的な感情を表しておられます。
《わたしは、めんどりがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。》(マタイ23:3)
このことから、一般に旧約の神は厳しく、子なる神はやさしく、哀れみ深く、慈悲深いなどと言われるように、旧約のイメージとして、み父はルールに則った毅然とした言動が際立ち、新約のキリストからは「許しや慰め」などのメッセージが際立っているといえるのでしょう。
言いかえれば、み父は父性性をおもな特徴とし、キリストは母性性を主な特徴としているとも言えるかもしれません。
ここで、今一度「生命のメカニズム」について記事の中で人触れた、「生物(生命)は「存在(創出、受胎)」と「維持(継続、成長)」が合体もしくは、一連の二つのスロセスで成立するという、生物の創造のメカニズムというか、生命体のシステムとも言えるものがある」ということについて、また「遺伝子の法則」の「X染色体」は「いのち(生命維持)」を意味しているということ思い起こして下さい。(X染色体が欠けた場合、生命体として存在し得ません)
さてイエスはご自身について「私は命である」と明言されました。
《イエスは彼に言われをたを。「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。》(ヨハネ14:6)
イエス・キリストの重要な役割は、アダムの子孫の失われた「永遠の命」の権利を元に戻し、再び人を神の元に連れ戻すことでした。
それは遺伝子的な発想で表現すれば、罪によって破損された霊的な「X染色体」とも言うべきものを修復して、命の存続を図るということになります。
父なる神によって地の塵から造られたアダムは、子なる神を通して「神の霊(生命力)」を与えられ「生きる者」となったとわたしは考えております。
アダムが神(エローヒーム[複数」)のかたちに創造された。「われわれのかたちとして、われわれに似せて・・・」と表現されているように、「神」が複数形であるのは、「唯一の神だが、尊厳を高める目的で複数形になっている」というような説明がよくなされますが、「我々の」と繰り返していることから、そうした解釈はナンセンスであり、やはりどう捉えてもここは複数であり、そして、それは他ならぬみ父と、「言葉」すなわち子なる神の二者であることは確かでしょう。
翻訳者にとって、ヘブライ語 エローヒームを「神々」と訳せなかったのは、言うに言われぬ深い事情があったのでしょうから、それはともかくとして、人称代名詞は歴然としていますから、英語で表せば[We]という二人称として何度も登場する語を[ I ]と いう一人称に改変してしまうことは流石に気が引けたのかもしれません。
ともかく、人間の事情がどうであれ、聖書に記されているのは「われわれ」であって、決して「わたし」ではないのですから、人の創造は父なる神による単独の業ではないことを、素直に認めるべきではないでしょうか。
そして、アダム[単数形]が神[エロヒム(複数形)]のかたちに造られたということは、遺伝子的な発想で表現すれば、身体的には当然文字通りの遺伝子ですが、言わば霊的な「Y染色体」と「X染色体」を二人の神から受け継いで造られたと言い得るように思えます。
そして神はそのアダムのあばら骨から「女」を作り上げる際にアダムのうちにあった文字通りの人間の染色体である[X]を受け継ぎそれを1対にして創造されたということでしょう。
人には両親が存在します。「親」ではあっても二人だけの関係で言えば、女は男の栄光であり、女の頭は男です。
しかし、子供からみれば、ふたりとも「親」です。
子供が、「私は親から〇〇してはいけませんと言われています。」と言うとき、それは、父なのかそれとも母なのかといったことを一々問題にしません。
親の意見、しつけは基本的に調和したものとみなされるからです。
そういう意味において子供にとって「親」という語はあたかも一人の人のようです。
「父と母を敬うよう」に教えている聖書は、父なる神と子なる神を敬愛し、崇拝するように教えています。
子供にふたりの親「両親」が存在するように、人には二人の神「両神」が必要なのです。
《それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、ふたりは一体となるのである。》創世記2:24
厳密にはこの創造の際に「父母」は存在しないので、これはモーセが何らかの資料から「創世記」を編纂した際の自らのコメントと思われますが、大変興味深い一文です。
この聖句の「男」と「妻」は一体となるという部分の原語ですが、
「男(ヘ語:イーシュ)」は「女(ヘ語:イーシャー)」と「一つ(ヘ語:エカド)」の「肉(ヘ語:バーサール)」となるとなっています。
この「肉(バーサール)」という単語はその前後の「そのところの肉をふさがれた。」「私の肉からの肉」2:21;2:23 という部分と同一です。
字義的に訳すと「彼らは一つの肉となる」となります。流石にこれでは生々しいので「一体」と訳されています。
そういう訳で、夫婦は「一つ(エカド)」となるということですが、しかし、無論この表現は比喩であり、実態は二人です。
「エローヒーム」という「神」の複数形が一人の人のように記されている箇所は少なくありませんが、単数形と複数形の表記を無視して単にどちらも「神」と訳されていますが、私は「エローヒーム」は「親」と訳すのがむしろイメージ的に適切なのではないかと思っております。
そういうわけで、「遺伝子の設計から神の実体を探る」結論として、「神」(エローヒム)の実態は、三位一体ではなく、二位一体でもなく、「神」としてその目的や行為、思考、価値観において一致しているゆえに「神」は二者一体と言えます。
まさにこれこそ、神に似せて造られた人間から見た、最も自然で合理的な結論だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
