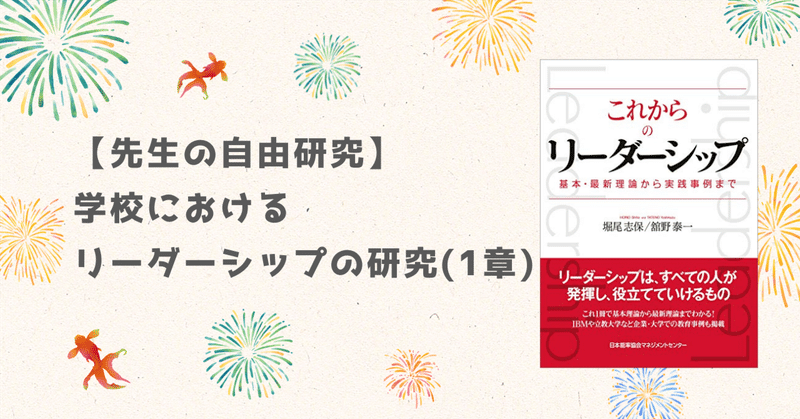
【先生の自由研究】〜学校におけるリーダーシップの研究(1章)〜
夏休み16日目。
小学校の教員をしている私たちは、もちろん夏休みが全てお休みではなく、研修や事務作業、休み明けの授業準備などをしています。
ただ、中学校や高校と違って部活や夏期講習などもないので、今週は比較的ゆったりと過ごすことができました。ゆっくりし過ぎて土日のありがたみを忘れかけている今日この頃…
毎日のように授業をしたり、子どもたちとおしゃべりをしたりする日常から一転、ほとんど人と話さないまま1日が終わってしまうなんて日もあると、普段そこまでおしゃべりな方ではない自分でさえ不調気味に…
そんなこんなで人とコミュニケーションを取ることの大切さを改めて感じているところです。(来週は旅行やキャンプなど、楽しみな予定がたくさん。)
さて、今日はタイトル通り、先日投稿した「リーダーシップに関する自由研究」の第1章について書き進めていきます。(前回の「まえがき」もぜひご覧ください。)
1章 リーダーシップとは
私が今、現在進行形で受講している「学習する学校 実践Lab」では、システム思考教育家の福谷彰鴻さんを講師に学びを進めています。
その第1回の講座で触れられたのが、「リーダー」について。
そこでは、「リード」という言葉の語源をもとに説明されていました。(詳しくはこちらの記事で分かりやすくまとまっていたので引用させていただきます。)
コンフォートゾーンから踏み出していくことが学ぶ行為だとお伝えしましたが、リードって言葉の語源がまさに、「一線を越えて踏み出す」なんですね。
学習する組織におけるリーダーというのは、敷居を越える人、一歩踏み出す人のことを指すので、役職は関係ありません。僕らはみんなリーダーで、みんな学ぶ存在で、その力をどう育むか。それが「学習する組織」を実践する上で、欠かせない視点だと思います。
「リーダー」や「リーダーシップ」というと、「校長」や「教務主任」といったように役職を持った方々が思い浮かんでいましたし、私自身も「体育主任」などの役職を任せられたことで「リーダーシップを発揮せねば。」と思うようになった経験があります。
そうしたこれまでの認識を真っ向から否定されたことも、今回「リーダーシップ」について学習したいと思うきっかけの一つとなりました。
この章では、「リーダーシップがこれまでにどのように捉えられてきたのか」、そして、「これまでの研究から、近年どのようなリーダーシップが求められているのか」ということについてまとめていければと思います。
1.リーダーシップの歴史
ここでは、参考書籍である『これからのリーダーシップ』100ページ分の内容を、ぎゅっと凝縮して自分なりに噛み砕いきながらまとめてみます。
①指揮者による偉人伝から始まった 特性理論
リーダーシップの研究は、紀元前までさかのぼるようです。
特性理論とは、「偉人と称される優れたリーダーには、共通する特性がある」という考え方。
紀元前からということですが、19世紀ごろまでは思想家や哲学者らが、あくまでも個人的見解に基づいて論じる程度で科学的な検証はなされていなかったとのこと。
20世紀に入り多くの研究がされるようになりましたが、「優れたリーダーとそうでないリーダーを明確に区別できる特性はない」と結論づけられたことで一度衰退します。ただ、特性を測る尺度の品質が上がったことで、近年再び注目されつつあるようです。
②リーダーの「行動」に着目した 行動理論
「リーダーシップは特性の視点だけでは説明できない」と結論づけられたことで、次に着目されたのは「行動」だったようです。
時代背景としても、第二次世界大戦後で多くのリーダーが必要とされ、それまで通りリーダーに適した人材をリーダーとするだけでは足りず、リーダー役を任じされた人材に望ましい「行動」を示す必要がありました。
代表的なアイオア研究では、「専制型」、「民主型」、「放任型」のそれぞれのリーダーシップ・スタイルの違いがグループに及ぼす影響について調べています。
グループの雰囲気、メンバーのモチベーション、仕事の成果などへの影響は、現在のクラスのリーダー(担任)のスタイルにもそのまま転用できると思いました。
リーダーシップには、「仕事」と「対人」の2軸が重要であると方向付けられたのもこの時期。日本において、PM理論が発表されたのも、こういった流れが影響していたようです。(PM理論については、2章でも取り上げようと思っています。)
③「状況」に着目した 状況適合理論(コンティンジェンシー理論)
「仕事」、「対人」の両面の行動が優れていれば、リーダーとしていつでもどこでもうまくいくかというと、そうではありませんでした。
そこで次に目を向けられたのが、リーダーが置かれている「状況」です。
この流れにおいて、もっとも有名なのがコンティンジェンシー理論。
リーダーシップの効果に影響を与える3つの状況要因として、以下の3つが挙げられました。
1.リーダーとメンバーの関係性(良好な関係が築かれているか)
2.課題の構造(仕事の手順やメンバーの役割の明確さ)
3.リーダーの権限の大きさ(人員配置、予算、人事考課などの権限をどれだけもっているか)
リーダーとメンバーの関係性が崩れてしまうとリーダーシップが発揮しにくい、ということは誰もがイメージしやすいのではないでしょうか。
④リーダーとメンバーの「交換関係」に着目した 交換理論
ここまでの研究が「リーダー個人とリーダーを取り巻く状況」への関心が主だったのに対して、ここからは「リーダーとメンバーの関係性を双方向的に」研究されていきます。
この交換理論では、リーダーからの命令や提案に対して、メンバーが従い、その対価としてリーダーがメンバーに物理的、心理的な報酬を与えることが前提となっています。
メンバーとリーダーのパートナーシップが成熟されるにつれて、「単なるギブ・アンド・テイクの関係」から、「行動面だけでない相互の尊敬・信頼関係」になっていくようです。
⑤組織を「変革」できる経営トップの特徴に迫った 変革型リーダーシップ理論
最後に紹介するのが「変革型リーダー」について。
時代背景として、1980年代のアメリカの貿易赤字、財政赤字の頃。
従来のように決められたことを決められたやり方で行うだけでなく、「人々の前面に立って組織変革を率いていく強いリーダーシップ」が求められていきました。
最も有名なのがコッターによる理論。
「マネジメント」と「リーダーシップ」を分けて考えている点が特徴です。
組織の維持・安定を指向するマネジメントだけではなく、組織の現状を打開する組織変革が求められていたことから、変化を指向するリーダーシップの重要性が強調されました。
ここでは、組織変革のプロセスとして以下のように挙げられています。
1.危機感を植えつける
2.同士を募る
3.ビジョンを打ち出す
4.ビジョンを組織内に浸透させる
5.障壁を取り除き、環境を整備する
6.短期的実績を出す
7.変革の加速を維持する
8.変革を組織に定着させる
この辺り、昨年度から取り組んでいる「働き方改革プロジェクト」の推進にもそのまま転用できそうなプロセスだと感じました。
以上、ここまで「リーダーシップ」の歴史についてまとめてきました。
自分の頭の中では、「リーダーって生まれもってそういう素質があるんだろう」と、一番最初の「特性理論」の考えでいたので、これらの変遷を知り、いい意味で常識が打ち砕かれた気分でした。
普段の記事以上の文字数に、早くも途中で投げ出しそうになっていますが、もう少し頑張りたいと思います…
2.近年求められるリーダーシップについて
歴史について調べたことで、「じゃあ結局、今はどんなリーダーシップが求められるの?」という問いが生まれてきますよね。
ここからは、そのことについてまとめていきます。
①集合的リーダーシップ
VUCA時代とも呼ばれる昨今、公式なポジションに就いているかどうかに関わらず、より多くの人材がリーダーシップを発揮することが求められています。
このように、複数名、またはグループメンバー全員で発揮している状態を「集合的リーダーシップ」と総称されているようです。
書籍では、「シェアド・リーダーシップ」、「コレクティブ・ジーニアス」、「DACフレームワーク」が紹介されていますが、どれも研究され始めたばかりの概念。
これらをうまく機能させるためには、どんな条件が必要なのかなど、まだまだ解き明かされていないことも多いようです。
②公式なリーダーに求められる在り方
より多くの人材がリーダーシップを発揮していくことの重要性は理解できましたが、そのような時代にこそ求められる「リーダー」の役割とは何なのでしょうか。
ヒントとなる理論として書かれていたのは以下の3つです。
一つ目は「サーバント・リーダーシップ」。
メンバーの前面に立ち、グイグイと引っ張っていくというイメージではなく、メンバーに奉仕し、日頃は目立たないけれどメンバーの大きな支えになるという真逆の考え方です。
サーバント・リーダーシップによってメンバーからのリーダーに対する情緒的信頼が生まれることで、チームの心理的安全性が向上し、その結果としてチームのパフォーマンスが高まることが明らかになっています。
二つ目は「オーセンティック・リーダーシップ」。
「オーセンティック」は「本物の」「真正の」などの意味をもっており、「自分らしくモラルあるリーダーシップ」と言えます。
ここで目に止まったのは、オーセンティック・リーダーシップを提唱した第一人者であるビル・ジョージの次の言葉。
「リーダーたちは、スーパーリーダーと評されている誰かを真似て外的な成功基準を追求するのではなく、自らに正直に向き合い、自分らしいリーダーシップ・スタイルを築くことが重要である。」
自分自身を思い返してみても、特に初任の頃は「学級担任としてクラスをまとめなければ」という思いが強く、いわゆる指導力のある先生を真似して厳しく子どもたちと関わる場面が多かったように思います。
でも、子どもたちとの関係はよくなっていかないし、一番は自分がそうやって演じることにしんどくなっていたように思います。(この辺り、第2章で詳しく触れたい。)
そして三つ目は「インフォーマル・リーダーシップ」。
これはメンバー側、つまり役職をもたない人のリーダーシップについて。
いくつかの研究をまとめると、表現の違いはあれど、非役職者がリーダーシップを発揮するには、「①まずは自分自身をリードし、②現状から変化をもたらすために
目標を掲げて活動し、③他者と協働して他者が動きやすいような働きかけをする」ことが重要だとわかっているようです。
以上、この記事では、リーダーシップの歴史と近年求められているリーダーシップについてまとめてきました。(とっても分かりづらいので、もっとわかりやすい記事を読みたい方は下のリンクから舘野先生の連載をご覧ください…笑)
歴史的な流れ、そして今の時代背景からもリーダーシップは「全員が発揮していくもの」。
とはいえ、「じゃ、そういうことだから、これからリーダーシップを発揮してね。」と言われてもですよね…
次回の第2章では、学校現場で求められるリーダーシップについて、自分の体験などをもとに考えていければと思っています。次回の更新もお楽しみに!
ダラダラと書き進めてしまったこんな文章を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!!
続きの記事はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
