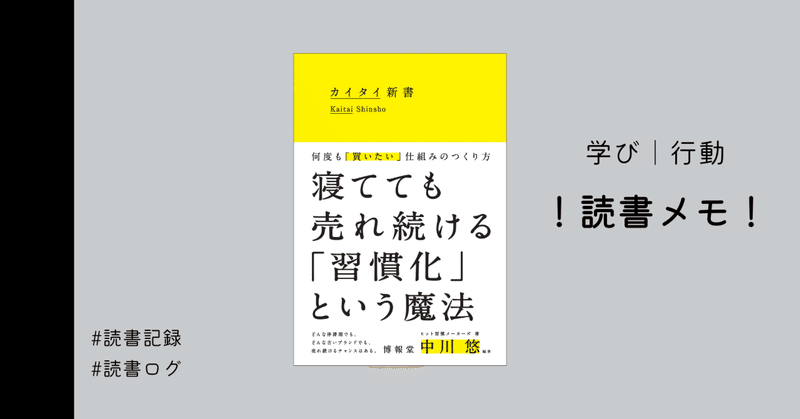
!読書メモ!カイタイ新書
学びメモ
●社会の変化による消費者行動の変化に目をつける
・人口減少→一人当たりの支出を増やすマーケティングへ
・高齢化社会→一人当たりの「LTV」(生涯にわたってもたらされる支払額)を増やす
・デジタル化→リアルでの接点をもつ
・情報化社会→選ぶのが面倒だからこそ、継続購入をしてもらえる商品作り
●持続的なマーケティング
・既存顧客が新規顧客のセールスパーソンになる
・一度のヒットを生み出す「仕掛け」ではなく、継続的に売れる「仕組み」を作る
・商品を使って顧客の新しい「行動」を作る
・顧客の時間価値を高め「習慣化」を目指す(マーケティング5.0)
●「習慣化」のポイント
・ストレスなく行動するため、生活者は本能的に習慣を求めている
・使いやすいものでも、頻度が低いものは習慣化しない
・習慣化をすることで、消費者との接点がなくても継続購入を促すことができる
●習慣の4分類①成長
「成長しているという実感」を生み出すことが重要。
これまでのデータ推移の可視化、顧客が成し遂げたかったことの支援など。
ex)家計簿アプリ、学習アプリ
●習慣の4分類②不満解消
「その解決のためなら、手間やお金をかけてもいい」という「ペインポイント」を見つけることが重要。
ex)消臭スプレー、コードレス掃除機
●習慣の4分類③快楽
性別、年代に関係なく、生活者の誰もが惹かれるような根源的な欲求を刺激するグッとくる「〇〇感」を作ることが重要。
ex)ビーズクッション、キャラクターを捕まえるアプリ、エナジードリンク
●習慣の4分類④不快解消
やらないとなんだか心地悪い状態を作ることが重要。
ex)漫画の背表紙、コンビニのレジ前の足跡
●習慣化のフレームワーク(PACフレーム)
・Prediction(習慣を予測する)
…世の中にある大小様々な習慣から、次にくる習慣を予測する。
これから広がるであろう「兆し習慣」からのその中にいる人たちを探り、その習慣を続ける理由(習慣インサイト)を深掘りする。
※「兆し習慣」の裏にある「衰退習慣」も炙りだす。
・Addiction(習慣を設計する)
…「兆し習慣」と自社の商品やサービスを組み合わせた際にどんな習慣が作れそうなのか?「習慣化コンセプト」を考える。
※実際にどんなことをしてもらうのか、習慣化ループのテンプレートを使用して習慣化4Pアクションを作成する
・Conversation(習慣を広げる)
・生活者同士の会をを作り、局所を攻めて(発信者を増やし)→マスを攻める(受信者に広げる)。
●Prediction(習慣を予測する)
・点ではなく線の時系列変化に注目する。
「今」多くの人が実践している習慣ではなく、「これからしばらくの間」実践する人が増えていくのか減っていくのか?
・3つの視点(大カテゴリ、小カテゴリ、ライフススタイル)を持つ
ex)ジュース
ジュース>飲料>買い物、仕事、健康…
・「衰退習慣」に注目し、新たな習慣が広がりやすいシチュエーション(時間、場所)やターゲットに目星をつける。
・「習慣インサイト」を探る
兆し習慣を複数の視点で見て解像度を上げ、情報の質を高める。
習慣を実践しているのはどんな人か?
どんなシチュエーションで実践しているか?
いつから成長トレンドに入ったのか?
なぜ成長トレンドに入ったのか?
一人一人がなぜその習慣を続けているのかを、時系列で観察する。
(習慣を始めるようになったきっかけや、習慣を行う前後のきっかけややりがい等)
→行動の前後にヒントが隠れている。
複数の兆し習慣をグルーピングし、本質的な習慣インサイトを導く。
・ターゲットを決める
実在する人物に置き換え、リアリティのあるターゲット設定をする。
●Addiction①(習慣を設計する)
・「こんな理想の世界があれば世の中はもっと良くなる」という想いを持ち、A(今の世界)→B(新習慣で実現したい理想の世界)の習慣コンセプトを検討する。
・ニーズ、新規性、自社らしさを掛け合わせて、シンプルで強い習慣化コンセプトに仕上げる。
・習慣化ループを描く(きっかけ、ルーチン、報酬、触媒)
<きっかけ>
はじめるきっかけ…「人生の転機」「社会の転機」に習慣はスイッチしやすい。
毎回続けるきっかけ…生活の中で、周期化すると定着しやすい。
<ルーチン>
習慣化している行動の条件:複雑、大変すぎず、シンプルで手軽なこと
→そのような習慣にするために、
・一度にやることの単位を小さくする
・遠い、時間指定などの障害を減らし、アクセシビリティを上げる
・低コスト化する
極端にハードルを下げて、今までの生活を極力変えることなく、取り入れやすいものにすることがポイント。
<報酬>
なぜその習慣をするのか?の理由:時代の変化に合わせて「メンテナンス」していく必要がある。
習慣の4分類(成長、不満解消、快楽、不快解消)のどこを狙うかで報酬が変わってくる。
<触媒>
無意識のうちについついやってしまう中毒性を組み込む。
ex)歯磨き粉のミントの刺激
・習慣をどう広めていくか?を4P視点で大胆に考える。
習慣化4Pアクション:Product、Price、Place、Promotion
・「習慣設計力」を磨くデコントレーニング
…好事例を習慣化コンセプト、習慣化ループ、習慣化4Pアクションに分解して学ぶ。
●Addiction②(触媒の魔力)
・潜在意識に入り込み、意思に関係なく自動的に繰り返し使い続けること=習慣化
→習慣化の生命線とも言えるのが触媒
・触媒の組み込み方
・原材料 ex)歯磨き粉のミント
・デジタル演出 ex)シャッター音や決済音
・パッケージ
・提供方法 ex)ジョッキのハイボール
・ネーミング…商品名にシズルワードを入れる
ex)濃厚チーズケーキ、ゴロゴロ野菜のカレー
・触媒の法則①ミント型
歯磨き粉のミントのような強い刺激(つい癖になるスパイス)を加える
・触媒の法則②コンフォート型
シャンプーの泡のような1秒の心地よさを組み込む
・触媒の法則③セレモニー型
加熱式電子タバコのように、過去の体験の記憶(快感)を思い出させるような儀式を組み込む
・触媒の法則④ダム型
家計簿アプリのように成長実感をグラフなどで見える化し、蓄積する楽しさを提供する
・触媒の法則⑤アナログ化型
電子決済の音ように、デジタル化で失われた「実感」をアナログ化して取り戻させる
●習慣を広げる
習慣を広げるための2つのステップ
…局所的に攻める(1→10)とマスへ広げる(10→100)
・1→10の手法
・「五感」を刺激して体験をリッチにする
・Conversationを生んでくれる味方は、量ではなく質の発想で探す
・あえて場所を限定することでConversationを生み、局地的なブームを作る
→「新習慣に箔が付く場所」で、人気だという事実を作る
・売り場を変えて、違和感からConversationを生む
・略したり、すでにある言葉とくっつけて新しい言葉を作る
・発売前に、生活者を習慣作りに巻き込む
・「象徴的で起業色のない」共感できる習慣のロゴマークを作る
・10→100の手法
・対立構造を作って議論を生むことにより習慣に愛着を持たせる
・「生活者視点」と「社会視点」で発見のあるデータを
・異なるフィールドへ習慣を広げることで、記事になる
・習慣に関わる人や団体から「スター」を作り表彰する
・事例を集めてメディアや第三者へ情報提供をすし、”イクメン”、”汗活”などの「社会記号」をつけてもらう
・自社だけでその習慣を独占せずに、「社会的意義」を提示して複数企業の賛同を得る
●PACワークショップ
<WEEK1〜2 兆し習慣を探す>
・大カテゴリ〜小カテゴリまで幅広く考え、複数アイデアを出す
・兆し習慣シートを作成する
…①兆し習慣(行動)②実際に行われている例③習慣インサイト(なぜその行動をしたいのか?)
・兆し習慣を仮説ベースで習慣インサイトごとにグルーピングする
<WEEK3 ターゲットを規定する>
・兆し習慣との親和性、ボリューム、会社の方向性とマッチしているのか?の観点から考え、ターゲットを定める
<WEEK4〜5 習慣化コンセプトを作る>
・既存サービスや商品をよく研究し、その一歩先を狙う
・習慣化コンセプトシートを作成する
…①選んだ兆し習慣(その裏にある衰退習慣)②ターゲットの特徴③習慣化インサイト(ターゲットの意識)④習慣化コンセプト(商品やサービスの現状/商品やサービスによって実現したい世界)
・習慣化コンセプトシートの、ターゲット/シーン/商品について細かく質問する
<WEEK6 投票で習慣化コンセプトを絞る>
・新規性/ニーズ/自社らしさから習慣化コンセプトを評価し、絞り込む
<WEEK7〜8 習慣化コンセプトを具現化する>
・習慣化ループシートを作成する
…①きっかけ(最初にその習慣を行いたいと思ったきっかけ/2回目以降にその習慣を行う引き金)②ルーチン(実際にどのような行動を行うのか)③触媒④報酬(ターゲットにどのようなメリットがあるか)
・中毒性のある触媒を組み込む
…報酬から思い浮かべるものを連想し、組み合わせる
<WEEK9〜10 商品に落とし込む>
・従来の商品、サービスから、残すものと変えるものを仕分ける
・要素をどこに生かせるかを考え、商品名やパッケージに当てはめる
<WEEK11 拡散方法を考える>
・ワーク①…口コミフレームを使用し、リアル/SNSでどのようなフレーズを用いておすすめされそうか?を考える
・ワーク②…マスフレームを使用し、商品が話題になった際にメディアでどのように取り上げられるか?を考える
・ワークで理想の発信内容を作り、そこから遡って拡散方法を決める
<WEEK12 調査で検証する>
・実際の生活者の行動を時系列で観察し、検証を行う
行動メモ
・習慣化フレームワーク(PACフレーム)を行う
・目にする商品やサービスについて、どんな触媒があるのかを日々意識して観察する
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
