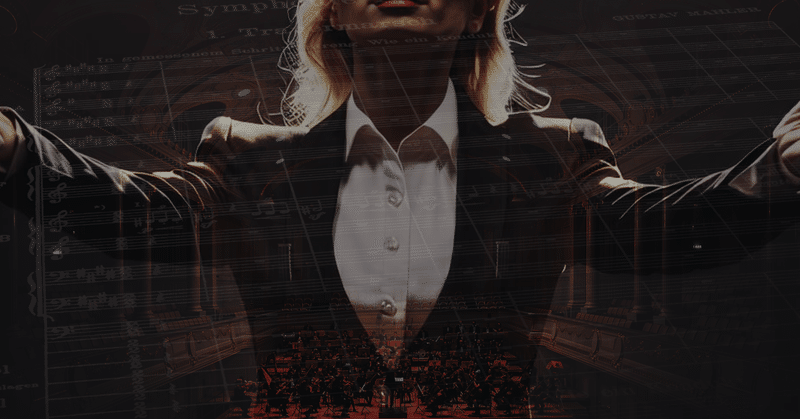
事実と真実
𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす
こんなことならちゃんと予習をしてから映画館に行くんだった。「なんか面白そうだから」「クラシック音楽が好きだから」そんな軽いノリで『TÁR』を観に行って激しく後悔した。
これは決して難解な作品ではない。権力と地位の頂点にいる指揮者リディア・ターが、スキャンダルによって失墜していく単純明快な話である。ただ、この映画は余白が多いというか、描かれていない部分を脳内で補完して観ないと理解できない。ジグソーパズルに例えると、すべてのピースが揃っているわけではなく、足りないピースがあちこちにあって、そこに何が描かれているかを想像で補うことによって、はじめて全体の絵が見えてくる。
一例をあげると、ターの住む家が突然70年代アメリカ風に変わるシーンがある。そこには何の説明もないが、観客は「ああ、ベンリンの家を失って、実家のある田舎に帰ってきたんだな」と察する。こういった感じの描写が続くのである。したがって、説明過多な近頃の日本の映画に慣らされている観客は、悲鳴を上げたくなるかもしれない。
本作は完全なフィクションだが、実話を元にしていると思われる部分もある。たとえば、ターの本名はリディアではなく、じつはリンダであることが明かされる。ターの綴りもTárではなくTarrだとわかる(筆者は詳しくないが、イランやトルコなど中東系の名前だろうか)。これはどうしてもカラヤンを想起してしまう。ヘルベルト・フォン・カラヤンというのは、じつは本名ではない。ドイツ人のフォンは貴族の出身であることを示すものだが、カラヤンのフォンは彼が勝手に名乗ったものである。先祖がギリシア系の貴族だとインタビューで話しているのを見たことがあるが、たぶん嘘だろう。ヘルベルトというのも本当は違う名前だったと思う。要するに、カラヤンは自分の名前に箔を付けるために、芸名を使ったのである。
カラヤンでもうひとつ思い出すのが、ザビーネ・マイヤー事件である。彼は晩年、ザビーネ・マイヤーというクラリネット奏者を入団させようとして、ベルリン・フィルと決定的に対立した。指揮者というのはオーケストラに対して絶大な権力をもっていると想像するかもしれないが、じつは指揮者はオケの一員ではなく、あくまで外部の人間である。言ってみれば、親会社から出向してきた部長みたいなものだろう。だから、楽団員の人選というのは、たとえカラヤンであっても独断は許されず、オケの総意で決定されなければならない。この史実を知っていると、ターがチェリストのオルガをソリストに起用して、オケから孤立してしまったストーリーが現実感を帯びてくる。
そして、この映画のもっとも目を見張る部分は、見る人によってその見方、とらえ方、感じ方が、大きく変わってくるところである。角度によって見えるものが変わる不思議な絵があるが(レンチキュラー印刷というらしい)、まさにあれである。たとえば、私のような古典的なクラシック音楽の愛好者にしてみれば、人気と実力を兼ね備えた指揮者があれよあれよと転落していくようすは、痛ましくショッキングに映る。だが、伝統や権力といったものに強い反発を覚える人は、むしろ痛快で気持ちいいと感じるかもしれない。ラストシーンも同様である。権威や教養をありがたがるスノビストにとっては目を覆いたくなるバッド・エンドだが、大衆文化やカウンターカルチャーに馴染んだ若者ならターの新しい出発に見えるだろう。肝腎なのは、そのどちらが正しいかということではなく、いろいろな受け止め方が生じるその構造自体を描いている点である。
凪良ゆうの小説『流浪の月』(東京創元社)をご存知だろうか。養父母から虐待を受けていた主人公の少女は、公園で出会った大学生に惹かれて自分から家について行き、そこで何ヶ月も一緒に暮らす。だが、世間は大学生が少女を誘拐したとしか思わない。当事者と第三者で、物事の見え方がまったく違う。
『流浪の月』は、どちらかとえいば、読者が主人公に共感するように書かれている。だが、『TÁR』はそうではない。ターは善人ではないが、悪人としても描かれてはいない。たしかに権力と富を恣(ほしいまま)にしているが、同時に才能と実力もあり、必要な努力も重ねてきた人物である。前述のチェリストの採用にしても、自分のお気に入りを依怙贔屓した側面は否めないが、オルガに才能がなければソリストには迎えなかったはずである。あくまで音楽に対しては真剣で真摯であり、その姿勢は最後まで崩れることはない。
ターは自分の浮気がきっかけで破滅してしまうわけだが、世間では今まさに、かつて超絶な美少女として人気だった女性が、有名シェフとの不倫によって転落しかけている。私は彼女と同い年で、同じ年に大学生になり、キャンパスも近くだった。だから味方というわけではないのだが、事情があるのだろうなとは考えてしまうし、そうかといって不倫を擁護するわけにもいかない。複雑な気分である。
物事には、見えている部分と、見えていない部分がある。すべての部分を余すところなく見ることができる者は、神しかいない。しかし、われわれはテレビやインターネットで目にした断片的な情報だけで、神のように物事を断罪してしまいがちである。名探偵は、真実はいつもひとつだと語る。じゃあ、この映画のただひとつの真実とは何だろうか。最初に私は、この映画は単純明快な話だと書いた。そう、真実はいつも単純だが、事実はもっと複雑なのである。
𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑏𝑦 𝑦𝑜𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑥
養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!
