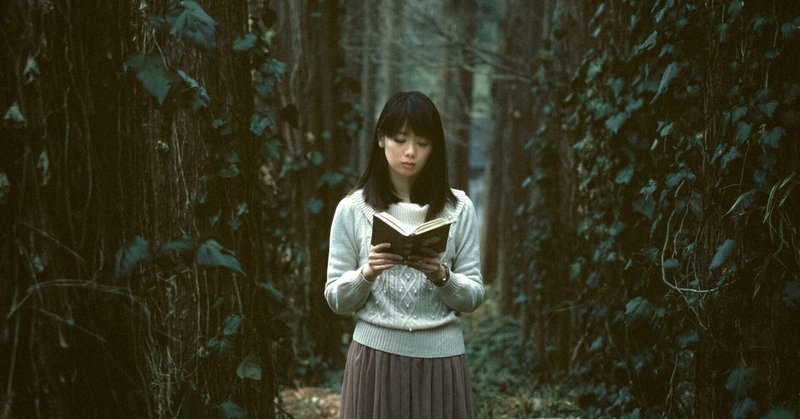
文学は何の役に立つか
𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす
ツイッターで面白い絵を見つけた。そこには十冊足らずの本が積み重なっており、男の足がその上に乗っている。床にはハサミで切られたロープが横たわっており、男がこれから首を吊ろうとしているところだとわかる。傑作なのは、その本の題名である。「◯◯になるための方法」「◯◯必勝法」「◯◯︎︎な人になる習慣」など、いわゆるハウツー本ばかりなのである。
「文学は何の役に立ちますか?」「小説を読んで何のためになりますか?」こういう質問はもうウンザリするほど聞いてきた。しかし、それに対して明快なというか、自分も相手も腑に落ちるような返答ができたことはなかった。そもそも文学や小説というものは、有用性という尺度の外側に存在するもので、役に立つか立たないかというようなモノサシではその価値を測ることができない。けれど、何の役に立つのかという質問は有用性の枠内でしか成立しない問いなので、すなわち存在するものはすべて何かの役に立つはずだ、立たねばならないという前提のもとで立てられた設問なので、役に立たないものの存在意義を説明しようとしても話が通じない。
一般に、「役に立つ」というためには、まず目標や目的が設定されていなければならない。仕事に役立つとか、人生のためになるとか、受験に受かるでもいい。しかし、そもそも人間という存在そのものには、目標や目的がない。それは人生において後から発見されるものであって、存在に先立つものではない。だから私は、「それが何の役に立ちますか?」と訊かれると、ムッとしてこう言う。「お前は何かの役に立っているのか?」しかし、相手は自分が有用な人間だと信じて疑わないので、ケロッとした顔で「かくかくしかじかで世の中の役に立っている」などと言う。私はそんなものは本人の妄想だと思う。なぜなら、その人がいなくなっても世の中はちゃんと回るからである。ただし、それを実証する勇気は私にはない。
ハウツー本、実用書、自己啓発本──こういった本は、たしかに役に立つ本だろう。そこには明確なゴールがあり、それに対する成果が定量的に示せるからである。しかし、いくら必勝法といったって、全員が受験に受かるわけではない。合格者がいれば、必ず不合格者もいるのが試験である。本を読んでその通りにやっても、できないことはある。本当に役に立つというなら、落ちこぼれなんて生まれないはずである。だが、実際は壁にぶつかったりどん底に落ちたりする。それが人生ではないのか。
こんなことを書くのは野暮だが、何をやってもうまくいかないときに、ハウツー本を読んで役に立つだろうか。むしろ、本の通りにいかない自分に嫌気がさすだけではないだろうか。冒頭で紹介した絵の中の男も、もし文学を読んでいたら自殺する必要はなかったかもしれない。
(二〇二二年五月)
養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!
