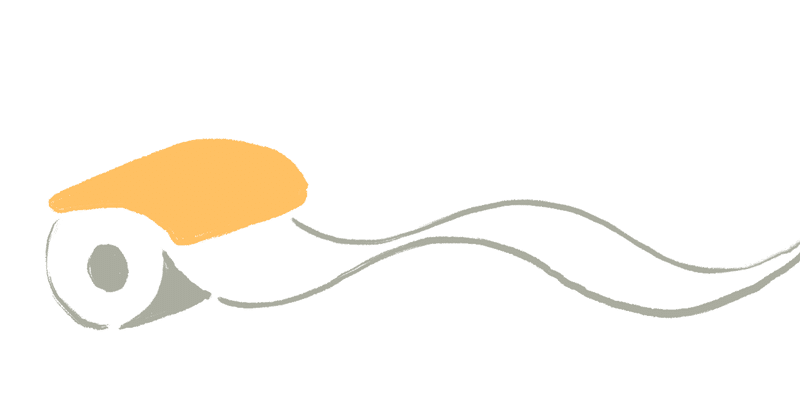
短篇小説「トイレの革命」
愛知県常滑市。知多半島の中央部にあって西側は伊勢湾に面している。平地が少なく大部分が丘陵地だ。古くから良い土が取れるとかで焼き物が盛んな土地柄だ。旧市街にはレンガ煙突が点在し、登り窯や土管坂で観光地としても有名だ。
祐樹の実家は、千九百五十年創業のおじいちゃんの義父の時代から続く水道工事店だ。伊勢湾に面した海辺の街道沿いに建っている。店では、主に二社の商品を扱っていた。KOKUTOとCHITAXだ。CHITAXは昔は知多製陶と言っていたが、今はコマーシャルも浸透してこの名前のほうがとおりがよい。本社が地元・常滑市にある。KOKUTOは昔は小倉陶器と言っていた。北九州が拠点のCHITAX最大のライバル社だが、なかなか品質が良く、とくに温水洗浄便座・ウォシャレットはお客さんの人気も高いので置いている。祐樹の店は、おじいちゃんの時代までは、蛇口や配管の水漏れの修繕など水道関係の仕事が中心だったが、父親の代からは温水洗浄便座の取り付けや、住宅設備機器の交換工事やリフォーム関係が増えている。祐樹は現在、名古屋の私立大の二年生だ。一人前に自分の工具箱も持っていて、店の仕事を時々手伝っているが、親は継がせたがっているものの、まだ先のことは決心していない。東京へ行って声優になる、なんて夢も捨てきれないでいる。
八月に入って連日、猛暑が続く。常滑の夏は半端じゃない。湿度が高く、じっとしていても汗の染みたシャツが身体にまとわりついてくる。祐樹は、この日も父親の軽トラックに同乗して、町はずれの高台にある常滑西団地を訪れていた。晴天の午後二時くらい。見晴らしがよく、伊勢湾が一望できた。太陽がまぶしい。このくらいの高台になると下から吹き上がる海風が心地よい。B棟901号室に住む、北野芳江おばあちゃんは祐樹の店の先代からの常連客だ。CHITAXの温水洗浄便座・シャワットトイレの調子が悪いので「早く来て」という連絡があったのだ。おばあちゃんは八十五歳過ぎの高齢で、息子夫婦がときどき様子を見に来るが、まだ頭もシャンとしているし、古い友達も多く住んでいるので、といってもだいぶ死んじゃったが、一人暮らしが快適だと言って息子の家には行こうとしない。シャワットトイレとの付き合いはもう五十年以上になるそうで、とくに一昨年に亡くなったおじいちゃんがお気に入りで、シャワットトイレの先代の初号機のサニタリーノのときから愛用しているそうだ。
「これがないと生きていけないわ」
今のは二十年前に購入した二代目で、部品を時々交換して使い続けているのだ。長生きの秘訣はシャワットトイレ、だそうだ。おばあちゃんは、もとは、知多製陶の女子事務員だった。集団就職で鹿児島からやってきた。工場のそばに知多製陶の女子寮があったそうだ。舎監の厳しいおばさんが常駐して、田舎から大切なお嬢さんたちをあずかっているのだからと、社長直々にお達しがあって、二十四時間見張っていたそうだ。
「それはそれは恐い舎監さんでした」
それでも土曜日の夜は、常滑および周辺の男どもがパブリカ、コンテッサ、スカイラインなどの新車で女子寮に乗り付けて、長い列を作って女子社員さんたちをデートに誘っていた。
「私ももてちゃって、名古屋の栄町でよくデートしたわ」
おばあちゃんの家のシャワットトイレの修理が始まった。父親は工具箱を開けるとペンチやモンキースパナ、プライヤーを手慣れた様子で取り出した。先代から譲り受けた年季の入った工具箱だ。
「どんな具合かな。祐樹、ちょっと座ってみろ」父親に言われて祐樹がシャワットトイレに腰かけた。
「お湯を出してみろ」
言われて祐樹は、ズボンとパンツを下ろし、シャワットトイレのスイッチを押した。
しゅしゅしゅわーーーー
その時だ。一瞬、祐樹の目の前がブラックアウトした。と思うが早いかすぐに目の前にまぶしい光がフラッシュした。――――タイムスリップ。
市内にひしめく焼き物工場のレンガ製の煙突からもくもくと黒煙があがり、昼間でも空がかすんで薄暗い。ここは千九百六十五年の常滑市。古くからの焼き物の街。タイムスリップの先は、六十年前の、常滑の衛生陶器メーカー知多製陶の工場の一角だった。五万平米の巨大な工場。東京ドーム約一個分だ。工場内では便器が粘土で成形され、焼成炉で次々と焼きあがっていた。まだ和式便器全盛の時代だ。いくつかの区画に粘土の塊が積み上げられ、工場内に土埃が舞っていた。大勢の作業員たちがいると思われるが、土埃で視界が遮られ、がやがやとした話声が聞き取れるだけ。作業員たちは上半身はランニングシャツ一枚、口元はマスクではなく、首に巻いた手拭いで覆っていた。作業用帽子のつばを頭の後ろに回し、したたる汗を腕で拭いながらひたすら作業に集中していた。しかもエアコンは台数が足らないのか効いている風がなく、代わりに大型の扇風機が各方面へ風を送っていたが、もわあっと猛烈な熱気が室内にこもっていた。作業員のランニングシャツから染み出た汗は塩の粉となって噴き出していた。焼成温度千二百二十度C。長さ百メートルの焼成炉のすぐ隣りに、掘っ立て小屋のようなベニヤで仕切った簡易なトイレが立てられ、ある実験を繰り返していた。水道ホースが何本も工場の外から引っ張り込まれていた。実験室の前には小さなテーブルが置かれて書類の束が積み上げられ、扇風機の風がやってくるたびに舞い上がっていた。
そこではシャワットトイレの前身・温水洗浄便器サニタリーノの開発の真っ最中だった。便座タイプではなく、温水洗浄機能が便器本体に組み込んである、いわゆる一体型だ。祐樹はちょうど実験中のトイレに腰をかけていた。ズボン、パンツを下ろしていた。
「おい、どうだ、秀雄? 」と外から声。
開発設計課課長の阿部祐太朗だった。百六十五センチくらいの中肉中背の四十代後半。眉毛が濃い四角い顔で精悍で理知的な風貌の男だった。祐樹は秀雄になっていた。秀雄の脳に祐樹の心がタイプスリップしたのだ。便器のノズルから熱湯が噴きだした。
「あっつううっ」秀雄は飛び上がった。
「温度調節がまだまだだな」
「だが角度はいいみたいだ。垂直に噴出している」
「だが、どうしてもノズルの動きが難しい。水の圧で動かしているんだがタイミングよく目標の位置へ出てこない」
残念そうな阿部課長の声が聞こえた。慌てている秀雄をほったまま、冷静に分析している。秀雄は、パンツをおろしたままでトイレから飛びだした。
「きゃあ」課長の助手が目をおおった。今年の春にこの課に配属されたばかりの少し小太りな女性事務員だ。ノートに記録を取っている。よほど暑いらしく、半袖の制服を肩までまくっている。ぽっちゃりした二の腕がかわいい。
「おいおい、はいてから出て来いよ」
「ここはどこなんですか。電子制御じゃないんですか?」
「何が電子だ。頭でもうったか? これを塗っておけ」
阿部課長は祐樹にオ〇ナイン軟膏のチューブを放ってよこした。
午後三時の休憩時間。祐樹は会社のトイレにいた。会社のトイレはまだ和式が中心だった。
床がコンクリートで湿っていて薄暗い。一番奥に洋式が一台あったが、もちろん温水洗浄機能はない。手洗い場に、端が欠けてひび割れた鏡があった。
「えっ、そんな、誰なんだ」
祐樹は、鏡をのぞいて、顔が違うので驚いた。そこにいるのは祐樹ではなかった。それでは誰なんだ?
「秀雄、おしりをお湯で洗うんだって?」
「秀雄、俺んちなんか新聞紙で拭いてるぞ」
トイレですれ違うみんなが、秀雄と呼び掛けてくる。秀雄とは誰なんだ。どこかで聞き覚えのある名ではあるが。
壁にかかっている丸型の時計が午後六時を指した。土埃でガラスが茶色に曇っている。
「今日も残業だ。家内に言っておいた」
と阿部課長が、やかんの水をがぶ飲みしながらつぶやいた。秀雄は、課長の家に居候しているのだそうだ。助手の女性事務員の姿がなかった。五時の定時に帰宅したらしい。午後十時。工場には誰もいない。
「秀雄、そろそろ上がるか」
阿部課長は、秀雄に声をかけた。トイレの実験室に今日は八時間、こもりっぱなしだった。熱湯を浴び続け、秀雄の肛門はひりひりだった。秀雄の中の祐樹の心は、今日一日、心の中で叫び続けた。
「俺はどうしちまったんだ。どうして秀雄になっちまったんだ」
答えは浮かばない。阿部課長に言われるまま、トイレの実験室から出て、ロッカーで着替えた。私服は、チェックの半袖シャツにジーパンだった。手には工具箱。祐樹は愛用の工具箱といっしょに未来からやってきた。工具箱をロッカーにしまうと、ふらふらのまま、秀雄は阿部課長のあとについていった。課長の家は、工場から歩いて十五分ほどの丘の上だった。壁一面に土管が埋めてある土管坂を登る。街灯の電球が切れそうなのか、ちかちかと点滅していた。便器に座り続けた上に坂道を歩き続けたので、秀雄の腰から下は感覚が鈍くなっていた。
「こんな実験を毎日やっているんだろうか」祐樹の心は元気を失った。
家の玄関では、外灯の赤色電球がオレンジ色の光を放って二人を出迎えた。木造の平屋住宅だ。小さな家に小さな庭があった。花壇がレンガで囲ってあった。千日紅が電球の明かりの中でピンクの花を咲かせていた。煙突式の臭突が家の奥に見えた。ここのトイレは汲み取り式らしい。電球の周りを蛾がぶんぶんと飛んでいた。
「ただいま」
阿部課長は玄関前で声をかけた。つづいて、
「おかえりなさい」
明るい奥さんの声が返ってきた。玄関の引き戸が開いて。四十歳くらいの、美人の奥さんだった。
「松原智恵子に似てるだろ」
阿部課長は秀雄の耳元で囁いた。祐樹の心はキョトンとなった。晩御飯の用意があった。ご飯とたくあんとみそ汁と、ほっけの焼き魚が一品だった。昭和の晩御飯だ。ご飯から湯気がたっていた。秀雄は、ご飯をかきこんだ。つづいて味噌汁もすする。冬瓜と油揚げの味噌汁だ。八丁味噌がのどにしみる。
「わあ、うまい」
「まあ、おなかペコペコだったのね」
「毎晩遅くまでご苦労様」と奥さん。気さくな感じだ。奥さんが、阿部課長のコップにビールを注ぐ。
「ノズルがね、あれがなんとかなれば、だいぶ進むんだが」
と阿部課長。ビールを飲みながらひとりでぶつぶつ言っている。
「秀ちゃんも」
奥さんが、秀雄のコップにもビールを注いだ。祐樹は二十歳になったばかりだが、秀雄はすっかり大人らしい。秀雄はいっきに飲み干した。
「うまい」
二十歳になったばかりの祐樹は、ビールの苦みが苦手で、これまでにおいしく感じたことはなかった。それが今夜は疲れを忘れるほどにうまく思えた。夫婦の会話から、秀雄は二十三歳で、昨年、名古屋の大学を卒業後に入社した開発設計課員で、出身が岡山だということまでわかった。阿部課長の部下は、秀雄と助手の女性の合わせて二人だった。
「うちの会社はタイルの製造が主流で、まだまだトイレ部門は日陰者扱いさ。水洗便器にモーターを取り付けるんだから漏電の心配がある。営業部はいまだに温水洗浄便器に大反対さ」
温水洗浄便器の開発設計課は、まだ会社では認知されていない部署のようだった。
「でもな、社長直々のプロジェクトなんだ。今に見てろ。そんな気持ちさ」
サニタリーノは、そもそも社長がヨーロッパを視察した際に、スイスの病院で使っていた医療用の温水洗浄便器を見て思いついた。阿部課長は、国立尾張大学工学部出身で、衛生陶器の設計一筋のエンジニアだった。創業家の社長には信頼されているが、研究熱心すぎて社内では変わり者あつかいされているらしい。
「また始まったわね」と奥さん。
「ごめんね。毎晩同じ話で」
阿部課長は酒を飲むと毎晩この話を秀雄にしてうさを晴らしているらしい。
一番風呂に入れてもらい、秀雄は課長のお古の浴衣に着替えた。
「うちの風呂いいだろ」
ビールのあとは地元の麦焼酎で晩酌を続けていた課長は、真っ赤な顔をして盛んに風呂を自慢した。ただのFRP(繊維強化プラスチック)のポリバスなんだが、この時代ではかなりめずらしかったようだ。知多製陶の製品らしい。風呂の自慢が口癖みたいだ。
「足が長いのね」
と奥さん。秀雄の膝から下が浴衣の裾からはみ出していた。その晩、秀雄は阿部課長に言われるままに、家の二階の一室に泊まった。娘が東京の大学に行っているとかで、昨年の秋からその部屋を使わせてもらっているようだ。ベッドに布団がしいてあった。窓は網戸になっていて、涼やかな海の風が注ぎ込む。風鈴が、チリンチリンと囁いた。蚊取り線香もたいてあった。壁には、富士山や東京タワーのペナントが貼ってあった。娘さんが修学旅行へ行った時の買い物らしい。昭和四十年のカレンダーがかかっていた。表紙は加山雄三だった。祐樹の心は知らないが、歌もお芝居もできる当時の若手大スターだった。
「昭和四十年・・・千九百六十五年か。東京オリンピックの次の年だな」
秀雄は、そんなことをむにゃむにゃ言っているうちに眠気に襲われて、夢を見ることなくぐっすり眠ってしまった。
次の日から、ふたたび実験の日々が始まった。朝の八時には実験が始まり、夜の十時、十一時は当たり前の毎日が続いた。
「おしりがもうだめです」
秀雄がおしりをおさえてトイレの実験室から出てくる。ノズルから出たお湯が肛門にジャストミートしないのだ。おしりのいろいろな場所にお湯が当たって、おしり全体が赤くなってしまった。温度センサーも調子が悪くなっていた。
「じゃ、一日、休憩しろ。今日は俺が座る」
秀雄は軟膏を渡されると阿部課長と交代した。助手の女性は、「たいへんね」といった表情で首を左右に振っていた。
ノズルの調整もだいぶ定まって、その年の冬、サニタリーノの第一号が発売されることになった。テレビCMは出稿料が高いので、新聞広告主体で宣伝が始まった。一台三十五万円で発売された。当時の大卒初任給が二万円だった。かなり高額な買い物で、乗用車のトヨタパブリカが買える値段だった。一般家庭の買い物としては高嶺の花だった。売れっ子芸能人や、会社社長、そしてやくざの親分が主な顧客だった。発売当初は、よく壊れた。修理できるものが社内には阿部課長と秀雄、そして数人の技術者しかおらず、手分けして全国の顧客の家へ修理にでかけた。全国の支店の車や電車を使って二泊ぐらいの出張はしょっちゅうだった。その間、次の開発はストップだ。ノズルの調子がたいてい悪く、交換部品を多めに持ってでかけた。
「この落とし前どうつけるんだ。うちの親分のいぼ痔が大やけどだ」
阿部課長と秀雄は、関西のある親分の屋敷によく呼びつけられた。小松の親分と慕われて関西では有名な親分だった。日曜日の早朝に阿部課長と二人で、やくざの黒塗りの高級車に拉致されて修理に行ったこともある。それでも親分は大変サニタリーノを気に入ってくれているらしく、直すまでは返してくれなかった。
「こんど壊れたら、大阪湾に沈むぞ」
それでも何度も壊れた。毎回同じことを言われた。
「もう嫌です」と秀雄。
「ノズルの改良を急ごう」と阿部課長。秀雄のグチを聞いていない。
お嬢と呼ばれる国民歌手の東京の豪邸に修理に行ったこともある。お付きの女性が数名いて、炊事、掃除、クリーニングの手配、仕事のマネジメントなど、ありとあらゆることをやって支えていた。
「玄関は通らないでね」と女中頭。二人は、裏口へ回された。廊下には奥にあるトイレまで便所紙が敷いてあった。トイレ関係者は不浄な人扱いだった。
「くやしいけれど、今は我慢、我慢」
阿部課長は秀雄に向けて諭すように、切れそうになる自分に言い聞かせた。二人の背後で終始、お嬢が修理の様子を見守っていた。サインをもらうことも忘れて阿部課長と秀雄はとにかく緊張して修理にあたった。直ったときは、「ありがとありがとありがと」お嬢から大変感謝されて、大きなぬいぐるみのお土産までいただいた。その熊のぬいぐるみは、秀雄の部屋に飾ってある。ぬいぐるみの背中には、「お嬢」と大きくマジックでサインがしてあった。それは、六畳の部屋でかなりの場所を占めていた。また、名古屋の地方銀行頭取の家に呼ばれたときは、奥方から、和式便器に温水洗浄をつけてくれと懇願されて困ったこともあった。「洋式ではウ○○が出ない」そうだ。
秀雄はなかなか優秀だった。阿部課長の修理技術をかなり早く習得した。秀雄に棲みついた祐樹の心も我ながら? 日々感心した。秀雄はよく勉強した。帰宅してからも自室で夜明けまでその日習得した技術をノートに写しながら復習した。
「早くひとりで修理できるようになるぞ」
秀雄の脳の中で、祐樹の心が占める割合はかなり低くなっていた。秀雄は阿部課長に頼まれて、たびたび名古屋の有名な肛門科専門病院へ、肛門関係の資料をもらいに出かけた。肛門の位置のデータが必要だったのだ。男女、年齢の差によっても肛門の位置が微妙に違うのだ。秀雄は肛門の資料を取りに来る男として、肛門病院の看護師さんたちの間で有名になった。
「控室で待っててね」
資料を待つ間、お茶を入れてもらったりもした。お茶菓子はういろうだった。ちょっとイケメンなので、看護師さんたちが代わる代わるのぞきにきた。秀雄は視線を感じながらお茶をすすった。
千九百六十六年夏。祐樹の心はすっかり秀雄の身体になじんでいた。
「いつになれば帰れるのだろう」
ときどきそう思いながらも、日々の仕事が忙しく、どんどん祐樹は秀雄になっていった。
あいかわらずノズルの不調が続いていた。新製品の発売が年明けに控えていた。ノズルを少しでも改善した新機種を出したい。阿部課長は焦っていた。工場の近所の飲み屋で、課長と秀雄は、ノズルの件でアイデア会議をすることもあった。酒を飲みながら、狭いカウンターに病院でもらった肛門の図解を広げて論議もした。
「阿部さん、もう店じまいだよ」
飲み屋のおやじさんが追い立てることもよくあった。阿部課長の酒量がだいぶ増えていた。
「俺も酒に弱くなったなあ」
足元がふらつく課長を抱えて、秀雄は家まで連れ帰ることもしばしばだった。
そんなおり、ライバルの小倉陶器でも温水洗浄便座の開発が進んでいるとの情報が営業部を通じて入ってきた。サニタリーノは便器一体型で、陶器の便器に穴を開けて最初から温水洗浄の機器を取り付けている。一方、営業部の報告では、小倉陶器の温水洗浄便座は、いわゆる便座で、どの洋式便器にも上から載せる形で取り付けができて、しかも安価だそうだ。知多製陶の社内は、いろめきたった。阿部課長は社長から呼びだされた。
「阿部君、小倉陶器にはどうしても温水洗浄便器の世界では負けたくない。
温水洗浄の民生品化は、そもそもわしが最初に思いついたんだ、頼むな」
こうして、阿部の温水洗浄便器の開発設計課はスタッフが増えた。といっても三名ほどだ。実験室も、工場とは別棟の元倉庫だったところをあてがわれた。ここは掃除道具を置いていた場所だ。だいぶ開発環境が整ってきた。とはいっても、うわさでは小倉陶器では、かなり大きな温水洗浄便座の開発室を建てたと聞くので開発環境も雲泥の差があるようだ。
「小倉陶器では、女子寮も建て直したそうですよ。しかも舎監のおじさんはショーン・コネリーに似てるとか」
と助手の女性。このままでは追い付かれるのも時間の問題だ。そんなおり、秀雄にデートの誘いがあった。スマホのない時代。会社の帰りに門のところで、るみからメモを渡されたのだ。神戸るみ。十九歳。総務部の女子事務員だ。るみは、地元の出身で実家が水道工事店だ。実家から工場へ通っている。男を誘うなんてこの時代にはかなり積極的な女性だ。アメリカの恋愛映画が好きで感化されたらしい。
「今度の日曜日は、名古屋でサウンド・オブ・ミュージックを見ようよ」
「いいよ。ぼくも見たかったんだ」
「ほんと? 」
秀雄は、るみとお付き合いを始めることになった。秀雄は丸顔のるみがひと目で気に入った。
『この時代で恋をしてよいのだろうか。
もう帰れないのかもしれない。・・・でも、もういいや』
秀雄は祐樹の心を脳の奥底へ押し込んだ。
ある夏の日曜日。夜九時頃。名古屋でのデートの通りに、二人は会社の女子寮の前を通りかかった。
「ここは毎週日曜日、渋滞してるね」
るみは、地元出身だから実家住まいだけれど、集団就職の女子社員たちは、女子寮住まいだ。日曜の夜は、女子寮の前は女の子を送って来た男の車が列をなしていた。恋人たちの別れの儀式があちらこちらで行われ、「ウエストサイド物語」みたい。るみは少し恥ずかしがった。午後九時が門限なのに、零時過ぎに塀を乗り越える強者女子もいるらしい。いつの時代でも、だけど、若者たちは青春を謳歌していた。
秀雄とるみは、デートを重ねた。三ヶ月後のある日。ふたりはついにキスをした。隣町の半田市でボーリングをした帰り道だった。海辺の道をゆっくり歩いているときだった。伊勢湾に沈む夕陽を眺めながら、
「なんかロマンチックな気分」とるみ。
「口に出して言うか」と秀雄。
二人は笑いあった。
さらにデートを重ね、やがて二人は結婚を意識することになる。しかしときどき秀雄の脳によみがえってくる祐樹の心は迷った。常滑のるみの実家の水道工事店を夫婦で継ぐことになるのか。自分は婿養子に入るのか。歴史がおかしくなりはしないか。この時代で結婚してよいのか。もう元の時代に帰れないならいいんじゃないか。いつもこの結論になった。しかし祐樹の心はどうしても結婚に踏み切れない。祐樹の心は葛藤した。
「もう少し時間くれる? 」
結婚に踏み切らない秀雄に、るみはいらだった。
「もう知らない」
知多遊園地のデート中に怒ってソフトクリームを秀雄にぶつけたこともあった。
るみは入社当初、工場で見かける秀雄のことを堅物で融通がきかない男だと思っていた。ところが祐樹の心が入ってから、もちろん、このことをるみは知らないが、あの堅物で勉強好きで、とてもボーリングや映画に行かないように見えた人が、よくデートに付き合ってくれるのだ。るみは祐樹の心が入った秀雄のことが好きになった。秀雄も、るみのことをかけがえのない存在に思えてきた。
大阪で、住宅設備業界の大きな展示会が開催された。大阪万博を三年後に控えて、大阪の街は活気に満ちていた。知多製陶にとっては、年明けの新製品の発売前の重要なイベントになる。秀雄は、阿部課長といっしょに商品の説明と売り込みに出かけた。全国の住宅設備関係の会社が出品していた。もちろんライバル社の小倉陶器も出展している。浴槽や流し台が主流で、まだ温水洗浄便座は出品していなかった。静かに開発を続けているに違いない。
「緊張しますね」と秀雄。
「すぐに慣れるさ」と阿部課長。だが、あいにくノズルがまたしても不調で、知多製陶のブースではとんでもない事態が生じていた。
「ひゃあ」
「どうしてくれるの? 」
ブースの中から悲鳴が上がった。ノズルから吹き出したお湯で顔を洗ってしまう人や、ズボンやスカートがべとべとになる人が出て、大混乱。中には、本当に用を足してしまう人がいて。知多製陶のスタッフは頭を抱えた。報告を受けた社長が本社から電話をよこして、阿部課長が受話器に耳を当てると、電話の向こうで怒声が響いた。
「何をやっとるんだ」
「申し訳ありません」
また、その日の翌日、出張の流れで関西のテレビ局のお昼の主婦向け番組に出て、阿部課長がサニタリーノの紹介をした。しかし、「トイレでおしりにシャワー」と聞いた出演中の漫才師が、おしりにシャワーを浴びて「あちち」と思い切り飛び上がるふりをするのを見て、司会者やガヤの主婦たちが嬌声を上げて笑い転げた。
「お尻の水が口から出るんじゃない?」
この放送を見ていた社長からまたしても阿部課長のもとへ電話がかかり、
「二度とテレビに出るな」と釘をさされた。
「申し訳ありません」
その日の夜、そんなこんなで大阪から知多工場へ帰ってきた課長と秀雄。すっかり気力がなくなり、開発設計課で二人はやけ酒を飲んだ。
「課長、もう終わりですか」
「いや、こんなことで終わりにしたくない」
阿部課長が引き出しにしまっていた麦焼酎を二人は二本あけてしまった。ふらふらになった秀雄は、家に帰ろうかと立ち上がったその時、足元の工具箱につまづいて転んでしまった。
「いてて」工具箱の蓋が空いていた。この工具箱は祐樹が未来から持ってきたものだ。そこにキラッと光るものがあった。ノズルだった。しかもステンレス製の。
「何だ、それは? 」
課長が手に取る。引っぱってみた。自動車のアンテナのように伸び縮みする。阿部課長は見たことのない形状に首を傾げながらもしげしげとながめた。課長はひらめいた。手にとった金属製のそれを、近くにあったサニタリーノの試作機にあてがった。この金属がなぜかサニタリーノ新型のノズルの位置にはまった。
「まるでこれの部品のようだな」
それにしても何の部品なんだろう。
「どこから持ってきた? 」
秀雄はおもわず未来のノズルだと言いそうになるが、おかしな奴と思われるのがオチなのでここは黙っていた。秀雄はわからないといった風に首を振った。
「そうか、車のアンテナのように伸び縮みさせればいいんだ」
阿部課長は左手で右の拳を握った。これがきっかけでサニタリーノ新型の開発が再始動した。阿部課長は今回はノズルに絶対の自信があった。開発が順調に進んだ。
「このノズルよいです。ぴたっとあたります。温度もちょうどいい」
トイレの実験室から秀雄のはつらつとした声が響いた。
「そうかそうか。じゃあ、出てこい。祝杯だ」と阿部課長。
しかし、沈黙が続く。いっこうにトイレの実験室から秀雄の声がしない。
「どうした。うれしくて泣いてるのか? 」
トイレから出てこないので、課長がドアをあけると、そこにはパンツを下ろしたまま秀雄が眠っていた。
「成功したぞ。・・・疲れたんだな。すっかり安心して」
実験室で成功したそのとき、トイレの実験室から、祐樹の心が消えていた。秀雄の身体を残して。秀雄は何かしばらく寝ていたような感じがしていた。そのまま立ち上がると、助手の女性が目をおおった。女性スタッフは二人に増えていた。
「きゃあ」
阿部課長は思わず秀雄のパンツを上げてやった。課長は、祐樹の心が現代に戻ったことに気がついていなかった。
現代。祐樹の心は常滑西団地のB棟901号室に住む、北野芳江おばあちゃんの家に戻っていた。父親はシャワットトイレの修理中だった。祐樹もしばらく寝ていたようなぼんやり感があった。トイレに座っていた。何事もなかったように、「そろそろ休憩にしよう」と父。祐樹の心が戻ってきたことに気が付いていないのだ。祐樹は立ち上がりトイレのドアを開けた。パンツを下ろしたままだった。
「きゃあ」
悲鳴があがった修理を頼んだおばあちゃんが、お茶とお菓子を持って立っていた。
「あれ、そういえば、あんた見覚えがあるわ。誰かに似てる」
おばあちゃんは、若き日の秀雄のことを思い出したのだ。名前は出てこないが。おばあちゃんは、昔、阿部課長の助手をしていた女性事務員だった。おばあちゃんは、首をひねっていた。休憩が終わり、
「これを取り付けろ」と父。祐樹はノズルの取り付けは初めてだった。父が祐樹に渡したノズルは、新品だった。伸び縮みする形状。とりはずした古いノズルはステンレス製。新しいのは抗菌仕様のプラスティック製だ。
「これのことを、CHITAXでは別名ヒデオと呼んでいるんだ。後発のKOKUTOに一時は抜かれたが、このノズルが開発されたことで、シャワットトイレは躍進し、その後シェアを奪取して国内一位になった。ヒデオも改良を重ねて五代目だな」
祐樹の脳裏には、一瞬、阿部課長の顔がフラッシュした。でも誰かはわからなかった。なぜか目が潤んだ。
「さっきはずしたノズルはどこへやった? 」と父。祐樹は、一緒にもどった自分の工具箱の中を見た。ステンレス製のノズルはどこにもなかった。
常滑市の海辺近くの街道沿い。二人は自宅に帰って、仏壇にお参りした。
「もうすぐお盆だな」と父。仏壇の上に、祖父母の写真がかかっていた。祖父は秀雄、祖母は、るみ。の顔だった。
「おじいちゃんは、知多製陶の開発設計課の社員だったときに、総務部の事務員だったおばあちゃんに出会って一目ぼれだったらしい。でもおじいちゃんは不器用だったから気持ちを伝えることができなくて、おばあちゃんのほうから声をかけたそうだ。おじいちゃんは、結婚を機に会社を辞めて、おばあちゃんの実家の水道工事店を継いだんだ。そして俺が生まれて、そしてお前が」と父。
「お前には話したことなかったかもな」
ちーーん。鐘を鳴らして、祐樹は手を合わせた。祐樹は、何か変な気分だった。遠い所へ旅でもしてきたかのような徒労感があった。海風が入ってきた。祐樹の頬をそよそよと撫でた。線香の煙が目にしみる。かたわらには母親が持ってきたスイカの乗った皿が。秋の気配がただよった。なんかしらんけど、これから頑張ろう・・・ふつふつとそんな感情が祐樹の心にわいてきた。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
