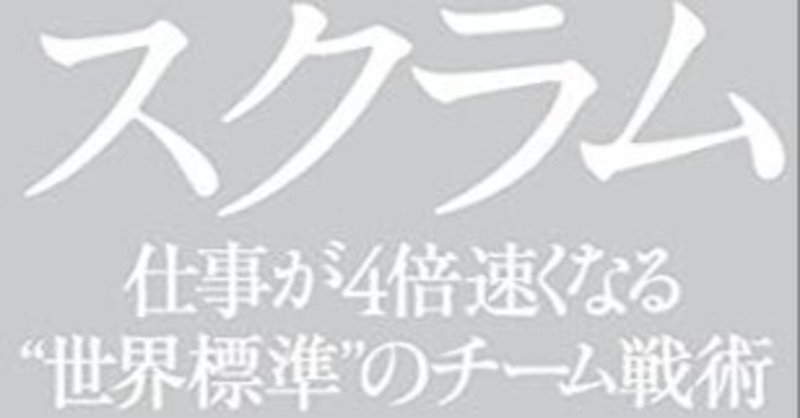
【書評】「スクラム~仕事が4倍早くなる世界標準のチーム戦術~」の思考を取り入れる
📚 この本を要約するとどんな本?
スクラムが誕生した背景・考え方をFBIや各社の事例をもとに解説しながら
スクラムの登場人物・イベントについて理解することができます。
私自体スクラム歴3ヶ月程度の初心者ですがこの本を読むことでスクラムの原則を再認識することができ非常に良かったです。
あくまでスクラムを実践したことがある・方法として理解している人に向けて書かれている本になるので初心者向きではないです。
スクラムが好きな方がこの本を読むとモチベーションも上がります!
📚 各章ごとの印象に残ったところを教えて!
第一章
計画は有効だが、何も考えずに計画に従うのは愚かだ。
早い段階で失敗し、早い段階で修正する
第二章
優れたチームとは、機能横断的で主体的、みずから動く力を持ち枠を超えた大きな目標を掲げている
憶測で済ませない。何をすべきか計画する。実行する。望んだ結果が出たか評価する。それを受けてやり方を改善する
第三章
それでも人はシステムではなくチームを責める。誰か個人のせいにできれば、自分自身が同じことをしてしまう可能性を認めずに済む
チームのパフォーマンスを変えること。個人のパフォーマンスを変えるより、その方が格段に大きな違いを生む。
第四章
今週はリストの中から何件できるかを話し合う。できるというのは完成させるという意味だ。
デイリースタンドアップ
チームがスプリントを終了するために、昨日何をしたか
チームがスプリントを終了するために今日何をするか
チームの妨げになっていることは何か
コミュニケーションを妨げるのは、仕事を専門化することだ。何かに特化した肩書きがつくと、人は概してその名前に合致した仕事しかしなくなる。そしてその役割についてくる権限を守ろうとして、自分の持つ知識にしがみつこうとするものだ。
待っているだけで無駄にしている時間がどれくらいあるだろう?無駄にした時間。ずっと仕事に埋もれていたいのならそれでいい。でも私なら、サーフィンにでも出かける方がいい
時間には限りがある。それを心して使うこと
デモで実物を見せる
肩書きを捨てる
第五章
自分ではうまくできると思っている人は、実のところ他の人よりもできていないのだ
得意だからマルチタスキングをするのではありません。注意力が散漫なためあれこれやろうとするのです。他のことに手をつけようとする衝動を制御できないということです。
常にマルチタスキングをする人は集中できていないだけという。そうせずにいられないのだ
プロジェクトを五件同時にかけていれば、その仕事の75%は何の成果も生み出さない。〜脳の構造上、限界があるからだ。
コンテクストを切り替えると損失があることを意識して欲しいと思う。名実にそうなのでこのロスを最小限に留めるよう努めるべきだ。
集中してやった方がいい一塊のタスクは一気にまとめてやり、この無駄をできるだけなくす方がいい。
こうしたタスクを時間の区切りで分割し、できれば電話にも出ず、邪魔をされなくて済む環境で取り組む。
途中までやった状態というのは本質的には何もしていないと同じだ
遅くまで働くのはコミットメントのしるしじゃない、うまくいっていないことの表れなんだ
みんなにバランスの取れた生活をしてほしいからいってるわけじゃない。その方が仕事が捗るんだ
スクラムでは、労働時間だけで評価するやり方からの脱却を求められる。かけた時間はかかったコストを意味する。時間ではなく成果を評価すべきなのだ
その仕事にどれだけ時間をかけたかが大事なのではない。大事なのはどれだけ速く、どれだけいい仕事ができたかだ
第六章
地図は実際の地形ではない
計画にうっとりしていけない。それはほぼ確実に現実とは違う。
必要な分だけ計画する
仕事はストーリ形式で
価値を得るのは誰なのか
どんな価値を提供したいのか
何のために必要なのか
第七章
幸福であることは、私たちの人生のほぼ全領域において成功に繋がっていると言っていい
論文的には人は成功しているから幸せなのではない。幸せだから成功するのだ。幸福は成功に先立つ要素であるということだ。
幸福度の低下はベロシティや生産性が低下する数週間前にも起きている
幸せとは主体性、スキルアップ、目的
誰でも自分の道を自分の手で切り拓きたい。今していることが上手くなりたい。自分の枠を超えた大きな目的のために役立ちたい
第八章
どんな仕事でも同じだ。最小の労力で最大の価値を生み出す部分は何かを考え、素早く形にする。鍵は優先順位の付け方だ
最小限の仕事で、顧客に何らかの価値を届けられるものがないかと自問してみてほしい。
変化のない停滞状態にいるのは死んだも同然だ。その意味するところはすなわち出口がないということなのだ
全てを守ろうとするものは何も守れない。リソースと気力をどこかに絞って集中させなければ、重要でないところで使い果たしてしまう。
📚この本を読んで実生活に活かしたいことを教えて!
デイリースクラムでは下記をしっかりと意識する。
・チームがスプリントを終了するために、昨日何をしたか
・チームがスプリントを終了するために今日何をするか
・チームの妨げになっていることは何か
仕事や私生活で特に下記を大事にしたい。
・途中までやった状態というのは本質的には何もしていないと同じだ
・遅くまで働くのはコミットメントのしるしじゃない、うまくいっていないことの表れなんだ
エンジニア、ひいてはいつ死ぬか分からない人生の中で下記を意識する必要がある
その仕事にどれだけ時間をかけたかが大事なのではない。
大事なのはどれだけ速く、どれだけいい仕事ができたかだ。
また、8章で説明していた下記部分は非常に参考になる
・どんな仕事でも同じだ。
最小の労力で最大の価値を生み出す部分は何かを考え、素早く形にする。
鍵は優先順位の付け方だ
・最小限の仕事で、顧客に何らかの価値を届けられるものがないかと自問してみてほしい。
・全てを守ろうとするものは何も守れない。リソースと気力をどこかに絞って集中させなければ、重要でないところで使い果たしてしまう。
終わりに
スクラムを実践している中でこの本を読めて非常に学びになりました。
「最小の労力で最大の価値を生み出す」を意識し、「大事なのはどれだけ速く、どれだけいい仕事ができたかだ。」の心でよりエンジニアらしく怠惰に働いていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
