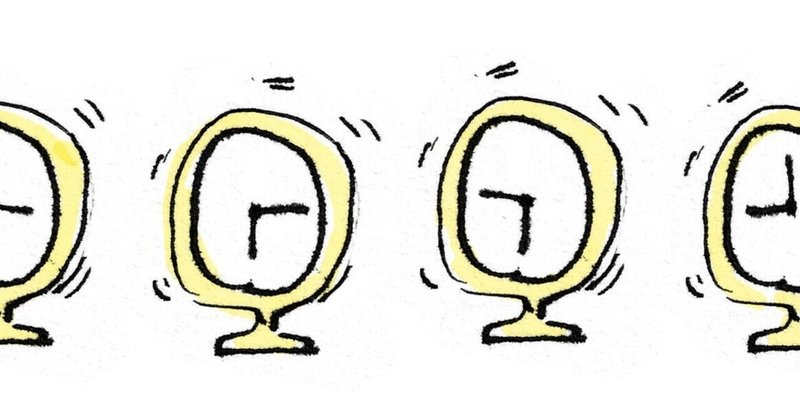
「十七時」(第102回聖翔祭 #1)
劇場版少女☆歌劇レヴュースタァライトまで見終えての二次創作です。
自分が次の駅に進むために作りました。
本作は、卒業してから初めての聖翔祭を控えた、星見純那と大場なな(と神楽ひかり)のお話です。以下本編です。
ふと目に入った時刻表示に驚く。もう二十二時を回っていた。通話時間も確かに一時間を超えていた。
画面の向こうの純那ちゃんは、まだ気づいていない様子だ。
「――西條さんには、まあ配信で見てもらうわけにもいかないし――」
第一〇二回聖翔祭。
卒業してから初めての、観客として臨む初めての聖翔祭が、ついに三日後となった。
華恋ちゃんや真矢ちゃんは入学前に見に行ったことがあるらしいけど、中学生の私にとって東京までの道のりには色々とハードルがあった。
それがイギリスに留学するなんて、あの頃の私に言ったらどんな顔をするだろう。
「――代わりにDVDを一枚もらって、それを渡そうって――」
今回はクロちゃんがそうだった。テアトロ・ドゥ・フランムの公演が間近で、どうしても日本に行けるのは来週になってしまうらしく、せめて映像だけでもクロちゃんに、ということになった。
その辺りの調整をしてくれたのが、ニューヨークにいる純那ちゃんと、東京にいるまひるちゃんだった。
「――ななは、予定どおりに来られるのよね。」
純那ちゃんはいつものように、現地で真っ先に買った星空の柄(と純那ちゃんは言うけど、たぶん国旗がモチーフのデザイン)のタペストリーを背にしている。
「え? うん、こないだのでもう予約したから。」
明日、三月四日の十七時、ヒースロー発。直行で半日後には羽田に到着する。東京時間で三月五日の十四時前。
あれ、三月といえば、
「ねえ、ニューヨークってもうサマータイム入ってるの?」
アメリカもヨーロッパも、確か三月から始まるんじゃなかったっけ。
「あー、まだだった気がするけど。いつからだったかしら。」
「そっちって今は何時だっけ。」
マイナス五時間だから今なら――
「えーっと、七時ね。」
「七時?」
あれ。サマータイムにしてもおかしいな。それとも間違えて覚えちゃってた?
画面を時計のアプリに切り替えると、ロンドンとニューヨークと東京の現在時刻が並ぶ。一番左の、ニューヨーク時間は――
と思ってたら、向こうから「あっ」と声が聞こえてくる。アプリを戻すと、純那ちゃんが眼鏡のツルを持ってかけ直したところだった。
「ごめんなさい、五時ね。十七時。私としたことが。」
ああ、七時と十七時。私もたまによくやるやつ。十七時ならぴったりマイナス五時間。
「再来週の日曜からみたい。ロンドンは月末ね。」
「あ、調べてくれたの?」
それならとりあえず明日の飛行機は大丈夫そう。十七時の……ん?
あれ?
「いまだに慣れないわ。去年のデイライト・セービングが終わる時も、図書館がいつもより早く閉まるっていうからおかしいなと思ったら。」
純那ちゃんは、ちょっと弛緩したような、気怠そうな雰囲気で話している。
「たまにそういうところあるよね、純那ちゃん。」
「いやいや、でもそのくらいよ――」
「純那ちゃんはいつなの? 飛行機、」
喋りながら座り直そうとする純那ちゃんの動きが止まる。視線だけがこちらに向く。
ほころんだ口元が小さくこわばっているように見える。
「何時発の便?」
重ねて尋ねると、純那ちゃんはゆっくりと椅子に腰を下ろし、口の周りに固まった糊をほどくように、おもむろに言葉を返した。
「えっと……ななよりは遅く着く予定なの。何時だったかしら……」
がくんと大きく画面が揺れる。立てかけていたスマホを手に持って、何かほかのアプリを開いて確認しているのかな。
あれ?
「そう。十八時半到着の便。ななは十三時五十分着だったわよね。」
「うん。」
「それじゃあ露崎さんの家には先に行っててくれるかしら。」
「うん。」
海外組(と言っても、今回は私と純那ちゃんだけだけど)は、聖翔祭の前日までに東京に来て、まひるちゃんの部屋に泊まらせてもらうことになっていた。久々に星光館の雰囲気を感じられると、まひるちゃんも快諾してくれた。
ほかにも東京を拠点にしている人はいるけど、華恋ちゃんは実家だし、双葉ちゃんは「私はいいんだけどさ……」って言うし、真矢ちゃんは「久々に露崎さんの実家の食材を使った大場さんの手料理が食べてみたいです」って言うし、自然と選択肢は絞られてしまった。
「神楽さんが留守番してくれているから、鍵は大丈夫ね。」
「うん。純那ちゃん、」
画面越しに純那ちゃんと目を合わせる。純那ちゃんの目を見る。
「待ってるからね。」
「え……ええ、もちろんよ。」
純那ちゃんは、一瞬だけ見せた戸惑いをすぐに裡に収めて、軽く頷いた。
それからまた画面が揺れる。スマホは元の位置に戻ったようだった。それに純那ちゃんも、何事もなかったように、
「そういえば、今日はどうしてるのかしらね。」
「今日って、香子ちゃん?」
「ええ。案外、バイクで東京まで来たりしてるのかしらね。」
「あれ、免許って結局とれたの?」
「……そうじゃなかったかしら。」
「何かで見た?」
「……インスタグラム……?」
「そっか! やっぱりやっておけば良かったなあ――」
そうして、私も何事もなかったように話し続ける。
けれど、そろそろこの電話も切り上げないといけない。帰国の準備が終わってなかったし。
その準備も、ひとつ増えてしまったことだし。
十四時前。羽田空港に到着する。オンタイムだ。
辿り着くまでもそうだったけれど、到着ロビーも思ったより人で溢れかえっている。これでは待ち合わせをしても、とても落ち合えそうにはない。特にこういう時には背が高いのは良いなと思う。
まっすぐ進めそうにもないので、ひとまず人の波から外れることにする。目指すは右手の壁のそば、どっしりと構えて入国客を迎える柱の脇へ。
柱は大部分がサイネージに覆われていて、今は来日した外国人に向けて日本の年中行事を紹介する広告が流れていた。人の間を縫って近づくごとに季節が巡っていく。
桜と富士、こいのぼり、夜空に上がる花火、そして笹から下がる七夕飾り。
去年のその時期はもう日本にいなかったから、思い出すのは、そう、あの高校三年生の初めの頃だ。
――まさか海外に行くなんて思ってもみなかった。ましてや――
身をひそめるように柱の脇に入り込むと、物思いを振り払って、少し背伸びをして辺りを見回す。
その時、覆いかぶさるように首に腕が回り込んできた。背伸びをする足が地面に押し戻される。
抱き着かれたことに気づく。抱き着いてきたのが、ななだと気づく。
「……なな? どうして……」
「まったく、純那ちゃんったら!」
振り返ろうとしたらななが肩に顔を寄せてきて、その横顔が間近に見える。
私がなぜ今ここにいるのか、そのことを尋ねるそぶりもなく、いつものように笑みをこぼしている。
「ぜんぶ分かってるわ、私には。」
その言葉に観念して、私は緊張で力んだ身体をほどいて、体重をななに預けてみる。おっとっと、と言いながらもバランスを崩すことなく私を受け止めてくれる。
えっと、どこで気づかれたのだろう。
「十七時?」
と問い返すと、ななは満足げに頷いている。その隣で純那は、壁から外して小さく折りたたんだばかりの星条旗の柄のタペストリーを握りしめ、ななの顔を覗き込んでいる。
「ひかりちゃんはわかる?」
まひるの家のリビングは、それこそ聖翔の寮とそれほど変わらないくらいでちょっと狭い。私とななと純那の三人で、ローテーブルを囲んでみたけど、ちょっと圧迫感がある。
「午後五時って意味で十七時と言おうとしたけど、引っ張られて七時って言っちゃうっていうのは、まあ。」
「うん。私もそうだと思ったんだけどね、純那ちゃん、こう訂正したの。」
――「ごめんなさい、五時ね。十七時。」
「どこか、おかしかった?」
そう尋ねる純那の顔は、怒っている……違う、ショックなのだろうか。
「この場合、引っ張られた元の『十七時』を先に言うのが、自然な感じがしない?」
「それは、まあ……」
そう言われれば、そんな気もしてくる。
「純那ちゃんはほんとうは、『七時』と『十七時』じゃなくて、『七時』と『五時』を間違えたのかな、と思ったの。だから先に『五時』が出た。」
純那を見てみると、さっきまでの様子と打って変わって、今はすっかり縮こまってうつむいている。どことなく耳の血色も良い。
こうなるのも仕方ない、これが図星なら。図星見純那。
「咄嗟に出た『七時』が純那ちゃんのいる本当の時間なんだとして、それでその時の日本時間が――」
「午前七時。三月四日の午前七時。ここで、あのとき電話してたのよ。」
少し締まりがちな喉から声を絞り出すようにして、純那が供述を始めた。
「そうしたら色々気づいてね。いつもと違う動きだけど身の回りの配置が普段と違うのかなとか、香子ちゃんの免許の話をする様子とか、」
「それで、私が帰国する便を聞いたのね。」
「ええ。その反応を見れば、違和感の正体がわかるかなと思って。」
わざわざ自分から言ったということは、その時にうまくかわせなかったという意識があるのかもしれない。ますます純那の血色が良くなっていく。
「それで、もしかすると先に日本に帰ってきているのかも、って思ったの。しかもそれをわざわざ隠していたり、私の帰りの便を念入りに聞いてくるから、ぴんと来て――」
「だからって、そこまで考えても、わざわざ裏をかいて一つ早い便に振り替えて羽田で待ち伏せしようなんて思わないでしょ神楽さん!」
急に顔を振り上げて私の方を見てくる。顔が上気したあおりで眼鏡が少し曇っている。
純那のその勢いに身を任せて頷いてあげようとも思ったのだけど――
「別に……」
確かに思ったことはないけど、それは例えば華恋がそうしたことがないからなのかなと思ってしまう。
純那が再び肩を落として縮こまるので、ついため息交じりに言い返してしまう。
「もともとそんなに手の込んだ計画でもなかったじゃない。」
二月半ばにNMDAのカリキュラムがいったん終了していわゆる春休みに入った矢先に、純那は一時帰国することとなった。というのも、年に一度は長崎に帰るという取り決めに、親が随分こだわっているらしかった。
「まあ、それでとりあえず長崎には帰ってね、けどもう地元離れちゃった子も多いからずっといるのもなんだし、かといって聖翔祭までにまたアメリカを往復するのも厳しいし、っていう話を、打ち合わせの時に露崎さんにしたのよ。」
私も隣で聞いていた。
「そうしたら、露崎さんの家に泊まらせてくれるっていうから、お世話になることにしたの。」
それで長崎からこの家にやってきた純那から、その時になって初めて、先に帰国していることをななにまだ話していないと知らされた。
「……ななには、聖翔にいる時から実家のことで心配させることが多かったから、」
「心配させたくなくて、ってこと?」
「も、あるけど、もっとあるのは……」
そう言って、純那がななの方へぐっと首を向ける。
近くない?
「また驚いた顔を見てみたかったなと思って。たいてい、ななには驚かされてばかりだったから。」
ななもななで、距離を詰めてきた純那に動じることなくまっすぐその目を見ている。と思ったら、不意ににっこりと微笑んでさっとテーブルに向き直った。
「純那ちゃん、」
「なに?」
「ありがと。」
その言葉を受け止めて、純那はじっとしている。
「それと、」
こくりと頷く。
「これじゃあまだまだ、私の知ってる純那ちゃんだったなあ、って!」
そう言って伸びをするななを見て、ぷっと噴き出した純那は天を仰いで、紅潮した顔を両手で扇ぎ始めた。すがすがしそうに見えるけど、真一文字に結んだ唇からは、そう、悔しさが滲んで見える。
それを横目にするななは、どこか満足げだ。
――二人はひとの家で何をしているのだろう……
それから不意に、純那が「あっ!」と声を上げて、ななと私を順に見て言った。
「ねえ、こっちって桜、もう咲いてる?」
そうして、私たちはまひるたちが帰ってくるまでの間、散歩に出ることにした。
まひるの家は新大塚の駅の近くにあって、しばらく歩くとサンシャインシティの方に出られる。その途中には去年できたばかりの広い公園があって、そこの桜はまだ咲いてはいなかったけど、しっかりと蕾がふくらんでいるのを見ることができた。
その日は三月の初めにしては寒さもゆるく、つい時間を忘れてあちこち歩き回りそうになったのだけど、途中で夕方のチャイムが流れて、ななの「帰ろっか」という言葉をきっかけに私たちは帰途につくこととなった。
そういえば、あれも十七時ね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
