
ブロックチェーン世代間戦争!勝つのは誰だ!? ~第二世代編②TRON~
こんにちは、you425です。
前回の記事を見てくださってる方は、タイトルで「おや?」と思った方もいらっしゃると思いますが、掘り下げるプロジェクトの順序をすっ飛ばして今回はTRONの話をしたいと思います。
何故そうなったかと言いますと、6月30日までに日本の取引所であるBITPointで口座開設するとTRONのトークン、$TRXが貰えるからです。
日本の取引所で扱う通貨ですのでもちろん変なものではありません。
ただ折角なので、僕も興味あった銘柄でしたし調べてまとめることにしました。
先に登録URL貼っときますね。
アフィリとかではないので安心(?)してください。
口座開設で1000円分、1000円入金で2000円分貰えるようです。

前提のブロックチェーンの世代に関してはこちらをご覧ください。
では、本題に入ります。
※個人の解釈や感想が強めに出ますのでお気をつけください。
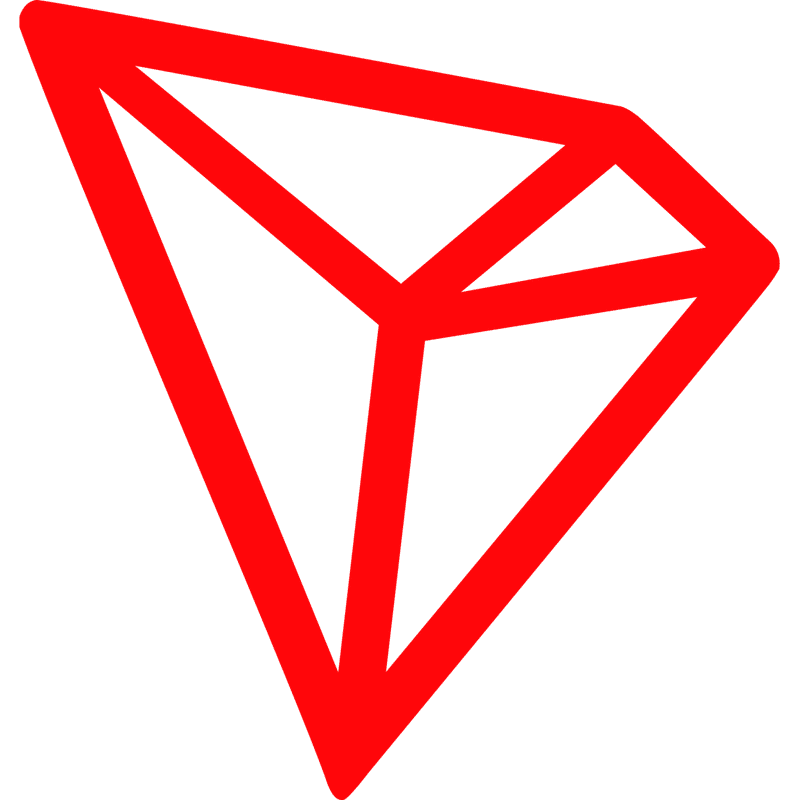
1.第二世代 代表②TRON($TRX)
TRONは、EthereumやEOSと同じ、第2世代のスマートコントラクトプラットフォームとして開発されました。
また、後述しますがゲームや動画、デジタルコンテンツを提供するプラットフォームになることを目的としています。
また、Ethereumにはないストレージ機能を備えています。
ここが差別化されている特徴的な点ですので覚えておきましょう。
テストに出ますよ!
2.DPoS(Delegated Proof of Stake)
TRONのコンセンサスアルゴリズムは、DPoSというPoSの一種を採用しています。
Delegate=委任という意味です。
各バリデーターにユーザーはTRXをステークすることで投票権を委任し、ブロックを承認していく仕組みです。
その際、多く委任されているバリデーター程ブロック報酬を得られやすくなりま。
PoSなのでPoWに比べて消費エネルギーは少なく、高速です。
TPSは理論上10000と、驚きの数字です。
ただし、バリデーターの数が少ないため分散性が足りておらず将来においての懸念となっています。
また、他のPoS系のプロジェクトと比べステーキング率が低いことも今後の課題となっています。
3.TVM(TRON Virtual Machine)
TRONではEVM(Ethereum Virtual Machine)ではなくオリジナルのVMを搭載しています。
とはいえ、もともとはEVMのフォークとして作られてるため、言語はSolidity(今後、対応言語追加予定)を用いて開発でき互換性もあります。
これは、EVM系のプラットフォーム(BSCやFTM、Polygon等)からDappsを移行したり、開発者がTRONで新しく開発始める可能性があるということです。
4.ストレージレイヤー
冒頭でも出しましたが、TRONにはストレージシステムがあります。
Ethereumにはこの機能はありません。
どういうことかと言いますと、Ethereumのノードに保存されていくのはトランザクションが入ったブロックのみです。
しかし、TRONではその他のデータもノードに保存することで、データサーバーとしての役割も果たすことができます。
5.垂直統合型のプロダクト戦略
TRONにおいて最も重要な点はこの垂直統合型のプロダクト戦略です。
聞きなれない言葉ですが、プラットフォーム開発をするにあたってこの戦略はものすごく有効です。
身近な例を挙げます。
MicrosftはOSとしてWindowsを開発しましたが、Windowsようにオフィスソフトのようなキラーアプリを開発することで大きなシェアを獲得しました。
また、AppleはiTunesとiPodを開発したうえでiPoneを発売することで、同じように大きなシェアを獲得しています。
どちらも、開発したプラットフォームで稼働するキラーアプリを運営側で用意することでユーザーを誘因する仕組みになっていました。
僕はよく、「どれだけ良いプラットフォームでもプロダクトがなければ使われずにトークンの価格なかなか上がらない」という話をしています。
垂直統合型のプロダクト戦略というのはこの点とても優れています。
※逆パターンに水平分業型といのもあります。
なぜEthereumを使うのか?
なぜBSCを使うのか?
なぜPolygonを使うのか?
使いたいDappsがあるからですよね、ということです。
プラットフォームに良いプロダクトが出来る→人が集まる→プラットフォームの価値が上がる→良いプロダクトが集まる→人が集まる→
このループです。
とても大事な流れですので覚えておきましょう。
では、話を戻します。
TRONでは、BitTorrentとdliveというアプリを買収や提携しています。
BitTorrentはP2Pのファイル共有システム、dliveはアメリカの動画配信サービスです。
どう展開していくかは予想になってしまいますが、
1,dlive上でTRON系のトークンを発行して利用できるようにしたり、TRONエコシステムに関わる広告などを出してトークンを配布(BraveのBATのように)。
2,配布されたトークンでDappsに参加したり、ゲーム関連のNFTの購入などに回したりすることで経済が回る。
3,Dappsやdliveの動画はBitTorrentを利用して保存される。
4,BitTorrentのユーザー数が増えることでストリーミングが安定し、よりdliveが使われるようになる。
というような感じで相互でよい影響を与え合うことで高いネットワーク効果を狙えます。
まだ統合が済んでいないので、今後に期待できるポイントです。
また、中国の動画配信サービスと提携しているのも良い点です。
6.10年に及ぶロードマップ
伸びしろがあってよいと思うか、遅すぎて悪いと思うかは人によるでしょう。
全部で6段階のアップデートがあり、現在3つ目の段階です。
ここからが本番と言えます。
1,Exodus (2017年8月~2018年12月)
プラットフォームの基本的な構築
2,Odyssey (2019年1月~2020年6月)
著作権の管理やクリエーターへの報酬システム構築
3,Great Voyage (2020年7月~2021年7月)
TRONのシステム管理に関する問題解決
4,Apollo (2021年8月~2023年3月)
システムを使って独自トークンを発行できる仕組み作りと問題解決
5,Star Trek (2023年4月~2025年9月)
独自のブロックチェーンゲーム実用化
6,Eternity (2025年9月~2027年9月)
開発側の資金調達やゲーム開発が自由にできるようにする
7.懸念点
長い目で見て期待できそうなTRONですが、懸念点があります。
TRONに限った話ではないですが、運営側の主導で開発が進められていることです。
これは開発スピードや意思決定が早いため良いところでもあるのですが、TRONのCEOに関してはFUDが目立ちます。
そのため、$TRXの価格に影響が出てしまうのは悪い点です。
それと、長大なロードマップも懸念となります。
開発に時間がかかっている間に他のプロジェクトに立ち位置をとられる可能性もあります。
8.まとめ
ということで、今回は日本ではあまり話題に上がらないTRONに関して書きました。
BITPointで口座を開くのに手間はかかりますが、とりあえずもらっておいて損はない銘柄だと思います。
まだまだ開発の途中なので、今後に期待…ですが、懸念点もありますのでトークン貰ってそのまま放置しとくのでいいかな…。
第二世代でここまで方向性が決まっているプラットフォームは珍しいので、やんわり見守っていきたいと思います。
では、長文にお付き合い頂きありがとうございました。
また次回をお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
