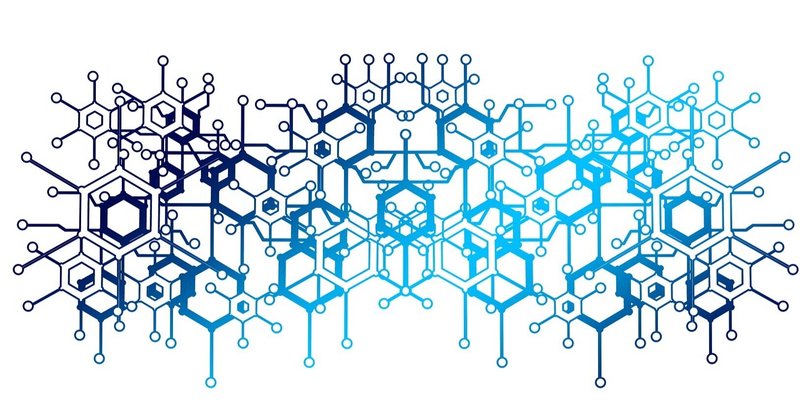
ブロックチェーンの世代と変化 1.0~3.0へ
こんにちは、you425です。
今回は、ブロックチェーンが経てきた歴史と変化について触れていきたいと思います。
少々長いのと小難しい話が続きますが、暗号資産に投資をするうえで把握した方がいいと思うことを書きました。
我々が触れているのはある分野の技術の最先端であるということを認識していただけると幸いです。
1.基本の基本、ブロックチェーン1.0とBitcoin ~送金と決済~
まず、ブロックチェーンの基本(分散型台帳技術)に関してはこちらのNTT DATAさんの記事が短くまとめられているのでご覧ください。
はい、ブロックチェーンというのは実は単なる分散型のデータベースという技術だということがお判りいただけたと思います。
ブロックチェーンの元祖と思われているBitcoinですが、ブロックチェーン技術を使って表に出たのがBitcoinネットワークというだけで、技術そのものは1991年には出ていたそうです。
実は30年も経っている分野なんですね。
では、Bitcoinネットワークは一体ブロックチェーン技術を使って何をしようとしたのでしょうか。
折角なのでご本人に聞いてみましょう。
英語難しいよ…。
ということでどういう思想の元で提案されたプロジェクトなのか、僕なりに要点をまとめました。
信用できる第三者機関としての金融機関に頼ることなく、P2P電子マネーによって直接オンライン取引を可能にしたい。
必要なのは、暗号化された証明に基づく電子取引システムであり、これを用いることで第三者機関を介さずに直接取引をすることが可能となる。
より自由で、第三者に管理されることのない取引システムを作りたかったんですね。
実際、第三者機関によって取引を却下されたり、多額の手数料を払うことになったり、送金スピードに問題があったり様々な不便さはあったと思います。
この論文に賛同した者たちが集まり、Bitcoinネットワークは構築されました。
2.ブロックチェーン1.0から2.0へ ~スマートコントラクト~
というわけで、最初に作られたBitcoinは送金と決済を目的として構築されました。
後に続いて作られる暗号資産も同じように、仕様の違いはあれども送金と決済を目的としています。
例を上げましょう。
ブロックチェーン1.0の例
目的:送金・決済
Bitcoin:$BTC
XRP(Ripple):$XRP
Litecoin:$LTC
Dogecoin:$DOGE
こうしていろいろなプロジェクトが発足しましたが、ある日若き天才ヴィタリック・ブテリンは「Bitcoinは分散型アプリケーションを構築するためのスクリプト言語が必要」とコミュニティ内で提案しました。
しかし相手にされなかったため、彼は新しくブロックチェーンベースの分散型コンピューティングプラットフォームの提案をしました。
彼が公開したホワイトペーパーに数多くの賛同者が集まり開発が進められることとなります。
そう、それが皆さんご存知のEthereumです。
ブロックチェーン1.0では送金と決済はできるものの、例えば「送金したけど商品は届かない」というように、P2P間での信頼を元に取引が行われるために契約が履行されないという問題がありました。
そこで実装されたのがスマートコントラクトという機能です。
Ethereumネットワーク上では、スマートコントラクトを利用することでトランザクションを通す条件を付けることができるようになりました。
スマートコントラクトを用いて稼働するアプリケーションをDapps(Decentralized applications:分散型アプリケーション)と呼び数多くのプロジェクトが稼働しています。
よくある例えですが、自動販売機のようなことができるようになったわけです。
今までは人にお金を渡して商品を受け取っていたものが、プログラムにお金を渡して商品を受け取れるようになったということですね。
人ではなくプログラムを信用することでTrustlessな取引が出来るようになります。
プログラムは嘘つかない、嘘をつくのは人間だけ。公正で合理的!
このようにして一世を風靡したEthereumですが、スケーラビリティ(拡張性:トランザクションの容量圧迫によりスピードが低下した)に問題がありました。
そしてブロックチェーン1.0の時と同じように様々なスマートコントラクトプラットフォームが立ち上がります。
ブロックチェーン2.0の例
目的:契約(スマートコントラクト)
Ethereum:$ETH
Cardano:$ADA
Eos:$EOS
Tezos:$XTZ
Tron:$TRX
3.ブロックチェーン2.0から3.0へ ~相互運用性~
様々なブロックチェーンプロジェクトが立ち上がり鎬を削る中、とある問題が立ち上がりました。
各ブロックチェーン間での相互運用性です。
それぞれが「僕の考えた最強のスマコンプラットフォーム」を作った結果、トークン規格の違いから暗号資産の行き来が非常にしづらくなってしまったのです。
通貨や資産において、流動性というのは非常に大事です。
多くの人が利用するからこそ値段が安定し、市場規模は大きくなり色々なところで利用できます。
しかし、各々の規格で作られているためにブロックチェーン間での移動が気楽にできません。
最近はブリッジが増えてきたために資産移動が楽になりましたが、それでもほとんどはEthereum系のブロックチェーン間でしか機能してなかったり流動性が足りておらず取引所を経由することも珍しくありません。
そこで、相互運用性を考えて開発されたのがブロックチェーン3.0と呼ばれる新世代のプロジェクトたちです。
ブロックチェーン3.0の例
目的:相互運用性(インターオペラビリティ)
Polkadot:$DOT
Cosmos:$ATOM
Avalanche:$AVAX
Solana:$SOL
この新世代たちがどのようにブロックチェーンの世界を広げていくのか、わくわくしてきませんか?
まとめ
ということで、ブロックチェーンの世代と変化 1.0~3.0へはここで辺で終わりにしたいと思います。
あなたが今HODLしている暗号資産はどの世代、またはどの世代のプラットフォームで稼働しているものでしたか?
もちろん、世代が新しいからと言って優れているというわけではありませんので、ご安心ください。
重要なのは、「どういう立ち位置でどういうことをしようとしているプロジェクトであるか」です。
このお話については、次回で触れようと思います。
長文となりましたが、最後までお付き合いありがとうございました。
次回、ブロックチェーン世代間戦争!勝つのは誰だ!?
お楽しみに!(このタイトルでやるかはわかりません)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
