
「ワイン」を学ぶ、学び方 〜仕事にも効く効果的な学習方法〜
2020年の新しいチャレンジとして、ワイン超初心者からのワインの勉強開始、J.S.A ワインエキスパート試験受験がありました。無事に一次の筆記試験、二次のテイスティング試験を通過し、晴れて合格となりました。
今回、意図的に幾つかの学習方法にトライしており、今回はその中でも効果が高いと感じられた3つのアプローチをご紹介したいと思います。これはワインの学習だけではなく、ビジネスを始め、他の分野にも応用が効くのではないかと考えています。
そもそも今回、ワインの学習を始めた理由として以下がありました。
・教育事業を展開する上で様々な学習理論・研究について学び議論し、自社としてサービス展開する上で、その効果について自身で実験をしたかった
・実験するのであれば、学習効果の差分が大きい(インパクトが大きい)領域がよかった(経営戦略やマーケティングは一定の知識の土台があり学んでも差分が小さいかと考えた。一方ワインは「赤と白の種類がある飲み物」くらいの知識しかなく、学習のインパクトがわかりやすく出そうだった)
・ワインを飲むのは好きながら全く知識はなく、「教養」の一分野としても理解しておきたいと思った
上記踏まえ、これから紹介するようなアプローチを取り、結果として「赤と白の種類がある飲み物」の知識しかなかった私が、半年間の学習で「わかりやすい指標としての資格取得」にいたり、直近あったテイスティング機会では白赤12品種中11品種当てることができました。ワインが好きな仲間と食事をする時も、料理に合わせたワインのセレクトを任されるようになり、そのワインで場が盛り上がるような嬉しい局面も増えてきました。もちろん、知見としてはまだまだで、自動車の運転でいうと免許を取ったくらいのイメージですが、一つの区切りとしてこちら書かせて頂きます。
今回は「Learn Better」という書籍で紹介されている実験・研究から応用した3つのアプローチを紹介します。
1.(学習の)意味を自ら発見する
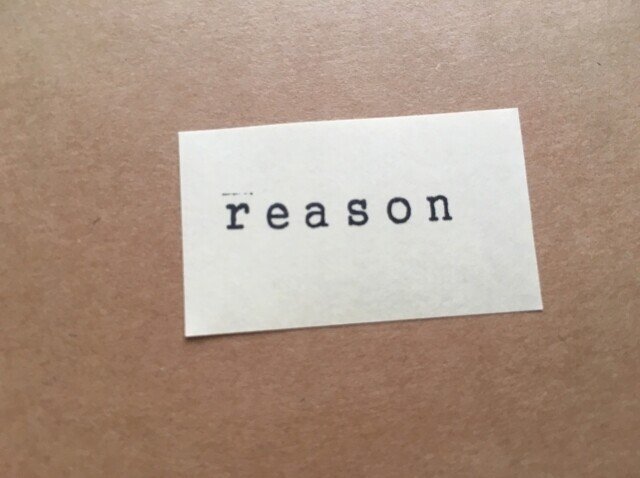
<実験内容要約>
ヴァージニア大学の心理学教授、クリス・フルマンの発見。フルマンが教えている心理学専攻の学生たちのほとんどが相関係数の話が出た途端に不満の声をあげる。統計学はつまらない、自分の生活には何の関連性も価値もないと見えてしまう。フルマンと共同研究者たちは学生たちにデータツールの価値を見出させる狙いで、学生たちに「自分の生活で統計学を使うシーンを想像できますか?」というお題を出しエッセイとして提出させた。結果は歴然としていた。自分の生活と統計学の関わりを意識することで、学生たちのモチベーションは大幅に上がり、成績が一段階上がった学生もいた。統計学が自分の将来の職業、趣味、いつか築く家庭にとってなぜ大事かを説明する行為によって、学習のレベルが一足飛びに向上した。
<実験からの示唆>
人は活動の意味を自分で見つけることにより、セルフ・モチベートされるということが言えそうです。我々が求めているのは結局のところ「意味」であり、それは誰かから押し付けられるものではなく、自分自身で発見する必要があるのではないかと考えます。
<ワインの学習への学び>
ワインを学習する意味合いを、自分自身のストーリーの中に如何に位置づけるかが重要だと考えました。私の場合、冒頭に述べたような「仕事で活用する理論について実体験を伴った検証をしたい」という動機がありました。ただ、それだけであれば、自身が詳しくない他の領域でもよいことになります。あまり認めたくはありませんでしたが、自分の時間が仕事に偏重していく中で、学生時代は大好きだった哲学や美術に触れる機会が少なくなり、現在の自身の「教養不足」を自認していました。リベラルアーツの一つの側面から「ありたい自身の姿の補完をしたかった」という想いもありました(ここは少し自分を拗らせていますね笑)。なかなか学習が進まない時、若しくは興味がない分野にさしかかった時、「何で自分はこの勉強やってるんだっけ?」と思ってしまいがちになりますが、そんな時この「意味合い」を思い出すことにより、私自身、学習を継続させることができました。
<ビジネスに通じる学び>
昨今、「社員のモチベーションを如何に高めるか」という論点が様々な場所で語られています。同時に私自身も周囲のメンバーから「自身のチームのマネジメントを行う上でどうメンバーを動機付けたらよいか」という問いも受けてきました。そんな時に私がいつも伝えている一つのアプローチが「自社の理念と自身の人生の結節点を言語化する」という試みでした。企業あるいは事業の目指している方向性が、自分自身の人生とどう繋がるのか言語化することにより、自らその企業あるいは事業に貢献することの「意味」を見出し内発的にモチベーションを高めていくというものです。これは自分自身が貴重な人生の時間をなぜここで使っているのか、理解する上でも重要な試みだと思います。
2. プロセスに分解して学ぶ
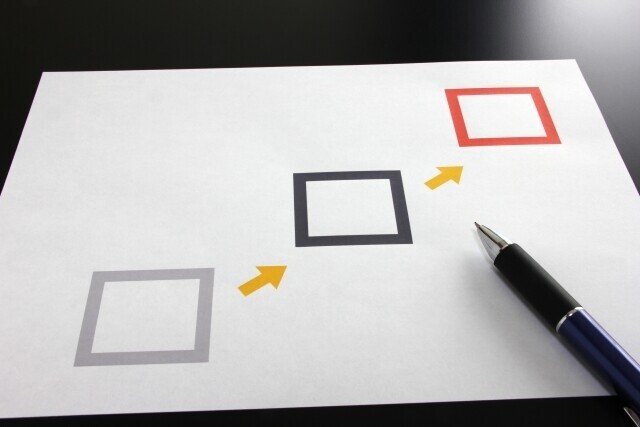
<実験内容要約>
ジョージ・メイソン大学のアナスタシア・キトサントスがNYの女子高で行った実験。被験者をグループ分けし、一方のグループにはただ「ベストを尽くせ」とだけ指示し、もう一方のグループには「ダーツの正しい投げ方に取り組み、ある程度上手くなったら的を狙って投げてごらん」と促した。その結果は歴然としており、後者のグループは前者の倍近い点数を叩き出した。キトサンタスは継続して調査を行い、ダーツ以外の他の分野でも、バレーボールから作文まであらゆるものにおいて、学習プロセスに力を注いだ方が成果が高くなることを発見した。
<実験からの示唆>
「適切な学習のプロセスに分解して学ぶことで習得の度合いと効果は大きく上がる」ということが理解できます。いきなり大きな粒度の成果を得ようとしてもそれは難しく、Stepを小分けに分解しながら、それぞれのポイントを学び得ていくことで、結果としての効率性・学習効果を高めることに繋がりそうです。
<ワインの学習への学び>
二次試験のテイスティングにおいては、何も考えないと「とにかく沢山ワインを飲んで違いを知ろう」という思考に陥りがちです。しかし、むやみにワインを沢山飲んでもテイスティングができるようにはなりません。学習プロセスとして「テイスティングとは何に答えるものでなければならないか」をまず学ぶ必要があります。少なくとも試験においては、「外観」「香り」「味わい」を識別することが重要だということに気づきます。では「外観」「香り」「味わい」はそれぞれどんな要素に分解をされるのか、その分解された各項目において、「どのような状態」であると「どんな表現として一般的に表現されるのか」を学ぶ必要があります。私は今回、アカデミー・デュ・ヴァンというワインスクールにお世話になりましたが、スクールでは当然のようにこのような学習プロセスが取られており、流石だなと思いました。私も、試験対策期間の前半はワインを飲むのではなくテイスティング要素の分解とその要素内における表現の分類及び判別方法を習得することに時間を使い、後半からワインを飲み、頭の中で分類した要素項目に感覚を振り分け言葉として表現に落とすというプロセスを取りました。テイスティングの試験対策にかけた時間は実質一カ月でしたが、この学習プロセスを取ったことは非常に効果的だったと思っています。
<ビジネスに通じる学び>
汎用的に適応可能な内容だと思われますが、一例として「育成」という観点でこのアプローチは応用できそうです。例えば、「BtoBの営業」について成果を発揮すべく、メンバーにどう学習をさせようかという局面にあったとします。ダーツの実験のように「ただただベストを尽くせ」と指示をするような根性論的なアプローチが必要な業界や事業ステージもあるかも知れません。ただ、今回の実験結果をもとに考えると、営業プロセスをバリューチェーン上に分解し、それぞれのプロセスにおいて重要となる要素(例えば、提案段階での効果的な資料作成、商談開始時におけるプレゼンテーション、クロージング時におけるネゴシエーション等)について学んでもらった後に現場の経験を積んでもらう方が、短期間に成果を出せる営業パーソンを育成しやすいのではないでしょうか。
3. 自分の脳内を「検索」する

<実験内容要約>
ある有名な実験で、被験者グループは文章を4回読んだ。別のグループは1回しか読まないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に二つのグループを追跡調査した所、思い出す練習をしたグループのほうがはるかによく文章を覚えていた。つまり、情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者のほうが、はるかに習得度が高かった。
<実験からの示唆>
認知心理学者のボブ・ビョークの述べる通り、「記憶から情報を取り出す行為は効果の高い学習法」と言えそうです。我々は何らかの学習をした後に復習する際、ついつい教科書を読んだりしてしまいがちですが、「自分の脳内を検索する」学習行動の方が時間効果が高くなることがわかります。アメリカを代表する記憶の専門家であるフロリダ国際大学のベネット・シュウォーツも同様の方法で知識に磨きをかけているそうです。
<ワイン学習への学び>
ワインの知識がほぼゼロだった私には最初に知識としてインプットすべきことがあまりに多くありました。比較的興味が強く且つ一次試験にも出題される「ワインの歴史」から学び始めましたが、この時まさに検索練習を使いました。具体的には、一度学んだワインの歴史について、自分の頭が自由になる時間に思い返し辿ってみるというアプローチです。
紀元前7000年~6000年頃の古代メソポタミアでワイン生産を目的としたブドウの栽培が始まり、キリスト教の重要アイテムとなりローマ帝国の進展とともにヨーロッパに広がり、大航海時代に新世界に展開され、そして現在アメリカと急成長する中国マーケットに大きな影響を受けているという流れは、その枝葉の部分含め、朝、シャワーを浴びながら頭の中で反芻をしていました。結果として何度も書籍を読み返すことなく、比較的スムーズに頭の中に入ったかと思われます。ブドウの醸造フローや各ワイン生産地域の地理なども同様の知識習得しました。
<ビジネスに通じる学び>
急激に変化する外部環境の中で生きている我々にとって、常に新しいことを学ぶことの必要性は論を待たないと思われます。例えば書籍を読む際に、私たちは気になる頁を折ったり、線を引いたりします。それ自体はよいのですが、自身の記憶に取り込む際、「この書籍において何が学びとなったのか」頭の中で思い出し、それを言語化し、アウトプットするということをよく行うようになりました。以前と比較し、得た情報を自身の中にストックできる深さと広さが拡大した実感を持っています。
余談
これは「Learn Better」からの学びではなく、私が展開するクラスにおいての話なのですが、経営戦略(事業戦略)のクラスにおける「戦略策定プロセス」も今回の学習のプロセス分解に応用ができました。
こちらのクラスでは戦略策定プロセスとして大きく、
①外部環境分析~KSF(Key Success Factor)の導出
②内部環境分析とKSFとの比較による経営課題特定
③経営課題を解決するための戦略オプション策定~評価
④実行
という4つのプロセスで考えることを奨めています。
特に今回の二次試験において上記プロセスを踏まえると、以下のような考え方を取ることができました。
①外部環境分析~KSF(Key Success Factor)の導出
→「過去の試験問題と傾向を分析し、今回の試験において合格する要件とは何か?」考え、自分なりの定義を行いました。
②内部環境分析とKSFとの比較による経営課題特定
→「①で導き出した要件に対して現在の自身が整合している部分・不整合を起こしている部分をどこか」明確にします。二次試験に関しては、配点の高さに関わらず全く理解ができておらず、感覚としても弱い「香り」が課題であることを明確化しました。
③経営課題を解決するための戦略オプション策定~評価
→②で特定した課題を解決するための戦略オプションを策定します。私は鼻腔内に骨がやや突き出ており、且つ鼻炎がちであったため、そもそも鼻の中を通る空気の流量が多くないという弱点がありました。この点踏まえ、例えば、今回、方向性としてざっと以下のようなオプションが考えられました。
-1) 鼻腔内に突き出した鼻の骨を削る
-2) 鼻炎(ハウスダスト等にも弱い)の治療を行う
-3) わずかな香りでも判断できる嗅覚を養う
-4) 外観と味わいから香りを想像し推察する
20歳の頃、ある事情により -1) のオプションは検討しましたし、-2) のオプションでの通院体験もありましたが、今回は時間リソースなども踏まえ -3) -4) の選択肢を取りました。
④実行
→③の 3) 4) を学ぶためにはどれくらいの時間と何の手段が必要か、その時間と自身の時間リソースはバランスするか、いつどこの時間で何を学ぶのか学習計画を立て、後は淡々と実行しました。
以上、結果としては成果を残すことができ、そのプロセスとしての学習方法のご紹介を今回はさせて頂きました。
長文にお付き合い頂き、感謝申し上げます。
ワインであれ、他の分野であれ、学習志向を持たれている方のヒントに少しでもなれれば幸いです。
よいお年を!
#ワイン #ワインエキスパート #ソムリエ #学習方法 #勉強方法 #LearnBetter
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
