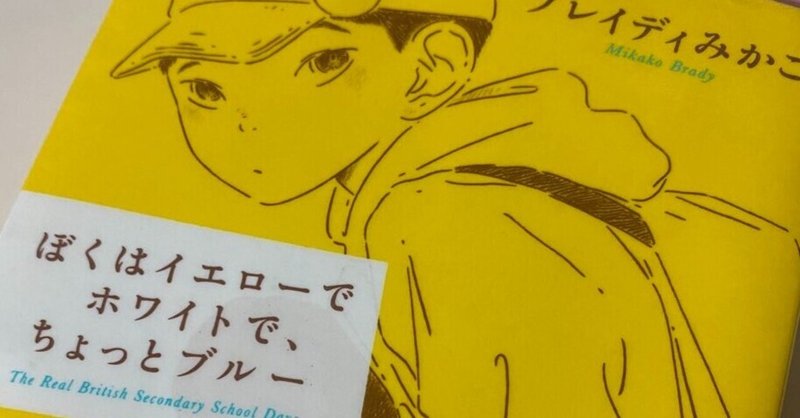
log2:「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」がくれる視点はいつでも大切で、大変だ
「アイデンティティ」と「多様性」について考えさせられつつ爽やかに読める一冊。
そう書くと一気に気難しそうに思えてきてしまうけれど、この本は筆者さんの息子くん(アイルランド人父と日本人母の間に生まれ、イギリスの学校に通っている)の中学校生活を通して見える景色のエッセイであり、深く唸ってしまいながらもさらっと読めると思う。
今回の本、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」公式サイトはこちら。(出版社特設サイト)
【今回の本選びについて】
以前から書店で並んでいるのをお見かけして興味はあったのだけれど、これまで手に取る元気に恵まれなかった…のだけれど、どうにもずっと引っかかっていたのでこの機会に手に取った。
とかく読むと何かしらの感想を書きたくなる本だと思う。「一生ものの課題図書」と帯で宣伝されるだけあって、中学生の息子くんの日常の中にそれこそ道端の草花のように雑多にあるあらゆる視点・問題は大人の我々こそ考えさせられる、普遍的なものばかりだ。
人種、貧困、性的志向、アイデンティティ…そんな、日頃は堅苦しく面倒に思えるテーマが、本当に日常的に転がっている。それへの向き合い方は、議会で政治家が罵倒とともに論をぶつのとも、twitter論壇で汚い言葉でレスバトルするのとも違う。
この課題がごろごろ転がっている環境の中に、わたしたちもまた生きている。生きていかざるを得ない。旗を揚げて戦わずとも、だ。
そういうところについてウーンと考えてしまう本である。
【ざっくり感想】
ざっくりでなくねっとりまとめたいところではある。けれどそうなると結構ポイントが分散してしまうように思うので、なんとかざっくりといきたい。
本書の中でも私があ~~そうだよねとかなり刺さってしまった一文があり、感想もこれに尽きるので以下に引用したい。それは、
「マルチカルチュラルな社会で生きることは、ときとしてクラゲがぷかぷか浮いている海を泳ぐことに似ている」
というものだった。
そうだよな…そうなんだよな、と思わず呟いてしまう。私は日本人で日本社会に生きているので、この「クラゲ」に行き当たることは海外よりも実際少ないと思うのだが、たまに何気ない会話の中にこのクラゲの脚の気配を感じ取り、慌てて言葉を修正することがある。
この一文は「わたし」が息子の通う中学校で行っている制服リサイクル販売(学校が元底辺校であり、イギリス版生活保護の家庭が多いこともあってこういう取り組みをしているようである)をしている段で出てくる。
学校にアフリカにルーツを持つ少女が転校してきて、その影響かはわからないが性教育の一環でいわゆる女性割礼(FGM)について教えられた、という出来事があった。
女性割礼は現在世界的な人権問題として取り上げられる話題であり、我々その習慣のない側からすれば性器を切ったり縫ったりするなんてとんでもないとなりがちなのだが、それが伝統通過儀礼である地域ではそうもいかない。故に、夏休みに密かに故郷に連れて帰って施術されてしまうケースも多いようで、学校で割礼について教育が行われたのもその防止、という面が強いようだ。
さて、筆者「わたし」がアフリカ人少女の母に制服を販売しようとした際に事件は起こるのだが、「わたし」は彼女に何気ない話題のつもりで「休暇はどちらに行くのか」と問う。
しかし、彼女はそれが「割礼をしに行くのでは?」という疑いのまなざしを向けられたものと捉えたのか、和やかだった雰囲気から一変して「アフリカには帰らないから安心しな」と言い捨てて場を去ってしまう。
「わたし」にはアフリカや割礼のことを問うつもりはなかった。しかし、彼女はそう捉えてしまった。
これが先の文によるところの「クラゲ」の存在である。
気をつけていてもクラゲに刺されるのはその存在に気付かないからだ。そしてそれが、その人自身のアイデンティティに深く根ざし、ときとして差別の対象になってしまう場合、当事者はどうしても敏感に反応せざるを得ない。うっかり触ることになってしまった側にそのつもりがなくても、である。
これは本書中盤に出てくるエピソードのひとつなのだが、これ以外にもこういったクラゲがあちこちに存在し、それをわざわざ指摘して喧嘩をしたりイジメを受けたりしてしまう少年もいれば、日常的なシーンでその断絶を感じ取って言葉を失う場面もある。
そしてそれはイギリスの住まいの近くだけでなく、帰省先の日本でも起こるので、イギリス特有の問題ではなく普遍的なものであることがわかる。
一方で、このお話で描かれている息子くんは白人とアジア人のハーフということで差別的に扱われることもあるのだが、本人としては「自分はどちらでもないので、どちらかに属している意識も持てない」と当事者意識を持てないことに悩むひとコマもある。この話が単純に単一のアイデンティティや差別の物語ではないところがわかる場面であるし、これにもまた考えさせられてしまう。
人間も社会も単一のアイデンティティで構成されていないし、そこに属せないと感じている場合もある以上、一筋縄ではいかないのだ。
多様性に意識を向けることの窮屈さがこのごろは大きく取り沙汰されることもあり、声を上げる人間を押し潰すような振る舞いも見られるようになった。
でも、そうなのだ。人間の多様性に目を向けていけば、「クラゲ」の存在に自然と行き当たり、ときとして痛い思いをする。その痛さを感じることそのものが、アイデンティティの異なる他者と向き合う最初の一歩であるように思う。それは痛いし、億劫だし、ときに自分のアイデンティティが傷つけられるかもしれない。それを繰り返し、異なるアイデンティティを持つ者がそれぞれ生きていく社会を捉えなおすのは、やっぱり途方もない作業である。
けれども、そんな中でも息子くんは友達と毎日を過ごし、道端にごろごろ転がる問題に頭からぶつかりながら成長していく。
その姿がなんだかとてもあたたかく爽やかなので、全体としては陰鬱になりすぎずに読めるというバランスが面白い本だ。息子さんのお友達との毎日も、喧嘩や差別発言やらイジメやらがあるのだが、その中でたくましく生きている姿が見えてくる。
最後の章で、息子くんは「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと○○」とブルーとは別の色を口にするのだけれど、そこにもまた未来を生きていく力を感じずにはいられず、ぜんぜん知らない相手なのにこれから先も健やかに生きてほしいと願わずにはいられなくなった。
私はもう大人になってしまったが、これを読んだ中学生の子たちはいったいどんな感想を得るんだろう?と俄然気になってくるが、当の中学生たちは夏休みの読書感想文を最終日に書きながら青息吐息、ネットで「タイトル 読書感想文 例文」で検索してしまっているかもしれない。
大人の思惑はうまくいかないものである。
【アイデンティティという言葉、多様性という海】
さて、ここから先は自分語り込みの感想である。
「アイデンティティ」という言葉をまともに考えたのは高校生のころだ。
私の高校の担任は3年間持ち上がりで、当時学校でも超怖いと有名な国語の先生だった。まだ体罰議論の真っ只中にあった15年程度昔のこと、彼は課題提出や予習を忘れてきた生徒には容赦せず、授業時間中に「立っておけ」と言うような男だ。
身長が高くて顔つきも鷹みたいで恐ろしすぎたが、ほぼ定年前なのにすらっとしたスタイルで声も穏やかで優しく、授業以外ではひょうきんで優しい面もたくさん見せてくれる。我々のクラスは彼の厳しい指導に怯えながらも彼のことが大好きでならず、卒業してからも訪問する者、彼と働きたいと教員になって戻ってくる者、退職時には駆けつけたりする者、そんな感じだった。
前置きが長くなったが、そんな先生が国語の授業で大事にしていたことが「語義をきちんと捉えること」だった。
それはどういうことかと言うと、現代文にしろ古語漢文にしろ、教科書に出てくるワードの意味をしっかり調べなさいということである。しかもこれが、単に辞書の解説を羅列するだけではダメで、辞書の解説が曖昧模糊としてわかりにくいものであれば、別の辞書を調べ、あるいはネットで検索し、なんとか己の言葉で解説するというところまで求められることもあった。
で、そのひとつのワードが「アイデンティティ」である。
授業の中で私たちクラスメイトがそこそこやり直しさせられながら最終的に導き出したこの言葉の意味は、
「『わたし』が何者であるかをとらえ、示すもの。『わたし』がほかの誰でもない『わたし』であるという自己同一性、『わたし』がどこに所属している者なのかという帰属意識、存在証明」
といった感じであったように思う。
当時高校生だった私は結構これに感動していた。というのも「帰属意識」が「わたしを示すもの」になるとは思っていなかったからである。
・わたしは、日本人だ。
・わたしは、○○高校△△科の生徒だ。
・わたしは、□□家の次女だ。
そういった要素をかき集めていくと、たしかにそれは「わたし」を特定するものになる。逆に言えば「わたし」はそういった非常に社会的な要素から成り立っているひとりの人間だ。それが、アイデンティティである。
そしてアイデンティティの異なる他人と向き合うとき、どうしてもその帰属する要素や育った環境、その人自身の思考…といったものから、同じものを見ているのに違うものが見え、それが原因で溝が生まれてしまうということもなんとなく理解した。ときとしてそれを悪意なく刺激してしまえば、相手を傷つけてしまうし自分が傷つくこともある、ということも。
思うに、わたしたちの生きる日本の社会は基本的にアイデンティティが単一になりがちで、だからこそ結束が強くなる場面があれば、異なるアイデンティティを持つ人間に対して手厳しくなってしまう面もあるのではないだろうか。
あんまり語るとそのスジの人に目をつけられて面倒くさいので(私は基本的に面倒くさがりである)詳しく語るつもりはないけれど、そういうシーンは日常的な会話でもtwitter論壇でもたくさん見てきた。
私自身はそういった帰属意識にあまり熱心ではないほうなので、そういう場面に行き逢うとどうしてもうげぇ…となりがちだし、そこから外れて苦しい思いをしてしまう人になんとか楽しく生きる環境を整えたいと思っているが、これもなかなか難しい部分がある。身近なひとと相談はできても、ひとりの力で社会はとても変えられない。
この本の内容に戻るが、「緊縮財政のために生保になった家庭が増え、その子たちの緊急的な支援(食べ物や日用品を買ってあげる)を教員が行ってしまっている」というくだりが出てきたときにもそう思った。これはイギリスの話だが、日本でもそういったことがなかったわけではなく、生保の家庭や児童生徒が教員の献身的なボランティアに支えられて卒業までなんとかもって行くということは往々にしてあるようである。
こういう事案が起きると日本では美談になりがちだが、そもそも教員はソーシャルワーカーでも慈善事業団体でもない。本来行政でも福祉サイドが担当する案件である。
しかし、そうは言ってもおなかをすかせた子どもや、家に帰れば保護者から育児放棄や虐待を受けている子どもも現実に目の前に存在する。してしまうのだ。そういうときにとりあえず自分が、と支援する場面は出てきてしまうが、彼らの環境が大きく変わるためにできることは限られている。
そしてそういった問題ごとは、日本の場合、彼ら彼女らの心や周囲との関係を大切にするために公になることはほぼありえない。こうして他者のアイデンティティは見えなくなり(見えるほうがいいとも思わないが)、そこに行き当たることのなかった子どもや周囲の大人は、貧困家庭のイメージがつかなくなってしまうだろうし、その問題に無関心でいられるのだろうし、場合によっては「あいつらだって特権を貪っている」と言い出したりするだろう。
それでいいのだろうか、という思いがいつも心のどこかにある。見ないことにしていてもクラゲはそこに浮いているし、誰かが痛い思いをしながら手を伸ばさなくてはならない事象もそこにはある。
「わたし」と異なる他者と衝突するとき、どう生き、どう接するのが正解なのか、わからなくなる。「わたし」自身のアイデンティティが揺らいでしまい、他者が「わたし」のために何かしてくれるときにさえ乗り気になれないこともある。
それは中学生の彼だけではなく、大人の私もそうなのだ。私もまだまだ『未熟』である。
重たい話になってきてしまったが、この本を読んでそんなことをつらつらと考え、大人である私たちはどんな後姿を彼ら子どもたちに見せてあげていたらいいのだろう、と、ちょっと考えてしまった。
若い彼らは彼らなりに一生懸命生きている。
そんな彼らが、いまの、クラゲだらけの海である社会に目を開いて漕ぎ出すとき、多少は傷ついてもどうしようもなく絶望的な想いにならないでくれたらいいが、と願っているし、その荒々しくも豊かな海を渡っていけるだけの「櫂」のひとつとなれるような言葉をかけられたらいいなと思った次第である。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
