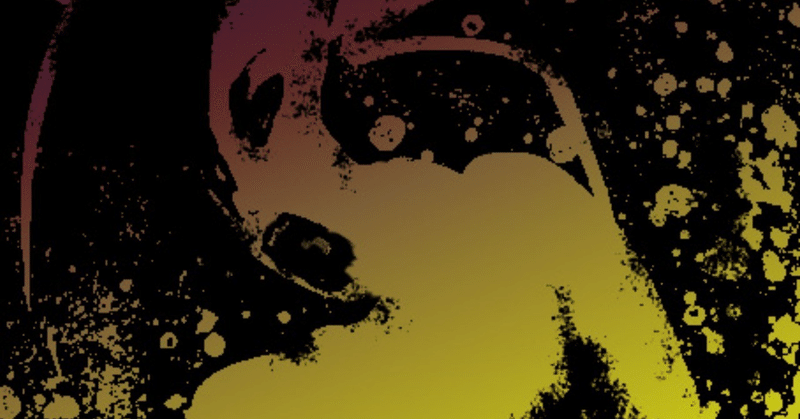
背鰭と青睡蓮の殺人-2
2
目を覚ますと深い闇の中に青い光が灯っている。米粒のように小さい光が宇宙にポツンと取り残された星のように見えた。寝違えたのか首が猛烈に痛い。首をゴリゴリと回しているうちに昼間の情景が思い出された。広がる田舎道で誰かが自分の名前を呼んだ。幽霊か疲れか、そんなことはどちらでもいい。俺は手元の電灯にスイッチを入れ青い星を消し去った。
外の風景が無性に見たかったのだ。とにかく外界のものを何か目に入れたかった。わずかに湿ったスリッパを履いてカーテンを開ける。眠りについてからずいぶんと時間が経ったのか外は黒一色で空には星すらない。手前の路上に目をやると飲み屋か何かの店内の光が漏れている。光は恋しいが、酔った常連客に混じって政治論など戦わせるほどの社交性は俺にはない。そんな人間を人里離れた場所に送り込んだ会社を呪った。もう明日が近づいてるのか数人の客が店から出て家路につくようだ。作業着を着た数人の男たちは肩を組んで闇の中に消えて行った。
ぼんやりとそのまま店の光を4階から眺めていた。あんな生き方もいいな。そんなことを考えたのは初めてだった。人恋しいのかもしれない。
永遠の静寂を突き破り巨大な積み荷のようなものが目の前を通過したのはその時だった。耳障りな摩擦音とともにそれは地面にドスンと落ちた。俺は腰を抜かしてその場に座り込んでいた。窓には何かの飛沫が飛び散っている。その液体はぬらぬらと窓の外を濡らしていた。まだそんなものが自分に残っていたのか、咄嗟の好奇心が働きケータイを手に取って窓を開け路上にカメラを向けた。カメラをズームし何かが落ちたあたりを見回す。どうやら店のそばに落ちたらしく女将らしき女が荷物に近寄っていく。が、それが何か分かると女将は悲鳴をあげて店の中に駆け戻ってしまった。何なんだ、あれは。カメラの明度をあげ俺はそれに出来得る限りズームした。その時の俺の顔は後で見るときっと赤面するほど血眼だっただろう。
…その路上に落ちた荷物は幾重にも縄で縛られた二人の人間だった。少なくとも人間以外のシルエットには見えなかった。店の薄明りに照らされぬらぬらした黒い液体が道に広がっていく。
その時の俺は不思議な達成感に包まれていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
