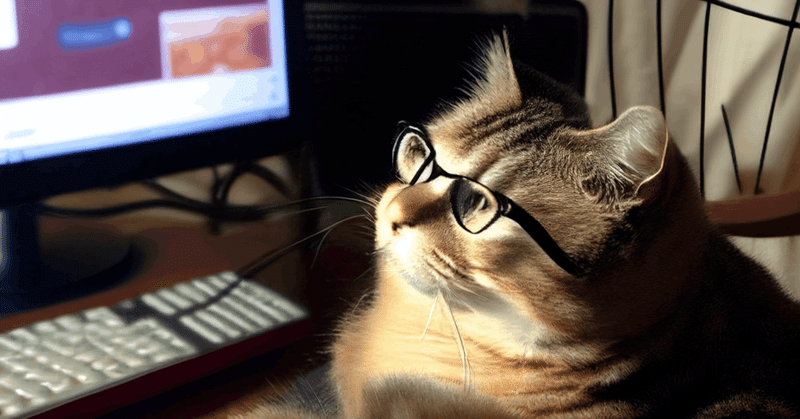
雲のでき方とか断熱膨張とかの話
noteの画像「AI」で検索すると女の子の絵がめちゃくちゃ出てきて怖い世の中ですなと思う今日この頃。
とにかく前回の記事が4ぬほど読まれてない(笑)
難しかったかな。いや、自分の中でも少し納得のいかない部分もあるし、コメントでも誤解を招いた部分がある。こいつはよくない。
前回の記事は、雲がなんでできるのかな?の原理を学ぶ、「断熱膨張」のお話でした。
今回はChatGPTを使って「断熱膨張」と気体の状態方程式やボイルシャルルの法則を用いて説明させてみた。
ってことでChatGPTに質問しまくったんですが、表現がぐるぐるしたり、間違っていたり、矛盾したりする。これは英語でやるべきだったか…。読めないけど。
(ホントはChatGPTとのやり取りを書いていたんですが、省略します)
前回の記事でわかりにくかった点?
昨日の記事のコメントにて、あっちんさんがくれた質問デス。
「温度が下がれば体積が増える」であってますか?
スープなどを冷凍すると容器が壊れてしまうというエピソードをいただきました。
正確には、「とある条件において、体積が増えると温度が下がる」ですね。
ちなみに「温度が上がれば体積が増える」のが一般的だと思います。
断熱膨張と逆です。
ヤカンでお湯を沸かすとき、それは温められた水は気体になることで、体積が非常に大きな水蒸気になります。(蒸気機関に活用されています)
あっちんさんのスープの件は、水の特殊性による容器の破損です。基本的に温度と体積は比例するシャルルの法則にしたがうので、水蒸気と水を比較すると圧倒的に水蒸気の方が体積が大きい。
水の特殊性ですが、例外的に水だけは4度以下になると体積が大きくなっていくという性質があります。
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/tea/sho/keyproject/pdf/rika_4nen2_04.pdf
またスープと容器の環境下では、温度を変化させていますね。この点も断熱膨張の環境とは異なります。
断熱膨張 vs ChatGPT
ということでChatGPTに聴いてみました。

聴き方を変えてみます

実際に、某知恵袋などにも同じような質問が多数あります。
何がわかりにくいのか?
わかりにくいのは僕だけ?いや、某知恵袋みたいなサイトにも同じような質問が多いんです。
混乱する要因は、
- 空気(気体)は見えない
- 圧力が見えない
- 計算は理想気体や特定の条件下である
だってさ、
空気が気圧の低いところに行くと体積が増えて温度が下がる。温度変化によって水蒸気が水滴に変わって雲が出来る。
空気の量が多いから気圧が高いわけで、その中で空気が移動するってどう想像すんの?この流動性のある気体とその気体からなる圧力。(混乱w)
ちょっと似たような例を探してみる
これ、空気と水(水蒸気)の関係だよね。
例えば、コーヒーとミルクで考えてみるかい?

下に落ちるミルクって、下でかたまる(沈殿する)
ちょっと混ぜてみると、ミルクが上に来た時に広がる
水圧の低いコーヒーの上の方に来ると、ミルク(の体積が)が広がる
って考えるとわかる?
もうひとつ、理想気体の話(気体の状態方程式)だけど、
PV = nRT
P : 圧力
V : 体積
n : 分子量
R : 気体定数
T : 温度
断熱膨張の時に考えてて、一日迷宮入りしたんですよ。
式の数値を全部1に簡略化して考えるよ。
断熱膨張って注射器をギューンって引く
(問題としては体積を大きくさせる)
その時、仮にVが1 から 2になったとする。
そもそも、注射器をギューンって引くんだから、
Vが2になっても、Pは1/2になって相殺されるから、温度変わらないよね。
迷宮1(伝わる?)
ChatGPTがいうには、「注射器を引いても圧力は変わらない」というわけ。
OK。じゃあ、
P x 2V になるよ。そうするとね、反対側のnRTの中で変数はTだけだ。
P x 2V = n R 2T
これだと…温度上がることにならない?迷宮2
勘違いしていたこと
問題はそうじゃないってことに気づくのに2日かかった。
問題をよく読むとね、”体積だけ大きくさせたとき”なんだよね。
だから、注射器を引いたことによる変化は無視して、
仮にP x 2V = n R T で成立している状況を想定してほしいんだということ。
そうすると、同じ分子量で純粋に体積が大きくなると
熱エネルギー、衝突エネルギー的に温度が低下する。
そのうえでP x 2V = n R T↓
温度がさがるから設定上のVは固定されているとすると、Pが下がる。
という理屈だ。
つまり、
”(理想的に)体積だけ大きくさせる”ことが目的だったということ。
この実験により学びたいことは、
気体の状態方程式ではなく、熱エネルギーとして、同一分子量、同一圧力下で体積を理想的に拡張した場合、温度が下がる。
体積と温度の関係を学ぶ中で、
シャルルの法則(同一圧力下で温度と体積は比例する)から考えると、
温度を上げる→分子の運動エネルギーを増やす
箱に閉じ込めておくと、体積が大きくできないから圧力が高まる(ヤカンの水蒸気)
逆に体積を大きくさせる(箱を柔軟にする)、圧力が一定に保たれる。
どの条件を固定して、何を変数とするか。
決して矛盾はない。
温度って何かね?
AとBは”同じ温度”って簡単に言うけど、言い方を変えると
「物体同士の体積当たりに働く分子の運動の大きさが同じ」ということ。
よって、体積だけを変化させると、温度が変わるのがわかるね。
上空に行くと水蒸気を含んだ空気の温度が冷え、雲が出来る
というのを実験で再現するために、無理やりやってるってこと。
温度って何か?分子の衝突だぜ!ってのを省略して説明しようとすると想像しにくい。
箱の中ではない(体積が固定されていない環境)、大気中
気圧が下がった環境で固定(圧力固定)されている、
その環境では体積は大きくなる、
水蒸気を含んだ空気の温度が下がる
雲が出来る。
大事だからもう一回いうね。
温度が同じとは、物体同士の体積当たりに働く分子の運動の大きさが同じ
体積だけ大きくしたときに、分子の運動エネルギーは与えられないから、温度は下がるんだよって話。
圧力を一定にしたときに、温度を上げると体積が大きくなる。
圧力の一定を想像しにくい部分があるが、
膨らむ風船を力で抑え込まない、一定の力で支えると、どんどん風船は大きくなるよね。
温度を上げて、体積を一定にしようとすると、抑え込む力(圧力)が必要になる。
そういう関係を学ぶのが断熱膨張の実験なんだと思います。
闇雲に覚えると応用が利かない。なるべく原理をイメージ出来ておくとどんな問題でも答えられる、そんな気がする。
あぁ、これもあんまり読まれなさそうだなぁ(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
