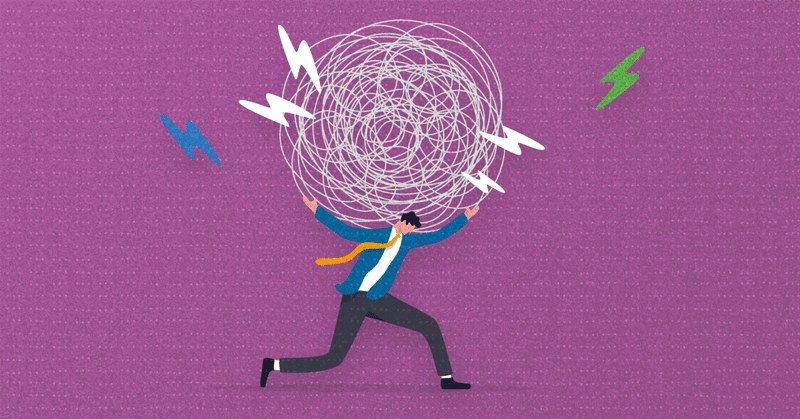
「課題」とはどうやって見つけるのか?
今日も今日とて、
現職で行っている研修の中で、改めてまとめておきたいことのメモを記事に仕立てていきます。
内容は「事業計画がタスクに落とし込まれるまでのプロセス」の作成です。
ただね、そう書くと難しい(だからタイトルにはしなかった)ですが、
皆さんも何か大きな目標に対して、計画を立て、何かしら課題を設けて取り組むことがあるかと思います。特に人と関わり合いながら進めていく場合のヒントになると思います。
さて、皆さんは「問題」と「課題」の違いは分かりますか?
もしくは、これらの言葉を使い分けていますか?
答えられなかった人、使い分けていないって人は
コチラをもう一度読んでおくとよいと思います。
以前に書いた話をもう一度書くなんて…。
今回は問題から課題の設定方法について、そしてその過程の意味についての記事になります。
今回は副部長Bさんの部下cさんとの仕事内容がベースとなっています。
cさんは僕と同じく法則型で、上司からの指示が不十分で困ることが多かった人です。
今回、法則型の人が思っていること、理解の仕方についても参考になるかもしれません。
多くの人は説明しないんじゃない、説明できるほど整理できていないだけなんだ!
結論ではなく、理由から話をしていきます。
指令型の上司と法則型の部下の関係ではしばしば起こりますが、
上司からの一方的な指示に対し、部下が行う理由について説明を求めたり反抗したりすることがあります。
説明を求めているだけなのに、「反抗している」と捉えてしまう(上司が一方的に解釈するもの)のも問題なのですが、それは互いに本能のタイプを知ることである程度回避することが出来ます。実際に、副部長Bさんや、その上司の部長から、タイプの説明を聴くことで、冷静になることが出来たという声を聴いています。
余談ですが、僕は最初、「上意下達(じょういかたつ)」という言葉を「一方的な指示」の言葉として使おうとしたのですが、意味を調べてみると違っていたので勉強になりました。
「上意」は、主君の命令や意思のこと。「下達」は、下の者に伝えることで、「げだつ」と読むのは誤り。
もちろん、法則型の部下に対してだけではなく、どの部下に対しても説明が必要です。ただ、その説明が対する相手によっては難しいということがあります。つまり、同じ説明をしても理解を得られる人と、得られない人がいるということです。
指示と同時に課題の説明をする必要がある
言い方は難しいのですが、
部下の人にやってもらいたいことは、事業の中の課題であるはずです。
課題じゃないものをやらせるというのは意味不明です。
「理想」と「現実」の間にあるものが「問題」
その「問題」を解決するために行うものが「課題」
何かの仕事(課題)を与えても、会社のなんの為にもならないことはする意味が有りませんよね。
法則型が気になっているのは、目の前に与えられた指示がどうつながっているのか?
「指示」→「課題」→「問題」→「理想」
つまり、目の前の指示に従うことでどんな未来になるのかを予想したいはずです。法則型はその未来予測を置いから仕事を行うと心地よいと感じます。極端に、「その仕事しても意味がない」ことを嫌う、とも言えます。
無駄なことを本当にしたくない。みんなそうだと思うんですが、あなた(法則型以外の人)が思っている以上に強く思っているのが法則型です。
他のタイプの人であれば、恐らく「事業として取り組むべき課題」までの説明が出来れば、仕事は進めやすいと思うはずです。法則型はちょっとそのあたり、めんどくさいです。
ただ、今回のcさんの場合は、
とにかく「指示」しか受けていませんでした。
続いて、僕がcさんにお願いした仕事を紹介します。
今から作成に取り掛かるものは、本来あなたの上司が上流の工程(事業企画部とかそういうところ)から受け取るもの
まだ、小さな会社ですから、事業企画とか、要は事業計画から実行に至る部分の落とし込みをする部署がないわけです。本来は、あなたの上司やその上の上司が考えるのがスジですが、できないものは仕方がない。
なので、あなたの上司が説明できないで困っていた根本を、これからあなたが作ります。
そういって私は表の穴埋を依頼しました。

社内で検索できる情報から、埋めてみてください。現状の部分は証拠(エビデンス)もつけてください。理想はcさんの理想で結構です。
作成の際、表にすることが大事です。
縦と横で属性やスケール感の違うことを書くと浮いて見えるようになります。見やすくなることで、同じカテゴライズできたり、まったく同じことだったり、ラジバンダリが見えるようになります。
いけ好かないビジネスマンが「MECE(ミーシー)になってない」なんて言ったり言わなかったりするんですが、
MECE は、Mutually Exclusive Collectively Exhaustive の略で、「重複と漏れがない」という意味合いのビジネス用語です。
「漏れなくダブりなく」することが大事です。
別な例としては、「状態」なのに「行動」を書いているなんてこともあったりします。
状態と行動は英語で言うとBeingとDoingです。
全然違うので、揃っていないと気持ち悪いです。
その気持ち悪さに気づくための表です。
問題→課題 と 課題→問題 双方向で通じるストーリーを描け!
いろいろとサポートしながら埋めていき、
さて、課題を埋めようとすると、途端に手が止まることがある。
課題として設定したことが、複数に重なることもある。
そんな単純な構造じゃないんよ。
簡単なら困らないし、上司も答えられる。
そんな時は左から右に、右から左に
双方向に意味が通じるストーリーを描くとよい。
〇〇という理想に対して現状は△△だ(問題)、それを解決するためにこの●●という課題に取り組む!
課題である●●を行うことで、△△が解消され、〇〇という理想に近づく!
課題として設定したものが、どうしても超細かくなりすぎることがあります。設定した理想や問題とのスケール感と合わない課題を設定してしまうと、双方向にストーリーが形成されません。
取り組む課題の優先順位を決めろ!
表が埋まってくると、次は優先順位を決めて終わりです。
優先順位の決め方はいろいろあると思いますが、一つのことで複数の問題に触れるものや、難易度など考慮するものは多数あります。
ここでは細かく優先順位の決め方は触れませんが、
事業としての現状、問題、課題を整理するというのはこれまでのプロセスを言います。
そこまで来て初めて、cさんへの「指示」になります。
法則型はそのタスクの位置づけを知ることで満足して仕事に当たるでしょう。
最後に忘れてはいけない「納期と達成基準(プラン)」を設定して、事前準備は終わりです。あとはタスクマネジメントを行いながら進めていくという感じです。
大きな会社では、プロセスまでは見えないが、
事業としての優先順位などが指示される際、このあたりことが考慮されているはずです。事業部としての優先事項や、課題が伝えられ、それを達成する計画を立て始めるはずです。
まとめ
今回、「課題の設定」であったり、「タスクに落とし込まれるまでのプロセス」を紹介しました。まとめると、
説明できないのではなく、説明できるほど整理ができていない!
部下には課題とそのストーリーを共有せよ!
問題と課題は、双方向で通じるストーリーを描け!
全ての仕事・タスクには
何らかの意味があって、メリットをもたらし、デメリットを解消する、そんな事業や組織の重要な部分であるはず。
「自分が時間を費やしている事」が所属する組織のどんな役に立っているのかを知ることは、「そんなこと」で済む話でしょうか?
これを読んでいる「あなた」はどんな立場かわかりませんが、
目の前の仕事は、組織のどんなことに役に立っているのか理解されていますか?もちろん、上に確認しても出てこない!なんてこともあるでしょう。
だったら作ればいいじゃない!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
