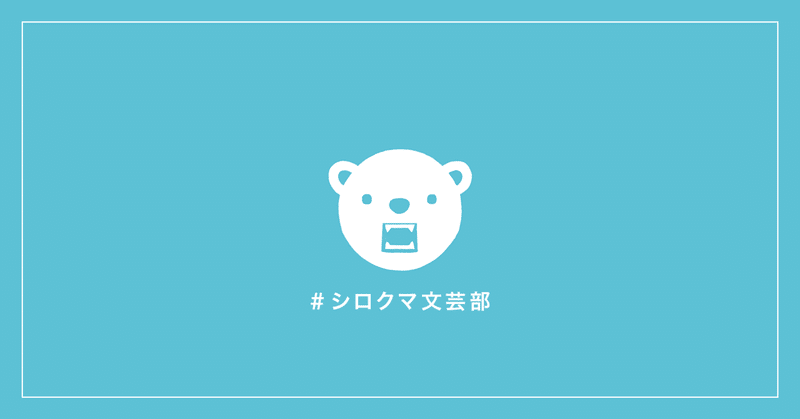
♯2 天女の帰還 【シロクマ文芸部】
愛は去ぬ。
満月が隠されて闇夜が虚しく横たわるのみ。
「朕はどうすればよいのだ・・・」
帝の嘆きは深く、その容色は光を失ったように儚げなのでした。
幼い頃から近しい人々を奸計で失い、時の朝廷に逆らうことなく身を処してきた帝は、人を愛することはあるまい、と心を閉ざして生きてこられました。
所詮、尊くも賤しくも、女は子を産ませる道具にすぎないのだと己に言い聞かせ、固く蓋をした心をいとも簡単に解き放ったのは、かの人であったのです。
矜持の高さが並々ならぬ美しい姫。
厳重な後宮の警備を物ともせず、まるで雨の雫のように月の光を纏い、眼の前に降り立ちました。
その瞬間を忘れることなどできましょうか。
「たれじゃ?物の怪か?」
彼女は愉快そうに薄く笑いました。
「お主上がわたくしを召されたのでしょう?」
光輝くように美しい。
「なるほど。そなたがかぐや姫か」
「あい」
姫はふわりと地に足を着きました。
「わたくしはこの地上の者ではございません。いずれ天上からの迎えを待つ身でございますれば、たれとも縁を結びませんでした」
「それでは何故そなたはこの地上に来たのじゃ?」
「さて」
本当にわからぬというように姫が首を捻るのが可愛らしく、帝は心の底から大きな声で笑われました。
目の端からは涙が滲む。
「かぐや姫よ、そなたに礼を言う。久しく笑うとことなど忘れておったわ。爽快じゃのう。朕を笑わせるために現れたのではあるまいか?」
「妾がお主上ごときを笑わせるために地上に落とされたと?」
「そう、ツンケンするな」
姫が口を噤む樣も美しいが、この人が笑えばさぞかし花がほころぶほどに麗しかろうと帝は思し召しました。
「そなた、情を理解できぬようだな。だからこのようなつまらぬ地上に落とされたのではあるまいか?」
冗談とも、笑みを含んだ言葉は姫の心を抉り、刹那に前の世の記憶が甦る。
姫を巡って争いが起こり、多くの者が命を落としました。
姫はそれを可哀想とも感じませんでした。みなこの美しさだけに惹かれて姫を見ようとはしない、そんな者達が死んでもその辺の虫が死ぬのと同じこと。
情のない女と罵られても、何も感じなかったのです。
「それでも赦される時が来れば、わたくしは去らなければなりませぬ。これ以上の縁は結びたくはございません」
「なるほど、非情な女かと思えば、かわいらしいところもあるのだな」
帝がくすりと笑う姿は美しく、姫は頭に血がのぼるように頬を染めました。
「別れがあるからほだしを作らぬ、とは情の深い証よ」
姫はこの言葉に鎧を剥がされたような不思議な気持ちになりました。
今別れたくなく思うのは、養い親の翁と媼。
それだけでも別れに耐えられるはずがない。
「それでも頑な姫じゃな。しばし朕の傍にて人というもの、情を学ばれよ。さすれば尊い天女がこの地に降りた理由もわかるやもしれぬぞ」
その言葉に抗うこともできず、姫はここに留まることとなったのです。
それから帝は公務の合間を縫っては姫に会いに訪れました。
「お主上、明け方にお別れしたばかりではございませぬか」
そう照れてかぐや姫が顔を隠した扇をいとも簡単に奪ってしまわれる。
「今更恥ずかしがる仲ではあるまいよ」
「嗜みでございますわ。お返しくださいまし」
帝は側の硯を引き寄せると、さらさらと愛の歌を取り上げた扇に綴りました。
「さて、姫のお返事は?」
このようにあからさまな寵愛は気恥ずかしく、
「天人は歌は詠みませぬ」
そうして姫は一筋の光となって消えてしまいました。
「よい、よい。歌なぞ詠まずとも。赦してつかわす」
帝が笑うと、姫は元ある場所に姿を現したのです。
帝の御姿は稀なる美しさ。
それに並ぶかぐや姫は天女らしく神々しい、まさに似合いの一対でした。
二人は深く愛し合うも、生まれた宿命が異なれば添うことはできないのが定め。
天上からの迎えが来た満月を二人がどれほど憎く、せつなく眺めたことでしょう。
屈強な武人が強弓で阻もうとしても、放たれた矢はなよなよと行く方を失い天人の行列を留めることをできませんでした。
天人に促されるまま、かぐや姫が差し出された薬を舐めると、
「姫さま、これで地上の穢れは祓われました。おめでとうございます」
恭しく膝を折る天人を姫は悲しく見つめられる。
そうしてその薬壺を帝に手渡されました。
「お主上、わたくしはこの地上にて与えられた物をすべて置いてゆかなければなりません。この不死の薬だけが今のわたくしの持ち物でございます。せめてこれをお主上にさしあげとうございます」
「あなたが私を忘れないでいてくれるならば、それでよい」
帝が不死の薬を返そうとすると、姫は透き通った涙を流されました。
「わたくしはあの羽衣を纏えばすべてを忘れてしまうのです」
「なんと・・・」
「どうかこの薬で永らえてくださいまし。そしてたまにはわたくしのことを思い出してくだされば、これほどうれしいことはございません」
そう言い終わるや否や、天人はかぐや姫に羽衣を着せ掛けてしまいました。姫の瞳はまるで知らぬ人を見るように変わり、静々と車に乗り込みました。
行列が天に上り、月に還るのを、視界が涙に塞がれて見ることはできまい。
帝は漆黒に包まれた中で、側近の僧に問いました。
「願い続ければいつの世か、姫とまた巡り会うこともあろうか」
「あるいは、御仏の慈悲があるやもしれませぬ」
「そうか」
それならば人としての生を全うしよう、と帝は不死の薬の壺を地に叩きつけました。
なんとも尊い幻の天薬を、と周りの者たちは騒ぎましたが、大気に触れると薬は溶けて消えてしまいました。
その形を崩した薬壺は神物として、倭の国一番の霊山に収められ、それが富士(=不死)の山と呼ばれるようになったのは、みなさまも知る通りでございましょう。
やはり源氏物語を書く私が挑戦するならば、このお題はピッタリですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
