『百年の孤独』と、始まる前に終わった恋
*このコンテンツは無料です。
『どうせなら、楽しく生きよう』の刊行を記念して書いたエッセイです。

私ほどたくさん失恋をしている人はいないのではないかと思いますが、そのなかでも26歳のときの失恋は最悪のものでした。
結婚の約束をしていた人と期限付きの長距離恋愛をしていたのですが、その待ち時間がようやく終わり、仕事をやめて異国に引っ越してきたその翌日に「母が猛反対するから無理」と別れを持ちだされてしまったのです。
異国で無職でホームレスになった私は、プライドだけを武器に学校に行きなおすことにしました。当分恋なんかしないつもりでいました。ところが、学校のランチの時間に毎日優しく声をかけてくる男性がいたのです。
彼はヘンリー・ミラーの『北回帰線』(Tropic Of Cancer、下記は1965年版で彼が持っていたのはたぶん古本のこれ)を読んでいました。親身になって話を聞いてくれる彼はふだん私が惹かれるタイプではなかったのですが、孤独が怖くて付き合うようになりました。ところが、彼は心理的DV(ドメスティック・バイオレンス)アビューザーだったのです。新しい人生をやり直すつもりで気丈にしているつもりだったのですが、心が弱くなっているときには捕食動物にとって「美味しい」匂いが漂っていたようです。
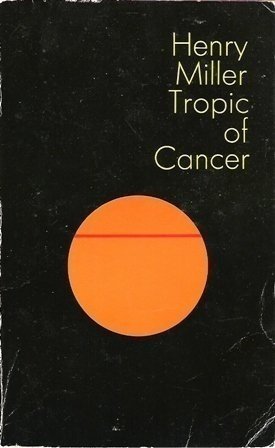
「おまえはダメな奴だ。前の彼氏に捨てられたのもしかたないな。がまんしてやるのは僕くらいのものだ」と言われても、私はヘラヘラ笑っていました。友だちの前でも平気で「おまえは本当にどうしようもない馬鹿だな」ということを平気で言うので、親しくしていた友だちは「付き合うの、やめたほうがいいよ」と忠告してくれたのですが、「口は悪いけれど良い人なのよ。私のことを思って言ってくれている」とかばったりしていたのです。私のほうも典型的なDV被害者の振る舞いをしていたわけです。
彼との別れのきっかけは、できそこないの恋愛小説のように、彼が二股をかけていた場面に無邪気に「たらら〜ん」と入場してしまったからでした。「君の心を傷つけないように気遣っていたのに、君はそれを責めて僕の心を傷つけた」となじられて、別れになりました。午前6時に泣きながら親友の英国人女性に「捨てられちゃった」電話をかけたところ「あら、良かったわね!あちらから別れてくれるなんて素晴らしい出来事だわ!おめでとう」と明るく言われてしまいました。
「しばらくは孤独でいよう」と(またしても)決意したときに声をかけてきたのは、同じコースに通っていた英国人男性でした。すでに社会人だった彼はとても紳士的で洗練されていて、いかにも英国の有名私立男子校出身という感じです。5ヶ国語ペラペラで、デートの場所は今最も話題の映画や最も人気があるバーです。そのデートがまた、英国の歴史小説に出てくるような「Courtship」という感じの慎ましさです。ジェイン・オースティンの小説が大好きな私は、すっかりそれに魅了されてしまいました。
この彼が私に薦めたのが、ガブリエル・ガルシア=マルケスの長編小説『百年の孤独』(下記のバージョンの英語版)でした。原書のスペイン語でなかっただけましですが、英語の本を読み慣れていない者がいきなり読んでわかるような小説ではありません。それでも私はせいいっぱい背伸びして読みました。
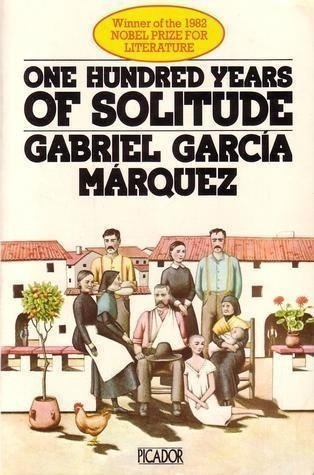
でも、彼とのデートはいつまでたっても本当にリージェンシーかビクトリア時代のcourtshipなのです。午後11時くらいになるとソワソワして「そろそろ駅まで送っていきましょう」と言いだします。まるであっちのほうがシンデレラです。私に興味がないならそれでもいいのですが、私のほうからは一度も誘わないのに、毎週2度几帳面にデートに誘ってきます。非常に不可解なので、英国人とイタリア人の女友だちに「どう思う?」と相談してみました。
すると、彼女たちは口をそろえて「彼はゲイよ」と言います。当時の英国ではまだ同性愛者に対する厳しい法律があったので、「僕はそうではないよ」というアピールをするために使われているのだろうと言うのです。「ルームメイトが病気なので、早めに戻ってあげないと」という「ルームメイト」は「恋人」なのだと彼女たちは断言します。
そう言われてみると、思い当たることはたくさんありました。
トレンディなバーで素敵な男性がフランス語で話しかけてきて彼が流暢なフランス語で返し、そのまま談笑が長引くこともありましたし、ともかくおしゃれなのです。
ある日私は思い切って彼に訊ねてみました。彼は真っ赤になって否定するのですが、その否定の仕方がますます怪しいのです。そこで「別に私は気にしないけれど」と言ったところ、なんだかほっとしたようでした。そして、その後は定期的なデートのお誘いが消えて、ただの友だちになりました。
その数カ月後に日本でアメリカ人の現在の夫に出会ったのですが、彼が読んでいたのは、トム・クランシーの『レッド・オクトーバーを追え!』(The Hunt for Red October、下記は1985年刊行のバージョン)やロバート・ラドラムの『暗殺者』(The Bourne Identity)といったスリラーでした。
それを知って、私はなんとなくほっとしたのでした。
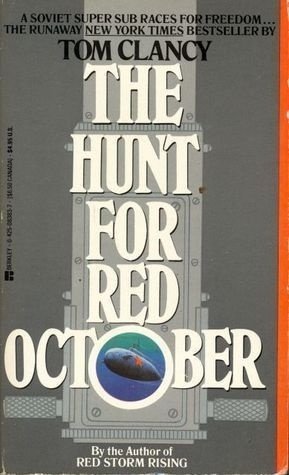
*** *** ***
『どうせなら、楽しく生きよう』(飛鳥新社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
