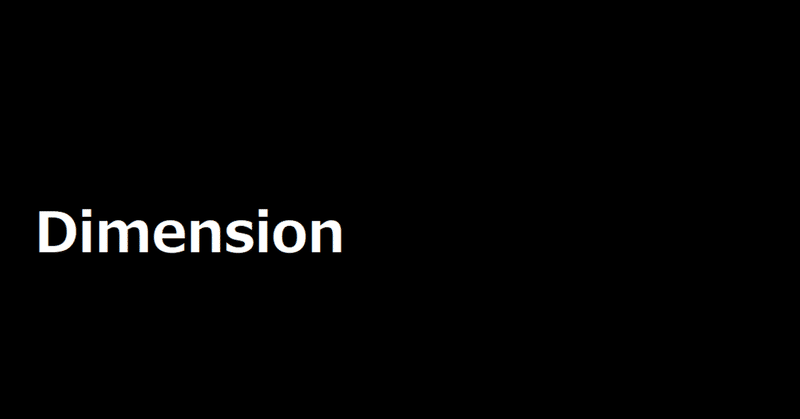
Dimension -ジン- 終
「姫様!!」
刹那、奴ら三人の内の一人からそんな言葉が発せられたのは耳にしたが、俺がその言葉をちゃんと認識した時には既に、俺は姫様に抱き締められていた。一瞬何が起こったのかはわからなかった。華奢な体にも関わらず、俺の胴回りにしがみ付いた姫様はとても強い力で、俺は動きを止められていた。姫様は戦場で、しかも今まさに刀を振り降ろそうとしている俺の所に、危険も顧みず飛び込んできていた。その思わぬ出来事と温かさに思考が止まる。
「姫・・様・・・?」
俺の体から力が抜けるなり、姫様は起き上がると俺の首に腕を回し、俺の事を抱き締め直す。
「姫様っ!何をなさっているんですか!」
押し退けようとすると、姫様は腕にさらに力を込めて、抱き締める。
「これまで、一人でいっぱい頑張ってきたんだね。ここまで来るために、たくさんの物を背負い続けてきたんだ。どんな時も、我慢して耐えて頑張って、そうしてこんなにも強くなったんだね。あんなにいつも傍にいてくれたのに、気付いてなくてごめんね。」
姫様は、まるで母親のように俺に言葉をかける。柔らかい響きに、俺の力が抜けるにつれて、姫様の力も優しくなっていく。様子の異様さに誰も言葉を発さず、辺りはとても静かで、そのせいか姫様の言葉がとてもはっきりと一言一言が耳に入ってくる。
「ジン達が言う通り、ここは戦場であなた達は戦士。だから、あなた達が命懸けで戦い合う事を、怖いけど、勿論否定したりなんかしない。あなた達の矜持を尊重して、ちゃんと見届けるつもりだった。でも、今のジンの姿を見てると、その先の未来を見るのが怖い。」
姫様の手が少しだけ強く俺の肩を抱く。
「ジン。あなたは、たった一人なんかじゃない。少なくとも私は絶対にいる。いつまでも絶対に忘れない。ジンの事も、そしてリクの事も。」
脳の辺りが熱くなるのを感じる。体が小刻みに震えている。これは、姫様に抱き締めて頂き、さらに優しいお言葉をかけて頂いている畏れ多さからくるものだろうか、それとも、喜びだろうか。
俺の目の前が一気に滲んでいく。
「リクはこの世界にちゃんと生きてた。ジンと共に生きてた。そして、戦場で使命に対して一心に生きた。私は一生そのことを忘れないよ。」
俺は声を上げて泣いていた。
リクは俺の親友だった。同じ村で生まれ育った俺達は、子供の頃から常に一緒だった。同じ飯を食い、日が落ちるまで遊び回り、ある程度の年齢になるとちょっとした悪さを覚えたり、多くの思い出を共有してきた。
そして、そんな俺達は大好きな故郷や家族に対する想いも同じだった。働ける年齢になった頃、俺達は同じ目標を持った。それは「大きな国で仕官して、家族に楽をさせてやること」だった。昔多少の悪さをしていたこともあり、腕っぷしにも多少自信があったから俺達は迷うことなくその道を選んだ。その後、すぐに仕官先は決まり、俺達は兵士として召し抱えられた。
この地域には、時折「姫」が現れる。それは最も神聖と言われている「神寄りの森」にて何千年も祀られている御神木の大きな根と根の間に建てられた祠の前に突如現れる女性で、この地域一帯では、その現れた女性を「姫」と呼び、その姫がいる国は安泰すると言われ、国に連れ帰ると丁重にもてなし、保護するのだ。
しかし、「どの国が連れ帰るのか」という掟は無い。その為、どの国も定期的に森の御神木を参拝し、いつかもわからない姫様が現れるのを待つ。そして最初に姫様と対面した国は、あらかじめ用意していた馬に乗せ、姫様を自国に連れ帰る。しかし、掟が無い為に、そんな簡単に他の国が諦めたりはしない。各国による姫様の略奪・奪還の争いや、それを根底に置いた各国の緊張感が絶えず発生している。だから、俺達の様な奴らの仕官先はいくらでもあった。そして俺達は仕官され、訓練期間が終わるとすぐに出兵が決まった。
三年前、「神寄りの森に姫様が現れる」というお告げを、各国が召し抱えている予言者から受けてすぐさま遣いを出した。しかし、偶然その時参拝していたある国が、姫様を既に連れ帰っていて、他の国はどの国も無駄骨となった。そこから各国は密偵を世界中に差し向け、情報戦からの略奪作戦が始まった。俺の国も例に漏れずその流れに乗り、ついに姫様の略奪に成功した。しかし、やはり戦はそれだけでは終わらず、奪われた国が奪還に動き出した。そしてその国が差し向けた戦士が、あの三人だった。奇しくも、三年前も今と同じ構図となっていたのだ。
俺はリクと共に第一迎撃団に配属されていた。初めて聞く緊急警報の音、慌ただしく巻き起こる周囲の光景に緊張しつつも、初仕事に気合を入れ直しながら装具の帯を締め直していた。リクも緊張しているようだったが、ふと俺の視線に気付くと気合の入った目で俺に笑顔を見せた。俺達は互いに笑い合って互いを鼓舞した。
隊列を組むと、騎馬隊の後を追って俺達は城から出た。何万という兵士の後方にいた俺とリクはただただ前の兵士の頭を見ながら走り続けていた。心臓の鼓動は進むほどに強く打ち、それによって研ぎ澄まされた皮膚感覚は、風の冷たさをより強く感じさせた。
「全体止まれぇぇー!!!」
前の方から指示が聞こえ、俺達は指示に従った。おそらく敵と遭遇したのだろうが、後方過ぎる俺達の所からは何も見えなかった。ただ、前の騎馬隊の兵士の退避勧告の声だけが聞こえていた。不思議なもので、まだ遭遇もしていない移動中はあれだけ緊張をしていたにも関わらず、実際に対峙すると自分の中から現実味は無くなり、退避勧告の後、あっさり引き返すことになるんじゃないかという風な感覚に陥った。
「総員、かかれぇー!!!!」
退避勧告から多少の間の後、急な怒号と共に、前から無数の唸り声が起こり始めた。前方に見えるたくさんの兵士の頭が波のようにうねりを起こし、と同時に荒波のように、四方八方に激しく行き交い出す。「始まったんだ!」そう思い、息を飲み直したのも束の間、荒波の様に行き交う兵士達の頭の波が、大波になって俺達のいる後方に向かってきた。間から数名の兵士が打ち上げられる光景が本当の波しぶきのように、後退する兵士達の流れがすごい勢いで押し寄せて来た。そんな波の中央に、一人の男が見えた。男はまるでチャンバラごっこで遊んでいるかのように楽しそうに周囲の兵士達を次から次へと斬り伏せていた。それも大人が子供たちと遊んでやっているかのように、半分片手間で兵士達の攻撃を捌いていた。というのも、その男は同じくその戦場の渦中にいる別の仲間と話しながら戦っていたのだ。仲間たちもその男と同様まるで子供の遊び相手をするかのように軽々と兵士達を捌いていた。
「ショウ!あんまり派手に暴れるなよ!逆上させたら、人数が増えて、無駄な労力が増えるだけなんだから!」
「そうだぞ!お前はもうちょっと加減っていうのを覚えた方がいい!」
「お前もだ、リュウ!」
その光景に困惑していると、俺は兵士達の流れに飲み込まれ、足を取られて倒れ込んでしまった。急いで顔を上げ、敵の男の方へ目を走らせると、斬り抜けた男の行く手の兵士達の中にリクが居た。完全に間合いに入っている。あまりの男の速さに驚きながらも、他の兵士達と同じく、リクはすぐに切り替え、柄を強く握り込むと男に斬りかかった。しかし、男はリクの刀を跳ね上げると、素早く胴斬りでリクの脇腹を斬り伏せていた。一瞬の出来事だった。流れるような速度と身のこなしで、次の瞬間には男はもう別の兵士達を斬り伏せていた。
俺は呆然と、倒れているリクを見ていた。不思議な感覚だった。急に目の前の光景に、現実味を感じられなくなっていた。幼い時からほんのついさっきまでずっと家族のように、そこに存在していることが自然の摂理であるかのように感じていたリクが、少し遠い存在になったような感覚になった。それと同時に頭が急激に熱くなっていくのを感じた。体がどうしようもなく震え、歯が打ち合ってカタカタと音を立てていた。そのまま放っておくと自分自身が爆ぜて崩れていくような気がして必死に歯を食いしばると、俺はリクを斬った男の方へ目をやっていた。そして立ち上がる。しかしどうしても足が覚束ない。いつも通りの力加減で動いているはずなのに、駆ける足が意識とうまく噛み合わない。脳が足が着くと思ったタイミングなのに、足自体はまだ着地をしていなくて、地面が急にグニャグニャと柔らかい布団に変わってしまったようにうまく進まない。視界もやたらとぐるぐると景色が動いていて、より一層進むのが困難になる。しかし、なんとか動く視界の中の男の姿だけに目を凝らすと、
「ぐぅあぁぁぁー!!!!」
唸り声と共に俺は刀を抜き、男に向かって行った。しかし、男に到達する寸前、男が大きく斬り払って吹っ飛ばした兵士達が俺の方に飛んできた。俺はその兵士達に巻き込まれると、兵士達の重みと倒れた時に強く打ち付けた頭の衝撃で、俺は意識を失ってしまった。
目を覚ますと、俺は上に覆いかぶさっている兵士の死体をどかして体を起こした。辺りは風の音だけが響き渡り、動くものは無く、ただ死体の山だけが広がっていた。戦闘中の足音や怒号といったさっきまでの喧騒が嘘のように、周囲は静かだった。その落差に呆然としていた俺の脳が徐々に現状を把握し始めた。
「・・リク!!」
俺は周囲を見回し、まだ完全には覚醒していない頭の中の微かな記憶を頼りに、リクを最後に見た方向へ駆け出した。同じ装束を付けたたくさんの血だらけの死体の中、リクは仰向けに横たわっていた。脇腹から血を流し、口元にも血が赤黒く滲んだ状態で、虚ろに目は開き、まるで視線の先に広がる空の青さを眩しがっているようだった。俺はリクの傍に近づくと跪き、リクを抱き上げた。声も涙も出なかった。ただ息苦しそうに見えたから、甲冑を外してやり、開いたままの瞼を閉じてやった。
「どうしてこうなったのか」
俺はまだぼんやりとしている頭の中で穴を掘るように、戦闘が始まってからの景色、リクの最後の瞬間を思い出していった。
圧倒的な強さで俺達四万五千という数の兵士達を次から次へと倒していく三人の男達。阿鼻叫喚や怒号、砂埃が巻き起こる中、右往左往する兵士達。そんな中で突如として目の前に躍り出て来た敵に対して、怯み、強張ることなく、瞬時に頭を回転させ、勇気を振り絞り、リクは刀を打ち込んだ。そして————。
男は、リクが打ち込んだ刀を跳ね上げると、いとも簡単にリクの脇腹を捉え、斬り払った。
会話をしながら。
記憶が連なり、明確に蘇ってきた。そう、その時男は仲間と会話をしていた。多勢に無勢の戦闘中でありながら、男は意識の大半を仲間との会話の方へ傾け、攻撃を受け、兵士を斬り払う際に顔は向けるものの、その相手個人については全く意識を向けていなかった。本当に子守をしているかのようだった。
そして、リクを斬る時男が口にしていた言葉。
「パパっと片付けちゃった方が楽じゃん!」
男が仲間との会話の中で発した一言。その言葉が発されたと同時に、リクは地面に崩れ落ちていた。
子供の頃から同じ村で育ち、泣き、笑い、たくさんの思い出を共有してきたリク。そのリクの命は、「楽」という言葉で簡単に斬り払われ、捨て去られて良いような代物なのだろうか?
たくさんの事を経験して大人になり、そして故郷の村の家族の事を考えて将来を決め、人生を精一杯生きて来たリクの最期は、目の端にすらも留められることはなかった。
リクがこの世に存在したという証自体が乱雑に丸めて捨てられてしまったような気がした。
冷たい風が吹く静かな荒野の中で、頬だけが熱かった。
俺は泣いていた。
地上の光景とはまるで別世界な真っ青な空を見上げながら、
俺は声を上げて泣いていた。
今、俺の体を温かいものが包んでいる。姫様はリクの事を覚えていてくれると言った。リクがこの世に存在していたことを認めてくれた。
姫様はリクに会ったことはない。でもだからこそ、身内ではない姫様が認めてくれたことは、世の中にちゃんとリクの存在が認めてもらえた瞬間のように感じた。俺は、時間が経っていくほどに、記憶が薄れ、リクが消えてなくなってしまうような錯覚に陥ていたのかもしれない。そして、奴らを斬ることがリクの存在を証明する手段だと思っていたのかもしれない。
俺は泣いている。
戦場には似つかわしくない、大きな優しさに包まれながら、
俺は声を上げて泣いている。
(終)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
