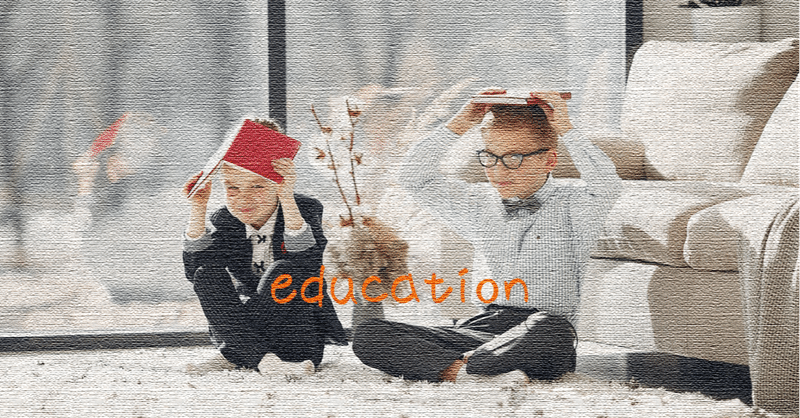
読書記録: 「麹町中学校の型破り校長 非常識な教え」(工藤勇一)
ジャンル:教育
お勧め度 ★★★★★ (5つ星)
以前から読んでみたかった工藤さんの著書。上記のタイトルが、Kindle Unlimited に入っていたので、早速読んでみました。
感想:共感度大。私が学んできた常に上位目的を考える「バリューエンジニアリング」の手法にも通ずる。「自律した社員」を育てたい会社の管理職の方にも学べる点があるのではないかと思う。以下、簡単に要点や感想をまとめてみた。
① 麹町中学校の最上位の目標は、「自律した子ども」(人のせいにしない子ども) を最上位の目標におき、そこから「人間はみんな違うし、対立が起きるのは当たり前である」「違いをのりこえるためにどうしたらいいか」を教えているという。
②では、いかに「自律した子ども」を育てていくか。やらされ感を持っていては、子供が自主的に学ぶことはできない。一律の与えられた宿題では、やらされ感がでるのは当たり前と思う。「「学び」は分からなかったことが分かるようになったとき、できなかったことができるようになったときにはじめて成立する。」という。そこで生まれた方針は、(1)「わかっていることはやらなくていい」(2) わからない箇所があったら、ひとつでも2つでのいいので、分かるようにする。この分からないことを分かるようにすることが、勉強であり、子供たちは、この点にフォーカスすることで、分かるようになるために何かをしなければならないということに自ら気づく、という。詳細は省くが、「再チャレンジが可能なテスト」(自己申告でもう一度受けられ、後の点が採用される)の導入は素晴らしい発想と思う。自ら気づいた子供たちがいかにして「自分に合った学び方を見つけるか」が重要で、その学び方は社会に出た後も一生使えるスキルになっていく。AIの導入により学びが効率化された事例も、今後の教育に重要な示唆を与えるものだと思う。
③「自律した子ども」を育てるために、できるだけ自由にさせたいが、絶対に守らなければならないルールは決めている。(1) 命に関わるような危険なことをしない」(2) 人権に反することはしない (犯罪・差別・いやがらせ・無視)ルールにおいては、メリハリをつけることがとても重要。
また、「心の教育」の問題点に触れている箇所も面白い。「良い行い」をしてもそこに「良い心」がなかったら、それは「偽善」になってしまう、という考え方。心のコントロールが非常に難しいことは、冷静に自分の内面を見つめてみれば明らかである、「心」は一旦脇に置き、「行動」で実践する、電車でお年寄りが目に入ったら、何も考えずに、席を譲る、という習慣づけをしたいものだ。「言葉と行動を変えようと繰り返し意識し続けていると、自分そのものが変わっていく」ということらしい。
④協調性を捨てる。「異なる意見者立場をいったんOKと受け止めた上で、相手との対立を無駄に激化させないように言葉を選び、働きかけていく。」社会に出てもとても重要なスキルである。自主運営をしている体育際において、「みんな違っていい」「一人一人を大切にする」を両立するために、生徒間で対話を進め、走りたくない人が1割いるリレーを止めて、運動が苦手でもできる競技に置き換えた、という話はとても面白かった。
⑤自立をはぐくむためには、「待つ」こと。つい手出しをしてしまうことが、自らの気づきを妨げてしまうことになります。
その他にも、日常生活でも使えるテクニックがいろいろと盛り込まれています。中学や高校でこんな学校に通わせられたら最高ですね。この本を皮切りに、多様性を許容する社会をどのように築いていけるか、より考察を深めていきたいと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
