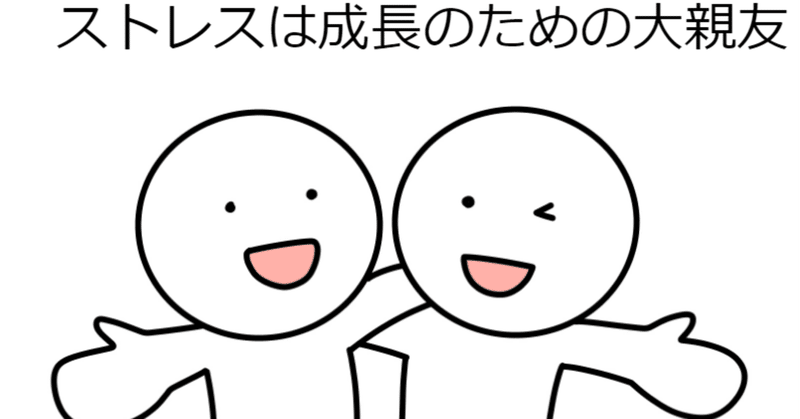
ストレスを避ける人は永遠に成長できないという話
ストレス社会という言葉がすっかり定着しています。ストレスがちょっとでもあると、まるでそれはバイキンみたいに忌み嫌われています。
でも、脳科学的に見ると、ストレスというのは自分を成長させてくれる原動力の原点です。ストレスを避けて人生を送ると、現状のママどこにも行けない人生を送ることになります。
つまり、そこに、めちゃくちゃ重要な逆説があります。

ストレスを感じる人は、まず現状がとっても嫌なわけです。そして、その嫌な現状から逃れる、つまりストレスを避けようとします。
そうすると、なんと、そのストレスを作り出している嫌な現状を克服することができなくなってしまい、結果的にその嫌な現状を認めてしまう⇒永久にストレスから逃れられないし、みじめな自分であり続ける。
ということになる……。
いやだーーーーー(゚0゚)
そんなのはいやだーーーー!
という人におすすめなのがこの本です。
ポイントは「ストレスには二種類ある」ということ
なんだか、ややこしい話になった様に見えますが、簡単です。
ストレスには、人を駄目にするダークストレスと、人間を成長させるブライトストレスというものがあるのです。
ストレスを忌み嫌う人というのは、ダークストレス、つまり抜け出せないストレスを避けようとして、感情を殺したり、怒らないようにしたり、ネガティブなことを考えないようにする、などをやみくもにやってしまうのです。これらは全部間違っています。

最近流行りの、間違った意味での反応しない練習とか、スルーするのがかっこいいとか、クールでいよう、とか人と距離を取ろう、とかネガティブな気持ちは手放そうとかいうのは、全部ダークストレスのことをやるならいいのですが、こういう事を言っている人は、それに気がついていません。
だから、人間を成長させるブライトストレスまで一緒に捨ててしまうので、結果的に成長の機会を失い、その場限りではなんとなく気持ちが楽になったように思えてもすぐに戻ります。
人生降りるわけに行かないので、またすぐ翌日になれば会社に行くとかが待っているわけです。現状を変えていないのだから、いくらストレスから逃れたつもりでも、日曜日にサザエさんが始まる頃には、土曜日になんちゃってマインドフルネスなどを駆使して避けていたストレスはまた、当たり前ですが、必然的に自分に舞い戻ってきます。
正しい脳科学を知れば、ダークストレスをブライトストレスに転換させることができてしまう
じゃあ、我らはいったん昭和の笑い話として捨て去ったはずの巨人の星の世界を再び人生の大事な考え方としなければならないのでしょうか。
大リーグボール養成ギブスだけが、私たちを成長させるというのは、やはり真実なのでしょうか……(゚0゚)。

もちろんそんなことはありません。
スピリチュアル系なんちゃって脳科学ですと、ここで、ストレスを手放そう!おしまい。だから大リーグボール養成ギブスなんてもっての他、ってことでブライトストレスまで手放してしまうのですが、正しい脳科学では素晴らしい方法があります。
ストレスの中の悪い部分だけ消すことが可能
ストレスこそが、現状を変革しようとすることで、根本的なストレス要因を取り除くというほんとうの意味でのポジティブ思考(ネガティブを捨てるという偽ポジティブ思考ではなく)を可能にします。
じゃあ、その時に感じる不快感というのは、やはりしょうがないのか、成長するならば苦痛を押し殺して生きていくことはやっぱり必要なのか、結局大リーグボール養成ギブスなのか、という話に戻りそうですが、そうはなりません。
いくつか方法があるのですが、中でもわかりやすいのは「DHEA」というホルモンの分泌割合を増やすという方法です。「DHEA」が多いと不快感からの回復が早まります。ですので、不快感を減少させながらストレスをポジティブに活用できます。
いわば、ニコニコ(^▽^)しながら大リーグボール養成ギブスを付けたままでいられるわけですね。
では、この「DHEA」分泌を促すにはどうしたら良いか。
それはなんと(゚0゚)「ストレスにはポジティブな側面がある」ということを知るだけでDHEA物質は分泌が促されるのです。
え!?そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、実験検証済みです。
本書ではこんなふうに書いてあります。
スタンフォード大学のアリア・クラム博士は、プラシーボ効果やマインドセットの研究を盛んに行っています。興味深い研究はいくつもあるのですが、そのなかでも、「ストレス=悪」と考えることによって、実際にストレスレベルが高まるという研究をしています。また、「ストレス=学び」というマインドセットを持つことによってストレスレベルが低下することも同時に報告されています。
つまり、おまじではなく、「ストレス=学び」というマインドセットを持つことによってストレスレベルが低下する時に先程の「DHEA」が分泌され、ブライトストレスは維持されたまま、そのストレスの中に含まれる、不快なストレス、ダークストレスだけが消えていく、という作用が脳内に起きることになります。
本書では、他にもストレスを肯定しながら、ダークストレスだけをコントロースして減少、消滅させていく方法がいくつも紹介されています。
たとえば「オキシトシン」という化学物質は「愛情ホルモン」などとも呼ばれますが、これは誰かを抱きしめたり、抱きしめられたりする際に分泌されます。
だから、子供に大リーグボール養成ギブスをはめたとしても、その後に頑張ったら抱きしめてあげれば、ダークストレスはどんどん減少します。
つまり、星一徹の間違いは、大リーグボール養成ギブスを付けたことにあるのではなく、大リーグボール養成ギブスだけ付けておいて、星飛雄馬を抱きしめなかったことにある。付けたギブスの上からギシギシいわせつつ、べたべた抱きしめればよかったのです!(アニメとしてはなんか、別のアニメになってしまいますが……(笑))。
まとめ ストレスを手放す人に成長はない
このようなわけで、ここでよくある、ストレスを手放そうという言葉の危険性を再度確認しておくことが大切だと思います。
ストレスを手放すとは、自分の成長機会を手放すことにほかならず、それは結果として現状維持、気に入らない環境も、気に入らない自分も認めてしまうことになるのです。
だから、ストレスは親友としていったん全部引受、その親友の性悪な部分だけをあなたが取り除きながら、肩を組んで二人三脚で、むしろストレスが自分の人生にあったこと、親友がいてくれたことに感謝しながらストレス社会を生きていくことが王道だということでした。
とても、納得の行く、本物脳科学の本ですのでぜひおすすめです。
こちも、動画にする予定です!
(^▽^)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
