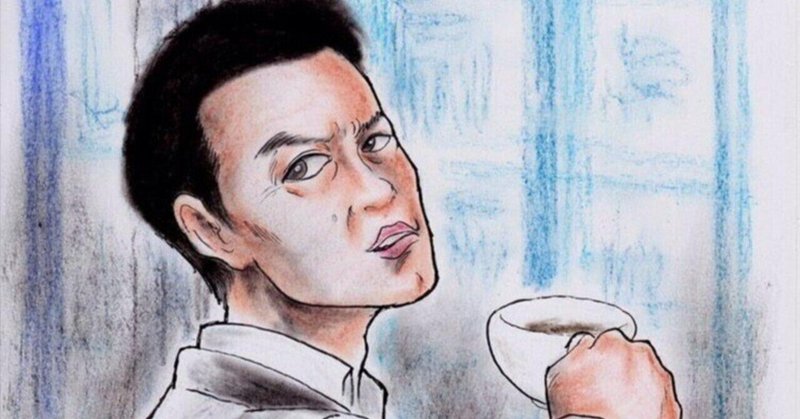
小説『衝撃の片想い』シンプル版【第四話】③
【ある男の運命が変わった日】
◆
――道理で社長さんが落ち着きがないのは、通報したのか。
「運転している男を除くと四人。やっぱり逃げますか、男らしく」
――うーん…。嫌味な女に豹変してる。警察はワルシャワの件は知らないだろうから、架空口座の疑いで、任意で引っ張るつもりか。
――ワルシャワのレストランの時と同じか。判断力がなくなったんだ。こうしているうちに、トラブルに巻き込まれるんだ。それでいいと思ってしまうし…。
肩を落としていると、
「もうすぐ、彼らが銀行に着きます」
とゆう子が言い、
「友哉さん、トキさんが言ってた友哉さんと違うなあ」
と、独り言のように呟いた。
『何が?』
「もっとすごい男の人だってニュアンスだった」
『まさにニュアンスだろ』
「PTSDは気にしないけど」
『PTSDじゃない』
「ちょっと幻滅かな。警察が来るって言ったら、目がオドオドしている。わたしがワルシャワのホテルで迫った時と一緒。ほんと、怖がりなんだね」
『父親の介護がしんどくて不機嫌か。八つ当たりしないでくれ』
――くそう。どいつもこいつも人を昔と違うってうるさい。昔にひどいめに遭ってきたから、もう終わりにしたい。ゆう子にも言ったのに。
『ゆう子』
「なによ」
冷たい返事がきた。
『俺にも夢があった』
「え?」
『あとは、のんびり暮らす夢。それは棄てる気はない』
「聞いたよ。三年後でもいいでしょ」
『三年間、のんびり、まったりしてよう』
「……」
『なにため息、吐いてんだ。ふざけるな』
「ふ……」
友哉はテラーの宮脇の肩に付いていた糸くずを払った。その時、リングが緑色に光った。
「早退の準備をして、僕の車の横か中で待っていてくれないか。特別色の朱色のポルシェだ」
ポルシェのキーを出すと、彼女はさっと受け取り、「はい」と微笑んだ。
そして足早に部屋から出ていく。富澤がびっくりして、部屋から出ていく彼女の背中を見ていた。
「新手のナンパだ!」
ゆう子が叫んだ。友哉は頭が割れるかと思い、
『うるさい。黙って俺の指示に従え』
「え? は、はい……」
『彼女が危ないから外に出したんだ。分かるか。事件になるかもしれない。おまえがそそのかすからだ。レベル2がどの程度の悪女か知らないから、話もしてみたい。それに社長からも目をかけられている美女だ。銀行に一人、仲間がいた方がいい』
「仲間なら、若くて美人じゃなくていいでしょうに」
『若い女の子なら万が一の時に役に立つんだろ』
「四十歳ほどの熟女は嫌なんですか」
『彼女がずっと俺をジロジロ見ていた』
「もてますねえ。それに今の光は何よ」
『知らない。トキが、困った時、女を口説くために頭全体に向けて、光を放てって言ってた』
「へえ。トキさんがそんな悪いことを言うの?」
『彼はそんな不道徳な言葉は作らない。危険な場所で言うことを聞かない女性とかを大人しくさせるのに有効で、ナンパにも使えるらしいけど、俺はナンパをしないって言っておいた』
「今した」
『面白いよ、ゆう子。今日の君は秘書だ。公私混同するな』
「あ、ごめんなさい」
ゆう子はやっと気持ちを切り替えたようで、
「もうすぐ部屋にお巡りさんたちが到着します。最後に入ってくる男がレベル3です」
と教えた。
『レベル3か』
「友哉さんみたいに性格が悪くて、女の子を平気で泣かす男のこと」
『気持ち、切り替えてないね』
冗談を言っている暇はないのに、宮脇という女子銀行員を光の力で好意を持たせた事に、余計に怒っているようだった。
『真面目にやらないなら、そこの窓から逃げる』
「あらあら、逃げ方はワイルドなのね。レベル4なら人殺しの過去があるとか詐欺の常習犯とか。5はサイコパス。人を殺すことをなんとも思わない奴。レベル3はその人間を調査した時に誰かと争っていた。恋愛の泥仕合とかも含めてね。または脳が異常に興奮していたり、悩みとかひどくて鬱状態だった。だけど実際は凶悪な前科がなくて判断ができないもの。もうお巡りさん、入ってきますよ。レベル3の人は友哉さんが見てどうするか判断するの。トキさん、あなたに丸投げが多いね」
『そうだよ。仕事を与えておいて無責任だ。俺に人を殺すか殺さないか任せるのか。俺に人を裁く裁かないを任せるのか。俺が子供の頃になりたくなかった職業が裁判官だ』
「丸投げ、丸投げ」
歌を口遊むように喋っている。
『危機感ないな』
「やっつけちゃっていいよ。無理だと思うけど」
ゆう子がそう言い終わらないうちに、応接室の扉が荒々しく開けられ、背広姿の男たちがゾロゾロと入室してきた。
最後に、浅黒い顔をした背の高い男が入ってきて、「富澤社長、久しぶりです」と言うが、頭を下げる様子はなかった。
――知り合い?いや、友達に近いな。
友哉がソファに座ったままでいると、蛙のような顔をしたその背の高い刑事が、
「あんたがササキトキさんか。ご同行願います」
と言った。
「大勢でやってきて、僕はとてもVIP待遇ですね。で、なんの容疑?」
「私は公安の者です」
「名乗れないよな、公安警察は」
「あなたが架空の取り引き口座を作ったようで」
「架空? 公安警察が架空口座の疑いの男を引っ張りに?公安の仕事じゃない」
「ササキトキなんて人間は日本にいないのです。あなたは危険人物としてリストに入っています」
「外事か?」
「外事警察を知ってるのですか。身分証を見せてほしい」
「持ってない。鞄を車に置いてきた」
「車はどこに?」
「捜せよ。警察はそれが得意だろ」
「後でな。まだ、あなたの素性がはっきりしないので」
「素性がはっきりしない人を警察は任意で引っ張るのか」
「だいたいわかってる」
「だいたいなら拒否する」
「……」
年長者の刑事が黙ったら、若い警察官が、
「あんた、立場をわかってんのか」
と怒った。
「立場?国家権力に市民は言いなりになれ、という立場か。答えろ」
友哉の反論に若い警察官が黙り込んだ。
ゆう子はAZからの現場の様子を食い入るように見ていた。
――また変わった。さっきまでの友哉さんじゃない。テロリストと戦うため、レストランから飛び出した時のあの友哉さんだ。
ゆう子は手に汗を握っていた。
「大輔、落ち着け。三百億円を大富豪から頂戴する奴だ。バックに何者かいるから、でかい口を叩けるんだ」
「かわいい秘書が一人だ。とにかく帰ってくれ。三百億円じゃ、国家は揺るがないでしょ」
「あなたは、ササキトキに似ていない」
「ササキトキですよ。それともササキトキと会ったことがあるのか」
「防犯カメラに写っていたササキトキさんは違う顔だと言ってるのですよ」
そんな初歩的なミスをしているのか、あの未来の兄ちゃん、と、ゆう子に言うと、苦笑いとともに、
「宇宙人もよく写真に撮られるしね」
センスのあるジョークで、ゆう子はトキを擁護した。
本当はトキの部下が架空口座を作ったのだ。
「警察官が四人もドアを塞ぐようにして立っている。怖くないですか」
と訊いた。
『怖い? 怖がったら、君が怒るんじゃないのか。さっきからそう説教されている』
友哉が、体を大きく見せながら立ち上がった。
「なんだ?」
友哉に近づこうとした公安の警察官が目を丸めた。
身長は175㎝だが、ほどよく付いた筋肉は、夏のせいで日焼けしていて磨かれた銅のような艶があり、いかにもバネがありそうだった。半袖のサマーセーターからは友哉の肌が露出していて、宮脇がその腕に見惚れているのを、友哉は応接室までの間に確認していた。トキからもらった筋肉ではなく、以前からそれなりに鍛えていた。
「先日、ワルシャワで起きた謎のテロリスト殺人事件」
芝居がかった大きな声で友哉は言った。
「逃げた日本人、あれは俺だ」
自らを嗤うと、警察官たちがざわつく。
「え? なに自分で言っちゃってんの?」
ゆう子が叫んだ。
警視庁公安部、外事四課。
桜井真一警部補。
友哉が、トキと出会い、足を治してもらわなければ出会わなかった二人。
桜井真一の運命が変わった日。
……続く。
【トキがすばる銀行に架空口座を作りにきた時の話。途中、部下と交替している。また利恵は口座開設窓口担当。隣に淳子がいる。トキと大富豪ジェイソン氏との会話もある】
普段は自己啓発をやっていますが、小説、写真が死ぬほど好きです。サポートしていただいたら、どんどん撮影でき、書けます。また、イラストなどの絵も好きなので、表紙に使うクリエイターの方も積極的にサポートしていきます。よろしくお願いします。
