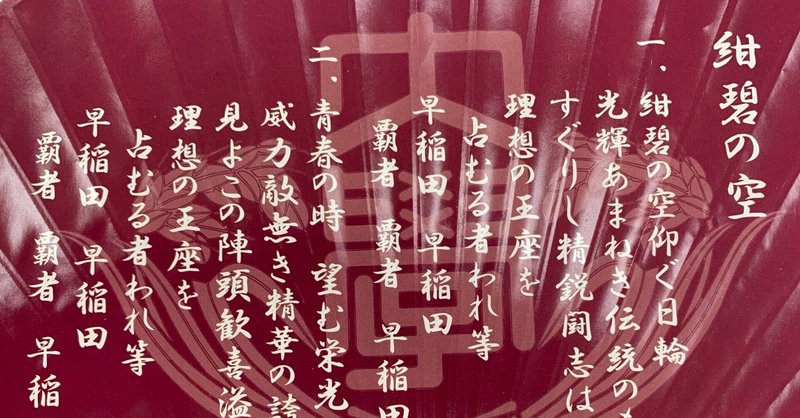
教科書だけで解く早大日本史 2021文化構想学部 5
2021文化構想学部編の第5回です。
※大学公式ページで問題を確認してください。
※東進データベースは要登録です。
◎4 平安後期から鎌倉初期の文化について
X 後白河法皇は貴族社会で流行していた漢詩文を集めて『梁塵秘抄』を編んだ。
Y 重源は宋出身の技術者とともに、平氏の焼き討ちにより焼失した東大寺の再建に尽力した。
Z 文章を用いずに絵だけで物語を表現する絵巻物が発達し、『伴大納言絵巻』などが制作された。
ア X- 正 Y- 誤 Z- 誤
イ X- 誤 Y- 正 Z- 誤
ウ X- 誤 Y- 誤 Z- 正
エ X- 正 Y- 正 Z- 誤
オ X- 誤 Y- 正 Z- 正
正誤判定の組み合わせの問題です。このタイプの問題はすべての文をしっかりと正誤判定できれば文句なしですが、とにもかくにも1つの正誤判定を確定させられれば攻略しやすくなります。
後白河上皇みずから民間の流行歌謡である今様を学んで『梁塵秘抄』を編んだことは、この時代の貴族と庶民の文化との深いかかわりをよく示している。今様は当時流行した歌謡であり、このほかに古代の歌謡から発達した催馬楽や和漢の名句を吟じる朗詠も流行した。(93頁)
引用にある通り、『梁塵秘抄』は漢詩文を編んだものではなく、民間の流行歌謡ですから、Xは誤文です。
この引用に先立って、「貴族文化は院政期に入ると、新たに台頭してきた武士や庶民とその背後にある地方文化を取り入れるようになって、新鮮で豊かなものを生み出した」とあり、院政期の文化の特徴をまとめています。「広く権力が分散していくことになり、社会を実力で動かそうとする風潮が強まっ」(90頁)たという特徴づけとあわせてよく理解しておきたいところです。
同じく院政期の文化であるZの「絵巻物」について先に見ておきましょう。
絵と詞書を織りまぜて時間の進行を表現する絵巻物が、この時代には大和絵の手法が用いられて発展した。『源氏物語絵巻』は貴族の需要に応じて描かれ、『伴大納言絵巻』は応天門の変に取材し、同じく朝廷の姿を描いた『年中行事絵巻』とともに、院政の舞台となった京都の姿を描いている。(94頁)太字は引用者による
絵巻物は「文章を用いず絵だけで物語を表現する」ものではなく、「絵と詞書を織りまぜて」表現したものです。引用に挙げた京都の貴族文化を表す絵巻物だけでなく、この後には聖の生き方や風景・人物を描いた『信貴山縁起絵巻』、動物を擬人化していきいきと描いた『鳥獣戯画』などが挙げられています。
そういうわけでZも誤文でした。
選択肢には、「X- 誤 Y- 誤 Z- 誤」という組み合わせが排除されているので、この時点で正解は「イ X- 誤 Y- 正 Z- 誤」に確定します。
芸術の諸分野でも新しい傾向がおこっていた。そのきっかけとなったのは、源平の争乱によって焼失した奈良の諸寺の復興である。重源はその資金を広く寄付に仰いで各地をまわる勧進上人となって、宋人陳和卿の協力を得て東大寺再建に当たった。その時に採用されたのが大仏様の建築様式で、大陸的な雄大さ、豪放な力強さを特色とし、東大寺南大門が代表的遺構である。(117頁)太字は引用者による
重源は、いまどきの表現だと「人力クラウドファンディング」で東大寺を再建しました。また、平重衡による南都焼き討ちは96頁に書かれています。
〇5 武士の政治と切り離せない思想や宗教について
誤文2つ
ア 平清盛は安芸の厳島神社を信仰し、美麗な装飾経を奉納した。
イ 鎌倉幕府に重用された栄西は、密教の僧侶としても活動した。
ウ 室町幕府が禅宗寺院に出版させた御伽草子は、五山版と呼ばれた。
エ 徳川家康は死没後、東照宮にまつられ、神格化された。
オ 明から渡来し黄檗宗の開祖となった隠元は、江戸幕府から布教を禁じられた。
誤文を2つ選択する問題です。5個の選択肢で誤文を1つ選択だと20%の確率ですが、誤文を2つ選択だと10%と一気に倍の難易度となります。確実に正誤判定をできる文をいかに増やせるかが勝負です。
民衆に好まれた物語に御伽草子があった。御伽草子は絵の余白に当時の話し言葉で書かれている形式のものが多く、読物としてだけでなく絵を見て楽しむこともできた。(145頁)
御伽草子は民間で流行したもので幕府が出版させたものではありません。
ウが1つめの誤文です。
宋学の研究や漢詩文の創作もさかんであり、義満の頃に絶海中津・義堂周信らが出て、最盛期を迎えた(五山文学)。彼らは、幕府の政治・外交顧問として活躍したり、禅の経典・漢詩文集などを出版(五山版)するなど、中国文化の普及にも大きな役割を果たした。(141頁)
五山版は臨済宗の僧によるものです。
②(本末制度が)中世から続く仏教諸宗派を対象にしたほかに、新たに17世紀半ばに、明僧隠元隆琦が禅宗の一派である黄檗宗を伝え、幕府に許容された。(177頁 脚注②)
2つ目の誤文はオです。隠元の開いた黄檗宗は「江戸幕府から布教を禁じられた」のではなく、「幕府に許容された」が正しい。
アは厳島神社「平家納経」です。95頁に写真資料が掲載されています。
イは鎌倉仏教の一つ臨済宗の開祖である栄西が「密教の僧侶としても活動した」という怪しな文ですが、これは正しい文です。
禅宗は、12世紀末頃、宋に渡った天台の僧栄西によって日本に伝えられた。栄西は密教の祈禱にもすぐれ、公家や幕府有力者の帰依を受けて、のちに臨済宗の開祖と仰がれた。幕府は臨済宗を重んじ、栄西の死後、南宋から来日した蘭渓道隆・無学祖元ら多くの禅僧を招いて、鎌倉に建長寺・円覚寺などの大寺をつぎつぎと建立していった。(114-115頁)太字は引用者による
鎌倉仏教の開祖たちはみな天台宗で学んでおり、密教についてよくわかった上での新しい宗派の創設でした。栄西については、『興禅護国論』だけでなく、源実朝にお茶の効用を伝えた『喫茶養生記』も重要です。
エの東照宮については、183頁で家康が日光東照宮にまつられたことが書かれています。
〇6 綱吉の将軍就任を受けた武家諸法度の改正
ア 武家伝奏の制度が新たに加えられた。
イ 参勤交代の制度が新たに加えられた。
ウ 殉死の禁止が新たに定められた。
エ 大名の第一に励むべき内容が「忠孝礼法」から「学問芸能」へと変わった。
オ 大名の第一に励むべき内容が「文武弓馬」から「文武忠孝」へと変わった。
綱吉将軍就任時の武家諸法度(天和令)について正しい文を選択する問題です。
武家諸法度については、最初に出された秀忠の元和令、家光の寛永令、家綱の寛文令、そして綱吉の天和令の順です。
武家諸法度(元和令)
一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
(『御触書寛保集成』)(200頁)
武家諸法度(天和令)
一、文武忠孝を励し、礼儀を正すべき事。
天和三年七月廿五日
(『御触書寛保集成』)(200頁)
正解は、オです。武断主義の政策をおこない、力で大名を従えた戦国時代の空気感を残している元和令に対し、戦乱の時代が終了し、文治主義の政治をおこなうようになった時代の天和令の違いは頻出事項です。
アの武家伝奏は朝幕間の取次ぎをした公家です。
イの参勤交代が制度化されたのは寛永令。
ウの殉死の禁止は寛文令。
エは禁中並公家諸法度の「天子諸芸能の事、第一御学問也」から作られたひっかけ選択肢です。
少し長くなってしまったので、今回はここまでにします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
