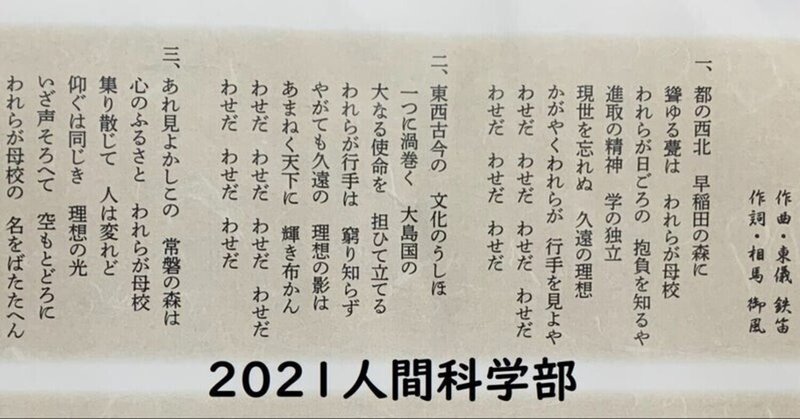
教科書だけで解く早大日本史 2021人間科学部 6
2021人科編の第6回です。大問Ⅱの残りをみていきましょう。
※大学公式ページで問題を確認してください。
※東進データベースは要登録です。
◎問6 「評定衆」を設置したのは誰か
ア 北条高時 イ 北条貞時 ウ 北条時宗
エ 北条時頼 オ 北条義時 カ 該当なし
該当なしならカを選択する問題です。この場合は各選択肢を確実に処理する必要があります。
幕府を開いた源頼朝の将軍時代は将軍独裁の政治をがおこなわれていましたが、頼朝が死去すると、御家人中心の政治を求める動きが強まり、有力御家人13人の合議制となります。いわゆる「鎌倉殿の13人」です。
その中で伊豆の在庁官人出身で将軍家外戚の北条氏が梶原、比企、和田らの有力御家人を倒して権力を握ります。
承久の乱前後では、政所と侍所の長官を兼ねた執権の北条義時と「尼将軍」北条政子が政治を主導し、政子の死後は義時の子泰時が執権として政治をおこないます。
承久の乱後の幕府は、3代執権北条泰時の指導のもとに発展の時期を迎えた。政子の死後、泰時は、執権を補佐する連署をおいて北条氏一族中の有力者をこれに当て、ついで有力な御家人や政務にすぐれた11名を評定衆③に選んで、執権・連署とともに幕府の政務の処理や裁判に当たらせ、合議制にもとづいて政治をおこなった。(102頁)
評定衆を設置したのは北条泰時です。選択肢に泰時はありませんので、該当なしのカが正解となります。
選択肢はいずれも「得宗」です。
義時ー泰時ー(時氏)ー時頼ー時宗ー貞時ー高時、の順です。
〇問7 ( 5 )の制度は室町幕府に引き継がれ、守護の新たな権限として制度化されていく
ア 使節遵行 イ 刈田狼藉 ウ 京都大番役
エ 鎌倉番役 オ 半済給与 カ 該当なし
空欄補充問題です。該当なしはカを選択します。
鎌倉時代末、係争地近隣の御家人や守護の死者が現地へ派遣され、係争地の勝訴者への引き渡しまでを担う( 5 )の仕組みが生まれ、幕府の裁許の内容を地域社会に受容させる取り組みが始まった。この( 5 )の制度は室町幕府へと引き継がれ、守護の新たな権限として制度化されていく。
資料文の該当部分はこのようになっています。( 5 )に入る語は鎌倉時代末からあった仕組みが室町幕府成立後に守護の新たな権限となったものになります。
鎌倉時代の守護の任務は、いわゆる大犯三カ条でした。
② 大犯三カ条は、諸国の御家人に天皇・院の御所を警備させる京都大番役の催促と、謀叛人・殺害人の逮捕で、平時の守護の任務でもっとも重要なものであった。(98頁 脚注②)
この他に鎌倉の警護につく鎌倉番役や財政的負担である関東御公事、元の襲来に備えた異国警固番役などは御家人の任務でした。
鎌倉幕府が滅び、南北朝の動乱が始まると、武士を国ごとに統括している守護は軍事的に大きな役割を担うようになり、守護の軍事力動員をあてにした幕府は守護の権限を大幅に強化します。
その代表例が、半済令、使節遵行権、刈田狼藉取締権でした。
半済令は観応の擾乱で尊氏派と直義派が争うさなかの1352(文和元)年に近江・美濃・尾張の3国で出され、のちに全国に広がった法令で、「守護に一国内の荘園や公領の年貢の半分を挑発する権限を認めたもの」(123頁)でした。
① 鎌倉幕府の守護の職務であった大犯三カ条に加え、田地をめぐる紛争の際、自分の所有権を主張して稲を一方的に刈りとる実力行使(刈田狼藉)を取り締まる権限や、幕府の裁判の判決を強制執行する権限(使節遵行)などが新しく守護に与えられた。(123頁 脚注①)太字は引用者による
残る2つは、裁判の強制執行権である使節遵行権、刈田狼藉を取り締まる権限でした。どちらも実力行使を伴う権限で、軍事力を動員できる守護の権限はさらに大きくなり、一国全体におよぶ地域支配権を確立する守護もあらわれました(守護大名と呼ばれることもあります)。
正解は、アの「使節遵行」でした。他の選択肢の内容については解説の通りです。
◎問8 荘園領主と地頭、地頭同士の紛争などについて 誤り1つ
ア 荘園領主と地頭の下地中分では、山野も含めた荘園の土地すべてを折半し、互いの支配権を認め合った。
イ 荘園領主が年貢の一部を地頭に支払い、地頭から荘園領主の一切を委ねられることを地頭請という。
ウ 紀伊国阿氐河荘では、荘民が地頭の過酷な支配を荘園領主に訴え、荘園領主と地頭も対立した。
エ 伯耆国東郷荘では、13世紀半ばに荘園領主と地頭との間で下地中分の和与が成立した。
オ 和与による下地中分や地頭請が行われた荘園では、地頭が現地の支配権を手に入れることになった。
まずは資料文の下線部dをみてみましょう。
地頭と荘園領主、あるいは地頭御家人どうしの訴訟が増加すると、幕府は対応に苦慮して和与を勧め、また、紛争当事者も、長い年月と多額の費用をかけて訴訟をするよりも和与を選択するようになったのであろう。
鎌倉時代の地方は公武二元体制の支配となっていました。幕府は守護・地頭を通して全国の治安維持に当たり、地頭には年貢の納入を厳しく迫るなど、朝廷の支配を助ける一面もありました。しかし、武家政権側の勢いが強まると守護・地頭と国司・荘園領主のあいだでの紛争が増加していきました。
特に段別5升の加徴米徴収権を得た新補地頭になることは旨みが大きく、東国の御家人が西国の地頭になったことなどから、現地支配権をめぐって紛争が拡大します。幕府が公正な裁判制度の確立につとめたのも、こういった状況に対応するためでした。
地頭の支配権拡大の動きに直面した荘園・公領の領主たちも、幕府に訴えて地頭の年貢未納などの動きをおさえようとした。しかし、現地に根をおろした地頭の行動を阻止することはしだいにできなくなり、紛争解決のために領主たちは、やむを得ず地頭に荘園の管理いっさいを任せて、年貢納入だけを請け負わせる地頭請所の契約を結んだり、さらには現地の土地の相当部分を地頭にわけ与え、相互の支配権を認めあう下地中分の取り決めを行ったりすることもあった。
幕府もまた、当事者間の取り決めによる解決(和与)を勧めたので、荘園などの現地支配権はしだいに地頭の手に移っていった。(106-107頁)
かなり長めの引用になってしまいましたが、増加する紛争を解決するために当事者間で地頭請所、下地中分(和与中分)などの取り決めがなされ、幕府も当事者間解決を勧めて訴訟の数を減らそうとしたということです。
選択肢をみると、イの誤りがわかります。地頭請は「地頭から荘園支配の一切を委ねられること」ではなく、荘園領主たちが「やむを得ず地頭に荘園の管理いっさいをまかせて、一定の年貢納入だけを請け負わせる」ものです。
イ以外の選択肢は正しい文になっています。
アは「教科書」本文だけでは「山野も含めた荘園の土地すべてを折半」が確定できませんが、106頁にある史料「伯耆国東郷荘の下地中分図」の説明で「田地・山林・牧野などを、それぞれ地頭分・領家分に二分している」と書かれています。エはこの史料でわかります。
ウの「紀伊国阿氐河荘」は111頁に「訴状」が史料として掲載されています。書くのもはばかられる地頭の横暴が列挙されています。
オは「教科書」引用の通りです。
大問Ⅱは以上です。◎4〇3△0×1でした。
次回から江戸時代初期から出題された大問Ⅲに入ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
