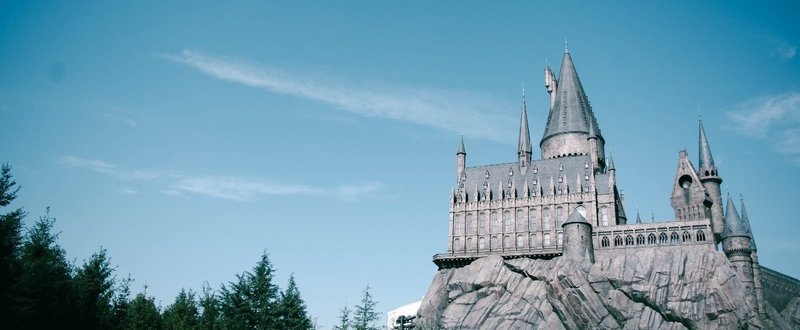
ハリポタ未翻訳の短編を和訳してみた
2008年にJ.K.ローリングが書いた、チャリティ用の短編です。
日本語版は今のところ出ていません。
コメディとしても読めるけど、本編の伏線もいっぱいあるし
いろいろ解釈も出来る短編です。
意識的な意訳はしてないつもりだけど、
語順はかなり変えてます。
(誤訳もあるかも・・・見つけたらぜひご指摘を!)
ではでは、お楽しみください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
暗闇の中、二人乗りで疾走するオートバイが急カーブを切った。「止まれ!」パトカーに乗った二人の警官は叫んだ。
フィッシャー巡査部長は大きな足で急ブレーキをかけた。後部座席に乗っていた少年が落下して車の下敷きになるのではないかと思ったのだ。
しかし、オートバイは少年たちを振り落とすことなく曲がりおおせた。そして赤いテールランプを一度、きらりと光らせると細い脇道へと消えた。
「これで捕まえたも同然だ!」アンダーソン巡査は興奮気味に叫んだ。
「そっちは行き止まりだ!」フィッシャーはハンドルにのしかかり、シフトレバーを乱暴に切り替えた。狭い路地を無理やり追いかけたため、車体側面の塗装が半分剥げ落ちた。
たっぷり十五分間にも渡る追走劇の末、とうとう獲物たちは身動きが取れなくなった。
ヘッドライトが彼らを照らした。高くそびえるレンガの壁とパトカーのあいだに二人は捕らえられていた。目をらんらんと光らせ、唸り声を上げる獣のようにパトカーがにじりよった。
車のドアと小道の壁とのあいだは狭く、フィッシャーとアンダーソンは車から出るのに一苦労した。悪ガキたちのところまで行くのにもカニ歩きをしなければならない。 警察の威厳も何もあったもんじゃなかった。
フィッシャーはでっぷり太った腹を壁にこすりながら進んだ。 その結果、シャツのボタンは弾け飛び、しまいには背中でぽっきりサイドミラーを折る始末だった。
青いライトを全身で浴びながら、まるで楽しむかのように少年たちはにやにやと笑っていた。
「バイクを降りろ!」フィッシャーは大声で怒鳴った。 彼らは言われたとおりにした。壊れたサイドミラーからようやく抜け出したフィッシャーは、憤怒の形相で少年たちを睨んだ。見たところ、十代後半のようだ。
運転していた方は長い黒髪だ。その端正で生意気な顔立ちは、不愉快にも娘のボーイフレンドを連想させる。ギターを弾いてばかりの怠け者だ。
もう一人の少年も同じく黒髪だが、こちらの髪は短く好き勝手な方向に撥ねていた。彼は眼鏡をかけ、にっこりと笑っていた。 そしてふたりとも金色の大きな鳥の絵が描かれたTシャツを着ていた。ばかみたいに騒いでうるさいだけのロックバンドのものに違いない。
「ヘルメット着用義務違反!」それぞれの頭を指さしながらフィッシャーは叫んだ。
「スピード違反もだ。しかも大幅に!」 (実は、そのスピードはフィッシャーの知るオートバイの限度というものをゆうに超えていた。)
「警官の停止要請も無視!」
「僕たちもおしゃべりしたかったんですけどね」眼鏡の少年が言った。 「ちょっと取り込み中で—」
「無駄口たたくな!お前らは袋のネズミだぞ!」アンダーソンが怒鳴った。 「名前を言え!」
「名前だって?」
長髪の少年が訊き返した。
「うーん、そうだな。ウィルバーフォースだろ、バスシェバに…エルヴンドークとか…」
「この名前の何が良いって、男の子でも女の子でも使えるとこだね」
眼鏡の少年が言った。
「おや、僕らの名前を聞きたかったのか?」 アンダーソンが怒りのあまりわめき散らすのを見て、最初の少年が尋ねた。
「なら最初っからそう言ってくれよ。こいつがジェームズ・ポッターで、俺はシリウス・ブラック。」
「いい加減にしないと、事態はもっとシリアスでブラックになるぞ。ふざけたガキどもめ—」
しかしジェームズもシリウスも全く聞いていなかった。
彼らは突如、猟犬のように緊張した面持ちになった。 フィッシャーとアンダーソンの肩越しに、パトカーの屋根のさらに先、暗い路地の入り口の方に目を凝らしていた。
そして二人同時に流れるような手つきでズボンの後ろポケットに手を伸ばした。 心臓が一拍、脈を打つ。
そのわずかな間、ふたりの警官はこちらを向く銃口を想像した。だがすぐさま気づいた。若者たちが取り出したのはなんと—
「ドラムスティックだと?」アンダーソンは嘲笑った。
「お笑いコンビか?おかしな奴らだな。もういい。お前らを逮捕する。容疑は—」
しかしアンダーソンは容疑を宣告しそこねた。ジェームズとシリウスがなにやら訳のわからない言葉を叫ぶと同時に、ヘッドライトの光が動いたのだ。
警官はあたりをきょろきょろ見回し、二、三歩後ずさった。 三人の男が飛んできた——文字通り本当に飛んでいたのだ——路地の上空を、箒にまたがって。と同時に、パトカーの前輪が宙に浮き、車は後輪で立ち上がった。
ドスン——バタン——ガシャン。
箒に乗った男たちが、逆さになったパトカーにぶつかって地面に落ちた。明らかに気絶している。木っ端微塵になった箒があたりに散らばっていた。
フィッシャーの膝は崩れ落ち、へなへなと座り込んだ。その両足につまづき、アンダーソンはフィッシャーの上に越え倒れこんだ。 オートバイが再び唸りを上げ始めた。
口が半分開きっぱなしのフィッシャーは、恐々と二人の少年の方を振り返った。
「どうもありがとう!」シリウスがエンジンをふかしながらいった。
「借りが出来ちゃったね」
「いやぁ、楽しかったです!」ジェームズが言った。
「あと、エルヴンドークは男女関係なく使えますからね。お忘れなく!」
地鳴りのような轟音を立て、直立していたパトカーが地面にひっくり返った。恐怖のあまりフィッシャーとアンダーソンはお互いに抱きついた。
いまやオートバイの前輪が宙に浮き、出発しようとしていた。警官たちがわが目を疑う暇もなく、オートバイは空へと飛び立った。ジェームズとシリウスは夜空の彼方へと小さくなっていった。
テールライトがルビーのようにきらりと瞬き、そして消えた。
From the prequel I am not working on – but that was fun! JK Rowling, 2008
サポートいただけたら、旅に出たときのごはん代にさせていただきます。旅のあいだの栄養状態が、ちょっと良くなります。
