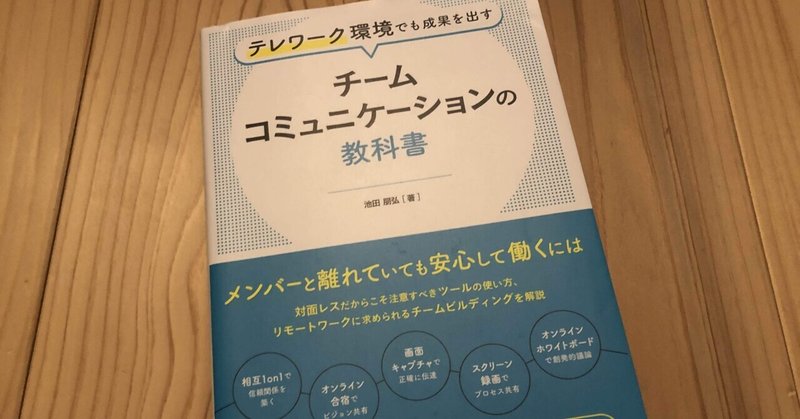
ほんの紹介『チームコミュニケーションの教科書』
リモートワークを続けていると生じてくる違和感。オフラインではできていたチームビルディングをいかにオンラインで実現するか、そのコツが書かれています。
テレワークによるコミュニケーション課題
・メンバーが互いに何をやっているかわからない
・雑談や相談がしづらい
・未経験のメンバーを指導できない
・モチベーションを維持できない
テレワーク導入への抵抗
・会社の一体感やカルチャーが失われる
→一体感やカルチャーはミッション・ビジョン・行動指針への共感が生む。入社段階の選別・日々の業務における浸透・定期的な振り返りが必要。
・生産性が下がる
・メンタルヘルスの問題が増える
・環境が整っていない
成果を生み出すチームには、良質なコミュニケーションによる信頼関係構築が重要
①心理的安全性。チームメンバーがリスクをとることを安全だと感じ、お互いに対して弱い部分もさらけ出すことができる
②相互信頼。チームメンバーが仕事を高いクオリティで時間内に仕上げてくれると信じている
③構造と明確さ。チームの役割、計画、目標が明確になっている
④仕事の意味。チームメンバーは仕事が自分にとって意味があると感じている
⑤インパクト。チームメンバーは自分の仕事について、意義があり、良い変化を生むものだと思っている
マネージャーは、次に示すコミュニケーションを行うことが推奨されています
・積極的な姿勢を示す
・理解していることを示す
・対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す
・意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す
・強情にならない範囲で自信や信念を持つ
チームとしては、次に示す取り組みが推奨されています
・チームからの意見やアイデアを集める
・個人的な仕事の進め方の好みをチームメンバーに伝え、チームメンバーにも自分自身の好みをチーム内に共有するように促す
次に示す要素はチームの効果性にそれほど影響しない
・チームメンバーが働く場所(同じオフィスで近くに座り働くこと)
・合意に基づく意思決定
・チームメンバーが外向的であること
・チームメンバー個人のパフォーマンス
・仕事量
・チームの規模
・先任順位
・在職期間
テレワークだとコミュニケーションはなくなりがち
コミュニケーションを補う仕組み・工夫が重要
リモートでは、ハイコンテクストが機能しづらい
・誰が何をやっているかわからない
・上司・同僚がいま何を考えているかわからない
・連絡したけど、伝わっているのかどうかわからない
・不満・不安をもっているのかもっていないのかがわからない
・言いたいことがあっても伝えづらい
ローコンテクストを身につけるには、発信と反応から
テレワークでは、これまで私たちが苦手としてきたあえて言葉にする、しっかり伝えるというコミュニケーションスタイルが必要です。ローコンテクストなコミュニケーションにおいて、最も重要なものは発信と反応です。これまでは、わざわざ発信しなくても、誰かが察してくれるという考え方がある程度は通用しました。テレワークではこの考え方は通用しません。発信しなければ伝わらなくて当たり前という考え方に変え、伝えたいことがあれば自身で発信しましょう。また、発信に対してしっかり反応しないと、伝わっていること・理解していること・または反対意見があることなどが何も伝わりません。既読スルーのような状態があると、ローコンテクストなコミュニケーションは成立しません。必ず発信に対して反応するように心がけましょう。
雑談がしづらい
雑談する機会がない→機会をつくる。オンライン朝会、相互1on1
雑談する余裕がない→会議時間の削除&圧縮。事前アジェンダ、会議時間は30分を基準に
雑談のネタがない→自己トリセツや自分チャネル
ミッションやビジョンなど熱い話をしづらい
しっかり議論する場がない→非日常の場をつくる。オンライン合宿。行動指針。
日常的に伝える場がない→日常的に伝える場をつくる。オンライン朝会。毎週1on1。ヒーロー称賛。
メンバーの人生観・価値観を知らない→知る機会をつくる。自己トリセツ。オンライン合宿。
アイデアを共有しづらい・発展させづらい
思いつきを共有しづらい→自分チャネルで独り言
議論を深めづらい→オンラインイベントの技法を習得
新しい取り組みを進めづらい→文章リテラシー・事前アジェンダで進める
文章では伝えづらい
文章コミュニケーションリテラシーが低い→実践で鍛える
文章では表現しづらい→画像・動画も活用
メールやチャットで連絡が遅れがち
期待値が揃っていない→共通認識をつくる。行動指針
状況が不透明→スケジュールを可視化する
PCをみるタイミングがない→スマホ化する
情報共有が遅い
情報共有の場がない→定例会をつくる
業務中の情報共有の場がない→自分チャンネルで分報
細かなニュアンスを伝えづらい
適切な語彙・表現がない→絵文字・スタンプを活用
文章だと厳しくなりがち→電話やオンライン会議を使う
双方向の議論がしづらい
論点が明確でない→事前アジェンダ
人数が多すぎる→少人数にわける、チャット活用
参加者の状況がわかりづらい
誰が参加しているかわからない→冒頭の挨拶、自分アピール
表情が読めない→映像オンにし、表情を活用
内容が理解しづらい
そもそも音が聞き取りづらい→ミュート徹底、環境・ツールでの雑音対策
議論対象がずれている→画面共有・議事録などで認識合わせ
指示が出しづらい
目的・方針が伝わっていない→背景から伝える
アウトプットをすり合わせづらい→画面キャプチャ・スクリーン録画も活用
仕事が止まってしまう→予備ワークを用意
進捗が把握しづらい
作業様子が見えない→メンバーの予定を可視化、分報などで逐一共有
全体状況がわからない→達成状況を可視化
評価が難しい
評価基準が曖昧→基準を明確にしつつ、1on1で定期的に確認
評価の納得感がない→評価前の説明、評価時の説明
不満を把握しづらい
不満を直接把握する仕組みがない→ギャップアンケートで把握する
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
