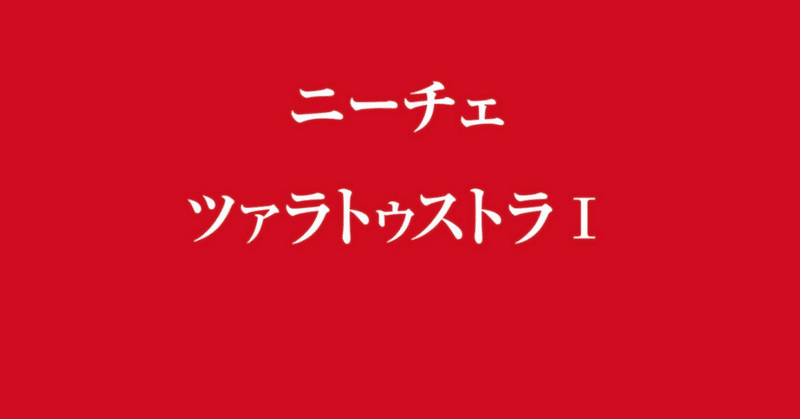
ニーチェ「運命愛と救済」
ニーチェの哲学は「肯定の哲学」ですが、彼は運命をも肯定します。それが「運命愛」として表現されています。運命愛とは、文字通り運命を愛することです。過去・現在・未来の出来事は偶然に支配されていますが、意志によって、「わたしがそれを欲した」と捉え直し、必然の出来事に変換します。これにより、運命・偶然に翻弄されることがなくなります。
運命愛は『ツァラトゥストラ』の「三様の変化」と密接に関係しており、「汝なすべし」を「われは欲す」に変える獅子の力が必要になります。駱駝の状態では運命を耐えることしかできませんが、苦痛や苦悩さえも、「わたしがそれを欲したから起きた(起こる)」と肯定的に捉え直すことで、受身的な運命・偶然の支配から自由になることができます。
「三様の変化」の最終段階である子供の特徴は遊戯と創造性です。運命の重さに耐え忍ぶだけの駱駝が、運命を肯定する獅子となり、子供の遊戯と創造性で重苦しい運命を軽くする、これが運命における「三様の変化」です。それは「救済」とも呼ばれます。超越的な神が救ってくれるのではなく、自分で自分を救うのです。
───────────
しかし、孤独の極みの砂漠のなかで、第二の変化が起こる。そのとき精神は獅子となる。精神は自由をわがものとしようとし、自分自身が選んだ砂漠の主になろうとする。
その砂漠でかれはかれを最後に支配した者を呼び出す。かれはその最後の支配者、かれの神の敵となろうとする。勝利を得ようと、かれはこの巨大な竜と角逐する。
精神がもはや主と認めず神と呼ぼうとしない巨大な竜とは、何であろうか。「汝なすべし」それがその巨大な竜の名である。しかし獅子の精神は言う、「われは欲す」と。
手塚富雄訳「三様の変化」
───────────
小児は無垢である、忘却である。新しい開始、遊戯、おのれの力で回る車輪、始原の運動、「然り」という聖なる発語である。創造という遊戯のためには、「然り」という聖なる発語が必要である。そのとき精神はおのれの意欲を意欲する。世界を離れて、おのれの世界を獲得する。
手塚富雄訳「三様の変化」
───────────
必然的なことはわたしの心を傷つけない。運命愛は、わたしのもっとも奥深い本性である。
『この人を見よ』「ワーグナーの場合」
───────────
そこでは、必然はすなわち自由であり、自由の刺をもてあそんで至福の遊戯をしているのだと、わたしには思われた。
手塚富雄訳「新旧の表」
───────────
おお、おまえ、わたしの意志よ、あらゆる困苦の転回よ。わたしの必然よ。すべての些細な勝利からわたしを守ってくれ。
手塚富雄訳「新旧の表」
───────────
君たちが確立した一つの意志を意志する者となり、そのことによっていっさいの困苦を転回させることが君たちに必然の名で呼ばれるとき、そこに君たちの徳の根源は生まれ出たのだ。
手塚富雄訳「贈り与える徳」
───────────
自分自身を一個の運命のように受けとること、自分が「別のありかた」であれと望まぬこと──これが、そのような状態においては、偉大な理性そのものなのである。
『この人を見よ』「なぜわたしはこんなに賢明なのか」
───────────
人間の偉大さを言いあらわすためのわたしの慣用の言葉は運命愛である。何ごとも、それがいまあるあり方とは違ったあり方であれと思わぬこと、未来に対しても、過去に対しても、永遠全体にわたってけっして。必然的なことを耐え忍ぶだけではない、それを隠蔽もしないのだ、──あらゆる理想主義は、必然的なことを隠し立てしている虚偽だ──そうではなくて必然的なことを愛すること──
『この人を見よ』「なぜわたしはこんなにも利発なのか」
───────────
これらのすべて──栄養の選択、土地と気候の選択、休養の選択──について命令を与えるのは、自己保存本能であるが、それがまぎれもなくはっきりと現われるのは、自己防衛本能としてである。多くを見ず、多くを聞かず、多くを身辺に近づけぬこと──これが機略の第一であって、われわれが偶然的存在ではなくて一個の必然であることの何よりの証拠である。この自己防衛本能を通りのよい言葉でいえば、趣味である。この趣味の支配権は、然りということが「自己喪失」を意味するような場合に否と言えと命ずるだけではなく、否を言うことをできるだけ少なくすることを命ずるのである。つまり、年じゅう否をあびせる必要があるだろうようなものから、離れろと命ずるのである。どういう理由でそうしなければならないかといえば、防御のための出費は、どんなに少額ずつでも、常例になり習慣になると、はなはだしい窮乏、しかもまったく無用な窮乏を招くからである。
『この人を見よ』「なぜわたしはこんなにも利発なのか」
───────────
あふれる豊かさから生まれたあの最高の肯定の方式、つまり、苦悩や罪、生存におけるあらゆるいかがわしいものや異様なものに対してさえ留保なしに「然り」という態度、この二つのものの対立である・・・・・・こうした窮極的な、この上なく喜びにあふれた、過剰なまでに意気盛んな生命肯定は、単に最高の洞察であるばかりでなく、これはまた、最深の洞察、真理と学問によって最も厳正に是認され、支持されている洞察なのである。
『この人を見よ』「悲劇の誕生」
───────────
生のもっとも異様な、そして苛酷な諸問題の中にあってさえなおその生に対して「然り」ということ、生において実現しうべき最高のありかたを犠牲に供しながら、それでもおのれの無尽蔵性を喜びとする、生命への意志──これをわたしはディオニュソス的と呼んだのであり、これをわたしは、悲劇的詩人の心理を理解するための橋と解したのである。
『この人を見よ』「悲劇の誕生」
───────────
およそ存在するものであるかぎり、何一つ排除してよいものはなく、何一つ無用なものはない──それどころか、キリスト教徒やその他のニヒリストたちがしりぞけた生存の諸側面は、価値の順位からいえば、デカダンス本能があえて是認し、善と呼んできたものより、無限に高い位階をもっているのである。このことを理解するには、勇気が必要であり、その勇気をもつ条件としては、ありあまる力が必要である。
『この人を見よ』「悲劇の誕生」
───────────
ツァラトゥストラという典型における心理学的問題は、これまで人々から然りと言われてきた一切のものにたいして未曾有の程度で否と言い否を行なう者が、それにもかかわらず、どうして否定精神の正反対になりうるかということである。
もっとも重い運命、使命という宿命を負うている精神が、それにもかかわらず、どうして、もっとも軽快な、もっともこの世を離れた精神たりうるか──どうしてツァラトゥストラが一個の舞踏者でありうるか──ということである。
現実にたいしてもっとも苛烈な、もっとも恐ろしい洞察をしており、「もっとも深淵的な思想」を思想した者が、それにもかかわらず、どうしてそれを生存に対して異議を唱える根拠にしないのか、そしてその生存の永劫回帰に対してさえ異議を唱えないでいられるのか、──異議を唱えるどころではない、さらに進んで、自分があらゆる事物に対する永遠の然りであり、「巨大な無際限の肯定と承認」であるということの根拠を、どうしてそこに見いだしているのか、という問題である・・・・・・ツァラトゥストラは言っている。「どんな深淵の中へも、わたしは、わたしの祝福する然りのことばを運ぶ」と・・・・・・。しかしこれもまたディオニュソスの概念そのものなのである。
『この人を見よ』「ツァラトゥストラ」
───────────
しかし、わたしは祝福する者であり、「然り」の発語者である。おまえ、清らかなものよ、光にみちた空よ、光の深淵よ、おまえさえわたしの頭上にいてくれるなら、わたしは決して祝福することを忘れまい。──どんな深淵のなかへも、わたしはわたしの祝福の「然り」の発語をたずさえて行く。
手塚富雄訳「日の出前」
───────────
わたしはかれらにわたしが努力し専念していることのすべてを教えた。すなわち、人間において断片であり謎であり恐ろしい偶然であるところのものを、凝集し総括して一つのものにすることを。──
──凝集者として、謎の解き手として、偶然の救済者として、わたしはかれらに、未来の創造に従事すべきこと、そして、かつてあったすべてのものを、──創造によって救済すべきことを教えた。
人間における過ぎ去ったことを救済し、いっさいの「かつてそうであった」を創り変えて、ついに意志をして「しかし、かつてそうであったのは、わたしがそれを欲したのだ。またこれからもそうであることを、わたしは欲するだろう──」と言うにいたらしめることを、教えたのだ。
──このことをわたしはかれらにむかって救済という名で説いた。このことだけを救済と呼ぶように、わたしはかれらに命じた。
手塚富雄訳「新旧の表」
───────────
ツァラトゥストラはある箇所で厳密に彼の使命──それはまたわたしの使命だ──を規定している、だれもその意味を取りちがえることがないためにだ。すなわち、彼は、過去にあった一切のことまでも是認し、救済するほどに、肯定的なのだ。
わたしは、未来の断片としての人間たちのあいだを歩いている者なのだ。わたしが観るところのあの未来の。
そして、断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一つのもの』に凝集し、総合すること、これがわたしの努力と詩作の一切なのだ。
人間は詩人でもあり、謎の解明者でもあり、偶然の救済者でもある。もしそうでなければ、どうしてわたしは人間であることに堪えられよう。
過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること──これこそはじめて救済の名にあたいしよう(『ツァラトゥストラ』「救済」)。
『この人を見よ』「ツァラトゥストラ」
───────────
いっさいの『かつてそうであった』は、一つの断片であり、謎であり、残酷な偶然であるにすぎない、──だが、創造する意志は、ついにそれにたいして、『しかしわたしはそれがそうであったことを欲したのだ』と言うのだ。
──創造する意志は、ついにそれにたいして、『しかしわたくしはそれがそうであったことを、今も欲しており、これからも欲するだろう』と言うのだ。
手塚富雄訳「救済」
───────────
過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること──これこそはじめて救済の名にあたいしよう。
意志、──それが解放し、喜びをもたらす者の名だ。そうわたしは君たちに教えた、わたしの友人たちよ。
手塚富雄訳「救済」
───────────
勇気は最も優れた殺し屋だ。攻めてかかる勇気は、死さえ打ち殺す。というのも、勇気はこう語るからだ。「これが生きるということだったのか。よし、ならばもう一度!」
手塚富雄訳「幻影と謎」
───────────
まことに、わたしは百の魂、百の道、百の揺籃と陣痛を経てきた。わたしはすでに幾度もの訣別をした。わたしは胸も裂ける別離の最後の瞬間がどんなものであるかを知っている。
しかし、わたしの創造的な意志、わたしの運命がそれを欲するのだ。もしくは、もっと率直にいえば、そういうわたしの運命を、わたしの意志は欲するのだ。
わたしの感受性は、つねに悩み、牢獄につながれている。しかし、わたしの意欲は、つねにわたしの解放者、わたしに喜びを与える者として、やってくるのだ。
意欲は解放する。これこそ、意志と自由についての真の教えである。──ツァラトゥストラはそれを君たちに教える。
もはや意欲せず、評価せず、創造しない。ああ、こういう大きい倦怠がいつまでもわたしに近づいてこないように!
手塚富雄訳「至福の島々で」
───────────
これからも、たとえどんな運命や体験がわたしを訪れようと、──それにはかならずさすらいと登高とが含まれることだろう。われわれの体験とは、結局ただ自分自身を体験することなのだ。
偶然の事柄がわたしに起こるという時は過ぎた。今なおわたしに起こりうることは、すでにわたし自身の所有でなくて何であろう。
つまりは、ただ帰ってくるだけなのだ、ついに家にもどってくるだけなのだ、──わたし自身の「おのれ」が。ながらく異郷にあって、あらゆる偶然事のなかにまぎれこみ、散乱していたわたし自身の「おのれ」が、家にもどってくるだけなのだ。
手塚富雄訳「さすらいびと」
───────────
「いっさいの事物の上には、偶然という空、無垢という空、気まぐれという空、放恣という空がかかっている」「気まぐれ」──これは貴族の特性として世界最古のものである。これをわたしはあらゆる事物に取りもどしてやった。わたしはあらゆる事物を目的への隷属から救い出した。
手塚富雄訳「日の出前」
───────────
わたしは神をなみするツァラトゥストラだ。わたしはどんな偶然をもわたしの鍋で煮る。そしてそれが完全に煮えたとき、わたしはそれを歓迎する、わたしの食物として。
まことに、幾多の偶然が専横な態度でわたしのところへやってきた。しかしわたしの意志はいっそう専横な態度でその偶然を迎えた。──すると偶然は早くもひざまずいて哀願した。──
──つまり、わたしから情けを受けて、わたしのところに泊まらせてもらいたい、というのだ。そして媚びながら、偶然はせがんだ。「おお、見よ、ツァラトゥストラよ、ただ友だけが友をたずねるのだ」
手塚富雄訳「卑小化する徳」
───────────
かれらはわたしの出会う偶然と不慮の災難とをあわれみさえする。──しかしわたしのことばはこうだ。「偶然がわたしのところへ来るのを妨げるな。偶然は幼子のように無垢なのだ」
手塚富雄訳「橄欖の山」
───────────
──またおまえがわたしにとって神的な偶然が踊る踊り場であるということ、神的な骰子と神的な骰子遊びをする者にとっての神的な卓であるということなのだ。
手塚富雄訳「日の出前」
───────────
かつて創造のいぶきがわたしを訪れたとするなら、──偶然をも強制して星の輪舞を踊らせるあの至福の必然のいぶきがわたしを訪れたとするなら、──
わたしがかつて創造的な電光の笑いで笑ったとするなら(その笑いには、行為という長い雷鳴が、不平の声をとどろかせながら、しかも従順についてくるのだ)、──
わたしがかつて、大地という神々の卓で神々と骰子の遊びを競い、そのために地が震い、破れ、火の河流を噴き出すにいたったとするなら、──
手塚富雄訳「七つの封印」
───────────
【引用】
手塚富雄訳『ツァラトゥストラ』(中公クラシックス)Kindle版
手塚富雄訳『この人を見よ』(岩波文庫)Kindle版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
