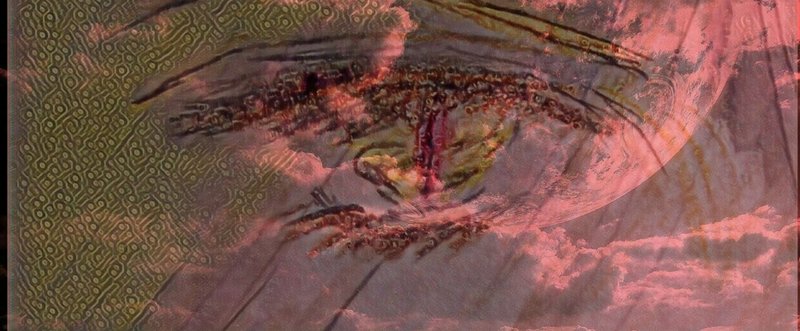
魔都に烟る~part30~
気がつくと、そこは見覚えのある一室。
ローズは長椅子に凭れかけさせられていた。
「……生きてる……?……何故……どうして私……?これは夢なの……?」
手で頭を押さえ、身体を起こしながら呟く。
夢であろうはずがない。壁や天井に走るヒビ、散乱した家具。屋敷のそこかしこに残る闘いの痕跡、それら全てが、あの出来事が現実であった、と物語っている。
━と。
「お気づきですか?ローズ様」
聞き覚えのある、落ち着いた声。
「……ヒューズ……?」
声の主を見遣ると、折り目正しく立っているヒューズの姿が目に入った。静かに近づいて来ると跪き、持っていたトレイから湯気の立つカップをローズに手渡す。
受け取ってひと口含むと、内臓を温める確かな感触。どう否定してもこれが現実であること、を否応なしに再認識させられ、そこで我に返る。
「……ヒューズ……レイは……?……レイはどこなの……?」
ローズの胸の中に、わかっていたはずの、しかし信じたくない予感が過る。
(……うそ……まさか、私だけが生き残ったの?……私のことも連れて行くって言っていたのに……最後に私を支えてくれた手はヒューズだったの……?)
半ば縋るような視線を向けるローズ。その顔を見つめていたヒューズは静かに答えた。
「あちらの部屋に……」
操られたように立ち上がったローズは、ヒューズの視線の先、隣の部屋へと駆け込んだ。
部屋の一角に置かれた椅子。そこにローズが求める相手の姿があった。
「……レイ……」
ローズの呼びかけに、ゆっくりと視線を向ける。その深い闇の色がローズを見つめた。
「……気がつきましたか?」
何も変わらない、何事もなかったかのような声音。しかし、なかったことではない。なかったことになど到底出来ない。
「……何故、私は生きているの?」
ストレートな質問に、レイの唇の端が微かに持ち上がる。以前なら腹立たしかったその表情。それが今は安心する材料となっていること、それこそが腹立たしかった。
「……全てを終わらせる、って言ってたじゃない。目的さえ果たされれば、私も思い残すことなんてないだろう、って言ってたじゃない……!ゴドー家も終わりだって……あれは全部ハッタリだったの!?」
何故、こんなことを問いただしているのか、自分でも不思議で堪らない。それでも、何か訊かずにはいられない衝動に突き動かされる。
一気に噴き出したローズの問いを黙って聞いていたレイの顔は、いつの間にか感情のこもらないものに戻っていた。
「……ハッタリ……ではありませんよ。ゴドー家はなくなります。……いえ、なくします……一切を」
「ならば、何故……!」
ローズの言葉を手で制し、レイはローズを椅子へと促した。渋々、座ったローズの目を、レイが真っ直ぐに見つめる。
「……これから、きみにはこの屋敷を出てもらいます。……ヒューズと共に……彼が連れて行く場所に」
「……私にだけ、ここを出ろと?どこへ行けって言うの!?それであなたはどうするつもりなの!?」
自分には何も言う権利などないことは充分にわかっていた。だが、それでも言わずにはいられない何かが、ローズの気持ちを昂らせる。
「……アシュリー子爵がお待ちです」
「……!……叔父様が……!?」
ローズの胸にこみ上げる懐かしさと思慕。父に良く似たその人の優しい声と眼差し。父を喪った日から、ずっとローズを守り、支えてくれる存在であった叔父。
「子爵は何年もずっと、きみを秘密裡に捜していらしたのです。きみと会う以前、私も何度か相談を受けていました」
ローズの身体が震える。
「事情を記した手紙をヒューズが届けたところ、すぐにでも確認しに行きたい、と。必ずお連れする、と約束して思い留まって戴きましたが、今か今かとお待ちのはずです」
ローズは言葉を発することが出来なかった。身体も小さく震えるだけで、螺子が切れたように動かない。
「アシュリー家に戻って全てを忘れなさい。そして、きみにとって当たり前であったはずの生活に戻るのです。これからは隠れて生きる必要はないのですから」
何も含んでいないレイの目と声。
(……レイ……あなたは……?)
それは言葉にはならず、ローズはただ、湿度を帯びた瞳で見つめ返すしか出来なかった。
「……ヒューズ。後を頼む」
「はい、セーレン様。……さあ、ローズ様」
答えたヒューズがローズの腕を掴んで促す。ヒューズに手を引かれ、ローズはまるで人形のようにただ足を動かしていた。
「……待って……待って、レイ……あなたは……あなたはどうするの……?……これから……」
扉の方に手を引かれて行くローズが、身体を捻りレイを振り返りながら問う。
「……私にはまだやることが残っています。さっききみが私に訊ねたことの答え……全て終わらせること、が」
その言葉の意味するところは一瞬で理解出来た。
「……レイ……」
言うべき言葉が見つからず、ローズは引きずられるように扉まで連れて行かれていた。空いている手で扉に掴まり、レイの方を見返す。
「……さようなら……ルキア」
一番、見慣れたはずの表情。一番、聞き慣れたはずの声。だが、呼ばれ慣れた名を呼ばれることはなく、わかれの言葉だけが告げられた。
「………………!」
時が止まったような刹那、何かを言おうとして声にならず、静かに扉は閉められた。
そのまま、ヒューズに半ば強制的に馬車に乗せられる。乗り込む直前、屋敷を見上げると、窓ガラス越しにレイが立っている。見送るように。
「さあ、ローズ様」
そう促されて押し込まれ、扉が閉まるまでのほんの数秒、絡み合う視線。
走り出す馬車の窓から、身を乗り出すようにして目に焼き付ける。
ゴドー伯爵の屋敷と、その屋敷の主、を。見えなくなるまで。
その様子を眉ひとつ動かさずに見つめていた屋敷の主は、走り去る馬車が見えなくなると、部屋の中心に立ち、目を瞑って左手を宙に掲げた。
「神宿る左が命じる。ゼロ宿る右よ……あるべきものをあるべき処へ還し、あらざるべきを終焉に導け……その禁忌を以って理の起点へと」
そう唱え、瞑目を解くと、その漆黒の右目の中心が黄金に輝く。
掲げた掌の上に焔のようなものが揺らめいた次の瞬間、何ら火の気がない屋敷の至るところから、突然、そして静かに、小さな炎が立ち上がった。
その小さな火の手は、次第に広がって大きくなって行く。
しばらく立ち尽くしていたレイは、何事も起きていないかのように、先ほどの椅子へと腰かけた。宙を見据えるその右目には、既に元の漆黒の艶めきが戻っている。
しばらく、何かを思い描くように宙を見つめていたレイは、やがて静かに目を閉じた。全てを終えて、全てを遮断するかのように。その目を開くことは二度とない、とでも言うかのように。
*
━どのくらいの時間が過ぎたのか。
眠っていたのか、何かを考えていたか、呼吸の動きさえわからぬほど静かに目を閉じていたレイは、ふと、気配を感じ、再び固い瞑目を解いた。
ゆっくりと気配の出処に視線を動かし、その瞳が驚きに見開かれる。
扉の傍に立っていたのは、息を切らせたローズであった。アシュリー子爵に会うために着替えたのであろう衣装も、整えた髪の毛も乱れ、かなり走って来た様子が窺える。
ローズの背後、室外には既に炎が広がっている。気休めとわかっているのか、いないのか、ローズは扉を閉め、僅かばかり炎を遮断した。
無言で見つめ合う中、こんなに驚いたレイの顔を見るのは初めてかも知れない。ローズは心の中で思う。もちろん、他の人間と比べたら、ほとんど変化していない程度ではあるが。
「……ルキア。何故、ここに?ヒューズはどうしたのです。アシュリー子爵が何と言われるか……」
レイの言葉を受け、ローズは呼吸を整えながら静かにレイに近づく。
「……叔父様には手紙を書いたわ。ヒューズに無理を言って預けたの」
ローズは坦々と告げた。
「……何故、戻ったのです?」
静かなようでいて、レイの口調が少し強くなったのがローズにはわかる。━が。
「……まだ私の目的が果たされていないから」
「……目的?きみの目的は果たされたはずです。これ以上、何をどうしようと言うのです?」
ローズは強い視線でレイを見据えた。
「……私の最後の目的……それは、自分の屈辱を晴らすこと……この手であなたの首を掻くことよ」
一瞬、レイが全ての機能を止めたかのように固まったのがわかった。しかし、それはすぐに解消され、口元にはあの見慣れた笑みが浮かぶ。
ゆっくりと立ち上がり、レイはローズと向き合った。面白がるような、嫌味を含んだその笑みを、ローズは精一杯の上目遣いで威嚇する。
「……無駄なことを。きみが手を下さずとも、直にゴドー家は消滅すると言うのに……」
「そんなことわからないじゃない。あなたのことだから、消えたと見せかけて、どこかに逃げおおすかも知れないわ。この目で見届けなければ信じられない」
ローズの反論に、レイは「やれやれ」と言った体で肩をすくめるが、面白くて堪らない、と言う様子も同時に滲み出ていた。
「……それでは、はっきりと言いますが、よしんば私が逃げたとして、どれだけ頑張ろうと、きみの力では私には勝てませんよ……例え100年かけても、ね」
ムッとした表情を浮かべたローズがレイににじり寄り、睨み上げる。
「あなただって四六時中緊張している訳ではないでしょう?絶対に油断する時があるはずだわ。……その時を見逃さずに、必ず寝首を掻いてやるわ」
ローズが言い放った瞬間、レイの唇の端がさらに持ち上がった。
右手でローズの顎をゆっくりと掬い上げる。
「……なるほど。では私は、きみに寝首を掻かれないよう、きみが寝首など掻けないよう、毎夜、頑張らなければならない、と言うことですね」
「……?……何を言って……」
瞬間的に言われた言葉の意味がわからずローズは固まった。しかし、脳内の伝達機能が動いて行くにつれ、レイが言わんとしている意味に気づき、徐々にその瞳が見開かれ、羞恥と怒りで顔が火照る。
「……ふざけないで!」
顎を掬うレイの手を振り払い、ローズは勢いよくレイの身体を押し遣った。椅子に倒れ込んだレイにそのまま圧し掛かり、その首に細腕を押し付ける。
「……さて、これからどうしますか?その細腕で私の首を絞める?」
言いながらローズの腕を掴み、もう片方の腕は腰を捉えた。明らかに楽しんでいるのがわかるレイの表情と口調。
「それでは『力』を使うまでもなく、きみに勝ち目はありませんよ」
「……甘くみないで!」
叫んだローズが腕に力をこめた瞬間、天井から煙が漏れ出し、次いで扉が燃えて炎と煙が吹き込んだ。あっという間に燃え広がり、部屋中が炎の紅と煙で充満する。
炎と煙が烟る中、霞む二つの影が滲み、揺らめくようにひとつに重なった……かに見えた瞬間━。
部屋の天井が崩れ落ち、屋敷中が炎に包まれた。
*
ゴドー伯爵の屋敷は数日間燃え続けた。
領内の住民が出火に気づいた時には、既に屋敷全体が炎に包まれ、消火のしようがなかったらしい。
いや、厳密には、消火しようと屋敷に向かった者たちは、ある信じられない現象に遭遇したのだ。
不思議なことに、住民が屋敷に近づこうとすると、何故か、一定の場所からは近づくことが出来ず、元来た場所の何れかに戻ってしまっている、と言う現象に。
ひたすら燃やし尽くすように赤く染まる屋敷を、住民たちは、ただ見守るしかなかったと言う。
火が沈静化し、燻りも収まった頃、ようやく住民は屋敷に辿り着けるようになったが、既に全てが燃やし尽くされ、燃え落ちた瓦礫以外は跡形もなかった。
そして、さらに不思議なことに、焼け跡からは、ゴトー伯爵や婚約者ローズ嬢はおろか、あれだけいた使用人の遺体ひとつ見つからなかったと言う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
