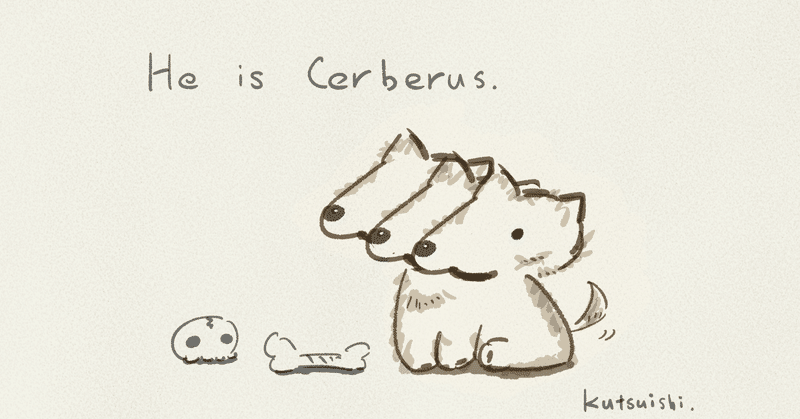
犬は死なない犬死にの歌【前】
※この記事は逆噴射小説大賞2023年に応募した小説作品の、800字より先を書いたものです。なお、犬は無事です。人間も無事です。
責任と愛をもつ飼い主達と、飼われる生物達に幸あれ。
1
センパイは吠えた。低く短く、人間も本気で犬の吠え真似をするとこんなにも似るのだなあという迫真の『バウ』であった。そうして通りすがりの犬に怯えられていた姿を、僕は曲がり角の影で目撃していた。明るい満月の夜だった。犬に逃げられたセンパイの背中は、妙に物悲しそうに曲がっていた。しかし、センパイと犬にまつわる接点といって思いつくのはその程度だ。今夜、センパイから話しかけられるまでは。
「犬が死ぬ歌って、許せなくないか」
バックルームからレジ側に出てきたセンパイは突然、真面目な顔で相談してきた。雑談として処理するにはあまりにも真剣な様子であった。
「なにを急にそんなことを」
内心、人だろうが犬だろうが、猫でもサメでもそれが歌の展開として必然か必要なら死ねばよい、と思う僕はなんとも返事がしづらかった。娯楽というのはなにをしても嘘なので、犬を銃で撃とうが許されているはずだ。
「街中で流行りの歌が流れてきたなあと思って、どうも犬の歌らしくかわいいなあと思ってね、歌詞をよくよく聞き取ってみたら最後に犬が死んでいたんだよ。不意打ちもいいところだ。犬が好きだからこそ真面目に聴こうとしたのに」
気の毒な事故にあったような話ではある。
「先輩が犬派なのはよくわかりました。飼っているんですか?」
「子供のころから喘息やアレルギーがひどくて、親には生物を飼うのを許されなかった。おれはすべての犬を飼い、飼い犬に愛される者にうらやましさと妬ましさを覚えている」
「そんなに?」
「だからねえ、歌でも犬が死ぬのを何度も聞くのは、あまりにもつらいんだよ」
センパイの顔色は土気色である。元々深夜帯バイト達の顔色といったら夜型らしい青白い肌ばかりだとは思うが、それにしたって具合悪そうではある。僕ですら、なにか慰めになる話でも投げかけるべきだろうと考えてしまうぐらいに。
「犬殺しが死ぬ歌でも流行れば、架空の犬も死ななくなりますかね」
そこではっきり僕に振り向き直ったセンパイは、なぜか今にも泣きそうな顔をしていた。
「人も死なないし犬も死なない平和な解決策がいいなぁ!」
面倒くさかった。とはいえセンパイが博愛主義である可能性を考慮しなかった僕も悪い。僕ときたら昔から、油断すると思ったことはよく考えもせずに口に出す節がある。一昨日も四つ歳上の姉に『体形が変わったかどうか』などと尋ねられたから、正直なことを言ってみて理不尽にもしばかれたばかりだ。
まあいいだろう。外はどうも雨が降り始めて、いよいよ客も来そうにない。普段は手の回らない棚の裏の掃除だとか、客のいない間にやった方がいいことは山ほどある。だがそれよりも架空の犬とセンパイのメンタルを助ける方法を真面目に考えようじゃないか。
「勧善懲悪はウケがいいと思ったんですけどね。それに架空でやるからこそ、犬を大事にしないやつから殺ッたるぜ! ぐらいの強い気持ちであたっていくのは必要なんじゃないかとか」
「悪を叩きたいのではなくて犬を助けてほしいだけだからね、おれは」
なんだかんだセンパイも雑談に乗り気であった。
「……でも、犬が可哀そうな歌よりは、犬がひたすら可愛い歌が流行ったらいいっていうのは、そうかもね」
「そうですよ。だから先輩が非業の死から犬が復活するようなハッピーな歌をつくればいいんです。そして公共の場でリクエストされるぐらい流行らせれば、許せないぐらい悲しい歌で死ぬ犬はいなくなるんです」
「相当無茶言うよな、西戸野くんも」
失笑かもしれないが、センパイの気分はいくらか緩んだらしい。僕だって本気でセンパイが犬の歌を作りはじめて、あまつさえ世界に流行らせるなんて思っていない。そのぐらい世の中がちょろいならなによりなのに、とは思うけれど。我々は犬の雑談を交えながら、なあなあのままの仕事をほどほどのやる気で再開しはじめる。
センパイが許しがたいのが犬の非業の死なら、僕が許しがたいのは陳列した食品をわざわざ後ろ側から取っていく客かもしれない。日付が変わると同時に廃棄になるデザート類を、雑にカゴに放り込みながら考える。
まだ消費できそうな食品を、この手で毎回大量に捨ててしまわなければならないなんて、コンビニバイトを始めるまでは考えもしなかった。最近は『食品ロスを防ぐために手前から品物を取るようご協力ください』と書いてある札が、値札と同じところでかでかと提示してある。それでも賞味期限の新しい後ろ側から品を取る客は減らない。人類は愚かだ。
「先輩は犬が死ぬ悲しい歌は許せないけど、歌ってる人とかをどうこうしたい訳じゃないらしいですね。でも実際に、実在の犬を虐待したり無責任に捨てる人間が目の前にいたら滅びるべきだァ――って考えます?」
「ううーん」
「襲っても犬のためなら罪に問われないなら?」
「それはひょっとして襲ってしまうかもしれない」
「実は先輩、犬の幸せのためなら人類は滅びた方がいいぐらいの過激な犬派だったりしません?」
「それは」
ホットスナック棚と向き合っていたセンパイはふと黙って、考え込んでしまった様子だった。また無暗に過激な話題の提示をしてしまったのかも、まるで誘導尋問のようにセンパイから過激な発言を引きずり出そうとしてしまったかも、などと僕はちょっと後悔した。そしてセンパイは、ゆっくり話し始めた。
「うん……でも、結局おれの愛する犬の姿というのは――」
話の続きは、だしぬけに鳴った入店ジングルで邪魔された。冷たい夜の雨でずぶぬれの客がひとり、店の中に入ってきたのだ。
「……いらっしゃいませ」「っしゃいませー」
センパイはジングルから遅れ、僕はセンパイから遅れて挨拶する。お客の服は上下真っ暗、ただし肩にかかった反射材タスキがぴかぴかと光っている。フードを目深に被っているため表情はうかがえないが、店員である我々の方をまっすぐ見てきた。だから買い物が目当てではないだろう、それがすぐわかった。
「あの、すみません」
荒れた息遣いと、かすれた声が、妙に怖い。
「すみません、そこの道路で犬が通りかからなかったか、見かけませんでしたか……」
客の握りしめられた片手から垂れているヒモは、きっと犬の首輪と繋がるリードだった。深夜手前のコンビニエンスストア。根暗な顔つきの男どもで、偶然にも犬を巡るトライアングルが完成した。実物の犬は一切、目の前に出てこないのに。
2
なんなら『僕には関係ないね』と切り捨ててもいい話だが、ともかくこの職場は犬過激派のセンパイには物憂い環境になってしまったことだなあと、出入り口に掲示された迷い犬のポスターを眺めながら考える。写真の中の黒くてふわふわな元ちゃんは、どことなく利発そうな顔つきでこちらを振り向いていた。
あの晩、かなり不審な客として登場した叉科囲さんは、翌日の昼になって再びこのコンビニを訪れたそうだ。彼は店長に『迷い犬探しています』のポスターを渡してきた。迷い犬ポスターはセンパイが店長に頼み込んだ甲斐もあったらしく、このように目に留まりやすい場所に張り出されている。しかしこの三日間、元ちゃんの居所について進展はない様子だ。こうしてポスターが貼られたまま、むなしくも変化がないのだから。
犬好きのコンビニストア店員にとって、悲しい出来事がもうひとつある。センパイが怨んだと思しき犬の歌は、人気歌手が歌っていた。歌手はこのコンビニチェーン販促部とタイアップしたようで、一時間に一回ぐらいの頻度で歌手のベストアルバム発売記念メッセージが店内放送で流れることになった。そのコマーシャルの裏で、犬死にのある歌のイントロ部分が流れてくるのだ。
センパイは曲名こそぼかしていたが、昨日になって歌詞を調べてみたところ、この歌の話で間違いない。さすがにサビ後半の直接的に犬が死ぬあたりは直接流れてこないが、おそらくセンパイはイントロを聞くたびに、犬の死ぬ部分を想うだろう。愛する者の死が職場にいる限り絶え間なく流れてくるのは、間違いなく苦痛ではないだろうか。
「次の方、こちらのレジにどうぞ」
客として菓子パンとアールグレイティーを買いに来た僕の眼前に、センパイは立っていた。センパイの顔色は、暗い。
「いらっしゃいませ、レジ袋はおつけいたしますか?」
「じゃあSサイズひとつお願いします」
センパイが落ち込んでいるかは正直よくわからなかった、顔が暗いのはいつも通りだからだ。そりゃあセンパイもいい大人だから、犬死にの歌に動揺しようがそれを隠して平時通りの仕事はできるだろう。何回もイントロが流れてくるうちに慣れることもできるだろう。それにこの店では店長もだいぶ生気のないおじさんのせいなのか、表情筋が死んでても声さえ出ていれば許されている節がある。僕にとってもありがたい話である。
僕はセンパイの手元と『とらみつ』と大きく文字の書かれた名札を眺めた。名札に印刷されたセンパイの顔もやはりというか、うっすらほほ笑んではいるものの不気味だ。そういえば、犬派だけど虎がいるな……と、ぼんやりしていたところに、急に名前を呼ばれた。
「西戸野くん」
「えっ?」
「帰り道、気をつけなよ、もう暗いから」
「……あ、え、どうも」
「ありがとうございましたー」
🐕
なんださっきの。
たぶん、客としての対応の間に知り合いとして世間話された、ということにしていいのか。コンビニを出てから考えながら歩いている。もしかして僕のぼんやりした雰囲気が迷子の犬と同レベルだから声をかけられたのかも。そうだったらちょっと嫌かも。
わざわざ声をかけられる、まっとうな理由は思いつく。この辺りは五年や十年ぐらい昔から、『人が消えやすい』と聞く。どうしてなのかはわからない。まあ、単なる偶然でしかないんじゃないか、と僕は考えている。自動車事故がちょっと他より多いぐらいの、点集合の外れ値のような地域。
少なくとも最近は、町内の防災放送で行方不明になった人のお知らせなんてのも聞かなくなった。とはいえ僕が子供のころは、たしかに放送は多かった。依然としてこの地域の人々はうっすらとした警戒が日々のしぐさに根付いていて、気がついた時にお互い声を掛け合う。そういうところは、あるかもしれない。
『住宅街付近の深夜コンビニでワンオペでも十分回せるのに、ほとんどの場合二人がシフトに入れられるのって、やっぱりなにかに用心しているんじゃないかなあ。なにかが何なのかは誰も知らないのにね』
ほとんど僕と入れ違いになるように辞めていった方の先輩が、夏場の夜におどろおどろしく話したのを覚えている。もう名前も顔もおぼろげになっているけれど、妙に生々しく話すものだから、忘れられずにいたようだ。創作怪談として聞くなら結構怖かったし、世間話として聞くなら程よくどうでもよく、当時の僕はとりあえず相槌を打っていた。
『この辺なんて犬飼ってる家やたら多いじゃん? それも室内飼い向けの小型犬じゃなくて、中型のが特にさ。俺の親世代あたりが、番犬として飼い始めたんだと睨んでいるよ』
僕は、番犬の最期についてよくないものを連想しそうになる。そういえば、なぜしょうもない死にざまのことを『犬死に』と呼ぶのだろう。ちゃんと見たことはないけれど、たとえば世界名作劇場のフランダースの犬は役に立って死んだと思う。主人を死から助けることはできなかったけれど、孤独に死なせることなく最後まで寄り添ったのだから。
そこで僕の頭の中では、少年とその飼い犬が倒れ伏す背景の陰からぬっと現れるや否や、『死なない方がいいんだけどなあ……』とつぶやく架空の虎三津センパイが生えてくる。そんな流れからふと、思いついた。
架空の犬が……もっとわかりやすくイメージしていこう。三つ首の犬が、地獄の門の前で自らの尻尾をおいかけて、くるくるくるくる回っている。これが急に現れたる英雄にさっくり倒されたのなら、僕もそこまで悲しくはない。けれど飼い主である冥府の番人との絆を描写されたあとで倒されるなら、たぶん悲しくなると思う。
だがセンパイは、英雄が出てきたあたりの不穏な気配で早くも『やめてくれぇ!』と叫びだす。そして歴史の中で人間がいかに犬を愛してきたか、犬が人間を愛してくれたか英雄に説き伏せるのだ。センパイは犬も人も平和な方がいいと考えている。甘ったれた考え方が、そして世の中のほとんどがその甘さを許さないだろうという仮想が、両方とも妙に僕の気持ちを、ざわざわと腹ただしくさせる。
嗚呼、いぬ犬いぬイヌ……。
しまった、気がついたら帰り道のほとんどを犬の事を考えながら歩いていた。というか最初に何を考えていたか犬のせいですっかり忘れた。秋の日暮れはとても早く、家を出るころはまだオレンジ色に照り返していたはずの道は暗い。
顔を上げると暗がりの向こう側から、犬と人が連れ立つ影があった。僕はそれらを避けるように脇道に逸れた。路地の道は狭いから、この方が向こうも歩きやすいだろう。犬の行動なんて僕には読めないから、リードが届かないぐらいのところで邪魔しない方がいい。
(ん?)
じわりと、よくわからない胸騒ぎがあった。それは、おばあちゃんが黒っぽい犬を散歩させている、ごく普通の光景でしかないはずだ。犬とおばあちゃんは僕のそばを横切って、向こう側へ歩いていく。犬は黒ビーグル犬似の中型。街灯に照らされた尾のあたりに特徴的な模様あり。よく似た犬を最近見た。暗がりだから確信はない。気のせいだと思いたい。え、いやだって、そんなことある?
(……犬泥棒?)
不穏な単語とともに、擬人化された二足歩行の犬が唐草模様のほっかむりと風呂敷を背負っているイメージも横切っていく。それはたぶん泥棒犬。ふざけている場合ではない。だが冷たい宵の空気にさらされているのにも関わらず、首の後ろに嫌な汗まで出てきた。
そうとも。僕が恐れるべきは町の気味悪い空白なんかより、タバコの番号を言わずにキレてくる恐喝客とか、道路交通法を無視する自動車とか、人の犬を盗んでしれっと散歩までさせるような現実の人間達の方だった。後者の方がよっぽど遭遇率が高いのだから当然だ! いるかどうかもわからない何かより先に、身の回りに想像の下の下をはるかに下回る下劣な人間は確実にいるんだから!
僕は声をかけようと思った。どうやって? 『それは盗んだ犬ですか?』なんて聞いたら馬鹿じゃないか。じゃあ、警察に電話すればいいんじゃないか? いや、というか、あれだけ似た犬がいたらすでに近所の人が通報しているんじゃないか? 急に犬が増えたらその近所の誰かが気がつくはずだ。 それとも世間は迷い犬に関心なんてほとんどないのだろうか? そもそも犬はおとなしい、単なる見間違いのほうがよっぽど可能性が高いじゃないか?
ワァーッとうるさくなる頭の中とは正反対に、僕の体は固まっていた。僕は、ただただ犬を見送る不審者に成り果てていた。
黒犬はゆっくり見えなくなっていく。僕は結局、おばあちゃんに声をかけるのを諦めた。眼を背けて家に帰っていった。あれは他犬の空似で、正真正銘おばあちゃんの犬に違いないと、自分自身に言い聞かせながら。
🐕
さらに三日が経った。コンビニの出入り口に貼り出されている迷い犬ポスターに、変化はない。
パワーがほしいです。面白い話だったな、とか頑張ってやっていって欲しいと思ったら是非サポートお願いします。
