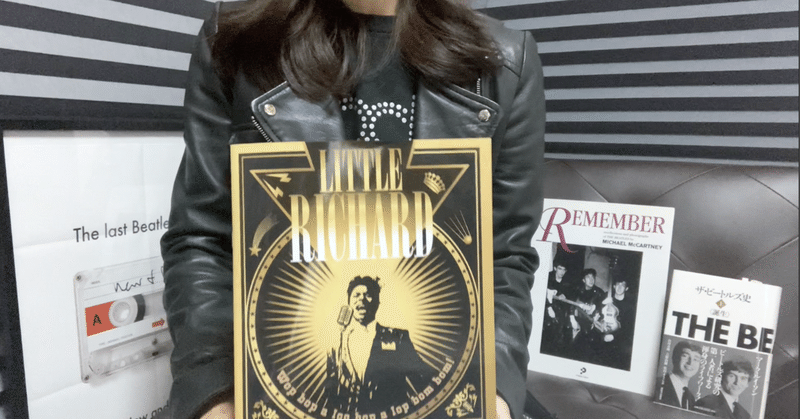
リトル・リチャードとロックンロールとビートルズ
気忙しい新年度ですが、スーパー・ビートリーなニュースが届きました!
マイケル・リンゼイ=ホッグ監督制作の 1970年のビートルズ公式映画『Let It Be』のレストア版が、ついに2024年5月8日(水)からディズニー・プラスで配信されることがアナウンスされました。
当初ピーター・ジャクソン監督のドキュメンタリー『The Beatles: Get Back』公開後に『Let It Be』もAI技術 ”MAL” でクリーンになって公開される予定だと報じられていましたが、ここ最近続報が途絶えており、お蔵入りになってしまうのかとヒヤヒヤしていました。
しかしここにきてやっと、私たちファンは 元祖『ビートルズの解散物語 Let It Be』を美しい映像と音で体験することが叶いそうです。
ひとまずディズニー・プラス独占配信ということなので、心待ちにされていた方はディズニー・プラスに加入して待機しましょう!
前置きが長くなりましたが、先日ビートルズも多大な影響を受けたリトル・リチャードの伝記映画『リトル・リチャード:アイ・アム・エブリシング /Little Richard: I Am Everything』を観ました。
リトル・リチャードについては、ビートルズがカバーしているいくつかの楽曲と、10代のビートルたちがとてつもなく大きな衝撃を受けたというような大雑把なイメージしか持っていませんでしたが、今回この映画を鑑賞することで、彼の素晴らしさや苦悩などを様々な角度から知ることができ、またそれにより改めてビートルズの魅力についても思いを馳せることができました。
そこで良い機会なので、リトル・リチャードとビートルズを繋いだロックンロール、そして彼らの交流についてまとめてみることにしました。
I AM EVERYTHING

まず、映画『リトル・リチャード:アイ・アム・エブリシング 』。
とても素晴らしい作品でした。
リチャードが実際に語る映像と彼と交流があった人たち、そして現代の歴史や文化の研究者たちのインタビューを軸に構成されていますが、とにかくリチャードの演奏とおしゃべりのシーンはどれも魅力がエクスプロージョンしていて本当に凄まじいパワーとエネルギーを持った人だったんだなと体感できました。
パンフレットにもミック・ジャガーを筆頭に、ポールやジョン、リンゴ、ボブ・ディラン、デイビッド・ボウイからブルーノ・マーズまで、リトル・リチャードを称えるたくさんのアーティストのコメントが掲載されており、劇中でも多数のアーティストが登場し彼を称賛しています。
リトル・リチャードは自ら「自分は革新者で創始者で解放者で、ロックンロールの設計者である」とたびたび語っていますが、彼に憧れ彼に続いたアーティストの言葉や音楽からも、それが単なるリチャードのビッグマウスなどではないことが理解できます。
また彼は自分のことを「美しい」と連呼しますが、それもまた正しいといくつもの画像や映像を見て納得しました。
ポールが、ハンブルクでの彼との共演を回想し、楽屋で準備を整えたリチャードが鏡を見て「美しすぎてどうしようもないな」と言っていたというエピソードを残していますが、その様子を立体的に想像できるようになりました。
才能に満ち溢れ型に嵌まることのなかったリトル・リチャードでしたが、黒人で且つゲイであるという属性により、その評価や対価は本来与えられるべきものよりずっと小さく、彼の苦悩を知るほどに、それでも歌い続けたリチャードを想い苦しくなります。
リトル・リチャードは彼以前の音楽からロックンロールを “設計” し、続く者たちのために道を切り拓いた功労者に違いありませんが、でも一方で彼自身は最後まで解放されることはなかったのかもしれません。
リトル・リチャードとビートルズ
そんなロックンロールの帝王リトル・リチャードは、我らがビートルズとどんな関わりを持っていたのでしょうか。
簡単に時系列にまとめてみました。

ジョン、ポール、ジョージ、リンゴとも折に触れて彼への敬意を口にしていますが、1957年の歴史的なジョンとポールの出会いの際にもリトル・リチャードは大きく絡んできます。
二人が始めてお互いに言葉を交わしたのはジョンの当時のバンド “クオリー・メン” がリヴァプールのセント・ピーターズ教会でライブを行った日で、二人の共通の友人によって引き合わされました。
ジョンのいい加減な歌とギターとそのカリスマ性に圧倒されたポールでしたが、一方のポールもこの日ジョンに強烈なインパクトを与えています。
クオリー・メンのライブの合間にメンバーと音楽の話で盛り上がったポールは、彼らの前でギターと歌を何曲か披露したとされています。
その際ポールがピアノを弾きながら熱唱したリトル・リチャードの “Long Tall Sally” はこの日ジョンに衝撃を与え、またその後結成されるビートルズにとっても重要なレパートリーのひとつとなっていきます。
人種差別や同性愛者への差別が酷かった時代に、世界的なバンドへと成長していくビートルズが、イギリスで、そしてアメリカでこの黒人でゲイという性的マイノリティであるリトルリチャードの “Long Tall Sally” をシャウトし続けたことは、リチャードに解放されたリヴァプールの4人の若者たちが今度は60年代の人々を多くの足枷から解放していった象徴のようにも思えます。
そんな憧れの存在であるリトル・リチャードとビートルズは、ステージで何度か共演しています。
リトル・リチャードはその天性の才能に加え、1955年自らの内に秘めた衝動を爆発させた “Tutti Frutti” を発表しブレイクした後、ヒットを連発し世界を股に掛けてロックンロールを演奏して回ります。
1956年にアメリカで製作された音楽映画『女はそれを我慢できない / The Girl Can’t Help It 』でジーン・ヴィンセント、エディ・コクラン、ファッツ・ドミノなど当時のロックンロールスターと共に登場したリトル・リチャードは、タイトルソングも担当しています。
若きビートルたちもこの映画にすっかり夢中になり、また1968年のホワイトアルバム制作中にイギリスで初めてテレビ放送された時には、レコーディングを中断しポールの家で仲良く映画を鑑賞してからアビーロード・スタジオに戻ってレコーディングを再開、その時の雰囲気は非常に良いものだったと言い伝えられているように、4人にとってもバイブル的な作品だったようです。
そんな人気も実力も絶頂だった1957年、リトル・リチャードは搭乗したオーストラリアへ向かう飛行機のエンジンが炎上し、その後火の玉を見るという体験を受けて、それらの現象は『悪魔の音楽』であるロックを演奏し続けている自分に対する神の怒りであると感じ引退を表明。
そして、聖職者への道へ進むため神学校で学んだ後牧師となり、その後は伝道活動に従事しながらロックンロールを封印し、ゴスペルを歌っていました。
しかし、金銭的な理由などから1962年に音楽界に復帰、ヨーロッパでライブを再開します。
それを鷹のような鋭さで狙っていたのがビートルズのマネージャーになったばかりのブライアン・エプスタインでした。
彼はビッグネームとビートルズを同じステージに立たせることで箔をつけ彼らの知名度を上げるべく、リトル・リチャードとビートルズが共演するライブをセッティング。
それが1962年の10月のビートルズのレコードデビュー直後に行われたNEMS企画 ”リトルリチャード・アット ザ・タワー” でした。
ニューブライトンのタワー・ボール・ルームで10月12日に行われたリトル・リチャードのイギリスでの復帰公演は、リチャードへの出演料や会場使用料・広告費などで出費が嵩んだものの5時間半におよぶ素晴らしいショーとなったようです。
前座はビートルズやビリー・クレイマー、ローリー・ストーム&ザ・ハリケーンズなど合計11組。ビートルズの出番はリチャードの直前でした。
また、出演したバンドのひとつ・リーカーティス&オールスターズのメンバーだったピート・ベストとは、8月にビートルズが彼をクビにして以来の再会となり、かなり気まずい空気が流れていた模様です。
マージービート誌用のビートルズとの記念撮影にも快く応じてくれたリトル・リチャードはインタビューの中で「(ビートルズは)姿を見ないと白人だとは思わない!正真正銘の黒人サウンドを持ってる」と称賛したと記録されています。
またリチャードは特にリンゴのことがお気に入りだったようで、ステージから何度もリンゴに向かって笑顔を見せていたと『ザ・ビートルズ史(マーク・ルイソン著)』には書かれています。
その後、ブライアン・エプスタインは10月28日にもビートルズ自身も初めてのステージとなるエンパイア・シアターでのショウを企画し、再びリトル・リチャードとボーイズを同じステージに立たせています。
この時エプスタインに尊大な態度を取られたリチャードは彼にイラついていたようですが(※詳細は記事末尾のYouTube動画で紹介しています。ご興味があればご欄ください)、一方で前回のタワーボールルームのショーの時に一緒に撮った写真を渡しに来たビートルズに対しては「 “Love Me Do” は素晴らしいと思う。君たちのようなサウンドを出す白人は非常に少ない。アメリカでビッグになれるはずだ」と語りかけたというリチャードの寛容さが窺えるエピソードも残っっています。
またリチャードは、「ポールとは強い絆で結ばれ兄弟のように親しくなったが、ジョンは嫌な性格なのであまり仲良くなれなかった」「ジョンは楽屋で臭いオナラをするのが嫌だった」みたいなことも言っていたようで、ジョンが嫌われすぎていてちょっと笑えます。
一方のジョンはこのレジェンドとの光栄な共演に関して「初めて会った時、畏敬のあまり硬直してしまった」「僕ら4人は偉大なロックンローラーを生で見られるだけでもワクワクしてたんだ。憧れの存在だった」と後に語っており、彼らが楽屋で絡んでいる様子を想像するとニヤついてしまいます。

そんなこんなで調子に乗ってリチャードをイラつかせていたエプスタインは、1962年11月のビートルズの4度目のハンブルク巡業でもリチャードとビートルズが共演できるよう手配しています。
映画の中では「リトル・リチャードがビートルズをハンブルクに呼んだ」というような表現がなされていたような気がしますが、アンソロジー本の中でジョンも「ブライアンがリチャードを連れて行った」と言っていて、また、ビートルズのハンブルク巡業は既に5回目まで日程が決まっていたんじゃないかと思うので、個人的にはリチャードがビートルズをハンブルクに呼んだ訳ではないんじゃないかなと思います。
ビートルズがハンブルクでリトル・リチャードと過ごしたこの経験は、多分ブライアンが目論んでいたよりずっと4人にとって大きく実りのあるものだったはずです。
派手な化粧をして最後は海水パンツ一枚になりながら演奏する彼のエネルギーに満ち溢れたパフォーマンスを毎晩間近でみることができ、楽屋も入らせてもらってステージ前の彼の様子を眺めたり聖書を朗読してもらったり、若かりし4人はリチャード牧師とのロックンロールな日々を満喫しています。
リンゴは「彼は僕らがステージの袖にいるか気にしていて、僕らの前ではちょっと格好つけるんだ」と語っていますが、きっとリチャードの方も自分が才能を認めたビートルズとの共演を楽しんでいたんじゃないかと思えてなんだか嬉しくなります。
ポールに至っては歌唱やシャウトの手解きを直接受け、シンガーとしての才能に一層磨きをかけました。
後のライブでポールの歌う “Long Tall Sally (リチャードのカバー)” や “I’m Down (ビートルズオリジナル)” は、ビートルズのライブのレパートリーとして象徴的な楽曲となりますが、その歌唱スタイルについてはリチャードもポール自身も「完全にリトル・リチャードから影響を受けたものだ」と認めています。
さらに素晴らしい出会いもありました。
リトル・リチャードのバンドでピアノを弾いていた当時16歳のビリー・プレストンです。
プレストンは後の1969年の “ゲット・バック・セッション” にビートルズの閉塞感を打ち破る素晴らしい演奏で参加し、まさに救世主的な働きをしてくれた素晴らしいミュージシャンです。
ビートルズの4人は当初嫌々ハンブルクへ向かいましたが、いざ行ってみると新しい仲間たちと充実の日々を過ごしていた様子が伺えます。
何より彼らにとってはリンゴがメンバーになってから初めてのハンブルクだったこともあり、重要な滞在に位置づけられるのではないかと思います。
ビートルズとロックンロール
リトル・リチャードからバトンを引き継いだビートルズが、ロックンロールに対して果たした役割はどのようなものだったのでしょうか。
ビートルズ研究家のマーク・ルイソン氏の『ザ・ビートルズ史』の中で紹介されているボブ・ウーラーの1961年の評論に興味深い言葉があります。
ボブ・ウーラーはビートルズが特にリバプール時代にお世話になったDJです。
ビートルズはここ何年ものうちでリバプールのロックンロール・シーンにもっとも大きな衝撃を与えた存在だ。
私はビートルズをナンバーワン・バンドだと思う。
なぜなら、ビートルズはロックンロールの原点であるスタイルを復活させたからだ。
そもそもロックンロールはアメリカの黒人歌手に由来するものだ。
ビートルズの音楽には、思わず叫び声をあげたくなるような要素がある。
そこには人を身体的にも聴覚的にも興奮させるものがある。
それは1950年代中期という倦んだ時代の若者の反抗心の象徴。
精力にみちたメンバーが目の前に存在し抗しがたいほど魅力的なビートを生み出している。
ロックの時計を逆回転させチャック・ベリー、リトル・リチャード、カール・パーキンス、コースターズ、その他時代の偉大なアーティストたちの曲を激しく演奏している。
上記はほんの一部の抜粋(中略あり)なので、素晴らしい評論の全文はぜひ書籍で読んでみていただきたいのですが、このボブ・ウーラーのビートルズについての分析は本当にかなり的を得ていて、4人はロックンロールを刷新し、更なる熱狂を投じる価値のあるものとして再構築したと言えるのではないでしょうか。
リトル・リチャードがロックを設計した “Architect” なら、ビートルズはさしずめロックを復活、再生させた “Rebuilder” と言えるかもしれません。
そしてビートルズは、リトル・リチャード同様自分たちで曲を作り演奏することができました。
リチャードはエルヴィス・プレスリーのことも評価していましたが、「でも彼は曲を作れない」とも言っています。
自ら楽曲を作り出しそれを演奏することができたことは、ビートルズがリチャードと同じようにロックンロールという枠を超越し、彼ら自身がひとつの音楽のジャンルとなっていった重要な要素のひとつではないでしょうか。
大切なのは愛
映画『リトル・リチャード:アイ・アム・エブリシング』の中でわたしが印象に残った彼の言葉がいくつかありました。
ちょっと記憶違いの言い回しもあるかもしれませんが紹介させてください。
ひとつは、「一番大切なものは?」と問われたリチャードが、「それは愛だ」と答えたことです。
「でも、自分が望む形の愛をまだ手に入れていない」とも言っていました。
ビートルズも “All you need is love” と歌ったように、やっぱり愛なんだな…と思ったのと、エルヴィス・プレスリーは普通の愛とは次元の違う「ステージで受け取る愛」に溺れ、それでも満たされず薬に走り最後は愛に殺された、、、と映画『エルヴィス』の中で表現されていたことも思い出し、偉大なスターが富と名声を得てそれで最後に求めるのは愛なんだと思うと少し苦しくなりました。
リトル・リチャードは最終的に自分の望む形の愛を手に入れることができたのか。とても気になります。
それから、「あなたにとって信仰と音楽どちらが重要か」みたいなことを問われたリチャードが「そのふたつは切り離せない。でもこの世の全ては音楽だ」と応えていたのも印象的でした。
最初彼にとって音楽は自分を解放する手段だったのかもしれませんが、結果多くの他者を解放したものの、多分自分自身は解放されるどころかロックンロールを歌うことと聖職者としてゴスペルを歌うことの狭間でずっと揺れ続けていたんだろうし、人種差別や同性愛差別のもと才能や需要に対して正当な評価をされず、全部自分で背負って交渉もしてなんとかギリギリのところで金銭的なラインと気持ちのラインを保ち、だけどステージ上ではいつも笑顔であんなに輝いて、本音を隠してジョークやユーモアを連発していて。
私にはリトル・リチャードは孤高のキングに見えました。
「ビートルズは4人でいられたからあの狂った日常を乗り越えることができた」と本人たちが語っているように、やはり一人で重圧や人気に伴う理不尽なあれこれを受け止め対処するのは並大抵の精神力では不可能なことだと思います。
実際エルヴィスも耐えることができなかったのでしょう。
リトル・リチャード、本名リチャード・ウェイン・ぺニマンは、2020年に87歳で他界しましたが、幼い頃から父親に認められず、劣悪な環境で働き、不当に搾取され、ゲイとしての自分を否定したり、薬に助けを求めたりもしつつ、多分かなり繊細な心を持ちながら表舞台ではいつも自信過剰で色んなことを笑い飛ばしてたくさんの人たちのヒーローであり続けた訳で、彼は破格の強さを持っていたんじゃないかと驚愕します。
1997年にやっとアメリカン・ミュージック・アウォードで功労賞を受賞し、「自分は貰うべきものを貰って来なかった」というリトル・リチャードがたくさんのミュージシャンからも絶対的なリスペクトを浴びて感極まり、60代とは思えない圧倒的なパフォーマンスを見せる姿には、思わず涙してしまいます。
彼によって解放され目覚めたアーティストたちのパワーがまた別の解放を生む。ビートルズもその連鎖の中の大きなエネルギーのひとつだったんだなと実感しました。
あと劇中でリトル・リチャードに影響を与えた人物のひとりとしてシスター・ロゼッタ・サープが登場しますが、彼女のものすごい説得力と歌唱力によるパフォーマンスを聴いていると、音楽ってやっぱり救いなんだなと思えます。
まとめ
こんな風に、脈々と続くアーティストからアーティストへのエネルギーと愛のバトンがあって、それがその時代や社会と深く結びつくことによって、誰かを支えたり励ましたり癒したり背中を押したりする音楽が爆誕するんだなと思えました。
ビートルズは60年代に人々を社会の足枷から自由にしていきましたが、わたしは彼らの音楽は時代を超越していつまでも私たちの心を刺激しつづけると思っています。
例えばビートルズが当時パット・ブーンの “Tutti Frutti” を聴いても多分まったく興奮しなかっただろうなと容易に想像できてしまうように、リトル・リチャードやビートルズの音楽には大勢の人々の心を鷲掴みにする "凄み" があります。
ステージの上から自分たちも愛を求め魂を消耗しながら、たくさんの人に愛を与えてくれた彼らに対する感謝と畏敬の念が、今回映画を観たことでますます大きくなりました。
リトル・リチャードの素晴らしい才能を体感するためにも、ここでは紹介しきれていない彼のヒリヒリする生涯をもっと知るためにも、チャンスがあればぜひ『リトル・リチャード:アイ・アム・エブリシング』をご覧ください。
2020年、彼の訃報を受けてリンゴやポールをはじめたくさんのアーティストが追悼の意を示していましたが、アーティストだけではなくありのままの自分で生きることにしんどさを感じている世界中の多くの人が彼に救われてきて、きっとこれからもそうなんだろうなと思います。
そんな出会いがほんの少しでも広がるように、わたしはこれからもビートルズや彼らのヒーローたちについて語り続けなければならないという謎の使命感を勝手に抱きました。
ビートルズおよびロックンロールのファンのみなさんも、ぜひその素晴らしさを周りにどんどんシェアしていきましょう!
5月は『The BEATLES : Let It Be』そして『ジョン・レノン 失われた週末』と、これまた注目の2つの映画が公開されます。
夏からはポール・マッカートニー写真展『Eyes Of The Storm』も始まります。
疲れない程度に今年度もビートリーな日々を満喫していきましょう。
▼『リトル・リチャード×ビートルズ』より詳しい内容の動画はこちら
サポートしてくださると、もれなく私が喜びます♡
